
法人税の減税や消費税増税という・・自公でもやらなかった暴挙を民主党が目指すのは自殺行為というしかない。米国のさらにいっそうの属国化も。
◆嘘だらけの法人税についての記事「日本の大企業負担(法人税・社会保険料)は他国より軽い - 法人税減税でなく欧州並みの負担増を」はー『ここ』
◆「強請りたかりの米政府ー普天間基地の海兵隊について、アメリカは日本にあと30億ドル出せと言っている」はー『ここ』
ー「隠し部屋を査察して」エリック・マコーマックよりー(2)
第一章
この入植地をつくった人々は、渓谷のヘリにあるフィヨルドの近くに建物を建てた。渓谷の両岸は古いケーキのようにぼろぼろとくずれているが、建物はしっかりしている。地面にうずくまっているような建物の地下には、かなり広い貯蔵室がある。
<地下室>、あるいは<地下牢>とよぶほうがふさわしいのだが、ここでは<隠し部屋>とよぶことが好まれる。とりわけ、地上部分に住んでいる管理人たちは、地下の状況を自慢げに力説する。隠し部屋には最新設備がそろっていることを、わたしとしても否定するつもりはない。すべてを査察して、わらマットの木製寝台や、セメントの壁にとりつけられた水道の蛇口や、急ごしらえの粗末な本棚やテーブルといった、快適な設備がととのっていることを証言できる。それでもときには、厚さが三十センチもある防音材や、拡声器からたえまなく流される陽気な行進曲といった涙ぐましい努力にもかかわらず、いわゆる<隠し部屋の住人>の苦悶の叫び声が、あらゆる障壁をつらぬいて、通行人の耳にまでとどくこともある。ほかの隠し部屋の住人がその叫び声を聞きつけるのは物理的に不可能なはずだが、つねにだれもが聞きつける。そうだ、聞きつけるのだ。フィヨルドの巨大な裂け目に沿った峡谷を吹きぬける風の、たえまないすすり泣きと混じりあって、それはまぎれもなく、彼らの不幸という事実をあらわにするのである。
ところでこの入植地だが、かつては森林だった大地の渓谷に沿って建設され、多くの地区に分けられている。各地区は六棟の建物で構成され、それぞれに隠し部屋があって、それらとはべつの建物に査察官が住んでいる。それというのも、各地区には政府から査察官が派遣されて、ほかの建物とそっくりの七番目の建物に住んでいるのだが、そこには隠し部屋がないのである。<査察官>と書かれた名札がドアに釘づけされている。
かくいうたたしも査察官であるが、わたしが担当している地区の建物は、縫合した傷のようにぎざぎざの渓谷のへりに並んでいる。この仕事は、ひきこもりがちな人間にはぴったりである。月にいちど、六つの建物の隠し部屋を査察して、報告書を作成する。月末になると、政府の特使が回収された報告書をもとにして、管理人は有能であり、隠し部屋の住人の世話はいきとどいていると当局に報告する。残りの時間は、自宅で本を読んだり、日記を書いたりしてすごす。行政当局は、あらゆる戸外活動や地区間の交流を認めていないからである。管理人たちが集会を開くこともないー少なくとも、招かれたことはいちどもない。
査察は必要である。これまでの経験から、管理人たちがかならずしも信用できないことはわかっている。彼らはいつも微笑をたやさず、隠し部屋の住人についてたずねると、心配ないとでもいうように頭を振って、いかにももっともらしい言葉を口にする。
「・・とてもしあわせそうですよ・・」
「・・よくなっていますよ・・」
「・・もうすぐよくなるでしょう・・」
だが、いかにも愛想のよさそうな瞳をのそきこんでいると、しだいに不快感がつのってくるのである。
行政当局の指示にしたがって、すべての建物は茶色に塗られている。昨年の指定色は濃紺だった。建物には窓がなく、軒樋もない。庭をつくることは禁じられている。そのために、慣れないうちは、それぞれの建物を見分けるのはむずかしいだろう。だから管理人たちは、それぞれの建物に凝った名前をつけ、それを木の板に焼き付けて、ドアに吊るしている。こうしてそれぞれの建物は、個性的な特徴がほとんど剥ぎとられた風景のなかで、それなりに個性を発揮しているのである。建物のまわりの広大な森や大地は、平坦にならされている。それぞれの地区は、丈のある茶色のキャンパス地の背景幕によって、ほかの地区や渓谷からさえぎられている。遠く離れたフィヨルドの崖を乱打する波の音に干渉しようとする試みは、一切なされなかった。その音は不規則であるが、すべての建物をわけへだてなく抱擁しているからである。
査察の時期になると、わたしはいつも、むせび泣きがしばらくやんでいるときに訪問を開始する。それは<静かな時期>とよばれている。むせび泣きがやまないときは、査察を中止することもある。「タイミングがすべてだ」というのが、わたしの前任者のせりふだった。そういうことにしっかりした男で、「査察とむせび泣きが重なったら、査察官のだれひとり生き延びることはできないだろう。どんなに意志が強くても、あのむせび泣きにむしばまれてしまうのだ」ともいった。
いつものように、まず最初に<貿易風>の茶色に塗られたドアをノックする。広大な凍土地帯のただなかにある建物にしては変わった名前であるが。
ドアがさっと開かれる。かなりふとった丸顔の中年女が顔をのぞかせる。わたしだということはわかっているくせにーその年、彼らを訪れるのはわたしだけなのだからーいかにも驚いたふりをしてみせる。査察はまるで儀式のように進行する。器量の悪い女か赤ら顔の大男。ふたりとも実直そうで、実直そうにふるまうことに慣れている。わたしはいつでも薄暗い部屋に案内される。黒っぽいマホガニーの家具のならんだ鏡のない部屋である。いつでも厚い詰め物をした肱掛椅子をすすめられる。いつでも、たまたま淹れたばかりのお茶をすすめられる。いつでも、わたしは断る。
はじめてこの地区を査察したときに、<貿易風>という名前にはびっくりした。といったことを憶えている。こんなところで、どうしてこんな名前を選んだのかとたずねたところ、器量の悪い女だったか、赤ら顔の大男だったか、いまでは憶えていないが、どちらかが大笑いして、それはこの世でいちばん自然な名前だといった。絶対に、この世でいちばん自然な名前だと。それ以来、名前についてたずねたことはいちどもない。
このあたりで、いつも儀式はぎくしゃくしはじめる。ふたりの微笑やおしゃべりの背後に不安が顔をのぞかせる。そろそろ隠し部屋の住人に会わなければならないと告げると、予想どおり、ふたりはしばらくためらってから、彼の状態についてあいまいな口調でつぶやく。
「・・だいぶよくなっていますよ・・」
「・・今日は静かでね・・」
「・・ほんとに愉快な人です・・」
ここまでくると、ふたりがわたしをいやがっていることがはっきりしてくる。
だが、ここでやめるわけにはいかない。隠し部屋の近くに吊るしておくことが規則で定められている赤いエナメル塗りのカンテラをはずしてー階段には電灯がないのだー黒っぽいマホガニーのテーブルにのせてから、ふたりに弱みを見せないように、マッチをしっかり握って火をつける。男が居間の隅のくたびれたカーペットをめくると、落とし戸が現れる。男はその扉をいかにも重そうにもちあげて壁に立てかける。わたしはためらわずに闇のなかに降りていく。
カンテラの光は階段を一段ずつ照らしだす。それを追って階段を降りていき、明るい光の輪に照らされた石畳にたどりつく。隠し部屋の鉛色の扉が目の前で湿っぽい光をはなっている。わたしは足もとにカンテラを置いて、格子窓のスリットを横にすべらせる。
かびくさいにおいがむっと鼻をつく。湿っぽい腐敗臭である。いつものようにからだをまるめて、ひとりの男が寝台に横たわっている。顔に腕をのせて、天井の格子電球から顔をそむけている。かすかな声で、なにやらリズミカルにつぶやいている。男にはいわくいいがたい気品のようなものがある。乱れた灰色の髪とぼさぼさのひげづらをおおう腕は、下生えに横たわる倒木を思わせる。
わたしは男に話しかけない。たとえ隠し部屋の住人が話しかけてきても、わたしはなにも話さない。わたしの職務ははっきりと規定されているのだ。わたしの仕事は査察であって、彼らとは視覚的接触しか許されていない。生きていくためには、そうするしかないのだ。
この男は、ほかのすべての隠し部屋の住人とおなじように、われわれのファイルにも名前が記載されていない。だが、名前は奪われているが、行政当局にとって興味深そうな行動を記録するために、査察官は彼らのこれまでの病歴を熟知することになっている。それがどのような行動なのか、いまだにはっきりしないが、前任者の忠告にしたがって、なにもかも報告することにしている。
わたしが格子窓から観察しているこの男は、北部地方からやってきた大家族の最後のひとりである。数百年のあいだに、男の先祖たちは、荘園の建物のまわりに人工の森をつくりあげた。十六世紀なかばから、天然の樹木や、家屋のまわりの潅木を丁寧に抜きとり、せっせと複製をつくってきたのである。細部はそれほど正確ではないが、全体としてはみごとな複製であった。初期の素材は針金を芯にした紙だったが、そのうちに、プラスチックと合成支柱になった。彼らがつくりあげた樹木には、アサダ、チンカピングリ、ベブヤナギ、ハナミズキ、あるいは、バルサムの採れるハコヤナギ、ヒッコリー、ブラクデドバルサム、あるいは、神樹、苺樹、生命樹、衰退樹、ユダの樹、などがあった、彼らは根まで複製し、精巧な工学技術を駆使して、天然の樹木を抜きとったあとの穴に挿入した。
その結果はじつにみごとなものだった。遠くから見れば本物そっくりの、何千ヘクタールにもわたって広がる人工の森林である。その恒常性は季節の変化に左右されなかった。秋になっても、枯れてゆく樹木は一本もなかった。
われわれの行政当局が権力を掌握すると、そのような異常な行為はすべて禁じられた。昆虫のようにつややかな青い制服を身にまとい、火炎放射器を手にした選りすぐりの青衛兵連隊が、森林を焼きつくせという命令を受けて派遣された。
焼却がはじまった。巨大な雲のような黒煙と火花が大気にたちのぼり、はるか遠くの首都からも見えるほどだった。森林は破滅を迎えた。
だれもが予想していなかったのは動物だった。炎が森林のへりに迫ったとき、まるでテーブルにこぼした水のように、何千頭もの森林動物たちが兵士めがけて殺到してきたのである。豪胆さで選ばれた青衛兵たちすらもおびえさせたのは、不自然な知性にきらめく瞳ではなかった。ポリフェニックな咆哮(わたしは報告書のことばを使う)でもなかった。観察者たちのことばを借りれば、それは動物たちの姿そのものだった。いままでだれも、そのような生物を見たことがなかった。全体的な姿は、ウサギ、リス、シカ、クマといった、森でよく見かける動物に似ていたが、その走り方は関節がはずれたようにぎくしゃくしており、その姿はなんとも形容しがたいものだった。異様な知性を宿した多色の瞳は、頭とおぼしい球状のふくらみにでたらめにとりつけられていた。口は胴体のあちこちにぽっかりと開いた穴にすぎず、歯のかわりのようなぎざぎざの骨に縁取られていた。四肢の位置もでたらめで、背中や腹から意味もなくつきだしているものもあった。これらの動物たちが炎に近づきすぎると、ふいに溶けて液体になってしまうか、生きた榴霧弾のように破裂してしまうのだった。青衛兵たちは冷静を保って皆殺しにせよと命じられた。
この隠し部屋に横たわっている男は、青衛兵の行為を目撃すると、「人殺し!人殺し!」と叫びながら突進してきた。わきに押しやられると、すすり泣きながら、せめていくらかでも生かしておいてくれと懇願した。そのことばも無視されると、しばらくしてから、また突進してきたが、今度は山刀を振りまわしたので、彼らは身を守るために、やむなく男を殴り倒したのである。
焼却の一夜があけて、広大な森がくすぶる石筍の共同墓地と化してしまうと、男はここに移送されてきた。それ以来、このようななんともいえない姿でここに横たわっている。ここ何年間も、ひとことも口をきこうとはしない。なにかしゃべったとたんに姿が消えてしまうとでも思っているかのようだ。われわれの行政当局は、いつの日にかこの男が口をひらいて、森に生きていた鳥たちについてしゃべることを期待している。鳥たちは山火事のあいだに姿を消してしまったが、いまでもときおり国じゅうで目撃されており、鳥というよりもむしろ空飛ぶ土くれのように、こどもたちの頭上をぎこちなく飛びすぎては、彼らをびっくりさせているのである。
けれども、男はなにもしゃべらない。ときおり声を殺してすすり泣くばかりである。そしてそれは、隠し部屋の住人たちのむせび泣きをいざなうこともある。
わたしは格子窓を閉めて急な階段をのぼっていく。管理人に礼をのべてから(ふたりの安堵は歴然としているが、わたしの安堵は隠されている)、消したばかりのカンテラのにおいに吐き気をもよおさないうちに、冷えびえとした空気のなかに出ていく。最初の訪問はこうして終わる。
わずかなちがいはあるが、残りの建物でも、ほとんどおなじ儀式がくりかえされる。人は好いが信頼できない管理人たちの、いかにももっともらしい驚き、湿っぽい隠し部屋への湿っぽい降下。訪問の終わりに双方が憶える心からの安堵。われわれはみなひとつの大きな希望を共有している。あのむせび泣きがはじまらないことだ。なにが引き金になるのか、だれにもわからない。いまのところ、査察官であるわたしにも、管理人である彼らにも、隠し部屋の住人を理解できないことだけがわかっている。ひょっとすると、行政当局がつきとめたいと思っているのは、彼らのむせび泣きの秘密なのかもしれない。
この地区には六人の隠し部屋の住人が住んでいる。わたしはひとり残らず知っているが、ほんとうはなにも知らないのだ。彼らはいつまでも親しい他人のままだろう
◆嘘だらけの法人税についての記事「日本の大企業負担(法人税・社会保険料)は他国より軽い - 法人税減税でなく欧州並みの負担増を」はー『ここ』
◆「強請りたかりの米政府ー普天間基地の海兵隊について、アメリカは日本にあと30億ドル出せと言っている」はー『ここ』
ー「隠し部屋を査察して」エリック・マコーマックよりー(2)
第一章
この入植地をつくった人々は、渓谷のヘリにあるフィヨルドの近くに建物を建てた。渓谷の両岸は古いケーキのようにぼろぼろとくずれているが、建物はしっかりしている。地面にうずくまっているような建物の地下には、かなり広い貯蔵室がある。
<地下室>、あるいは<地下牢>とよぶほうがふさわしいのだが、ここでは<隠し部屋>とよぶことが好まれる。とりわけ、地上部分に住んでいる管理人たちは、地下の状況を自慢げに力説する。隠し部屋には最新設備がそろっていることを、わたしとしても否定するつもりはない。すべてを査察して、わらマットの木製寝台や、セメントの壁にとりつけられた水道の蛇口や、急ごしらえの粗末な本棚やテーブルといった、快適な設備がととのっていることを証言できる。それでもときには、厚さが三十センチもある防音材や、拡声器からたえまなく流される陽気な行進曲といった涙ぐましい努力にもかかわらず、いわゆる<隠し部屋の住人>の苦悶の叫び声が、あらゆる障壁をつらぬいて、通行人の耳にまでとどくこともある。ほかの隠し部屋の住人がその叫び声を聞きつけるのは物理的に不可能なはずだが、つねにだれもが聞きつける。そうだ、聞きつけるのだ。フィヨルドの巨大な裂け目に沿った峡谷を吹きぬける風の、たえまないすすり泣きと混じりあって、それはまぎれもなく、彼らの不幸という事実をあらわにするのである。
ところでこの入植地だが、かつては森林だった大地の渓谷に沿って建設され、多くの地区に分けられている。各地区は六棟の建物で構成され、それぞれに隠し部屋があって、それらとはべつの建物に査察官が住んでいる。それというのも、各地区には政府から査察官が派遣されて、ほかの建物とそっくりの七番目の建物に住んでいるのだが、そこには隠し部屋がないのである。<査察官>と書かれた名札がドアに釘づけされている。
かくいうたたしも査察官であるが、わたしが担当している地区の建物は、縫合した傷のようにぎざぎざの渓谷のへりに並んでいる。この仕事は、ひきこもりがちな人間にはぴったりである。月にいちど、六つの建物の隠し部屋を査察して、報告書を作成する。月末になると、政府の特使が回収された報告書をもとにして、管理人は有能であり、隠し部屋の住人の世話はいきとどいていると当局に報告する。残りの時間は、自宅で本を読んだり、日記を書いたりしてすごす。行政当局は、あらゆる戸外活動や地区間の交流を認めていないからである。管理人たちが集会を開くこともないー少なくとも、招かれたことはいちどもない。
査察は必要である。これまでの経験から、管理人たちがかならずしも信用できないことはわかっている。彼らはいつも微笑をたやさず、隠し部屋の住人についてたずねると、心配ないとでもいうように頭を振って、いかにももっともらしい言葉を口にする。
「・・とてもしあわせそうですよ・・」
「・・よくなっていますよ・・」
「・・もうすぐよくなるでしょう・・」
だが、いかにも愛想のよさそうな瞳をのそきこんでいると、しだいに不快感がつのってくるのである。
行政当局の指示にしたがって、すべての建物は茶色に塗られている。昨年の指定色は濃紺だった。建物には窓がなく、軒樋もない。庭をつくることは禁じられている。そのために、慣れないうちは、それぞれの建物を見分けるのはむずかしいだろう。だから管理人たちは、それぞれの建物に凝った名前をつけ、それを木の板に焼き付けて、ドアに吊るしている。こうしてそれぞれの建物は、個性的な特徴がほとんど剥ぎとられた風景のなかで、それなりに個性を発揮しているのである。建物のまわりの広大な森や大地は、平坦にならされている。それぞれの地区は、丈のある茶色のキャンパス地の背景幕によって、ほかの地区や渓谷からさえぎられている。遠く離れたフィヨルドの崖を乱打する波の音に干渉しようとする試みは、一切なされなかった。その音は不規則であるが、すべての建物をわけへだてなく抱擁しているからである。
査察の時期になると、わたしはいつも、むせび泣きがしばらくやんでいるときに訪問を開始する。それは<静かな時期>とよばれている。むせび泣きがやまないときは、査察を中止することもある。「タイミングがすべてだ」というのが、わたしの前任者のせりふだった。そういうことにしっかりした男で、「査察とむせび泣きが重なったら、査察官のだれひとり生き延びることはできないだろう。どんなに意志が強くても、あのむせび泣きにむしばまれてしまうのだ」ともいった。
いつものように、まず最初に<貿易風>の茶色に塗られたドアをノックする。広大な凍土地帯のただなかにある建物にしては変わった名前であるが。
ドアがさっと開かれる。かなりふとった丸顔の中年女が顔をのぞかせる。わたしだということはわかっているくせにーその年、彼らを訪れるのはわたしだけなのだからーいかにも驚いたふりをしてみせる。査察はまるで儀式のように進行する。器量の悪い女か赤ら顔の大男。ふたりとも実直そうで、実直そうにふるまうことに慣れている。わたしはいつでも薄暗い部屋に案内される。黒っぽいマホガニーの家具のならんだ鏡のない部屋である。いつでも厚い詰め物をした肱掛椅子をすすめられる。いつでも、たまたま淹れたばかりのお茶をすすめられる。いつでも、わたしは断る。
はじめてこの地区を査察したときに、<貿易風>という名前にはびっくりした。といったことを憶えている。こんなところで、どうしてこんな名前を選んだのかとたずねたところ、器量の悪い女だったか、赤ら顔の大男だったか、いまでは憶えていないが、どちらかが大笑いして、それはこの世でいちばん自然な名前だといった。絶対に、この世でいちばん自然な名前だと。それ以来、名前についてたずねたことはいちどもない。
このあたりで、いつも儀式はぎくしゃくしはじめる。ふたりの微笑やおしゃべりの背後に不安が顔をのぞかせる。そろそろ隠し部屋の住人に会わなければならないと告げると、予想どおり、ふたりはしばらくためらってから、彼の状態についてあいまいな口調でつぶやく。
「・・だいぶよくなっていますよ・・」
「・・今日は静かでね・・」
「・・ほんとに愉快な人です・・」
ここまでくると、ふたりがわたしをいやがっていることがはっきりしてくる。
だが、ここでやめるわけにはいかない。隠し部屋の近くに吊るしておくことが規則で定められている赤いエナメル塗りのカンテラをはずしてー階段には電灯がないのだー黒っぽいマホガニーのテーブルにのせてから、ふたりに弱みを見せないように、マッチをしっかり握って火をつける。男が居間の隅のくたびれたカーペットをめくると、落とし戸が現れる。男はその扉をいかにも重そうにもちあげて壁に立てかける。わたしはためらわずに闇のなかに降りていく。
カンテラの光は階段を一段ずつ照らしだす。それを追って階段を降りていき、明るい光の輪に照らされた石畳にたどりつく。隠し部屋の鉛色の扉が目の前で湿っぽい光をはなっている。わたしは足もとにカンテラを置いて、格子窓のスリットを横にすべらせる。
かびくさいにおいがむっと鼻をつく。湿っぽい腐敗臭である。いつものようにからだをまるめて、ひとりの男が寝台に横たわっている。顔に腕をのせて、天井の格子電球から顔をそむけている。かすかな声で、なにやらリズミカルにつぶやいている。男にはいわくいいがたい気品のようなものがある。乱れた灰色の髪とぼさぼさのひげづらをおおう腕は、下生えに横たわる倒木を思わせる。
わたしは男に話しかけない。たとえ隠し部屋の住人が話しかけてきても、わたしはなにも話さない。わたしの職務ははっきりと規定されているのだ。わたしの仕事は査察であって、彼らとは視覚的接触しか許されていない。生きていくためには、そうするしかないのだ。
この男は、ほかのすべての隠し部屋の住人とおなじように、われわれのファイルにも名前が記載されていない。だが、名前は奪われているが、行政当局にとって興味深そうな行動を記録するために、査察官は彼らのこれまでの病歴を熟知することになっている。それがどのような行動なのか、いまだにはっきりしないが、前任者の忠告にしたがって、なにもかも報告することにしている。
わたしが格子窓から観察しているこの男は、北部地方からやってきた大家族の最後のひとりである。数百年のあいだに、男の先祖たちは、荘園の建物のまわりに人工の森をつくりあげた。十六世紀なかばから、天然の樹木や、家屋のまわりの潅木を丁寧に抜きとり、せっせと複製をつくってきたのである。細部はそれほど正確ではないが、全体としてはみごとな複製であった。初期の素材は針金を芯にした紙だったが、そのうちに、プラスチックと合成支柱になった。彼らがつくりあげた樹木には、アサダ、チンカピングリ、ベブヤナギ、ハナミズキ、あるいは、バルサムの採れるハコヤナギ、ヒッコリー、ブラクデドバルサム、あるいは、神樹、苺樹、生命樹、衰退樹、ユダの樹、などがあった、彼らは根まで複製し、精巧な工学技術を駆使して、天然の樹木を抜きとったあとの穴に挿入した。
その結果はじつにみごとなものだった。遠くから見れば本物そっくりの、何千ヘクタールにもわたって広がる人工の森林である。その恒常性は季節の変化に左右されなかった。秋になっても、枯れてゆく樹木は一本もなかった。
われわれの行政当局が権力を掌握すると、そのような異常な行為はすべて禁じられた。昆虫のようにつややかな青い制服を身にまとい、火炎放射器を手にした選りすぐりの青衛兵連隊が、森林を焼きつくせという命令を受けて派遣された。
焼却がはじまった。巨大な雲のような黒煙と火花が大気にたちのぼり、はるか遠くの首都からも見えるほどだった。森林は破滅を迎えた。
だれもが予想していなかったのは動物だった。炎が森林のへりに迫ったとき、まるでテーブルにこぼした水のように、何千頭もの森林動物たちが兵士めがけて殺到してきたのである。豪胆さで選ばれた青衛兵たちすらもおびえさせたのは、不自然な知性にきらめく瞳ではなかった。ポリフェニックな咆哮(わたしは報告書のことばを使う)でもなかった。観察者たちのことばを借りれば、それは動物たちの姿そのものだった。いままでだれも、そのような生物を見たことがなかった。全体的な姿は、ウサギ、リス、シカ、クマといった、森でよく見かける動物に似ていたが、その走り方は関節がはずれたようにぎくしゃくしており、その姿はなんとも形容しがたいものだった。異様な知性を宿した多色の瞳は、頭とおぼしい球状のふくらみにでたらめにとりつけられていた。口は胴体のあちこちにぽっかりと開いた穴にすぎず、歯のかわりのようなぎざぎざの骨に縁取られていた。四肢の位置もでたらめで、背中や腹から意味もなくつきだしているものもあった。これらの動物たちが炎に近づきすぎると、ふいに溶けて液体になってしまうか、生きた榴霧弾のように破裂してしまうのだった。青衛兵たちは冷静を保って皆殺しにせよと命じられた。
この隠し部屋に横たわっている男は、青衛兵の行為を目撃すると、「人殺し!人殺し!」と叫びながら突進してきた。わきに押しやられると、すすり泣きながら、せめていくらかでも生かしておいてくれと懇願した。そのことばも無視されると、しばらくしてから、また突進してきたが、今度は山刀を振りまわしたので、彼らは身を守るために、やむなく男を殴り倒したのである。
焼却の一夜があけて、広大な森がくすぶる石筍の共同墓地と化してしまうと、男はここに移送されてきた。それ以来、このようななんともいえない姿でここに横たわっている。ここ何年間も、ひとことも口をきこうとはしない。なにかしゃべったとたんに姿が消えてしまうとでも思っているかのようだ。われわれの行政当局は、いつの日にかこの男が口をひらいて、森に生きていた鳥たちについてしゃべることを期待している。鳥たちは山火事のあいだに姿を消してしまったが、いまでもときおり国じゅうで目撃されており、鳥というよりもむしろ空飛ぶ土くれのように、こどもたちの頭上をぎこちなく飛びすぎては、彼らをびっくりさせているのである。
けれども、男はなにもしゃべらない。ときおり声を殺してすすり泣くばかりである。そしてそれは、隠し部屋の住人たちのむせび泣きをいざなうこともある。
わたしは格子窓を閉めて急な階段をのぼっていく。管理人に礼をのべてから(ふたりの安堵は歴然としているが、わたしの安堵は隠されている)、消したばかりのカンテラのにおいに吐き気をもよおさないうちに、冷えびえとした空気のなかに出ていく。最初の訪問はこうして終わる。
わずかなちがいはあるが、残りの建物でも、ほとんどおなじ儀式がくりかえされる。人は好いが信頼できない管理人たちの、いかにももっともらしい驚き、湿っぽい隠し部屋への湿っぽい降下。訪問の終わりに双方が憶える心からの安堵。われわれはみなひとつの大きな希望を共有している。あのむせび泣きがはじまらないことだ。なにが引き金になるのか、だれにもわからない。いまのところ、査察官であるわたしにも、管理人である彼らにも、隠し部屋の住人を理解できないことだけがわかっている。ひょっとすると、行政当局がつきとめたいと思っているのは、彼らのむせび泣きの秘密なのかもしれない。
この地区には六人の隠し部屋の住人が住んでいる。わたしはひとり残らず知っているが、ほんとうはなにも知らないのだ。彼らはいつまでも親しい他人のままだろう

















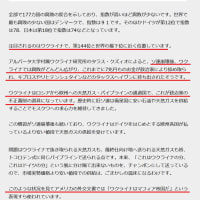



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます