
小欄は、筋金入りの「嫌中」「反中」だ。
だが、その根底には“中国大好き”がある。
要は、昔の中国は好きだが、共産党政権下の中国は好きになれないというところだ。
昔の中国には、民衆の中から“不義を正す”という意識が必ず芽生えた。その力は“夏の桀王”“商の紂王”を倒し、秦も漢も倒した。
日本人は、こういう中国の自浄の歴史に深い感銘を抱き、“羊頭狗肉”の晏子を尊敬し、近代革命の先人といわれる孫文を慕ったりするのだ。
しかし現下、中国人民は全くの無力で、自浄能力を失っている。これが、中国の魅力を失わせている原因で、その落差が、“大好き”を「嫌中」「反中」にしている。
伊藤正著・小平秘録下巻の寄稿文で何清漣氏に“盗賊型政権”と形容された“胡錦濤政権”は、“黄巾党政権”のようだ。日本語の、読みもよく似ているではないか。
もはや、中国には黄巾賊徒を討とうとした劉備玄徳のような人物は現れないのだろうか?
小欄は、機会を窺うものがいることを信じている。
日本人の根強い「嫌中感情」はどこから来ているのか?【ビジネスマンのための中国経済事情の読み方】(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
だが、その根底には“中国大好き”がある。
要は、昔の中国は好きだが、共産党政権下の中国は好きになれないというところだ。
昔の中国には、民衆の中から“不義を正す”という意識が必ず芽生えた。その力は“夏の桀王”“商の紂王”を倒し、秦も漢も倒した。
日本人は、こういう中国の自浄の歴史に深い感銘を抱き、“羊頭狗肉”の晏子を尊敬し、近代革命の先人といわれる孫文を慕ったりするのだ。
しかし現下、中国人民は全くの無力で、自浄能力を失っている。これが、中国の魅力を失わせている原因で、その落差が、“大好き”を「嫌中」「反中」にしている。
伊藤正著・小平秘録下巻の寄稿文で何清漣氏に“盗賊型政権”と形容された“胡錦濤政権”は、“黄巾党政権”のようだ。日本語の、読みもよく似ているではないか。
もはや、中国には黄巾賊徒を討とうとした劉備玄徳のような人物は現れないのだろうか?
小欄は、機会を窺うものがいることを信じている。
日本人の根強い「嫌中感情」はどこから来ているのか?【ビジネスマンのための中国経済事情の読み方】(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース










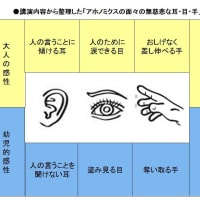

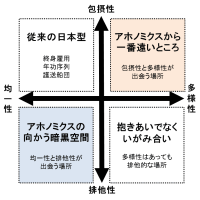

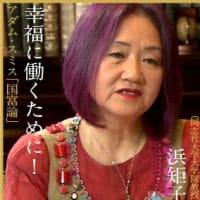










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます