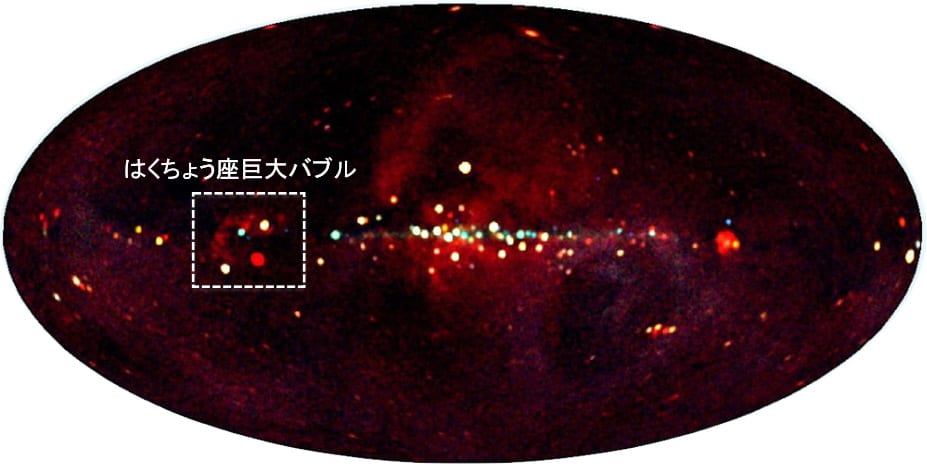アポロ計画で採取した月の高地の石から、微量の水が発見されました。
月の形成に関して有力視されているのは、誕生したばかりのころの地球に火星サイズの天体が衝突し、その残骸が集まってできたという巨大衝突説です。
その衝突のとき、大量の水が蒸発して宇宙空間へ逃げ出し、
その結果、誕生時の月はほとんど水のない乾燥した環境だったと考えられています。
今回、アメリカのノートルダム大学の研究チームが発表したのは、そうした月形成理論を覆す研究成果で、
1970年代にアポロミッションで持ち帰られた石を分析し、鉱物の結晶構造中に微量の水を見つけています。

分析対象となった石の1つ
“ジェネシスロック”
分析対象となったのは、月の高地(月面の明るい部分)から採取された斜長石。
生まれたての月の地殻が固まる前、まだどろどろに溶けたマグマの海が広がっていた頃に結晶化して表面に浮いたものと考えられています。
つまり、当時の記憶を残している石なんですねー
そこに水が含まれるということは、形成当時の月に水が存在していたことになります。
ひょっとすると、従来説のプロセスよりももっと長い時間をかけて、マグマの海が固まっていったのかもしれません。
月の形成に関して有力視されているのは、誕生したばかりのころの地球に火星サイズの天体が衝突し、その残骸が集まってできたという巨大衝突説です。
その衝突のとき、大量の水が蒸発して宇宙空間へ逃げ出し、
その結果、誕生時の月はほとんど水のない乾燥した環境だったと考えられています。
今回、アメリカのノートルダム大学の研究チームが発表したのは、そうした月形成理論を覆す研究成果で、
1970年代にアポロミッションで持ち帰られた石を分析し、鉱物の結晶構造中に微量の水を見つけています。

分析対象となった石の1つ
“ジェネシスロック”
分析対象となったのは、月の高地(月面の明るい部分)から採取された斜長石。
生まれたての月の地殻が固まる前、まだどろどろに溶けたマグマの海が広がっていた頃に結晶化して表面に浮いたものと考えられています。
つまり、当時の記憶を残している石なんですねー
そこに水が含まれるということは、形成当時の月に水が存在していたことになります。
ひょっとすると、従来説のプロセスよりももっと長い時間をかけて、マグマの海が固まっていったのかもしれません。