いいかげん何か書かないとね、と。
まぁむずかしいこと考えず、
オイラが好きな傾向の配置について語ってみようかと思います。
・リズミカルである
結局のところ、音ゲーのほとんどは「リズムアクション」ですからね。
7鍵盤であってもその意識は変わりません。
旋律にそった配置があったとしても、最終的にはフェイクにすぎませんし。
(フェイクだからこそ、配置に説得力を持たせることがとてもとても重要なんですけどね)
あ、もちろんメロ叩きがイカンというわけじゃないですよ。
リズミカルに進行するメロディだって沢山あるわけで。
・キーに手ごたえがある
音がデカイ、とか言う事に限らず、
副音オブジェとか、リアクションのでかいキー配置が好きです。
低難度の曲ほど、この辺がしっかりできてるかどうかがカギになりますね。
穴抜け配置(長いフレーズの欠けを補完するだけのオブジェ)はイヤン。
あとは、さっきも言った「説得力」ですね。
何故このキーにこの音が配置されているのか、と言う部分が分かりやすいほうが、
手ごたえとして指に伝わってくるものだと思います。
・緩急がある
ずっと叩きっぱなしってのも疲れるし、暇なだけでもイヤですし。
要所要所に休憩できる箇所や、難所が設けられていたほうがいいです。
ここで言う「難所」が、
腕前が未熟な人に成長を促すものであれば完璧です。
(例えば連打、乱打の練習になるとか指運びが達者になるとか)
・個性がある
要は、例えば譜面だけを誰かに見せた時に「あっ、あの曲だ」というふうに
すぐに連想できるような配置が好きです。
演奏感だけじゃなく、見た目のインパクトも重要ですね。
(某氏にいただいたコピー本に収録されていた漫画で
「あいつしかいねえ!」「人を配置で思い出すな!」ってやりとりがあったなあ)
まとまりなく書いてみました。
深く考察すべき点があればいずれやります。やらないかもしれないけど。
これからもこう言うテキトーなノリでやっていければいいなあと思います。
まぁむずかしいこと考えず、
オイラが好きな傾向の配置について語ってみようかと思います。
・リズミカルである
結局のところ、音ゲーのほとんどは「リズムアクション」ですからね。
7鍵盤であってもその意識は変わりません。
旋律にそった配置があったとしても、最終的にはフェイクにすぎませんし。
(フェイクだからこそ、配置に説得力を持たせることがとてもとても重要なんですけどね)
あ、もちろんメロ叩きがイカンというわけじゃないですよ。
リズミカルに進行するメロディだって沢山あるわけで。
・キーに手ごたえがある
音がデカイ、とか言う事に限らず、
副音オブジェとか、リアクションのでかいキー配置が好きです。
低難度の曲ほど、この辺がしっかりできてるかどうかがカギになりますね。
穴抜け配置(長いフレーズの欠けを補完するだけのオブジェ)はイヤン。
あとは、さっきも言った「説得力」ですね。
何故このキーにこの音が配置されているのか、と言う部分が分かりやすいほうが、
手ごたえとして指に伝わってくるものだと思います。
・緩急がある
ずっと叩きっぱなしってのも疲れるし、暇なだけでもイヤですし。
要所要所に休憩できる箇所や、難所が設けられていたほうがいいです。
ここで言う「難所」が、
腕前が未熟な人に成長を促すものであれば完璧です。
(例えば連打、乱打の練習になるとか指運びが達者になるとか)
・個性がある
要は、例えば譜面だけを誰かに見せた時に「あっ、あの曲だ」というふうに
すぐに連想できるような配置が好きです。
演奏感だけじゃなく、見た目のインパクトも重要ですね。
(某氏にいただいたコピー本に収録されていた漫画で
「あいつしかいねえ!」「人を配置で思い出すな!」ってやりとりがあったなあ)
まとまりなく書いてみました。
深く考察すべき点があればいずれやります。やらないかもしれないけど。
これからもこう言うテキトーなノリでやっていければいいなあと思います。













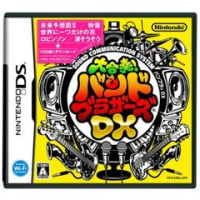
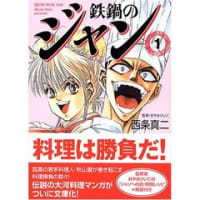
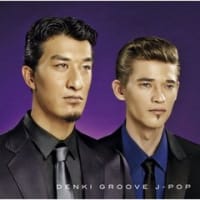
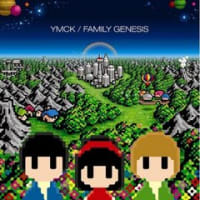

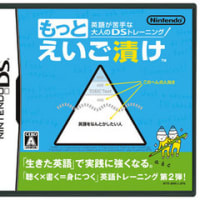

でもせっかくなので残します。