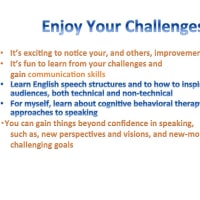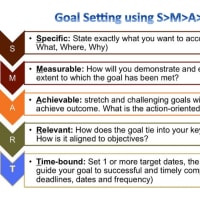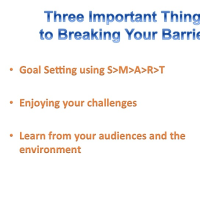最近「糖尿病・代謝内分泌関連の論文の抄読会を一人で行っています。 」っていう(ちょい内向き)一人抄読会なるブログの存在を知った。
結構コアな内容の論文を全訳付きで解説している殊勝なブログである。
それにならって、ちょっと一人で勉強したことを備忘録がてらに一人勉強会としてまとめておいた。お題はFRETである。
FRETとは、Wikipediaによると、蛍光(フェルスター)共鳴エネルギー移動(Fluorescence resonance energy transfer)のことであり、
難しく言うと「近接した2個の色素分子(または発色団)の間で励起エネルギーが、電磁波にならず電子の共鳴により直接移動する現象。このため、一方の分子(供与体)で吸収された光のエネルギーによって他方の分子(受容体)にエネルギーが移動し、受容体が蛍光分子の場合は受容体から蛍光が放射される。」
生物分野では基本的には蛍光タンパクを使ったバイオセンサーに利用されることが多く、その場合ざっくりいうと、
二つの蛍光タンパクが適度な距離かつ適切な方向で並んでいるときに、片方が励起されると、もう片方が励起されていないのに蛍光を発する現象である。
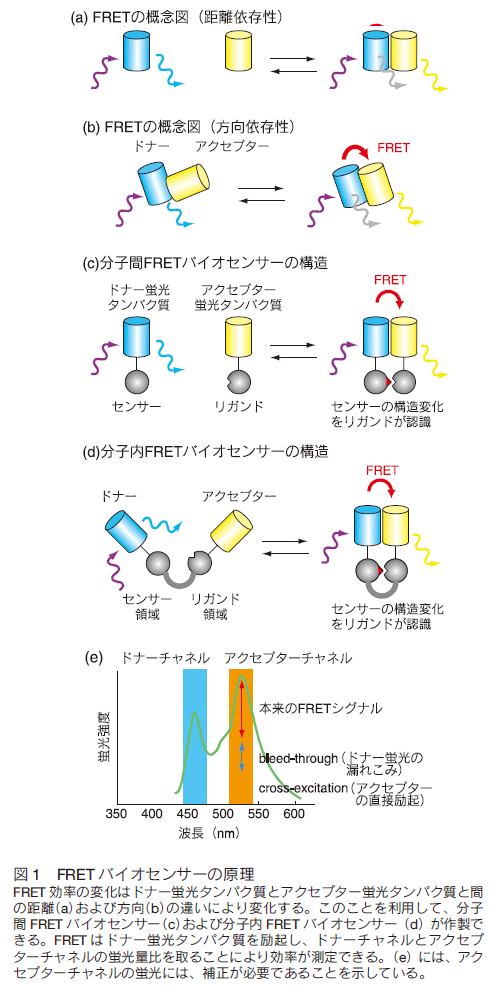
(松田道行先生のレビューより)
詳しくはこの分野の第一人者である松田道行先生のレビューを参照するとよいが、こうした現象を利用して、タンパクの結合やシグナル伝達分子の活性化をモニターするバイオセンサーがいくつもつくられている。
私もこうしたバイオセンサーを最近利用しようとして今勉強中なのだが、
このバイオセンサーの特徴は次のようなものになるらしい。
1)二つの蛍光タンパク分子を使う分子間型バイオセンサーと二つの蛍光分子が一つのタンパク内にある分子間型バイオセンサーがある。
分子間型は作るのが非常に大変なようである。
2)二つの蛍光物質の最適な組み合わせは
ECFPとYpetである。
ECFPの代わりにAmcyan, TFP,CFP
Ypetの代わりにYFP, Venus
なども用いられる。
http://comtec.semrock.com/Catalog/SetDetails.aspx?SetBasePartID=143&CategoryID=20
3)リンカー部位がセンサーとしての効率にかなり寄与する。
松田先生に言わせると
「FRET バイオセンサーを見ると、リガンド領域とセンサー領域が結合した際に FRET 効率が上昇するものと下降するものに二分される。距離が主たる影響を与えているものと、方向性が主たる影響を与えているものがあるからだと解釈されている。論文中に記載されていることはほとんどないが、実際のところは、作ってみないとこのどちらのタイプになるかはわからない」
らしい。

(松田道行先生のレビューより)
4)安定株ができにくい
この部分が一番重要なのだが、レトロウィルスベクターやレンチウィルスベクターを用いてセンサーを導入しても、「おそらく逆転写反応の際に (同じオワンクラゲ由来で遺伝子の似ている)CFP 遺伝子と YFP 遺伝子との間の組換えが起きて、CFP もしくは YFP のみしか光らなくなるものが大部分である」(上記レビューより)というらしい。
これに関してはCFPとは由来の違うサンゴ由来のTFPを使うと組み換えが起こらず安定細胞株が楽に作成できるらしい(レビュー及びMol Biol Cell. 2010 Mar 15;21(6):1088-96参照)。ただTFPの場合はFRET効率がだいぶ低くなってしまうらしい。
また piggyBac トランスポゾンを使う方法というのも有効であるらしい。
これに関しては、semrockというメーカーのサイトにコンパチブルな組み合わせとして
CFP (cyan GFP), CyPet, AmCyan, AmCyan1,
YFP (yellow GFP), YPet, Venus
紹介されているから、
やはりサンゴ由来のAmcyanとクラゲ由来のYFPもしくはmVenusという組み合わせが取れるのではないかと思う(*)。
現在検討中のバイオセンサーは、こうした注意点を既存のものを改良する形である。いいツールができるればよいな。。
(*)その後調べたところ、
Amcyanはaggregationを作りやすいのでmTFP1の方が良いという文献Quantitative Comparison of Different Fluorescent Protein Couples for Fast FRET-FLIM AcquisitionやmTFP1が一番というブログあった。
ただいくつかの例で、Amcyan-YFPでFRETを観察している例があるので、そんなに悪い組み合わせではないと思う。
JCS February 1, 2014 vol. 127 no. 3 583-598
Molecular Pharmacology December 2011 vol. 80 no. 6 1147-1155
特に2つ目の例は、胆汁酸応答分子の分子内及び分子間活性化制御機構と生理代謝調節によると、「AmCyan,ZsYellow,ECFP,EYFPの4種類の蛍光たんぱく質を用いてFRETペアの検討を行い、AmCyan/EYFPの新たな2分子FRETペアを見出した。」とあるから、そこそこよさそうです。
結構コアな内容の論文を全訳付きで解説している殊勝なブログである。
それにならって、ちょっと一人で勉強したことを備忘録がてらに一人勉強会としてまとめておいた。お題はFRETである。
FRETとは、Wikipediaによると、蛍光(フェルスター)共鳴エネルギー移動(Fluorescence resonance energy transfer)のことであり、
難しく言うと「近接した2個の色素分子(または発色団)の間で励起エネルギーが、電磁波にならず電子の共鳴により直接移動する現象。このため、一方の分子(供与体)で吸収された光のエネルギーによって他方の分子(受容体)にエネルギーが移動し、受容体が蛍光分子の場合は受容体から蛍光が放射される。」
生物分野では基本的には蛍光タンパクを使ったバイオセンサーに利用されることが多く、その場合ざっくりいうと、
二つの蛍光タンパクが適度な距離かつ適切な方向で並んでいるときに、片方が励起されると、もう片方が励起されていないのに蛍光を発する現象である。
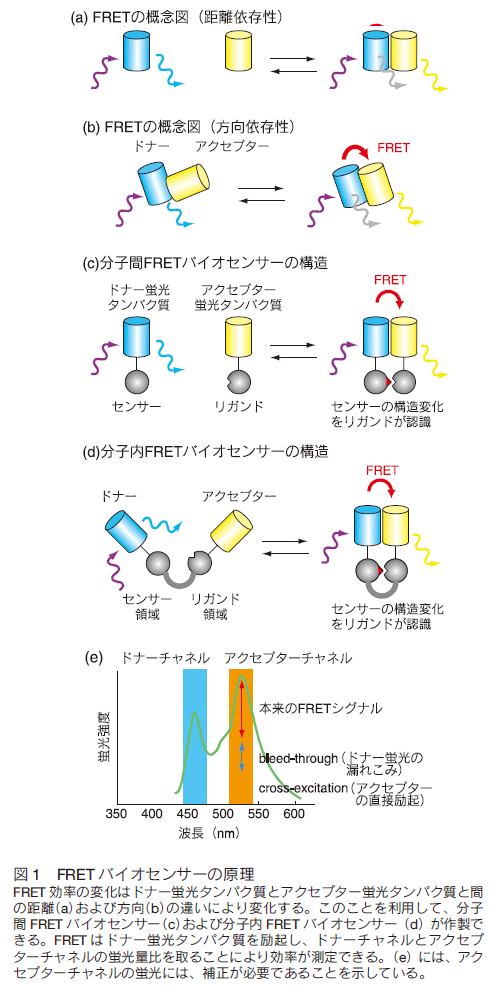
(松田道行先生のレビューより)
詳しくはこの分野の第一人者である松田道行先生のレビューを参照するとよいが、こうした現象を利用して、タンパクの結合やシグナル伝達分子の活性化をモニターするバイオセンサーがいくつもつくられている。
私もこうしたバイオセンサーを最近利用しようとして今勉強中なのだが、
このバイオセンサーの特徴は次のようなものになるらしい。
1)二つの蛍光タンパク分子を使う分子間型バイオセンサーと二つの蛍光分子が一つのタンパク内にある分子間型バイオセンサーがある。
分子間型は作るのが非常に大変なようである。
2)二つの蛍光物質の最適な組み合わせは
ECFPとYpetである。
ECFPの代わりにAmcyan, TFP,CFP
Ypetの代わりにYFP, Venus
なども用いられる。
http://comtec.semrock.com/Catalog/SetDetails.aspx?SetBasePartID=143&CategoryID=20
3)リンカー部位がセンサーとしての効率にかなり寄与する。
松田先生に言わせると
「FRET バイオセンサーを見ると、リガンド領域とセンサー領域が結合した際に FRET 効率が上昇するものと下降するものに二分される。距離が主たる影響を与えているものと、方向性が主たる影響を与えているものがあるからだと解釈されている。論文中に記載されていることはほとんどないが、実際のところは、作ってみないとこのどちらのタイプになるかはわからない」
らしい。

(松田道行先生のレビューより)
4)安定株ができにくい
この部分が一番重要なのだが、レトロウィルスベクターやレンチウィルスベクターを用いてセンサーを導入しても、「おそらく逆転写反応の際に (同じオワンクラゲ由来で遺伝子の似ている)CFP 遺伝子と YFP 遺伝子との間の組換えが起きて、CFP もしくは YFP のみしか光らなくなるものが大部分である」(上記レビューより)というらしい。
これに関してはCFPとは由来の違うサンゴ由来のTFPを使うと組み換えが起こらず安定細胞株が楽に作成できるらしい(レビュー及びMol Biol Cell. 2010 Mar 15;21(6):1088-96参照)。ただTFPの場合はFRET効率がだいぶ低くなってしまうらしい。
また piggyBac トランスポゾンを使う方法というのも有効であるらしい。
これに関しては、semrockというメーカーのサイトにコンパチブルな組み合わせとして
CFP (cyan GFP), CyPet, AmCyan, AmCyan1,
YFP (yellow GFP), YPet, Venus
紹介されているから、
やはりサンゴ由来のAmcyanとクラゲ由来のYFPもしくはmVenusという組み合わせが取れるのではないかと思う(*)。
現在検討中のバイオセンサーは、こうした注意点を既存のものを改良する形である。いいツールができるればよいな。。
(*)その後調べたところ、
Amcyanはaggregationを作りやすいのでmTFP1の方が良いという文献Quantitative Comparison of Different Fluorescent Protein Couples for Fast FRET-FLIM AcquisitionやmTFP1が一番というブログあった。
ただいくつかの例で、Amcyan-YFPでFRETを観察している例があるので、そんなに悪い組み合わせではないと思う。
JCS February 1, 2014 vol. 127 no. 3 583-598
Molecular Pharmacology December 2011 vol. 80 no. 6 1147-1155
特に2つ目の例は、胆汁酸応答分子の分子内及び分子間活性化制御機構と生理代謝調節によると、「AmCyan,ZsYellow,ECFP,EYFPの4種類の蛍光たんぱく質を用いてFRETペアの検討を行い、AmCyan/EYFPの新たな2分子FRETペアを見出した。」とあるから、そこそこよさそうです。