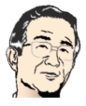25日、大阪市立大学 文化交流センター「専門家講座 2月」 マスコミコース《新聞で宝塚と大阪を語る》の1回目「宝塚歌劇100年への道」を受講しました。講師は、産経新聞社文化部の平松 澄子さんです。平松さんは、宝塚をはじめミュージカル中心に記事を書いているそうです。
1914(大正3)年に宝塚少女歌劇公演開始以来、昨年で95周年を迎えました。平松さんは、宝塚歌劇95年の歴史と魅力を熱く語りました。出演者は綺麗で若い魅力があるそうです。男性も遠慮せずに観に行くと良いとおっしゃっていました。詳細は[こちら]をご覧下さい。
1914(大正3)年に宝塚少女歌劇公演開始以来、昨年で95周年を迎えました。平松さんは、宝塚歌劇95年の歴史と魅力を熱く語りました。出演者は綺麗で若い魅力があるそうです。男性も遠慮せずに観に行くと良いとおっしゃっていました。詳細は[こちら]をご覧下さい。