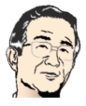11日追手門学院大阪城スクエアで、「大阪文化の深読み講座」第2回「大阪の宗教空間」を受講しました。講師は、大阪城天守閣研究主幹 北川央さんです。内容は以下の通りです。
1、生國魂神社 と坐摩神社
・生國魂神社と坐摩神社は伊勢神宮成立以前のわが国の国家神。生國魂神社は「大八洲 霊 わが国の土の霊魂を祀り、坐摩神社は「大宮地 の霊 」、すなわち大王(天皇)の宮殿が営まれる土地の守護霊を祀る。両神社の祭神は、「宮中神卅六座 」に数えられ、宮中においても、「生島の巫 」「坐摩の巫 」と呼ばれる専門の巫女が」いて奉仕した。
・生國魂神社は、大化の改新(645)で孝徳天皇が遷都した難波長柄豊碕宮 の近傍に鎮座し、室町時代後期には現在の大阪城地にあった大坂(石山)本願寺に近接して鎮座した。
・羽柴(豊臣)秀吉による大坂築城、それにともなう城下町建設、また大坂城の拡張工事などによって、生國魂神社も坐摩神社も遷座。
・坐摩神社の社地は同神社の「行宮」となり、江戸時代の大坂城本丸には生國魂神社の神木とされる「生玉の松」があった。
2、四天王寺とその周辺
・四天王寺は聖徳太子により創建された。南大門・中門・五重塔・金堂・講堂が南北に一直線に並ぶ伽藍で、配置は四天王寺式伽藍配置と呼ばれる。本尊は救世観音。
・多くの子院と周辺には七宮が鎮座。
・太子信仰の聖地。
・浄土信仰の聖地。
3、熊野神社と渡辺別所
・渡辺津を起点とする熊野街道。
・上町台地には、窪津(渡辺)王子、坂口王子、郡戸王子、上野王子、安倍王子が鎮座。
・渡辺津にあった渡辺浄土堂は、重源が諸国に設けた七別所の一つである渡辺別所の中心施設。⇒渡辺津から四天王寺周辺に至る上町台地一帯が浄土信仰の聖地になった。
4、浄土真宗の本拠
・明応5年(1946)本願寺八世蓮如が現在の大阪城地に大坂(石山)御坊を建立。この大坂御坊はやがて本願寺本山となり、大坂は本願寺王国の首都に。
・大坂本願寺は10年にわたる織田信長との戦争の結果、大坂を退去。紀州鷺森、泉州貝塚を経て、天正14年(1586)にはいちど大坂
・天満に戻ってくるが、文禄元年(1592)京都・七条堀川(現、西本願寺)に移転。江戸時代には、船場の西本願寺津村別院(北御堂)、東本願寺難波別院(南御堂)が浄土真宗の拠点。
5、寺町
・羽柴(豊臣)秀吉の大坂築城にともなう城下町建設で成立。わが国初の「寺町」。
・圧倒的多数を占める浄土宗寺院。一方で、浄土真宗寺院が一ケ寺もないのが大きな特徴。
・都市巡礼の場。
・さまざまな庶民信仰の場。
・七墓巡り。
講義の後、北川央さんと高島幸次さん(大阪大学CSCD招聘教授、追手門学院大阪城スクエア企画アドバイザー)の対談がありました。
1、
・生國魂神社と坐摩神社は伊勢神宮成立以前のわが国の国家神。生國魂神社は「
・生國魂神社は、大化の改新(645)で孝徳天皇が遷都した
・羽柴(豊臣)秀吉による大坂築城、それにともなう城下町建設、また大坂城の拡張工事などによって、生國魂神社も坐摩神社も遷座。
・坐摩神社の社地は同神社の「行宮」となり、江戸時代の大坂城本丸には生國魂神社の神木とされる「生玉の松」があった。
2、四天王寺とその周辺
・四天王寺は聖徳太子により創建された。南大門・中門・五重塔・金堂・講堂が南北に一直線に並ぶ伽藍で、配置は四天王寺式伽藍配置と呼ばれる。本尊は救世観音。
・多くの子院と周辺には七宮が鎮座。
・太子信仰の聖地。
・浄土信仰の聖地。
3、熊野神社と渡辺別所
・渡辺津を起点とする熊野街道。
・上町台地には、窪津(渡辺)王子、坂口王子、郡戸王子、上野王子、安倍王子が鎮座。
・渡辺津にあった渡辺浄土堂は、重源が諸国に設けた七別所の一つである渡辺別所の中心施設。⇒渡辺津から四天王寺周辺に至る上町台地一帯が浄土信仰の聖地になった。
4、浄土真宗の本拠
・明応5年(1946)本願寺八世蓮如が現在の大阪城地に大坂(石山)御坊を建立。この大坂御坊はやがて本願寺本山となり、大坂は本願寺王国の首都に。
・大坂本願寺は10年にわたる織田信長との戦争の結果、大坂を退去。紀州鷺森、泉州貝塚を経て、天正14年(1586)にはいちど大坂
・天満に戻ってくるが、文禄元年(1592)京都・七条堀川(現、西本願寺)に移転。江戸時代には、船場の西本願寺津村別院(北御堂)、東本願寺難波別院(南御堂)が浄土真宗の拠点。
5、寺町
・羽柴(豊臣)秀吉の大坂築城にともなう城下町建設で成立。わが国初の「寺町」。
・圧倒的多数を占める浄土宗寺院。一方で、浄土真宗寺院が一ケ寺もないのが大きな特徴。
・都市巡礼の場。
・さまざまな庶民信仰の場。
・七墓巡り。
講義の後、北川央さんと高島幸次さん(大阪大学CSCD招聘教授、追手門学院大阪城スクエア企画アドバイザー)の対談がありました。