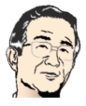2月24日、立命館大阪プロムナードセミナー 木津川計の一人語り劇場「『生きる』これから」を受講しました。いつもの通り会場は満席した。講義の内容は以下の通りです。
14時に木津川計さんが入場されました。会場は補助椅子も含めて満席でした。14時、会場が真っ暗になり、やがて明るくなり、木津川さんが登場しました。「大往生かポックリ死か」について講義を始めました。
若者は人生いかに生くべきかを真剣に考え模索する。一方、高齢者はいかに死ぬべきかを考えめぐらす。人生の終盤を迎えると、人間はその幕のひき方を考える。長生きして平穏に退場したい人は<大往生>したいと願う。だから、永六輔さんの『大往生』(岩波新書、1994~95)が大ベストセラーになった。
NHKで週一回レギュラー担当している「ラジオエッセイ」(関西エリア)で、永さんの『大往生』を参考に、大往生の条件を五つにまとめた。大往生の条件は、①苦しむことのない安らかな死 ②男は85歳以上、女性は90歳以上 ③悼まれる死 ④寝たっきりで一年まで ⑤身近な人に看取られる
ところが、④「寝たっきり一年まで」が長すぎる。私はコロッと逝きたいという人が少なからずいる。いわゆる「ポックリ死」を願う人たちがいる。ポックリ死の条件は、張りのある日常を送ること。(1)趣味 (2)学習 (3)スポーツ (4)献身
『婦人公論』(2010年9月号)に、埼玉県帯津三敬病院名誉院長・帯津良一氏が「ポックリ逝くための7つの習慣」を載せている(詳細省略)。病院では年間100人以上の患者が亡くなるが、たとえ病気になっても、自分の生命エネルギー高めることを最後まで意識してきた人は、みな間違いなく「ポックリ」と逝き、いい死に顔である。
木津川さんが「1952年、黒澤明監督の『生きる』を語り始めました。
主人公は市役所で市民課長を務める渡辺勘治。毎日変わりのない日常を過ごし、黙々と仕事をするばかり。そんな時、身体の不調を感じ病院に行き、自分が胃がんであることを知る。あまり時間が残されていないことを知った渡辺は、これまでの人生を考えて苦悩する。
初めて欠勤をし、貯金から5万円をおろし夜の街を歩く。知り合った小説家と遊び回るも空しい気持ちが残る。偶然、街で出会った同僚の女性 小田切とよと何度か食事を一緒にする中で、その若さ・生命力に魅かれていく。渡辺は、とよに胃がんであること・生き方への悩みを告げる。そこで、とよから「何か作ってみたら?」と提案され、渡辺の新たな人生が始まる。
数日ぶりに出勤し、渡辺は人が変わったように仕事に打ちこみだす。以前から、たらいまわしにされていた公園建設に精力的に取りくみ、各方面に粘り強く交渉し、公園の完成を目指す。やがて命をかけた努力が実り公園が完成する。ある雪のふる晩、その公園のブランコに座り揺られながら、渡辺は息を引き取る。
公園を作ることを目標に、命をささげた。渡辺は大往生ではないが、ポックリ死に近い満足な死であった。
14時に木津川計さんが入場されました。会場は補助椅子も含めて満席でした。14時、会場が真っ暗になり、やがて明るくなり、木津川さんが登場しました。「大往生かポックリ死か」について講義を始めました。
若者は人生いかに生くべきかを真剣に考え模索する。一方、高齢者はいかに死ぬべきかを考えめぐらす。人生の終盤を迎えると、人間はその幕のひき方を考える。長生きして平穏に退場したい人は<大往生>したいと願う。だから、永六輔さんの『大往生』(岩波新書、1994~95)が大ベストセラーになった。
NHKで週一回レギュラー担当している「ラジオエッセイ」(関西エリア)で、永さんの『大往生』を参考に、大往生の条件を五つにまとめた。大往生の条件は、①苦しむことのない安らかな死 ②男は85歳以上、女性は90歳以上 ③悼まれる死 ④寝たっきりで一年まで ⑤身近な人に看取られる
ところが、④「寝たっきり一年まで」が長すぎる。私はコロッと逝きたいという人が少なからずいる。いわゆる「ポックリ死」を願う人たちがいる。ポックリ死の条件は、張りのある日常を送ること。(1)趣味 (2)学習 (3)スポーツ (4)献身
『婦人公論』(2010年9月号)に、埼玉県帯津三敬病院名誉院長・帯津良一氏が「ポックリ逝くための7つの習慣」を載せている(詳細省略)。病院では年間100人以上の患者が亡くなるが、たとえ病気になっても、自分の生命エネルギー高めることを最後まで意識してきた人は、みな間違いなく「ポックリ」と逝き、いい死に顔である。
木津川さんが「1952年、黒澤明監督の『生きる』を語り始めました。
主人公は市役所で市民課長を務める渡辺勘治。毎日変わりのない日常を過ごし、黙々と仕事をするばかり。そんな時、身体の不調を感じ病院に行き、自分が胃がんであることを知る。あまり時間が残されていないことを知った渡辺は、これまでの人生を考えて苦悩する。
初めて欠勤をし、貯金から5万円をおろし夜の街を歩く。知り合った小説家と遊び回るも空しい気持ちが残る。偶然、街で出会った同僚の女性 小田切とよと何度か食事を一緒にする中で、その若さ・生命力に魅かれていく。渡辺は、とよに胃がんであること・生き方への悩みを告げる。そこで、とよから「何か作ってみたら?」と提案され、渡辺の新たな人生が始まる。
数日ぶりに出勤し、渡辺は人が変わったように仕事に打ちこみだす。以前から、たらいまわしにされていた公園建設に精力的に取りくみ、各方面に粘り強く交渉し、公園の完成を目指す。やがて命をかけた努力が実り公園が完成する。ある雪のふる晩、その公園のブランコに座り揺られながら、渡辺は息を引き取る。
公園を作ることを目標に、命をささげた。渡辺は大往生ではないが、ポックリ死に近い満足な死であった。