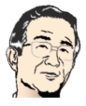25日(日)13時から16時30分まで淀川区役所5階で開催された「ものがたりの’ちから’~人の流れ、川の流れ、歴史・文化の流れ~」に参加しました。
人形劇公演や紙芝居、絵本の読み語り、かるた大会など、淀川区内で活動する団体やボランティア等が連携して、淀川の人や歴史・文化を感じることができるような「ものがたり」を様々な形で表現していました。
私は、かるた大会の手伝いを行いました。かるた大会では、淀川区コミュニティスタッフが作成した「淀川区わがまち 百景いろはかるた」が使用されました。10組(小学年低学年、小学校高学年、一般)に分かれてかるた大会を行い、最高枚数を取った2名の小学生にかるたが進呈されました。なお、かるたは会場でも販売されました。
人形劇公演や紙芝居、絵本の読み語り、かるた大会など、淀川区内で活動する団体やボランティア等が連携して、淀川の人や歴史・文化を感じることができるような「ものがたり」を様々な形で表現していました。
私は、かるた大会の手伝いを行いました。かるた大会では、淀川区コミュニティスタッフが作成した「淀川区わがまち 百景いろはかるた」が使用されました。10組(小学年低学年、小学校高学年、一般)に分かれてかるた大会を行い、最高枚数を取った2名の小学生にかるたが進呈されました。なお、かるたは会場でも販売されました。