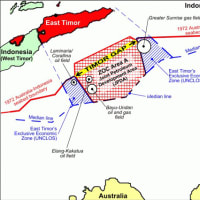──タンガニーカ湖畔──
 反乱軍のヤコブレフ40で快適な空の旅を楽しんだあと、我々「記者団」はカレミ(Kalemie)に着いた。
反乱軍のヤコブレフ40で快適な空の旅を楽しんだあと、我々「記者団」はカレミ(Kalemie)に着いた。
空港へ降り立つと反乱軍の車両で、我々は何もないタンガニーカ湖畔の砂浜へ運ばれた。
砂浜を歩いていくと、遠くに青いビニールシートが何ヶ所か広げられているのが見えた。砂浜を掘った穴も見える。さらに近づいていくと、シートの上には布に包まれた細長い塊がずらりと並べられていた。遠めにも、それが遺体であるとわかる。20体くらいだろうか。シートのところまでいくと、布が広げられた。異臭が鼻を衝く。砂にまみれ半分白骨化した遺体だ。

別のシートには、掘り出されたままの遺体が並べられていた。やはり砂にまみれ白骨化している。すべての遺体がほぼ同じ状態なので、同じ時期に埋められたことが分かる。虐殺されたのは、二ヶ月前だという。
掘り出されたのは、40体ほどだが、まだ発掘中のものもある。ほとんどの遺体が、後ろ手にきつく縛られていた。
反乱軍のコメントによると、ここでの虐殺はカビラ政府軍によって、三日間のあいだにおこなわれたらしい。軍人、市民問わず虐殺の対象となった。
ナイロビの爆弾テロ以降、遺体ばかり目にしている。あまりにも多くの遺体を目にしていると、次第に何も感じなくなる。そして「被写体」として淡々と写真を撮るようになってしまう。半腐乱半白骨化した遺体の30センチの近さからでも、平気で撮っていた。
かつてインドのベナレスで、犬が人間の遺体を食っているのをはじめて見たときは、顔をそらして二度と見ることができなかったのだが。
 砂浜に並べられた40体あまりの遺体を、淡々と撮り続ける自分に、少し戸惑いを感じた。
砂浜に並べられた40体あまりの遺体を、淡々と撮り続ける自分に、少し戸惑いを感じた。
目の前の遺体は、自然死ではない。おなじ人間に殺されたのだ。
しかし、そのときの僕には、あくまで「被写体」でしかなかった。AP通信のカメラマンもスイス人の若いフリーランスも、同じように淡々と仕事をこなした。
 報道写真家には、ある種の感覚麻痺がおこるのだろう。知らず知らずの間に、人の死に対して無感覚になってしまう。目の前の虐殺遺体が、単なる「被写体」と化すのは異常事態だ。自分は人間として何かが欠けてしまったのか、とも思った。でも、一瞬だ。つぎの一瞬には、アングルを変え、何度もシャッターを切っていた。
報道写真家には、ある種の感覚麻痺がおこるのだろう。知らず知らずの間に、人の死に対して無感覚になってしまう。目の前の虐殺遺体が、単なる「被写体」と化すのは異常事態だ。自分は人間として何かが欠けてしまったのか、とも思った。でも、一瞬だ。つぎの一瞬には、アングルを変え、何度もシャッターを切っていた。
しかし、一年後、僕は人の死を撮ることに苦痛を感じるようになった。苦痛というより、恐怖と言った方がいいのかもしれない。「僕もこの人のように死体になっていたのだろうか・・・」。遺体を前にすると、そう思ってしまう。ファインダーの中に、僕自身の遺体を見て震えてしまう。別に幻覚を見るわけではなく、観念的なものだ。人の命を奪うことがどれだけたやすく、そして殺される者の恐怖がどれだけ凄まじいかを知ってしまったからだろう。「この人は、あの凄まじい恐怖の中で殺されていったのか・・・」と、その恐怖を何度も体感してしまう。彼の恐怖は、僕の恐怖なのだ。彼の命は奪われ、僕はなぜ生き延びたのか。死と生に、とても混乱してしまう。しかし、それはまだ一年後のことだ。
 カメラマンと記者がそれぞれの仕事を終えるのを見計らって、反乱軍プレスセンター責任者ファストンは車に乗るように言った。いや、命令にちかい。
カメラマンと記者がそれぞれの仕事を終えるのを見計らって、反乱軍プレスセンター責任者ファストンは車に乗るように言った。いや、命令にちかい。
カビラ政府軍の攻撃で難民になった村人がいるので、そこへ案内するという。車に分乗し、少し離れた村の集会所のようなところへ案内された。集会所には300人ほどの人がいたが、難民となった人は全部で3500人。この人たちの村では112人が政府軍に殺害された。
しかし、お膳立てされた難民を前にしても、僕はとてもインタビューしようという気にはなれなかった。彼らが難民ではないとは思わなかったが、セットアップされた環境では、セットアップされたコメントしか出てこないものだ。
 そして、まだあった。次に案内されたのは、巨木にたたずむ二人の捕虜だ。
そして、まだあった。次に案内されたのは、巨木にたたずむ二人の捕虜だ。
流れ作業のような展開にうんざりし始めた。
ウガンダのメディアがインタビューをはじめた。その模様を何となく撮影した。
僕には、彼らが殺されることはないという確信めいたものがあった。彼らの表情にも、不安は読み取れない。そのかわり、何か、鋼鉄のような無を感じる。それは、彼らが運命を受け入れたからなのか、それとももっと別の理由からなのか・・・僕にはわからない。僕の「確信」は、単に戦争を知らない日本人の淡い希望なのだろうか。
戦争の前に、人間の運命はあまりにもはかない。
 反乱軍のヤコブレフ40で快適な空の旅を楽しんだあと、我々「記者団」はカレミ(Kalemie)に着いた。
反乱軍のヤコブレフ40で快適な空の旅を楽しんだあと、我々「記者団」はカレミ(Kalemie)に着いた。空港へ降り立つと反乱軍の車両で、我々は何もないタンガニーカ湖畔の砂浜へ運ばれた。
砂浜を歩いていくと、遠くに青いビニールシートが何ヶ所か広げられているのが見えた。砂浜を掘った穴も見える。さらに近づいていくと、シートの上には布に包まれた細長い塊がずらりと並べられていた。遠めにも、それが遺体であるとわかる。20体くらいだろうか。シートのところまでいくと、布が広げられた。異臭が鼻を衝く。砂にまみれ半分白骨化した遺体だ。

別のシートには、掘り出されたままの遺体が並べられていた。やはり砂にまみれ白骨化している。すべての遺体がほぼ同じ状態なので、同じ時期に埋められたことが分かる。虐殺されたのは、二ヶ月前だという。
掘り出されたのは、40体ほどだが、まだ発掘中のものもある。ほとんどの遺体が、後ろ手にきつく縛られていた。
反乱軍のコメントによると、ここでの虐殺はカビラ政府軍によって、三日間のあいだにおこなわれたらしい。軍人、市民問わず虐殺の対象となった。
ナイロビの爆弾テロ以降、遺体ばかり目にしている。あまりにも多くの遺体を目にしていると、次第に何も感じなくなる。そして「被写体」として淡々と写真を撮るようになってしまう。半腐乱半白骨化した遺体の30センチの近さからでも、平気で撮っていた。
かつてインドのベナレスで、犬が人間の遺体を食っているのをはじめて見たときは、顔をそらして二度と見ることができなかったのだが。
 砂浜に並べられた40体あまりの遺体を、淡々と撮り続ける自分に、少し戸惑いを感じた。
砂浜に並べられた40体あまりの遺体を、淡々と撮り続ける自分に、少し戸惑いを感じた。目の前の遺体は、自然死ではない。おなじ人間に殺されたのだ。
しかし、そのときの僕には、あくまで「被写体」でしかなかった。AP通信のカメラマンもスイス人の若いフリーランスも、同じように淡々と仕事をこなした。
 報道写真家には、ある種の感覚麻痺がおこるのだろう。知らず知らずの間に、人の死に対して無感覚になってしまう。目の前の虐殺遺体が、単なる「被写体」と化すのは異常事態だ。自分は人間として何かが欠けてしまったのか、とも思った。でも、一瞬だ。つぎの一瞬には、アングルを変え、何度もシャッターを切っていた。
報道写真家には、ある種の感覚麻痺がおこるのだろう。知らず知らずの間に、人の死に対して無感覚になってしまう。目の前の虐殺遺体が、単なる「被写体」と化すのは異常事態だ。自分は人間として何かが欠けてしまったのか、とも思った。でも、一瞬だ。つぎの一瞬には、アングルを変え、何度もシャッターを切っていた。しかし、一年後、僕は人の死を撮ることに苦痛を感じるようになった。苦痛というより、恐怖と言った方がいいのかもしれない。「僕もこの人のように死体になっていたのだろうか・・・」。遺体を前にすると、そう思ってしまう。ファインダーの中に、僕自身の遺体を見て震えてしまう。別に幻覚を見るわけではなく、観念的なものだ。人の命を奪うことがどれだけたやすく、そして殺される者の恐怖がどれだけ凄まじいかを知ってしまったからだろう。「この人は、あの凄まじい恐怖の中で殺されていったのか・・・」と、その恐怖を何度も体感してしまう。彼の恐怖は、僕の恐怖なのだ。彼の命は奪われ、僕はなぜ生き延びたのか。死と生に、とても混乱してしまう。しかし、それはまだ一年後のことだ。
 カメラマンと記者がそれぞれの仕事を終えるのを見計らって、反乱軍プレスセンター責任者ファストンは車に乗るように言った。いや、命令にちかい。
カメラマンと記者がそれぞれの仕事を終えるのを見計らって、反乱軍プレスセンター責任者ファストンは車に乗るように言った。いや、命令にちかい。カビラ政府軍の攻撃で難民になった村人がいるので、そこへ案内するという。車に分乗し、少し離れた村の集会所のようなところへ案内された。集会所には300人ほどの人がいたが、難民となった人は全部で3500人。この人たちの村では112人が政府軍に殺害された。
しかし、お膳立てされた難民を前にしても、僕はとてもインタビューしようという気にはなれなかった。彼らが難民ではないとは思わなかったが、セットアップされた環境では、セットアップされたコメントしか出てこないものだ。
 そして、まだあった。次に案内されたのは、巨木にたたずむ二人の捕虜だ。
そして、まだあった。次に案内されたのは、巨木にたたずむ二人の捕虜だ。流れ作業のような展開にうんざりし始めた。
ウガンダのメディアがインタビューをはじめた。その模様を何となく撮影した。
僕には、彼らが殺されることはないという確信めいたものがあった。彼らの表情にも、不安は読み取れない。そのかわり、何か、鋼鉄のような無を感じる。それは、彼らが運命を受け入れたからなのか、それとももっと別の理由からなのか・・・僕にはわからない。僕の「確信」は、単に戦争を知らない日本人の淡い希望なのだろうか。

戦争の前に、人間の運命はあまりにもはかない。