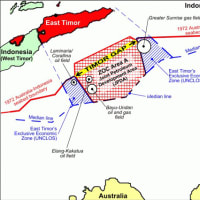──資源戦争──
我々の泊まったホテルには、食料がなかった。
キンドゥ(Kindu)についた翌日の朝、みんなで食料を持ち寄り、貧しい朝食をとった。まさか、食べ物がないなどとは思っていなかったので、食料を持ってきている者は少なかった。水すら満足になかった。前日も、我々はろくに食っていなかった。朝、みんなが飢え、渇いていた。
僕は、ナイロビの宿で早稲田の探検部の青年にもらったアメリカ製のエマージェンシー・フードを一袋持っていた。それを提供した。
みんなで、ささやかな食事をしていると、遠くから人が大勢歩いて来るのが見えた。ほとんどの人が、頭に大きな荷物を載せていた。あとからあとから人は流れてきた。
 すぐに、カメラを持って外に出た。
すぐに、カメラを持って外に出た。
通りを歩く住民は、戦闘が終わったことを知り、ジャングルから出てきて家に帰るところだった。町中の人々がジャングルに疎開していたのだ。町に入り、頭に荷物を載せたまま通りで立ち話をする女性が多かった。住民の表情は明るいとは言えなかった。戦闘が終わったものの、いつまた戦場になるかわからない。反乱軍は、キンドゥをどのように統治するのかもわからない。そんな複雑な表情だった。それでも不気味だった無人の街は、血液が流れたように生き返った。
僕とAPのカメラマン、スイス人のフリーランスとで、そのまま街をまわることにした。集合時間の10時までは十分時間があった。
キンドゥでの市街戦はなかったようだ。建物の損傷はほとんどなかった。唯一、道路に迫撃砲弾らしきあとを、ひとつ発見しただけだ。政府軍は、市街戦をすることなく撤退したようだ。住民にとっては、幸いであった。
 ホテルに戻る途中、頭に木箱を載せた集団に出くわした。どうも木箱は弾薬のようだった。迫撃砲弾を両手に持っている者もいる。集団の周りを反乱軍兵士が警備していた。かなりの弾薬の量だ。
ホテルに戻る途中、頭に木箱を載せた集団に出くわした。どうも木箱は弾薬のようだった。迫撃砲弾を両手に持っている者もいる。集団の周りを反乱軍兵士が警備していた。かなりの弾薬の量だ。
10時に、ホテルに戻ると、反乱軍プレスセンターの責任者ファストンが目を剥いて怒っていた。しかし、10時までホテルで待機しろとは指示されていない。彼は軍人ではないので、怒ってもあまり迫力はなかった。我々は、はいはい、ごめんねぇ、という感じで受け流した。短時間だったが、自由に町を歩き自由に写真を撮るのは快適だった。
11時に、トラックに乗り戦利品の取材へ。
さきほどの集団が運んでいたのは、この弾薬だった。郊外の建物の中に、おびただしい量の武器弾薬が運び込まれていた。政府軍が、打ち捨てていったものだ。政府軍は、よほど慌てていたのだろう。あるいは、武器を捨てて民間人に化けようとした者も多かったのかもしれない。
反乱軍によると、政府軍は非常に弱いということだが、あながちうそではないようだ。
 コンゴの内戦で、政府軍の主力となったのは、ジンバブエ、アンゴラ、ナミビアの外国軍だ。これら三国がコンゴ政府を支援するのは、コンゴ領内に利権を持っているからだ。
コンゴの内戦で、政府軍の主力となったのは、ジンバブエ、アンゴラ、ナミビアの外国軍だ。これら三国がコンゴ政府を支援するのは、コンゴ領内に利権を持っているからだ。
アンゴラはコンゴ民主共和国とコンゴ共和国の間に、アンゴラ領「カビンダ飛地」を持ち、ここに製油基地がある。ナミビアは、コンゴ南部のTshikapaでダイアモンド鉱山をアメリカの企業と共同運営している。ジンバブエもコンゴ内で企業を運営している。この三国は自国の利権を守るために、コンゴ政府の要請を受けて出兵してきた。そういう事情で、これら諸国の正規軍は、コンゴ正規軍よりも真剣であったのかもしれない。
周辺諸国の利権に加えて、欧米諸国や多国籍企業の利権もからみ、コンゴの内戦を複雑化長期化させることになった。

しかし僕がコンゴにいた当時は、利権国の部隊は、まだ戦線に到着していなかった。コンゴ政府軍の中身は、カビラ政権にうんざりしているコンゴ人部隊と、やる気のない傭兵が主体だった。そのため、政府軍は簡単に撃破される結果となった。反乱軍は、2ヶ月ほどの間に広大なコンゴ民主共和国の東半分を確保してしまった。
反乱軍が捕獲した多量の戦利品を取材したあと、またもや捕虜の取材となった。空き地に200人ほどの捕虜が集められていた。捕虜とは言うものの、彼らに緊迫感はなかった。
反乱軍によると、政府軍から軍事訓練を受けていたコンゴ人で、いまは、反乱軍に加わって戦うことを望んでいるということだった。
「彼らは捕虜じゃないね」
スイス人のフリーランス、マイケルが僕に耳打ちした。彼は、スイスのフランス語圏出身なので、ある程度彼らの会話を理解した。コンゴの公用語はフランス語だが、正確にはコンゴ訛りのベルギー・フレンチと言うべきものだ。そのためマイケルにも半分くらいしか理解できないようだった。
 反乱軍としては、内外に反乱の正当性を主張する必要がある。また、勢力を誇示する必要もある。政府軍による虐殺と、捕虜はそのための格好の材料なのだ。したがってこういう「ニセ捕虜」の演出も生まれてくる。
反乱軍としては、内外に反乱の正当性を主張する必要がある。また、勢力を誇示する必要もある。政府軍による虐殺と、捕虜はそのための格好の材料なのだ。したがってこういう「ニセ捕虜」の演出も生まれてくる。
反乱軍は勢力を誇示することによって、他国からの援助を期待していた。
コンゴの内戦は、巨大な利権のかかった資源戦争だ。
反乱軍が蜂起してまだ2カ月、特に欧米諸国や多国籍企業はコンゴの戦況から目が離せない時期だった。カビラ政府を援助した方が得なのか、それとも反乱軍を援助した方が得なのか。通信社の発信するニュースにかじりついている者が大勢いたはずだ。
ただ、一番賢いやり方は、言うまでもなく両方援助することだ。政府軍が勝っても、あるいは戦線が膠着状態でも、常に利益を得られる。
無政府状態の方が、都合のよい人たちもいる。コンゴでどれくらいのダイヤモンドが採掘され、それがどういうルートで誰の手に渡っているか、ほとんど把握されていない。
国連は、デビアスなどのダイヤモンド関連会社が、コンゴでのダイヤ略奪を煽っていると非難したこともある。
 ただ反乱軍としては、国の半分を維持支配すれば十分といえる。政府を倒して政権を取ってしまえば、国家を運営しなければならない。
ただ反乱軍としては、国の半分を維持支配すれば十分といえる。政府を倒して政権を取ってしまえば、国家を運営しなければならない。
しかし国の東半分を支配している限り、法の支配も国際社会の監視も受けず、また住民の福利厚生を行う必要もなく、ただひたすら天然資源から得られる利益を独占できる。国際社会には、カビラ腐敗政権を打倒して民主国家を実現する、と言えば名目は立つ。
ローラン・カビラ大統領自身が、何十年にも渡り「反政府勢力」として、莫大な利益を得てきたのだが、カビラは最終的に国を丸ごと望んだために自滅した。カビラ大統領は、2001年1月、自分のボディ・ガードに撃ち殺された。
カビラの息子のジョゼフ・カビラが現在の大統領だ。選挙は行われていない。ただ、父親と違って独裁色は濃くない。反乱軍を支援するルワンダ大統領とも会談し、和平を進める姿勢を持っている。2002年に、ルワンダ政府はルワンダ軍の撤兵に合意した。ジョゼフ・カビラ大統領は、国連軍の派遣も受け入れた。
しかし、反乱軍の方はその後、さまざまな勢力に分裂し、それぞれの支配地域を死守している。話し合いによって、各勢力すべてと和平合意を取り付けることは、現実的に不可能だ。それぞれの勢力の背後には、利害を共有する国家や企業が存在する。
あくまでも、この戦争は資源争奪戦争だ。
資源を取り巻くあらゆる勢力、国家、企業が納得する条件など存在しない。奪ったもの勝ちであり、平等に仲良く分けるなどという観念はない。たとえ仲良く分けたとしても、コンゴ国民は最初から除外されている。それでは、たいした意味はない。もちろん、まず虐殺がなくなることが、先決ではある。しかし、戦乱による虐殺のあと、飢餓と貧困という更なる虐殺が待っているかもしれない。欧米の唱える和平とはそういうものだ。
国連も、最終的には大国の利益代表であり、大国の不利益になることなどしない。
コンゴはひたすら、資源を奪われ続ける。
そして、コンゴの人々は生活を奪われ続ける。
「捕虜」を取材した後、我々記者団はジェットに放り込まれ、ゴマへと送り返された。一泊二日のお膳立て取材だった。コンゴ民主共和国での取材は、結局のところ反乱軍のお膳立したものだけを見るというだけの結果に終わった。
そこで生きる人々とこころを通わせる機会は最後までなかった。人々と同じところに住み、同じものを食べ、同じ空気を吸う。そういうところから、僕は取材をしたい。
98年8月にはじまったコンゴの内戦で、すでに240万人が死亡している。
コンゴ内戦 完
我々の泊まったホテルには、食料がなかった。
キンドゥ(Kindu)についた翌日の朝、みんなで食料を持ち寄り、貧しい朝食をとった。まさか、食べ物がないなどとは思っていなかったので、食料を持ってきている者は少なかった。水すら満足になかった。前日も、我々はろくに食っていなかった。朝、みんなが飢え、渇いていた。
僕は、ナイロビの宿で早稲田の探検部の青年にもらったアメリカ製のエマージェンシー・フードを一袋持っていた。それを提供した。
みんなで、ささやかな食事をしていると、遠くから人が大勢歩いて来るのが見えた。ほとんどの人が、頭に大きな荷物を載せていた。あとからあとから人は流れてきた。
 すぐに、カメラを持って外に出た。
すぐに、カメラを持って外に出た。通りを歩く住民は、戦闘が終わったことを知り、ジャングルから出てきて家に帰るところだった。町中の人々がジャングルに疎開していたのだ。町に入り、頭に荷物を載せたまま通りで立ち話をする女性が多かった。住民の表情は明るいとは言えなかった。戦闘が終わったものの、いつまた戦場になるかわからない。反乱軍は、キンドゥをどのように統治するのかもわからない。そんな複雑な表情だった。それでも不気味だった無人の街は、血液が流れたように生き返った。
僕とAPのカメラマン、スイス人のフリーランスとで、そのまま街をまわることにした。集合時間の10時までは十分時間があった。
キンドゥでの市街戦はなかったようだ。建物の損傷はほとんどなかった。唯一、道路に迫撃砲弾らしきあとを、ひとつ発見しただけだ。政府軍は、市街戦をすることなく撤退したようだ。住民にとっては、幸いであった。
 ホテルに戻る途中、頭に木箱を載せた集団に出くわした。どうも木箱は弾薬のようだった。迫撃砲弾を両手に持っている者もいる。集団の周りを反乱軍兵士が警備していた。かなりの弾薬の量だ。
ホテルに戻る途中、頭に木箱を載せた集団に出くわした。どうも木箱は弾薬のようだった。迫撃砲弾を両手に持っている者もいる。集団の周りを反乱軍兵士が警備していた。かなりの弾薬の量だ。10時に、ホテルに戻ると、反乱軍プレスセンターの責任者ファストンが目を剥いて怒っていた。しかし、10時までホテルで待機しろとは指示されていない。彼は軍人ではないので、怒ってもあまり迫力はなかった。我々は、はいはい、ごめんねぇ、という感じで受け流した。短時間だったが、自由に町を歩き自由に写真を撮るのは快適だった。
11時に、トラックに乗り戦利品の取材へ。
さきほどの集団が運んでいたのは、この弾薬だった。郊外の建物の中に、おびただしい量の武器弾薬が運び込まれていた。政府軍が、打ち捨てていったものだ。政府軍は、よほど慌てていたのだろう。あるいは、武器を捨てて民間人に化けようとした者も多かったのかもしれない。
反乱軍によると、政府軍は非常に弱いということだが、あながちうそではないようだ。
 コンゴの内戦で、政府軍の主力となったのは、ジンバブエ、アンゴラ、ナミビアの外国軍だ。これら三国がコンゴ政府を支援するのは、コンゴ領内に利権を持っているからだ。
コンゴの内戦で、政府軍の主力となったのは、ジンバブエ、アンゴラ、ナミビアの外国軍だ。これら三国がコンゴ政府を支援するのは、コンゴ領内に利権を持っているからだ。アンゴラはコンゴ民主共和国とコンゴ共和国の間に、アンゴラ領「カビンダ飛地」を持ち、ここに製油基地がある。ナミビアは、コンゴ南部のTshikapaでダイアモンド鉱山をアメリカの企業と共同運営している。ジンバブエもコンゴ内で企業を運営している。この三国は自国の利権を守るために、コンゴ政府の要請を受けて出兵してきた。そういう事情で、これら諸国の正規軍は、コンゴ正規軍よりも真剣であったのかもしれない。
周辺諸国の利権に加えて、欧米諸国や多国籍企業の利権もからみ、コンゴの内戦を複雑化長期化させることになった。

しかし僕がコンゴにいた当時は、利権国の部隊は、まだ戦線に到着していなかった。コンゴ政府軍の中身は、カビラ政権にうんざりしているコンゴ人部隊と、やる気のない傭兵が主体だった。そのため、政府軍は簡単に撃破される結果となった。反乱軍は、2ヶ月ほどの間に広大なコンゴ民主共和国の東半分を確保してしまった。
反乱軍が捕獲した多量の戦利品を取材したあと、またもや捕虜の取材となった。空き地に200人ほどの捕虜が集められていた。捕虜とは言うものの、彼らに緊迫感はなかった。
反乱軍によると、政府軍から軍事訓練を受けていたコンゴ人で、いまは、反乱軍に加わって戦うことを望んでいるということだった。
「彼らは捕虜じゃないね」
スイス人のフリーランス、マイケルが僕に耳打ちした。彼は、スイスのフランス語圏出身なので、ある程度彼らの会話を理解した。コンゴの公用語はフランス語だが、正確にはコンゴ訛りのベルギー・フレンチと言うべきものだ。そのためマイケルにも半分くらいしか理解できないようだった。
 反乱軍としては、内外に反乱の正当性を主張する必要がある。また、勢力を誇示する必要もある。政府軍による虐殺と、捕虜はそのための格好の材料なのだ。したがってこういう「ニセ捕虜」の演出も生まれてくる。
反乱軍としては、内外に反乱の正当性を主張する必要がある。また、勢力を誇示する必要もある。政府軍による虐殺と、捕虜はそのための格好の材料なのだ。したがってこういう「ニセ捕虜」の演出も生まれてくる。反乱軍は勢力を誇示することによって、他国からの援助を期待していた。
コンゴの内戦は、巨大な利権のかかった資源戦争だ。
反乱軍が蜂起してまだ2カ月、特に欧米諸国や多国籍企業はコンゴの戦況から目が離せない時期だった。カビラ政府を援助した方が得なのか、それとも反乱軍を援助した方が得なのか。通信社の発信するニュースにかじりついている者が大勢いたはずだ。
ただ、一番賢いやり方は、言うまでもなく両方援助することだ。政府軍が勝っても、あるいは戦線が膠着状態でも、常に利益を得られる。
無政府状態の方が、都合のよい人たちもいる。コンゴでどれくらいのダイヤモンドが採掘され、それがどういうルートで誰の手に渡っているか、ほとんど把握されていない。
国連は、デビアスなどのダイヤモンド関連会社が、コンゴでのダイヤ略奪を煽っていると非難したこともある。
 ただ反乱軍としては、国の半分を維持支配すれば十分といえる。政府を倒して政権を取ってしまえば、国家を運営しなければならない。
ただ反乱軍としては、国の半分を維持支配すれば十分といえる。政府を倒して政権を取ってしまえば、国家を運営しなければならない。しかし国の東半分を支配している限り、法の支配も国際社会の監視も受けず、また住民の福利厚生を行う必要もなく、ただひたすら天然資源から得られる利益を独占できる。国際社会には、カビラ腐敗政権を打倒して民主国家を実現する、と言えば名目は立つ。
ローラン・カビラ大統領自身が、何十年にも渡り「反政府勢力」として、莫大な利益を得てきたのだが、カビラは最終的に国を丸ごと望んだために自滅した。カビラ大統領は、2001年1月、自分のボディ・ガードに撃ち殺された。
カビラの息子のジョゼフ・カビラが現在の大統領だ。選挙は行われていない。ただ、父親と違って独裁色は濃くない。反乱軍を支援するルワンダ大統領とも会談し、和平を進める姿勢を持っている。2002年に、ルワンダ政府はルワンダ軍の撤兵に合意した。ジョゼフ・カビラ大統領は、国連軍の派遣も受け入れた。
しかし、反乱軍の方はその後、さまざまな勢力に分裂し、それぞれの支配地域を死守している。話し合いによって、各勢力すべてと和平合意を取り付けることは、現実的に不可能だ。それぞれの勢力の背後には、利害を共有する国家や企業が存在する。
あくまでも、この戦争は資源争奪戦争だ。
資源を取り巻くあらゆる勢力、国家、企業が納得する条件など存在しない。奪ったもの勝ちであり、平等に仲良く分けるなどという観念はない。たとえ仲良く分けたとしても、コンゴ国民は最初から除外されている。それでは、たいした意味はない。もちろん、まず虐殺がなくなることが、先決ではある。しかし、戦乱による虐殺のあと、飢餓と貧困という更なる虐殺が待っているかもしれない。欧米の唱える和平とはそういうものだ。
国連も、最終的には大国の利益代表であり、大国の不利益になることなどしない。
コンゴはひたすら、資源を奪われ続ける。
そして、コンゴの人々は生活を奪われ続ける。
「捕虜」を取材した後、我々記者団はジェットに放り込まれ、ゴマへと送り返された。一泊二日のお膳立て取材だった。コンゴ民主共和国での取材は、結局のところ反乱軍のお膳立したものだけを見るというだけの結果に終わった。
そこで生きる人々とこころを通わせる機会は最後までなかった。人々と同じところに住み、同じものを食べ、同じ空気を吸う。そういうところから、僕は取材をしたい。
98年8月にはじまったコンゴの内戦で、すでに240万人が死亡している。
コンゴ内戦 完