
ほとんどがテント、もしくは青空だったが、
わずかながら、建物を利用した学校もあった。
ドアも窓も開け放たれていたのは、
避難のためだったのだろう。





















 崩壊したあとに簡易橋が架けられているが、激しく揺れる。
崩壊したあとに簡易橋が架けられているが、激しく揺れる。








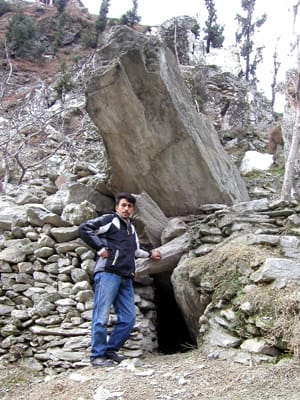 シェル・プルーフ(避難壕)。
シェル・プルーフ(避難壕)。



 画面右下に見える橋は、インド側に救援物資を運ぶために再建された。
画面右下に見える橋は、インド側に救援物資を運ぶために再建された。

 途中何ヶ所か崖崩れがある。
途中何ヶ所か崖崩れがある。 村まで二時間ほどの登り道。途中、休息をとる親子。
村まで二時間ほどの登り道。途中、休息をとる親子。

 いつ倒壊してもおかしくないであろう。住むためには、一度解体して組み直すしかない。
いつ倒壊してもおかしくないであろう。住むためには、一度解体して組み直すしかない。


 建物が倒壊したあと、巨石に直撃された家屋。住人はかろうじて避難。
建物が倒壊したあと、巨石に直撃された家屋。住人はかろうじて避難。 応急処置をほどこして人が住んでいる家屋。はたして安全なのかどうか。
応急処置をほどこして人が住んでいる家屋。はたして安全なのかどうか。



 崖の上は台地になっており、農地が広がっている。
崖の上は台地になっており、農地が広がっている。 対岸へはボートで渡る。
対岸へはボートで渡る。
 ダニマイサイバの家屋のほぼすべてが全壊。
ダニマイサイバの家屋のほぼすべてが全壊。



 崖下には、流された家屋の屋根も見える。
崖下には、流された家屋の屋根も見える。 崖の縁はかなり危険な状態にある。
崖の縁はかなり危険な状態にある。 川も土砂で完全に埋まってしまった。
川も土砂で完全に埋まってしまった。
