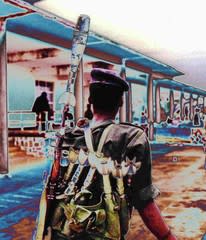英語の通じる地域へ取材に行くことはまずない。
どこへ行っても、一応、挨拶や数字、その他基本的な言葉は、ある程度は覚える。しかし、会話ができるほど習得できるわけではない。
したがって、現地で通訳を探さなければならない。しかし、プロの通訳を雇うほどの資金があるわけではないし、どこで通訳を求人できるかもわからない。だいたいがひっくり返ったような現場なので、人材紹介のような機関もない。いきおい、成り行き任せとなる。いなかったら仕方あるまいという感じだ。あまり積極的には求人できない。大手と同じくらいもらえると思われては困るから。相場もさっぱりわからない。こちらが払える限度内で承諾してくれる人に頼むことになる。
タリバーン政権下のアフガニスタンでは、外務省の役人が通訳となった。というより、プレスカードの発行条件として、外務省の通訳を雇うこと、と言い渡された。選択の余地がない。一日50ドル。ホテル、タクシー、通訳の費用が三日間で計454ドルにもなった。手持ちのドルキャッシュは1000ドルしかなかった。三日でカブールを退散したが、結局二週間しかアフガニスタンに滞在できなかった。
DRコンゴ(コンゴ民主共和国)では、ゴマに着くと、すぐに何人かの通訳志願者が宿を訪ねてきた。
すでにゴマからルワンダ人難民は帰還し、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)などの機関やNGOも引上げていた。これら国際機関が来ると、通訳や事務、警備、雑務などさまざまな職種が募集される。しかし、これらの機関の撤収とともに、雇用は失われる。
僕がゴマに着いたのは、そういう時期だった。耳が早いというか、三人が入れ代わるように宿を訪ねてきた。こういうことはめずらしい。最初にきたのは、内戦で学業の中断を余儀なくされた大学生だった。次に、外国人ジャーナリストの通訳経験のある中年のおじさん。それから、通訳の経験があるという二十代の男性。学生はエリート意識がみなぎっていて、協調性に欠けていた。学生を危険なところへ連れて行くのも、はばかられた。中年のおじさんは、いかにも場慣れし、オレにまかせておけ、という態度に少々不安を持った。アフガニスタンでの外務省の通訳は、僕の都合などお構いなしに、適当にこんなところを見せておけばいいだろう、という感じだった。それと、ダブるものを感じた。結局、一番控えめな三番手の志願者、ジャックを雇うことにした。が、結果は大失敗だった。

通訳の経験があるというのは、おそらくウソだった。別にそれは、かまわない。困るのは、取材が進むにつれ、ジャックの態度がだんだんでかくなっていったことだ。あげくのはては、「おい、奴を撮れ」などと、僕に命令しだした。あるときは、10項目ほどのインタビュー内容を、たった五行のメモですまされたこともある。捕虜となったルワンダ人ゲリラを取材したとき、ジャックは、まるで自分の捕虜であるかのような態度をとった。血管が切れそうになって、頭がクラクラした。
とんでもない奴を雇ってしまったと思ったが、すでに手遅れだ。陸の孤島では、解雇もできない。それが分かっているのか、いくら注意しても、ジャックの態度は改まらなかった。それどころか、勝手にどこかへ行って、何時間も帰ってこないこともあった。自分の見る目のなさを呪うしかない。
取材中に地元の人から、彼をいくらで雇ったのかと、何度か訊かれた。一日15ドルと答えると、誰もが顔を引きつらせた。そのときDRコンゴでは、一ヶ月50ドルあれば一家族が暮らせた。ジャックは、三日ごとに一ヶ月分の生活費を稼ぐことができたのだ。
普通に仕事をしてくれれば、一日15ドルは何でもない。しかし、ロクに仕事もしない、態度はでかい、勝手な行動をとる、そんな人物に、人も羨む賃金を払わねばならないのかと思うと、あまりいい気分ではなかった。もちろん、最後にきちんと支払った。12日×15ドル=180ドル。ジャックはホクホク顔だったが、でも、彼は知らなかった。途中からでも普通に仕事をしてくれていれば、僕は最後にボーナスを出すつもりでいたことを。
戦争をしているような現場で、完璧な仕事など最初から求めてはいない。多少の手抜きは、覚悟のうえだ。通信社ほどカネを出せるわけではないのだから。しかし、通訳がいなければ何もできないという、こちらの弱みにつけ込み、主従逆転現象まで起こされるのは、実に腹立たしい。ちなみに、一日50ドル以上出す通信社といえども、どうやら事情は似たようなものらしい。だいたい通訳の話となると、顔が歪む。
次からは、完璧な契約書を作るしかない、と思ったが、世の中、そう甘くはなかった。その後の東ティモールの取材でも、何人もの通訳に泣かされた。いつも、なめられて終わりだ。もちろん、それは、僕自身が甘いからだとは分かっている。

東ティモールでは、地元の友人の紹介でプロテスタントの若い牧師さんを雇ったことがある。UNTAET(ウンタエット:国連東ティモール暫定統治機構)時代の基準で、彼にサラリーを約束した。月220ドルだ。友人の紹介の牧師さんなので、契約書は失礼になると作らなかった。
普段の仕事は、地元新聞をざっと読んで、簡単に要約するという程度のものだった。ページ数の少ないタブロイドなので、記事数も少ない。しかし、牧師さんはひとしきり新聞を読むと、あとはたたんでしまう。そして、「あなたに必要なニュースはない」の一言で終わりだ。そ、そんな・・・。新聞を広げて、適当な記事を指し、これは何と書いてある、と訊くと牧師さんはいやいや訳しだす。連日こんな感じだった。訊かなければ、訳そうとしない。俗世間を知らない聖職者だから仕方がないか、と自分をごまかした。
その後、ある町へ行き、彼にこれからの取材の基本的な状況説明をした。武装襲撃で焼け落ちてから何年も経つ家を指して、
「この家に泊めてもらっていたときに、民兵の武装襲撃を受け、火を放たれ、銃弾を撃ちこまれ、そして65歳の家長(ヴェッリッシモ氏)が殺害された」
と僕は説明した。すると若い牧師さんは、両手をポケットに突っ込んだまま、
「65歳、イナッフ」
と言ってのけた。
一瞬、唖然としたが、そのときは、何も言わなかった。まだ取材もはじまっていない。個人的な感情は抑えた。数日後、取材がすべて終わってから、牧師さんに問い質した。
「この町に着いたとき、あなたはヴェリッシモ氏の殺害について、”65歳、イナッフ ”と言いましたね。イナッフとはどういう意味ですか?」
数日間の取材が終わり、のんきに構えていた彼は、少し狼狽して、
「つまり・・・彼は、いま・・・別の世界で新しい人生を送っているという意味です」
と言った。新しい人生?聖職者に対するいままでの敬意は薄れていった。
「うそだ!イナッフとはどういう意味で言ったのか、説明してほしい!」
「・・・・」
牧師さんは何も言わなかった。
「もし、あなたが65歳になったとき、民兵がやってきて、あなたを殺そうとしたら、イナッフと言って、平然と命を差し出すのか!」
僕は、少し興奮したが、牧師さんは、我関せずという表情だった。
もはや、こちらも言葉もない。
「ディリに戻っても、インタビューテープの翻訳は必要ありません。これまでの通訳料は日割りで計算してお支払いします」
とだけ付け加えた。

首都ディリに戻ってから、何か大きな文化的相違があるのだろうかと思って、紹介してくれた友人に、このことを報告した。東ティモールでは、24年におよぶインドネシアの武力支配下で、20万人が命を落としたと報告されている。人の死はもはや当たり前のことなのだろうか。平均寿命50年のこの島では、65年も生きれば、殺されても、もはやイナッフなことなのだろうか。
しかし、僕の説明に友人は呆れかえっていた。「彼は、大きな過ちを犯した」と。信者から、過ちを犯したと言われているようでは話にならない。
その後、僕は、気心の知れたこの友人を通訳に引っ張り出すことが多くなった。
65歳のヴェッリッシモ氏を殺害した襲撃事件に加わり、現在、刑務所に収監されている元民兵三人(殺害の実行犯ではない)へインタビューするときも彼に協力してもらった。
囚人三人の口は重かった。彼らも24年に及ぶインドネシア支配の犠牲者とも言える。犯罪の大物はみな安全なインドネシアで、悠々と暮らしている。だだっ広い部屋に流れる空気はひどく重かった。インタビューを終えたとき、友人は僕に、「少しだけ時間がほしい」と言った。
彼は囚人三人に、
「あなた達と、わたしは宗派は異なりますが、あなた達と家族のためにお祈りを捧げたいのですが」
と告げた。
友人は東ティモールではごく少数派のプロテスタントで、囚人三人は国教のカトリックだったが、彼らは申し出を受けた。閑散とした部屋に沈んでいる重い空気の中で、三人は彼の言葉を聞いた。
最後に、彼らにお礼を述べ、部屋を出た。
終始、かたくなな表情だった元民兵が、笑顔で見送ってくれた。











 虐殺と焦土作戦が開始される寸前の東ティモールから、僕は逃げた。
虐殺と焦土作戦が開始される寸前の東ティモールから、僕は逃げた。 そんなもの、できるわけがない。
そんなもの、できるわけがない。 99年に東ティモールでそういう体験をした。
99年に東ティモールでそういう体験をした。 この襲撃の中、家長のヴェリッシモ氏65歳が、民兵数人と格闘し、刀で滅多切りにあって惨殺された。この襲撃のとき、家の中には、僕を含めて8人が潜んでいた。しかし、我々は散り散りになり、互いのことがまったくわからなかった。ひとりひとりが、どん底の恐怖の中で、ただ、死の到来を待っていた。
この襲撃の中、家長のヴェリッシモ氏65歳が、民兵数人と格闘し、刀で滅多切りにあって惨殺された。この襲撃のとき、家の中には、僕を含めて8人が潜んでいた。しかし、我々は散り散りになり、互いのことがまったくわからなかった。ひとりひとりが、どん底の恐怖の中で、ただ、死の到来を待っていた。 英語の通じる地域へ取材に行くことはまずない。
英語の通じる地域へ取材に行くことはまずない。 通訳の経験があるというのは、おそらくウソだった。別にそれは、かまわない。困るのは、取材が進むにつれ、ジャックの態度がだんだんでかくなっていったことだ。あげくのはては、「おい、奴を撮れ」などと、僕に命令しだした。あるときは、10項目ほどのインタビュー内容を、たった五行のメモですまされたこともある。捕虜となったルワンダ人ゲリラを取材したとき、ジャックは、まるで自分の捕虜であるかのような態度をとった。血管が切れそうになって、頭がクラクラした。
通訳の経験があるというのは、おそらくウソだった。別にそれは、かまわない。困るのは、取材が進むにつれ、ジャックの態度がだんだんでかくなっていったことだ。あげくのはては、「おい、奴を撮れ」などと、僕に命令しだした。あるときは、10項目ほどのインタビュー内容を、たった五行のメモですまされたこともある。捕虜となったルワンダ人ゲリラを取材したとき、ジャックは、まるで自分の捕虜であるかのような態度をとった。血管が切れそうになって、頭がクラクラした。 東ティモールでは、地元の友人の紹介でプロテスタントの若い牧師さんを雇ったことがある。UNTAET(ウンタエット:国連東ティモール暫定統治機構)時代の基準で、彼にサラリーを約束した。月220ドルだ。友人の紹介の牧師さんなので、契約書は失礼になると作らなかった。
東ティモールでは、地元の友人の紹介でプロテスタントの若い牧師さんを雇ったことがある。UNTAET(ウンタエット:国連東ティモール暫定統治機構)時代の基準で、彼にサラリーを約束した。月220ドルだ。友人の紹介の牧師さんなので、契約書は失礼になると作らなかった。 首都ディリに戻ってから、何か大きな文化的相違があるのだろうかと思って、紹介してくれた友人に、このことを報告した。東ティモールでは、24年におよぶインドネシアの武力支配下で、20万人が命を落としたと報告されている。人の死はもはや当たり前のことなのだろうか。平均寿命50年のこの島では、65年も生きれば、殺されても、もはやイナッフなことなのだろうか。
首都ディリに戻ってから、何か大きな文化的相違があるのだろうかと思って、紹介してくれた友人に、このことを報告した。東ティモールでは、24年におよぶインドネシアの武力支配下で、20万人が命を落としたと報告されている。人の死はもはや当たり前のことなのだろうか。平均寿命50年のこの島では、65年も生きれば、殺されても、もはやイナッフなことなのだろうか。 万年赤字状態のため、取材費捻出はとても苦しい。
万年赤字状態のため、取材費捻出はとても苦しい。 別にそれが悪いとは言わない。売れるものは売ればいいと思う。しかし、「バブル期」に出版された書籍に、読む価値のあるものがいったいどれだけあるだろうか。出版界にとっても、本の売れないこの時代に降って沸いた好機だった。まさにバブルに乗って出版されたに過ぎない。
別にそれが悪いとは言わない。売れるものは売ればいいと思う。しかし、「バブル期」に出版された書籍に、読む価値のあるものがいったいどれだけあるだろうか。出版界にとっても、本の売れないこの時代に降って沸いた好機だった。まさにバブルに乗って出版されたに過ぎない。 取材には、ほぼすべてポジ(リバーサル)フィルムを持っていく。一般的には、スライドフィルムと呼ばれている。ポジで撮るのは、印刷を念頭においているからだ。ネガはプリント用で印刷には向かない。フィルム自体の性能としても、ポジの方が優れている。直接見る場合は透過光を使うので、透明感があり、とても美しい。
取材には、ほぼすべてポジ(リバーサル)フィルムを持っていく。一般的には、スライドフィルムと呼ばれている。ポジで撮るのは、印刷を念頭においているからだ。ネガはプリント用で印刷には向かない。フィルム自体の性能としても、ポジの方が優れている。直接見る場合は透過光を使うので、透明感があり、とても美しい。 速報性を要求される通信社や新聞社は、2000年ごろまでは、ネガフィルムを使っていた。簡単に現像できるからだ。
速報性を要求される通信社や新聞社は、2000年ごろまでは、ネガフィルムを使っていた。簡単に現像できるからだ。 報道の世界では、2000年あたりから、ほんの数年で銀塩フィルムからデジタルへと移行した。デジタルは、速報性こそが命の大手通信社、新聞社に革命的利便性をもたらした。いまや報道の世界はデジタル一色だ。
報道の世界では、2000年あたりから、ほんの数年で銀塩フィルムからデジタルへと移行した。デジタルは、速報性こそが命の大手通信社、新聞社に革命的利便性をもたらした。いまや報道の世界はデジタル一色だ。 報道カメラマンにとって、これが一番大事かもしれない。
報道カメラマンにとって、これが一番大事かもしれない。

 いままで、ツーリストビザしか取ったことがない。それでも、ちゃんと取材できる。
いままで、ツーリストビザしか取ったことがない。それでも、ちゃんと取材できる。