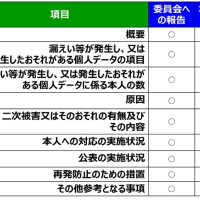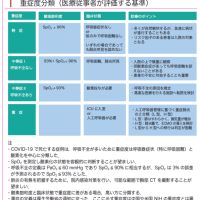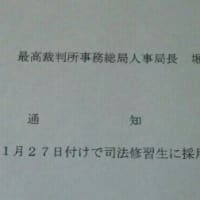何度も日曜答練刑訴法第3回の解説講義を聴いて理解できました。
刑訴法312条1項の「公訴事実の同一性」の意義について
訴因変更の要否
抽象的防御の利益、具体的防御の利益、縮小認定
これら3つを相互考慮して判断。
すなわち、
抽象的防御として、両訴因が被告人の不利益とならないか?
ならない場合(訴因変更不要)であっても、
具体的防御として、訴因変更をせずとも被告人の防御権に支障を来たさないか。
↓
防御権を来たすならば、訴因変更が必要といえる
さらに、縮小認定はそもそも被告人が検察官が掲げる訴因に対して防御した結果、裁判所の心証が訴因ではなく、防御した結果に落ち着く。
すなわち、被告人の防御が功を奏していないならば、縮小認定はそもそもあり得ない。
これらを総合的に判断すると、
抽象的に被告人の防御権が不利益になるか?
→不利益なら訴因変更必要の可能性
具体的に被告人の防御権が不利益になるか?
→不利益なら訴因変更必要の可能性
ということになり、
縮小認定は、被告人の具体的防御があり、これに応じた判決であれば、訴因変更をせずとも認定してかまわないとする意味である。
訴因変更の可否
同一性の判断
公訴事実の同一性が要求されるのは、一回的訴訟解決、被告人の防御権を害さないため。
両訴因の基本的部分が同一
これは、訴訟資料の流用+自然的社会的事実が同一かどうか
両訴因が択一的かどうか
これは、検察官の訴追意思の認定
この2つは、基本的部分が同一か、両訴因が択一関係かどうかを順番に考慮するのではなく、総合考慮すべき。
判例の覚せい剤事件も同様の結論。
ある日時→一定の範囲の日時
ある場所→一定の範囲の場所
特定の方法→何らかの方法
このような変更であって社会的自然的事実が同一でなくても、検察官が最終の一回の行為を訴追する意思であるならば、訴因変更は可能。
今後は、訴因変更の問題が出たら、このような流れで書いていこうと思います。
刑訴法312条1項の「公訴事実の同一性」の意義について
訴因変更の要否
抽象的防御の利益、具体的防御の利益、縮小認定
これら3つを相互考慮して判断。
すなわち、
抽象的防御として、両訴因が被告人の不利益とならないか?
ならない場合(訴因変更不要)であっても、
具体的防御として、訴因変更をせずとも被告人の防御権に支障を来たさないか。
↓
防御権を来たすならば、訴因変更が必要といえる
さらに、縮小認定はそもそも被告人が検察官が掲げる訴因に対して防御した結果、裁判所の心証が訴因ではなく、防御した結果に落ち着く。
すなわち、被告人の防御が功を奏していないならば、縮小認定はそもそもあり得ない。
これらを総合的に判断すると、
抽象的に被告人の防御権が不利益になるか?
→不利益なら訴因変更必要の可能性
具体的に被告人の防御権が不利益になるか?
→不利益なら訴因変更必要の可能性
ということになり、
縮小認定は、被告人の具体的防御があり、これに応じた判決であれば、訴因変更をせずとも認定してかまわないとする意味である。
訴因変更の可否
同一性の判断
公訴事実の同一性が要求されるのは、一回的訴訟解決、被告人の防御権を害さないため。
両訴因の基本的部分が同一
これは、訴訟資料の流用+自然的社会的事実が同一かどうか
両訴因が択一的かどうか
これは、検察官の訴追意思の認定
この2つは、基本的部分が同一か、両訴因が択一関係かどうかを順番に考慮するのではなく、総合考慮すべき。
判例の覚せい剤事件も同様の結論。
ある日時→一定の範囲の日時
ある場所→一定の範囲の場所
特定の方法→何らかの方法
このような変更であって社会的自然的事実が同一でなくても、検察官が最終の一回の行為を訴追する意思であるならば、訴因変更は可能。
今後は、訴因変更の問題が出たら、このような流れで書いていこうと思います。