 ここは鹿児島に住んでいる
ここは鹿児島に住んでいる物理学教授の自宅
ドイツ Hofheim-Instruments社の30センチドブソニアン望遠鏡を見せてもらった
ドブソニアンとは
米国のアマチュア天文家、ジョン・ドブソン氏が考えたもの
大口径の望遠鏡を、安価で軽量に作ったもの
欠点はたくさんあるが
なるべく大きな望遠鏡を
なるべく暗い星空を求めて移動して
なるべく気軽に
星を見て楽しむ事ができる
スグレモノである
考案者のドブソンさんは
今年の1月に亡くなられた
享年なんと98歳
ドブソニアン望遠鏡でもいろんなタイプがあり
実に様々
鹿児島に住んでいる私の高校時代の先輩であるS氏
最近
ドイツ製のドブソニアンを導入された
 中は精密機械なので
中は精密機械なのでショック吸収用のウレタンに囲まれていた
これをAとする
もうひとつ小さめの箱を持ってきた
これが、主鏡が入っている箱B
 蓋を開けてみた
蓋を開けてみたじゃん!
 「この、大きな鏡を見るだけでわくわくしますねぇ」
「この、大きな鏡を見るだけでわくわくしますねぇ」鏡の直径は30センチ
人の瞳の直径を7ミリとすると
300÷7=42.85 42.85を2乗すると
なんと
1837
実に、肉眼の1837倍の集光力をもつのである
通常、星を望遠鏡で見る場合
月や惑星などを除くと、極端に淡いものがほとんどである
その、暗くて淡い天体を
あるかないか、わからないようなものを探すのに
この集光力が役に立つのである
「ん?よく見ると、主鏡のうえに2つトッテの様なものが貼りついてますが…」
 尋ねてみると
尋ねてみるとどうも上にアクリルで出来たカバーがあるらしい
あまりにもカバーがきれいなのでわからなかった
もちろん
観測する時にそのカバーを外すらしい
上の写真
3つに分かれて鏡の回りに2つずつ肌色のボタンの様なものがある
それに
アルミで出来た棒をねじ込んでいくのである
 この作業は
この作業はすごく気を使うらしい
トラス構造をしているので、まっすぐ垂直ではない
微妙に傾いている
「ちょっとでも角度がちがうと、たちどころにねじ山壊して壊してしまうよー」
慎重にアルミ製の棒をセットしていく
 完了!
完了!つぎはまた箱Aにうつる
なにやら上にリング状のものがある
これを取りだし
 先ほどのアルミ棒の先端にセット
先ほどのアルミ棒の先端にセット これがまた
これがまたはめてしまうまで時間がかかった
微妙な力加減を要するらしく
やりにくいが
一人でしないと、やはりねじ山を破壊する可能性があるらしい
次は
箱Aの上にあった木の蓋
 左右に丸い切り込みがある
左右に丸い切り込みがあるどうもこれは
ただのバーツ入れの蓋ではなく
このドブソニアン望遠鏡の重要なバーツになるのだ!
さて
箱Aの中のパーツ、三日月の形をしたものを2つ
主鏡の箱の左右と取り付けた
 そろそろ完成かな?
そろそろ完成かな?先ほどの、箱Aのカバーだった
左右に円形の切り込みが2箇所あるところに
三日月の外周の部分を合わせて
合体!
 完成した!
完成した!いろいろとお話しながら組み立てたので10分くらい要したが
普通は5分程度で仕上がるようだ
このドブソニアン望遠鏡は
もちろん
山の上の最高の星空でのもとで観望するもの
晴れた日に
暗くなってパーツを持っていき
現地で組み立てるのである
本番前に何回か組み立ての練習をして
組み立てで失敗しないようにする
実に繊細なものである
ドブソニアンでもいろんな種類がメーカーから発売されている
組み立てが嫌な人は
もっと
最初から組み立ててある製品もあるのでそれを選べばいい
ただし
30センチもとなると長さは2メートル弱
車で運ぶにも
まず車内に入らないといけないのだが…
さて
今度はこれで星空を見せてもらおー
実に楽しみにである












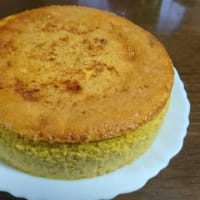
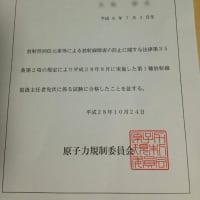
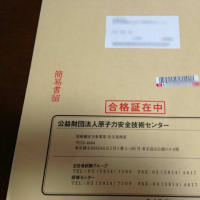






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます