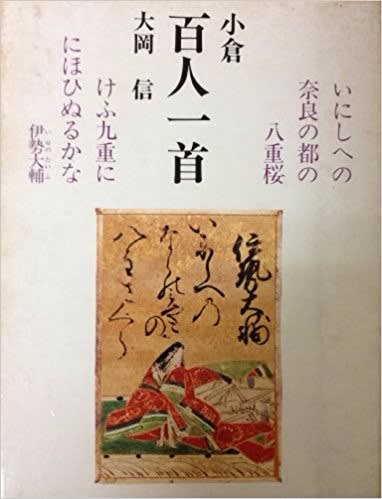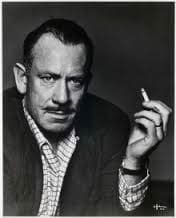今夏、芥川賞を受賞した
又吉直樹 さんについて、ちょっとミーハー的な自慢をさせてください。
受賞作
『火花』 は受賞前の三月にすでに出版されてますが、私は新聞広告が出てすぐに買いました。何となくこれは面白そうだというカンがはたらいたんですね。もちろん、ピース又吉ってお笑い芸人のことなど何も知りませんでした。そしたら七月になって見事に受賞したじゃないですか。そうしてみるみるうちに二百万部突破。
どうだ、俺って先見の明があるだろう、と、これだけの自慢で終われば、ほんとのミーハーですね。別に芥川賞もらったからとか、ミリオンセラーになったからとかで自慢してるわけじゃないんですよ。そんなこと、どうでもいいです。芥川賞って文藝春秋の賞で、この作品も文芸春秋刊。まあ、ほとんど初めから授賞は決まってたんでしょうな。
それはともかく、じつは私、この作品、半年間「つんどく」にしてました。少し暇ができたので、どんなもんかいなと思って今度読んでみたんです。そうしたら、
これ、なかなかの優れものですよ 。どういうところが優れてるか、あとで言います。
純文学系の小説作品をここ何年もほとんど読んでないので、全然大きなことは言えませんが、この作品は、近年の純文学界におけるかなりの収穫と言っていいんじゃないんでしょうか。とにかく、私のカンは間違ってなかったんです。買っておいて損しなかった(本体1200円)。
ちょっと小声で悪口。以前、いまや純文学界の重鎮とも目されている
赤坂真理 さんの
『東京プリズン』 (河出書房新社)を読んだんですが、紫式部文学賞、毎日出版文化賞、司馬遼太郎賞と、三つも賞もらってながら、ひとりよがりそのもので、神がどうのこうのと観念があっちこっち勝手に飛んで、おまけに純文系作家がよせばいいのに、戦後日米関係の歴史認識を持ち出し、いまや誰でも知ってる東京裁判についての誤解なんかをもったいぶって講釈したりして、ちっとも面白くなかった。いまの純文学界の権威主義を象徴しています。読み終えるのがとにかく苦痛でした。これは損しました(本体1800円)。
閑話休題。又吉作品についてもう一つ自慢。
読み始めてじきに、これって
太宰治 に似とるなあ、そうとう太宰の影響受けとるんちゃうか(なぜか関西弁)と感じたんですよ。そうしたらあるロングインタビューで、彼は太宰に心酔してきた経験を語ってるんですね。これもアタリ!
ゴロウ・デラックス 2015年8月13日 150813 芥川賞作家・又吉直樹SP!
VIDEO
(この動画は、一部音声が途切れます)
ちなみに何を隠そう、批評家としての私の処女作は太宰治論なんです(『太宰治の場所』弓立社)。私はおくてなくせに生意気で、高校時代に太宰を読んでも感心しなかったんですが、大学出てから、あるきっかけで読み返して、これ読み過ごしてた俺は文学がわかっちゃいなかったぞって痛感したんですね。それで、よし、批評で挑戦してやろうと思って書いたんです。で、これはとても生硬で読みづらい文章ではあるんですが、上の動画で又吉さんが太宰について言ってることとけっこう重なり合うんですよ。
この自慢もややミーハー的ですね。ここから先は自粛してもっぱら又吉さんを褒めることにします。
彼は
『人間失格』 を100回くらい読んだそうですが、さすがにその甲斐あって、まことに的確なことを言ってます。大意は次の通り。
この作品はふつう、こんなかわいそうな自分がこんなにつらい思いして生きてきたことが書かれていると受け取られるが、じつはそうではない。純粋で可愛くてまともな少女の歯痛ならだれもが同情するが、悪人の歯痛には自業自得だとして誰も同情しない。しかしその痛みそのものはどちらも同じだ。それと同じように、ある人が悩んでいると、多くの人は、世の中にはもっと苦しんでいて悩むことすらできないかわいそうな人がいるんだという比較を持ち出してきてその悩みを相手にしない。それは確かにその通りなんだけど、でもだからといってその人の悩みをないことにしなきゃいけないのか。そういうことが書かれている。
これじつに、福田恒存の言う「一匹と九十九匹と」と同じです。
私自身は、『人間失格』という作品はメッセージ性が強く出過ぎていて、太宰作品全体の中ではやや点数が低いと思ってるんですが、又吉さんの言ってることは、
文学の本質を分かりやすい言葉で見事に突いている と思います。文学には文学固有の存在意義があって、それを道徳的価値や政治的価値で推し量ってはいけないということですね。
また又吉さんは、太宰文学の魅力を問われて次のようなことも言ってます。
これも太宰批評としてとても的確で、太宰はいつも自己自身を戯画化することで、自分を見てる他者の目をきっちり取り込んでるんですね。この二重化された自意識のあり方が、まさに「面白いもの」を「たくさん」創作できる独特の構えにつながってると思うんです。例として挙げると
、『春の盗賊』『お伽草子』『親友交歓』『男女同権』『トカトントン』『女神』『新郎』『十二月八日』 など。
なお最後の二作は、パッケージとして太宰の本領発揮です。余計な老婆心かもしれませんが、『新郎』だけ読んで、日米開戦の報に接して厳粛な思いに浸る男性主人公にクソまじめに同化してしまわないように。あれもホント、これもホント。
さてここからようやく『火花』を批評してみたいと思うんですが、話は前段からつながってます。漫才や落語の話芸というのは、自己戯画化をどこまでできるかが勝負みたいなところがありますね。非常に知的センスが要求されると言ってもいい。ですから太宰文学と似てるんです。
私は又吉さんがどういう縁からお笑い芸人の道を選んだのか、その個人的事情については知りませんが、少なくとも内面的には、彼のこれまでの職業と、こういう太宰的な作品を書くことになった事態との必然的な関係があるように思います。
ちなみに彼の漫才、You Tubeで探しましたが、あまりいいのが見つかりませんでした。どなたか決定版でも教えてくれたら幸いです。初期のものは、ごくオーソドックスみたいだけど、相方が
綾部 に代わってからは、適応系と不適応系のコントラストでもたせてるようですね。これって、「地を演技へ向かって成熟させる」っていう彼の戦略なんでしょう。
とにかく、彼がシャイで、言葉少なで、非モテ・コンプレックスいっぱいで、ゆっくり口調で(つまりたいへん内面的で)、それを意識的にボケの条件にしてることは確かなようです。顔だけ見てるとけっこうイケメンだけど、身長が相当低いようで、そのアンバランスも売りなのかな?
『火花』は、四つ年上の漫才師・神谷さんに天才性を感じた「僕」が師弟関係を交わしてから、どっちもほとんど売れない何年間かの交流を描いたもの。神谷さんは、酔っ払って自己流の笑いの哲学をさかんに「僕」に説いたり、日常行動でもちょっと常軌を逸した漫才的振る舞いをやったり、生活力全然なくて優しく鷹揚な女性に依存しきってたり、とまあ、ありていに言って破滅型というヤツですね。
小池重明 という天才的なアマチュア棋士の伝記を
団鬼六 が書いたのを読んだことがありましたが、あれを連想しました。
「僕」は時々、彼の漫才哲学に違和感を感じることもあって議論を吹っ掛けたりもするんですが、究極のところで、この人こそ笑いの何たるかを知ってると何度も再確認して、どうしてもその魅力から離れられない。と同時に、自分は神谷さんにはやはりなれないという自覚がしだいに深まっていって、少しずつ違う道を行くしかないなと思うようになります。長くなるけど、そのギャップを感じ始める発端あたりの部分を引用してみましょう。合コンみたいな不慣れなことをしたときに神谷さんから、女の子たちの面前で、こいつは「盗聴が趣味や」と言われて傷つき(といっても心底傷ついてるわけでもない)、帰りの電車の中で神谷さん相手にそのことを問題にした後――
僕は周囲の人達から斜に構えていると捉えられることが多かった。緊張で顔が強張っているだけであっても、それは他者に興味を持っていないことの意思表示、もしくは好戦的な敵意と受け取られた。周りから「奴は朱に交わらず独自の道を進もうとしている」と半ば嘲りながら言われると、そんなことは露程も思っていなかったのに、いつの間にか自分でもそうしなければならないような気になり、少しずつ自分主義の言動が増えた。すると、その言動を証拠として周りがそれを信じ始める。ただし才能の部分は一切認めていないので残酷な評価になる。確固たる立脚点を持たぬまま芸人としての自分が形成されていく。そのように自分でも戸惑いつつも、あるいは、これこそが本当の自分なのではないかなどと右往左往するのである。つまり、僕は凄まじく面倒な奴だと認識されていた。
どうです。しっかり「純文学」してますね。前半の繊細な自己分析、これは自意識の強い不適応系の人が集団関係を生きなくてはならない場面に何度も直面してきた経験を踏まえて、そのときの自我の動きというものを緻密に追いかけてる部分です。そうして後半は、それを受けて、不器用どうしの「同病相憐れむ」感覚をよりどころにして神谷さんへの同化感情を自分に納得させていた今までのあり方にかすかに亀裂が入り始める描写です。
で、これってじつは、
自分はけっこうまともな部分も捨てられない人間 で、神谷さんのように意志的に(あるいは天性として)人々から逸(はぐ)れることを徹底できる人間じゃないんだということを覚っていく場面でもあると思うんです。
ここからは、又吉さんにこの作品を書かせた二つのモチーフが浮かんできます。一つは――こういう厄介な規定はあまりしたくないんですが、ほかに適切な言葉がないので――、彼はお笑い芸人としての経験を記述しつつ、その中に自分なりの
ビルドゥングス・ロマン の要素を込めようとしたのだということ、あの
『魔の山』のハンス・カストルプ のように。そしてもう一つは、神谷さんというキャラは、作者の投影としての「僕」にとって「笑い」の本質、つまり
規範からの逸脱と超越を究めた理想像 であって、そこには永遠にたどり着けない自分を知ったということ。
まあ、二つは同じことで、つまりは青年らしい理想の挫折が、この作品のメインテーマだと言ってもよいでしょう。私は初め、神谷さんにはモデルがいるのかな、と思ってましたが、読み終えてから、いや、これは又吉さんの純粋な造形に違いないと信じるようになりました。イメージがあまりにくっきりし過ぎているからです。
ちょっと結論を急ぎ過ぎました。
神谷さんは同棲していた女性に恋人ができたため、すでにその男がいる彼女のアパートから荷物を引き払わなきゃならなくなります。神谷さんは、「僕」に同行を頼むんですが、それだけじゃなくて、別れ際に哀しくなったり惨めになったりするのがいやだからなんか笑う材料がほしい、だから「僕」に勃起してくれと頼みます。おまえの股間を見たら笑えるだろう、と。僕はいやいやながら、ともかくエロ動画を携帯に取り込んでおきます。さてその現場。
真樹さん(神谷さんのこれまでの同居人――引用者注)は少し髪が伸びたように感じたが、下ろしているだけかもしれない。
文中、「あの男」というのはもちろん真樹さんの新しい恋人ですが、この男は風俗で真樹さんを見染めてから通い詰め、ついに真樹さんを口説き落とした肉体労働者風の男です。モトカレが来るというので、手ぐすね引いて待っていたようです。「
あの男の覚悟を、真樹さんの想いを、神谷さんなりの下手糞な優しさを、この美しい世界を僕は台無しにしなければならない。 」――いい文章ですね。
古典的です 。
やがて「僕」は、自分なりのスタイルを見つけて、けっこう有名になります。テレビにもたびたび出るようになる。一方神谷さんは奈落へと突っ走り、借金がかさみ、姿を隠したりするんですが、一年ほどしてからまた出てきて、「僕」と旧交を温めます。私は、神谷さんは死ぬんじゃないかと思ってたんですが、そうじゃありませんでした。ネタバレするので結末は言いませんが、やっぱりありきたりの悲劇にしないで、最後までこういうふうに笑いのノリで「To be continued」の雰囲気を余韻として残したほうがいいのかな、と今では思います。
「笑い」は続くんですよね。日常が続くのだから、どんな哀しい時間帯でも、首を絞められている苦しさから首を斜め横にひねるように、それは続かなくてはならない。
そう言えば、これを書いてる最中に、深夜テレビをつけてみたら、折よく、若いお笑い三人が以前書いた本(小説)を古参タレントの二人が取り上げて、いろんな賞を与えるという番組をやってました。もちろん又吉さんの受賞にあやかろうというギャグです。賞には五つあったんですけど、四つまでしか憶えてません。
①作中、自薦の一文を朗読して、名文に賞を与える――受賞したのは名文ではなく最もマンガ的な文章でした。
②ディスカウント賞――今、古本ネットで定価よりいくら下がっているか、一番差額が大きい人がもらえる。三人のうち二人までが1円でした。
③捨てるのもったいないで賞――自分の本を使って卓球の勝負をする――サイズの大きい本の勝ち、文庫本の負け。
④芥川賞――フラダンスのおばさん先生に読んでもらって真面目に判定してもらう。先生の名前は、芥川。
けっこう笑えました。こうして、小説は形の上だけでは終わりますが、やっぱり現実世界は、ネタが新しいネタを生んで続いていくんですね。
最後に、『火花』について、難点、というか気になるところを一つ。
風景描写などで、少し凝った重々しい名文調を使いすぎるように思います。出だしの部分などは、
横光利一 ばりの文体なんですが、全体にそれが貫かれているわけではないし、特に会話の部分が大阪弁の軽いノリで進むので、そこにちぐはぐさを感じました。この不統一感は、彫琢不足のなせるわざか、意識的か。意識的なら逆効果なので、たぶん前者なんでしょう。というのも、軽く、優しく、滑るような語り口のうちに深い課題を提出して見せる、というのが文学としてほんとにかっこいいことだと思うからです。太宰作品がそうであるように。
この記事を読んだ読者のみなさんが、じゃあ『火花』を読んでみようかと思ってくださることを祈ります。そして何よりも、
私の言葉が又吉さんご本人に届きますことを 。