「ベートーヴェンの交響曲」(金聖響+玉木正之)を読んだ。
私は演奏する側ではないので、よく分からないところが多い。
ただ、「指揮者」がどのようなことを考えて作品に向かい合っているのか、と
いうところが仄見えて、興味深かった。
「大指揮者」と括って、
フルトヴェングラー・トスカニーニからチェリビダッケなどに対して
批判的に見ているように感じた。
彼らを「勝手に演奏している」と評し、
「楽譜に帰る」ところに重点を置いているようなのだが、
個人的には疑問がある。
「楽譜通りに演奏する」のであれば、
指揮者による違いって何なのだろう。
結局、個々の指揮者の存在意義ってないんじゃないの?
(貴方、世の中に存在しなくても構わないんじゃないの?)
という感覚。
そこまで「楽譜」が具体的に記述されている訳でなく、
解釈が入るから完全に同一にはならない、
ということかも知れないが、
バラエティは小さくなるだろう。
その小さいバラエティの中で、こせこせ微妙な違いを主張されても、
聞く側としては「知ったことではない」と思うのだが。
私は演奏する側ではないので、よく分からないところが多い。
ただ、「指揮者」がどのようなことを考えて作品に向かい合っているのか、と
いうところが仄見えて、興味深かった。
「大指揮者」と括って、
フルトヴェングラー・トスカニーニからチェリビダッケなどに対して
批判的に見ているように感じた。
彼らを「勝手に演奏している」と評し、
「楽譜に帰る」ところに重点を置いているようなのだが、
個人的には疑問がある。
「楽譜通りに演奏する」のであれば、
指揮者による違いって何なのだろう。
結局、個々の指揮者の存在意義ってないんじゃないの?
(貴方、世の中に存在しなくても構わないんじゃないの?)
という感覚。
そこまで「楽譜」が具体的に記述されている訳でなく、
解釈が入るから完全に同一にはならない、
ということかも知れないが、
バラエティは小さくなるだろう。
その小さいバラエティの中で、こせこせ微妙な違いを主張されても、
聞く側としては「知ったことではない」と思うのだが。
















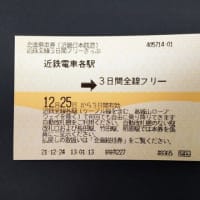
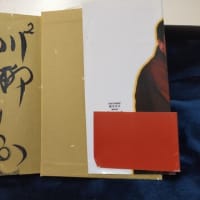

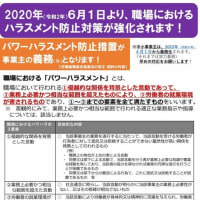








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます