
諏訪神社
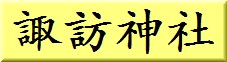
(すわじんじゃ)
神戸市須磨区須磨本町1-1-44

「須磨の天神さん」綱敷天満宮から道路を1本挟んで隣接している諏訪神社。
〔御祭神〕
建御名方神
(たけみなかたのかみ)
無実の罪で失脚、大宰府へと左遷される失意の旅の途中、船の針路を嵐に阻まれた菅原道真公が須磨に上陸してひと時の休息を求めたという故事から創建された綱敷天満宮。須磨を代表する神社のひとつとして広くその名を知られる綱敷天満宮の西側に、道を隔ててもう一つ神社が鎮座されている事に気付かれる方も多いのではないでしょうか。この神社は、建御雷神(たけみかづちのかみ)、経津主神(ふつぬしのみこと)と並んで日本三大軍神の一柱として崇敬を集める「武」の神・建御名方神(たけみなかたのかみ)を祀っている諏訪神社です。

境内は月極駐車場となっていますが、その中央に雰囲気のある社殿が鎮座しています。
創建時期については詳しいことは分かりませんが、一説には綱敷天満宮が創建されるよりも以前から須磨の地で祀られていたといわれています。「須磨」という地名は、摂津国の西端に位置する「隅(すみ)」の土地だということから「スミ」が訛って「スマ」となったという説、「住み良い土地」という意味の「栖間(すみま)」が訛ったものという説などが有力ですが、諏訪神社の「スワ」が訛ったものだという説もあります。そう考えると、かなり古くから「諏訪」の名を持つ神社が祀られていた可能性が考えられます。
東向きに建てられた社殿にちなんで「東向明神」とも呼ばれていた諏訪神社は、西須磨地域で古くから勢力を伸ばしていた名家である前田家・頼広家・友好家・貴答家・岡本家の5家によって奉祀され、守られてきました。また、長田神社が「漁」の守護神とされているのに対して諏訪神社は「狩」の守護神として人々の厚い崇敬を集めていたといい、「狩」の神に捧げる祭祀として、11月8日には猪狩の神事が執り行われ、猪肉を食べる習慣があったそうです。


境内入口の手水鉢(左)。ムクノキやウバメガシなどが枝を伸ばしています(右)。
アクセス
・JR「須磨駅」下車、東へ徒歩10分
・山陽電車「山陽須磨駅」下車、東へ徒歩8分
・山陽電車「須磨寺駅」下車、南へ徒歩3分
 諏訪神社地図 Copyright (C) 2000-2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.
諏訪神社地図 Copyright (C) 2000-2008 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved. 拝観料
・無料
拝観時間
・常時開放





















私がふと思ったのは、菅原道真公は偶然立ち寄ったのではなく、「諏訪神社」に立ち寄ったのでは?ということ。
菅原道真公は、スクナヒコナ神と一緒に、「天神社」に祀られていることが多いですが、武御名方神とも関係があるのか、と思うとわくわくしてきました。
またいろいろと教えてください。
ありがとうございました。