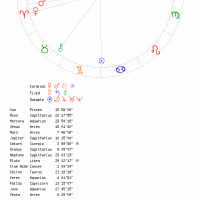孝生さんとの散歩は、すごく楽しかった。誰かと喋ってこんなに楽しいなんて、本当に久しぶりだった。
それ以上に、黙っている時、ひとりで先を歩いて振り返ると孝生さんが軽く手をあげて応えてくれた時が、何よりも嬉しかった。いつも見守られているような気がして。
「孝生さんも、もしかして俺の事、ちょっとは好きになってくれたのかなぁ」
好きどころか、性行為まで三浦は考えはじめているのだが、裕貴はさっぱり気づいていない。
男同士でセックスできるという知識があっても、それが自分に関わる可能性には思い至っていない。
裕貴から恋愛対象外の烙印を押されている三浦は、といえば、今は台所で昼食の準備をしていた。裕貴は庭掃除にひと段落ついたので、いったん切り上げて家の中に入った。
「お腹すいちゃった。ご飯は何?」
洗面所で手を洗い台所に入ると、カフェエプロン姿の三浦が鍋にパスタを投入していた。
「初めてだな。おまえが、腹減ったって言うのは」
「本当だ。お腹がすいた、なんて思うのは、久しぶりだ……」
裕貴は家族を失ってから食欲を覚えなくなっていた。
孝生さんとなかよくなったから……かな?
そう考えただけで裕貴の胸が温かくなり、三浦が好きだという想いが湧き上がる。
裕貴は黙って三浦が料理をする姿を見ていた。
ニンニクと鷹の爪を刻んでオリーブオイルを流したフライパンに入れる。そして昨晩から砂抜きをしていたアサリを投入し、白ワインをふりかける。
「孝生さんって、グルメっていうか、食べ物にこだわるよねぇ……」
「どうせ食べるなら、旨い物を食べたいんだ。幸い、作る時間はたっぷりある。手間暇かけて何が悪い」
「そうだね。会社勤めでもないみたいだし。――孝生さんは無職なの?」
口の開きはじめたアサリを見ながら質問する。三浦の職業は、裕貴にとって謎だった。
毎日二階にこもってるから、その時に何かしているんだろうけど……。
「違う」
「もしかして、ウェブ関係の仕事?」
「ノーコメント。詮索されるのは好きじゃない。おまえもそうだろう?」
「そうだね。お互い、余計な事は聞かない方がいいか」
興味はあるが、強引に聞き出すような真似はしない。裕貴が素直に引き下がると、三浦が『いい子だ』と褒めてくれたので、そっちの方が嬉しかった。
「孝生さん、大好き」
いい子と言われて喜ぶなんて、自分でも幼児返りしているのはわかっている。
しかし、頼りになる大人に遠慮なく甘えられる今の状態は、あまりにも居心地が良かった。
飼い犬っていいなぁと思いながらてらいなく愛を告げると、三浦がうんざりという顔をした。
「おまえ……。発言に好きとか愛とか、多くないか?」
「そう? 今は好きって言えるだけで嬉しいんだ。ちょっと前まで何を見ても何も感じなかったから」
裕貴の言葉を聞き、三浦が軽く眉を寄せる。
「僕は孝生さんが大好き。初めて会った時から好きになるって決めたんだ」
あの時の感情が甦り、思いつめた瞳で三浦を見つめた。裕貴の瞳に気圧されたように、三浦が視線を逸らす。
「好きになると決めたって……。そんな事、できるわけない」
「できる。孝生さんは命の恩人だからね。恩人を好きになるのは、とても簡単な事だよ」
「そう言われれば、そうかもな。俺は自殺しようと思った事などないからわからないが」
「あれは自殺じゃない。賭けだったんだよ」
「賭け……? 自分の命を賭けたって事か? なんだってまた、そんな事を?」
「……秘密」
「わかったよ」
三浦が肩をすくめて茹で上がったパスタをフライパンに入れた。手早くかきまぜればボンゴレの出来上がりだ。パスタの盛った皿を裕貴が持ち上げてリビングに運んだ。
そして、テーブルにボンゴレとコンソメスープ、そして緑黄色野菜に半熟ゆで卵を飾ったサラダが置かれ、食事となった。
L字型ソファの別々の辺に座る。裕貴が両手を合わせて『いただきます』と言うと『どうぞ』と声が返ってきた。
そんな当たり前の事がとても嬉しくて、パスタにも手をつけず、裕貴が三浦を見つめた。
「なんでこっちを見るんだ?」
「孝生さんを見てると、胸が温かくなるんだ。生きてて良かったな……って思う」
「大袈裟だな。俺なんかに、そんな価値はないぞ」
「わかってないなぁ、孝生さん。孝生さんの価値はね、僕が決めるの。僕が大好きだから、孝生さんにはそれだけの価値があるんだよ」
「随分偉そうに言うな。……本当にそうだといいんだが」
三浦の顔が歪んだ。照れるというより、自分を責めているような表情だった。
「そんな事より、さっさと食え。パスタがまずくなる」
ニンニクの効いたボンゴレパスタは、麺もいわゆるアルデンテで、その辺の店より、ずっとおいしい、と裕貴が思った。
孝生さんが作ったから……って点を割り引いても、やっぱりなんか違う。
「このパスタ、おいしいね。もちもちしてる」
「生だからな。一般的なパスタは乾麺だろう? これは乾燥させてないパスタ。賞味期限が短いのが難点だが、味はこっちの方が上だ」
「へぇ。そんなのがあるんだ」
「昨日買い物に行った時、ハムチーズの側にあった。覚えてないのか?」
「そうだっけ。僕、孝生さんばっかり見てたから、売り場の事はよく覚えてないんだ」
その瞬間、三浦がパスタを喉につまらせた。肩を揺らしながら、ゴホゴホとせき込む。
「大丈夫? 水飲む?」
裕貴の問いかけに、三浦がうなずいた。急いで台所に行きグラスとペットボトルを持って戻った。ボトルの中身をグラスに注いで、三浦に手渡す。
「はい、お水」
「すまない」
苦しげな声で礼を言うと、三浦がいっきに水を飲み干した。一息ついた三浦の背中を裕貴の手が上下する。
「触るな!」
まただ。また、拒絶された。どうして孝生さんは僕に触られるのを嫌うんだろう。
愛しているなら、愛する者の希望に沿う行動を取るのが『正解』なのだと思う。今までの裕貴の常識はそう告げていた。
でも――。
裕貴の脳裏に、さきほどの三浦の歪んだ顔が甦る。あの顔を思い出したら、手を離すのが正しい事とは思えなかった。
気がついたら、体が動いていた。三浦の体に腕を回して、脊中から抱き締める。
「孝生さん。僕を拒まないで。お願い」
「だから……っ。俺に触ると、おまえがいずれ後悔すると言ってるんだ」
「どうしてそんな事言うの? 触るとうつるような病気を持ってる……とか?」
「そんなんじゃない」
「だったらいいじゃない。背中をさするくらい」
「今は、抱きついてるだろう?」
苛立った声が返ってくる。このまま抱きついていたら『出て行け』と本気で言いかねないほど、三浦は怒りを露わにしていた。
怖い。孝生さんに、嫌われたくない。でも――。孝生さんは何か隠してる。そして、それは嫌な経験を思い出すからかもしれない。
心に傷を負った人間は、恐るべき嗅覚で同類を見つけ出す。裕貴が三浦に感じたのもそれだった。
でも、僕の悲しみは孝生さんに会う事で消えてしまった。少なくとも、孝生さんがいれば幸せなんだ。
孝生さんにも、同じように癒されてほしい。僕の存在で。
ううん。僕でダメなら他の誰でもいい。孝生さんの苦しみを取り去ってほしい。
けれど、この場にいるのは裕貴だけだった。
体中の気力をふり絞り、三浦を癒す事だけを考えて語りかけた。
「僕は孝生さんを好きだよ。絶対、嫌いにならない。教えて。孝生さんは、リクの事もそんな風に拒絶したの?」
「しない。するわけない」
「だったら、僕もリクと同じようにしてよ。僕はリクと同じなんだよ。あなたが好きって事しか考えられない」
「……」
「僕、本当に犬だったら良かった……。そうしたら、孝生さんに触れたのに。傍にいられるのに……。それなら僕は、犬になりたい。人間でいたくない」
心の底から犬になりたい、という言葉は、裕貴の真実であった。これまでは苦しみから逃げて犬になりたかったのだが、今は違う。犬だったら三浦を癒せたという思いからだ。
その想いが、言葉に重みを与え、三浦は裕貴の言葉を神妙な顔で聞いていた。
裕貴が口を閉ざし、リビングに沈黙が広がる。三浦は迷っているようだった。『いや……』『しかし』といったつぶやきを、時折もらす。
「……わかったから、離してくれ」
「やだ」
「おまえに首を絞められて、息が苦しいんだよ」
「ごっ、ごめんなさい!!」
慌てて裕貴が手の力を緩めた。三浦は大きく息を吐くと、胸元にある裕貴の腕に触れた。
「ほら、触ったぞ」
優しい声と三浦の方から触れたことで、裕貴の体から力が抜けた。
「おまえは俺に、どうしてほしいんだ」
裕貴の腕を外し、三浦が向きなおった。鋭い瞳が裕貴を射抜く。
どうしてこんな事をわざわざ聞くんだろう?
「普通に、むせたら脊中をさすったりとか、そういう事ができればいいよ」
「手を握れとか、そういう訳じゃないんだな?」
「それは恋人同士とか、親子がやる事でしょ? ……もしかして、孝生さん、僕にお手とかおかわりとか教えたいの?」
シリアスな場面であっても、裕貴のとぼけた発言は健在だった。いや、本人は至って真面目なだけなのだ。それだけに性質が悪い、と言えたが。
「まさか」
「だよね。それくらいできるもん」
「待て、だけは出来ないようだがな。触るなと言うのに、抱きつきやがって」
「それは……。孝生さんがつらそうだったから、なんとかしたいと思って……」
「つらい? 俺が?」
信じられない、という顔で三浦がおうむ返した。
そうか。孝生さん、自分がどんな顔しているか、気づいてなかったんだ……。
「触るなって言うたびね、つらい顔してた。僕は、孝生さんと出会えて幸せになれたから、孝生さんにも幸せになってほしい」
外された手を再び伸ばし、三浦の手に重ねた。
孝生さんが、少しでもつらい顔をしなくて済みますように。そう心から願いながら、三浦に愛情を込めたまなざしを向ける。
「わかったよ。これからは触っても怒らない。ただし、過剰なスキンシップはやめろよ」
そう言って、ぽんぽんと三浦がソファのシートを叩いた。
隣に座れって事?
裕貴が真夏のひまわりのように晴れやかな笑顔を浮かべた。そうして、いそいそと三浦の横に座ると、三浦が目を細めて懐かしそうな声で言った。
「リクも、こうやって何かと俺の傍にいたがったな。ソファに座れば足元にうずくまったし、仮眠を取ると体の上に乗って来た」
「こんなかんじ?」
裕貴がソファから降りて床の上に座った。ソファに半ば寄りかかりながら、三浦の太腿に頭を預ける。さすがに体の上に乗るのはハードルが高いので、裕貴なりに少しアレンジして足元にうずくまってみたのだ。
「そうだな。こんなかんじだった。構ってほしいというリクのアピールだから、俺はいつもこうやって背中を撫でてやった」
大きな手が裕貴の髪に触れた。温かな手に頭を撫でられ、吐息のように言葉がこぼれる。
「気持ち良い……」
「リクもそうだったのかもな。目をつぶって、うっとりした顔をした」
その時の事を思い出しているのか、三浦が遠い目をして手を動かした。裕貴もリクを見習って目を閉じる。
すごく、安心する。大好きな人に優しく撫でられるのは、なんて心地良いんだろう。
こどもの頃、父や母に抱かれた感覚にとてもよく似ていた。
「孝生さんって、お父さんみたい」
「俺はおまえみたいにでかいガキのいる年じゃないぞ」
「ごめんね。でも、同じくらい安心する」
「……百歩譲って保護者だな。飼い主だから、似たようなものか」
この瞬間、裕貴は三浦と心がつながったような気がした。
裕貴は三浦に癒され、三浦もまた、裕貴を癒す事で癒されている。とても不思議な時間だった。静かで、そして満ち足りた時間。
――このままずっと、このままいられればいいのに――
心の底から、裕貴が願った。夢のような幸福は、夢のように儚い。砂糖菓子を水に浸すように、あっという間に崩れ落ちてしまう。
そして、幸福な時間を破壊するチャイムが鳴った。