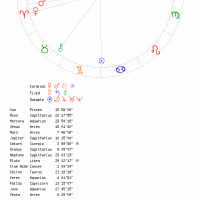「いいか。二階は俺のプライベートエリアだ。絶対に上がって来るな」
「わん」
「だから、それはやめろ。客用布団なんてないから、おまえはソファで寝ろ。それと、毛布は……これを使え」
三浦が古びた毛布を少年に手渡す。いかにも犬用というかんじの、分厚い茶色の毛布だ。
「クッションを枕にして……。他に必要な物はあるか?」
「わん」
ない、という風に首を振りながら返事をする。
あくまでも犬のフリを続ける少年に、三浦は絶句し、そして肩を落としてリビングを出て行った。
電源が落ち、ライトスタンドのほのかな明かりがリビングを照らす。静まり返った部屋に少年が、ひとり取り残された。少年は、ゆっくりと階段を上る足音に耳をそばだてる。
少年の名前は藍原裕貴(あいはら ゆうき)。二十一歳。少年、というには少々育ち過ぎているが、童顔のため年より若く見える。
裕貴はソファの上に体を伸ばした。L字型の大きなソファは、幅こそ少々狭いが、裕貴が十分足を伸ばせる長さがあった。
渡された毛布を首まで被ると、犬の臭いが鼻を掠め、裕貴は顔を顰めた。
「まぁいいか。これくらい。予想よりずっといい待遇だし」
ソファに横たわったまま、三浦のリビングを改めて見渡した。百坪近い一軒家で、一階に、風呂とトイレと台所以外はリビングしかない。
当然、リビングも広い。六畳間が三つは入りそうだ。フローリングの床に、毛足の長いふかふかの絨毯。壁にはチェストが並び、暖炉まである。
「すっごいお金持ち……なんだろうなぁ」
だからといって、裕貴の心は動かなかった。心というより感情全体の動きが鈍くなっていたからだ。
金持ち、という認識はできる。しかし、それは裕貴に何の情動も呼び起さなかった。
「なんやかんやいって、ごはんもちゃんと食べさせてくれたし、寝る所もあるし、僕はいいご主人様に飼われたって事だよね」
三浦の顔を思い出しながら、クッションに顔を押し付ける。
不精髭に覆われた顔を見た時は驚いたけど、鬚を剃ったらなかなかのハンサム……なんじゃないかな。目つきが鋭くて、背が高くて、ちょっとけんか腰で喋るけど。
怖い、とは思わない。本当は優しい人だ、というのはわかっている。
――あの時、僕は賭けをした――
衝動的に電車に乗って、知らない駅で降りて。海に向かうバスに乗った。
人っこひとりいない夕暮れの海を見ていたら、突然この世から消えてしまいたくなった。死にたかったんじゃない。消えたかった。空気の中に、溶けてなくなるように、この世から消えてしまいたかった。
そして、思った。
このまま、まっすぐ海に向かって歩いて行こう。そうすれば、このまま消えてなくなれる。でも、もし誰かが僕を見つけて助けてくれたら――
僕は生きる事を選ぶ。そして、その人を愛そう、と。
男でも女でも。こどもでも大人でも老人でも。誰でもいい。誰かに僕を見つけてほしい。
そして、誰かが僕を見つけてくれたら、僕はその人を全身全霊で愛する。そうすればきっと、生きる意味がわかるから。
まぶたを閉ざすと、裕貴の瞳から涙が流れた。
あぁ、まただ。一瞬でも気が緩むと、涙が……。
泣きたくて泣いているわけではない。なのに、泣くのを止められない。
壊れた蛇口のように、涙は次から次へと流れ出す。
「僕は、犬になる。そして、拾ってくれたご主人様のために生きていく。あの人に、僕のすべてを捧げるんだ」
そうひとりごちると、ほんの少しだけ心が軽くなった。
孝生さんにとっては迷惑なんだろうなぁ。僕の、こんな身勝手な感情や決意は。
ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。
謝りながら、三浦を愛しいと思う気持ちが、不思議なほどに高まってゆく。
犬になる、というのはこういう事かもしれないな。
理屈も何もない。ただ、好きなのだ。
余計な事を考えずに済むし、飼い犬になるっていうのはいいアイディアだったかも。
誰かを――あの冬の海そのもののような孤独の中から、自分を救いだした人を――愛せる喜びに、裕貴は満たされていた
「わん」
「だから、それはやめろ。客用布団なんてないから、おまえはソファで寝ろ。それと、毛布は……これを使え」
三浦が古びた毛布を少年に手渡す。いかにも犬用というかんじの、分厚い茶色の毛布だ。
「クッションを枕にして……。他に必要な物はあるか?」
「わん」
ない、という風に首を振りながら返事をする。
あくまでも犬のフリを続ける少年に、三浦は絶句し、そして肩を落としてリビングを出て行った。
電源が落ち、ライトスタンドのほのかな明かりがリビングを照らす。静まり返った部屋に少年が、ひとり取り残された。少年は、ゆっくりと階段を上る足音に耳をそばだてる。
少年の名前は藍原裕貴(あいはら ゆうき)。二十一歳。少年、というには少々育ち過ぎているが、童顔のため年より若く見える。
裕貴はソファの上に体を伸ばした。L字型の大きなソファは、幅こそ少々狭いが、裕貴が十分足を伸ばせる長さがあった。
渡された毛布を首まで被ると、犬の臭いが鼻を掠め、裕貴は顔を顰めた。
「まぁいいか。これくらい。予想よりずっといい待遇だし」
ソファに横たわったまま、三浦のリビングを改めて見渡した。百坪近い一軒家で、一階に、風呂とトイレと台所以外はリビングしかない。
当然、リビングも広い。六畳間が三つは入りそうだ。フローリングの床に、毛足の長いふかふかの絨毯。壁にはチェストが並び、暖炉まである。
「すっごいお金持ち……なんだろうなぁ」
だからといって、裕貴の心は動かなかった。心というより感情全体の動きが鈍くなっていたからだ。
金持ち、という認識はできる。しかし、それは裕貴に何の情動も呼び起さなかった。
「なんやかんやいって、ごはんもちゃんと食べさせてくれたし、寝る所もあるし、僕はいいご主人様に飼われたって事だよね」
三浦の顔を思い出しながら、クッションに顔を押し付ける。
不精髭に覆われた顔を見た時は驚いたけど、鬚を剃ったらなかなかのハンサム……なんじゃないかな。目つきが鋭くて、背が高くて、ちょっとけんか腰で喋るけど。
怖い、とは思わない。本当は優しい人だ、というのはわかっている。
――あの時、僕は賭けをした――
衝動的に電車に乗って、知らない駅で降りて。海に向かうバスに乗った。
人っこひとりいない夕暮れの海を見ていたら、突然この世から消えてしまいたくなった。死にたかったんじゃない。消えたかった。空気の中に、溶けてなくなるように、この世から消えてしまいたかった。
そして、思った。
このまま、まっすぐ海に向かって歩いて行こう。そうすれば、このまま消えてなくなれる。でも、もし誰かが僕を見つけて助けてくれたら――
僕は生きる事を選ぶ。そして、その人を愛そう、と。
男でも女でも。こどもでも大人でも老人でも。誰でもいい。誰かに僕を見つけてほしい。
そして、誰かが僕を見つけてくれたら、僕はその人を全身全霊で愛する。そうすればきっと、生きる意味がわかるから。
まぶたを閉ざすと、裕貴の瞳から涙が流れた。
あぁ、まただ。一瞬でも気が緩むと、涙が……。
泣きたくて泣いているわけではない。なのに、泣くのを止められない。
壊れた蛇口のように、涙は次から次へと流れ出す。
「僕は、犬になる。そして、拾ってくれたご主人様のために生きていく。あの人に、僕のすべてを捧げるんだ」
そうひとりごちると、ほんの少しだけ心が軽くなった。
孝生さんにとっては迷惑なんだろうなぁ。僕の、こんな身勝手な感情や決意は。
ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。
謝りながら、三浦を愛しいと思う気持ちが、不思議なほどに高まってゆく。
犬になる、というのはこういう事かもしれないな。
理屈も何もない。ただ、好きなのだ。
余計な事を考えずに済むし、飼い犬になるっていうのはいいアイディアだったかも。
誰かを――あの冬の海そのもののような孤独の中から、自分を救いだした人を――愛せる喜びに、裕貴は満たされていた