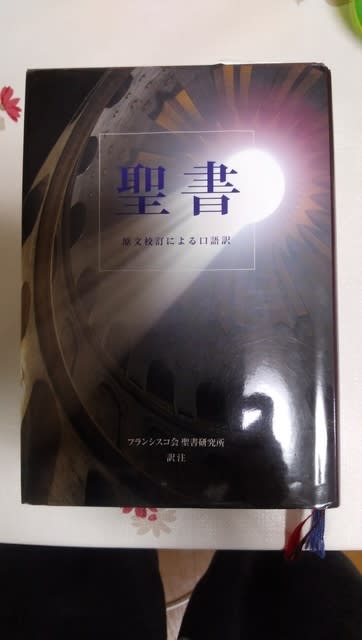お香というものは極めようと思えばきりがない。
私が買い付けるのは京都の松栄堂ですが、ここは永平寺御用達でもあります。
永平寺の門前町でもお土産に線香を買えますが、日本のお香の本家本元といえば松栄堂だといえるでしょう。
ここで乳香を買ったときは線香のスタイルでした。
後にアマゾンで樹脂香を買ったんですが、やはりいい値段がします。さらに没薬となると10g単位でもめちゃめちゃ高い。今回はそんな没薬をキロ買いしたおっさんの話をしましょう。
出典は
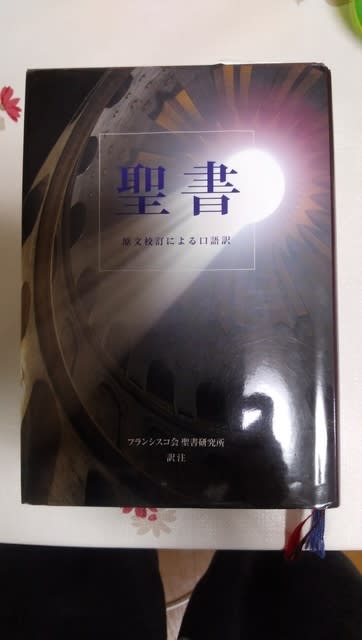
聖書です。お香の達人の名前はニコデモ。当時のユダヤ教では民衆レベルで支持が多かったと思われるファリサイ派で地位の高そうな人です。
この人、キリストの処刑の日に皆さん罵声を浴びせるか悲しむか、兎に角キリストの市中引き回しと処刑を見に集まってるなかで、何をしてたかといえば没薬とアロエか沈香をキロ買いするのに奔走してたわけです。
新約聖書を読めばわかると思いますが彼が属するファリサイ派とキリストが始めたナザレ派(ここから世界最大の宗教キリスト教が出てきます)は少くとも良好な関係とは言えませんし、キリストのファリサイ人批判とファリサイ派のキリストへのあら探しはお互い口を極めてました。
そんな中でキリストを弁護した珍しい種類のファリサイ人でした。
現代社会の出来事ならニコデモのスマホにはファリサイ派のグループチャットで「ナザレのイエス処刑ざまぁw」みたいな着信をかわしつつアマゾンやアラビア関係のネットショップで最短で没薬のキロ買いが可能なところを検索し続けたことでしょうけど、もちろんこの時代にそんなものはありません。
店頭販売でキロで買えるところを探して相当な金額を現金払いで、33キロともなると輸送も大変。そんな中でキリストの埋葬に間に合うように調達できたって冷静に考えるとスゴいとしか言いようがありません。ネットでも没薬のキロ買いってなかなか出来ることではない。
ってことでお香マイスターを古典から探すならこのニコデモっておっさんがイチオシですね。