
京大本部旧物理学教室建物 Photo by Rakuhoo
<第180回 京大俳句会作品>
一句兼題 :「御忌」及び傍題
受付順に並べています。互選はありません。
1) 恵方巻きに幸せ祈る法然忌 嵐麿
2) 光る君俺ももてたし清涼寺 嵐麿
3) 御忌や水をわたくしする勿れ 赤野四羽
4) おばちゃんは基督信ず梅の花 赤野四羽
5) 終活も煩悩ならん法然忌 清水楽蜂
6) 紅梅や帝大理科の赤煉瓦 清水楽蜂
7) 御僧の背ナに衰へ法然忌 つよし
8) 筆走る音に被さる雪の音 つよし
9) 西山へ京(みやこ)の空を御忌の鐘 游々子
10) 菜の花や水より暮るる汽水域 游々子
10) 菜の花や水より暮るる汽水域 游々子
11) 念仏の御忌や細胞入れ替わる 堀本吟
12) 凍星を摘みしか兵士白文地 堀本吟
註・井上白文地。京大俳句事件に連座のち満州に出征。
当地で行方不明。脱走か射殺されたか、諸説あり。
13) 御忌詣枝垂桜を潜りつつ 黒岩徳将
14) 傾いて豆雛凭れ合つてをり 黒岩徳将
15) どの子にも光遍く御忌詣 蒼草
16) 幾世かの黄塵駆くる兵馬俑 蒼草
17) 銀閣寺 下りて黒谷 御忌阿弥陀 二宮
18) 真如堂 降り真如荘 喫茶カンナ 二宮
18) 真如堂 降り真如荘 喫茶カンナ 二宮
19) 声明の和す声太し法然忌 遥香
20) ほどけゆく光のかけら薄氷 遥香
21) 御忌小袖まとひて京の遊山かな 幸男
22) 冬至る柚子とコロナのせめぎあい 幸男
23) 川のほとりを白く嘆いて春鮎子 武史










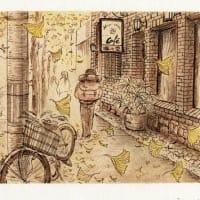















冬帽子脱いでおしゃべり現われる 徳将
水玉の玉の弾けて夏休み 徳将
今回、投句いただいた黒岩徳将さんは, まことに懐かしい。ブログの記録によると、「冬帽子」の句は、第24回(2011年1月)京大吉田寮での句会で提出されている。「水玉の」は、それより前、かなり初期(1-10回)での作品である。当時、徳将さんは京大生だったが若者らしい独特の感性に溢れた作品で皆を驚かせた。京大俳句の休会に合わせた里帰りである。
自句自解
紅梅や帝大理科の赤煉瓦 清水楽蜂
解説の必要もない写生句であるが、上掲の写真をご覧になってもわかるが、紅梅と赤レンガの「赤」の組み合わせは視覚的に重複せず、それぞれを引き立てている。旧帝大の赤レンガ建物は保存建築物として、いまも京大の事務棟の一つとして利用されている。このそばに佇むといつも心が落ち着く。
● 恵方巻きに幸せ祈る法然忌 嵐麿
恵方巻は、節分に頂く縁起ものですが、法然上人のⅠ月25日にも黙った恵方巻をいただくのですか??寡聞にして、その知識がありませんので、これは少し飛びすぎ過ぎの感をもちます。。
● 光る君俺ももてたし清涼寺 嵐麿
こちらの方は、気持ちがわかります。ファン心理ですね。
● 御忌や水をわたくしする勿れ 赤野四羽
法然院には山門を入ると両側に、白砂を敷きつめた「白砂壇」がある。これは水を表している。このたたずまいを知ると、法然の聖地への挨拶の句であるとも読める。しかし、この句の意味は、「御忌」に、「水」というメタファで表しているのだろう。水が、万物を清めることと、生命を生成するという考え方が、仏教にあるという(よく読み込んだものではないが)。浄土教の他力本願の思想は、水のように形ないものに我執を溶解することにも通じるのではないだろうか?この教義と、一致するかどうかそれは私にはわからないが。観念性が強いにもかかわらず、取り合わせの妙というのか、「御忌」と「水をわたくしする勿れ」の緊密な関係を受け取る。法然や浄土宗に関わることだと、強く意識される。一句の音楽性。「御忌や」と三文字。「ぎょ」「き」「や」と三音で止めたところが、リズムに破調をもたらしている。作者のリズム感覚の繊細さや、技巧の工夫をみる。「水をわたくしする勿れ」では、「私有」する勿れということに引き寄せるだけではなく、ここで我=自分自身に関わる思考から解放されることの大切さを言う。水面の広がるごとく、生命の普遍性に自分も溶けこむのだ、ということか。軽快なリズムで深遠なことがらを伝える。季語の内容を展開した、力作だと思う。
● おばちゃんは基督信ず梅の花 赤野四羽
前の句とは、がらりと雰囲気を変えている。「基督」を信じている「おばちゃん」教義ではなく、万民の身代わりになって十字架に架かった人間を信じている。こういうときにこういう季語を使うかな?という意外感。これは取り合わせが、やや飛び過ぎではあるが、が上手く絡んでいるので、「御忌」の荘重な雰囲気ではない在り方で、、庶民の信仰心の在り方に気づかせる。
● 終活も煩悩ならん法然忌 清水楽蜂
まことに共感おく能わざる、私の実感でもある。終活は一瞬の区切りにすぎない。物質の歴史と精神の歴史はまだまだつづく。
● 紅梅や帝大理科の赤煉瓦 清水楽蜂
これは、この建物の歴史と現地を知る人、またはそこに学んだ人、奉職した人にはたまらないほど郷愁を感じさせるだろう。「帝大理科」「京都帝国大學」創立の時には、理学部が一番先にできたのできたのですね。これを詠むために京大俳句会があった、というべき記念碑的一句です。
● 御僧の背ナに衰へ法然忌 つよし
敏感な視線ですね。年齢に逆らうことはできませんが、人間には、優しさや、モノに応じて心を拡げる柔軟性が授かっています。法然上人の浄土宗はまさにその他力の境地を教えているのかも。
● 筆走る音に被さる雪の音 つよし
「筆走る音」も「雪の音」もかそけき音。重なれば、自分の心に走るかそけくも確かな思いの音となる。書きすすめながら「音」をききとり、見えぬ「音」を見事に形象化している。つよしさんのこころの深みに、同道させられそうなかそけき思いが湧いてきます。
● 西山へ京(みやこ)の空を御忌の鐘 游々子
東山、北山はそれぞれ、固有のエリアである。それからこの西山は宗教の地として最近脚光あびている。浄土宗のことはあまりよく知らないので申しわけないが、その西山へ、東山にある法然院の鐘の音が京都の空を渡って西山派の浄土宗の聖地へ渡ってゆくというのだろうか、地理的に言うとそうなるが。
● 菜の花や水より暮るる汽水域 游々子
河口、海水と淡水の交わるあたりのこと。ふつう、水面の夕焼けなどが最後まで明るいのが、ここでは、水面から暮れてゆく。岸辺の菜の花明りのせいだろうか。「菜の花や」、と来れば、「月は東に日は西に・与謝蕪村」と覚え込んでいる。まずそこに反射している光線が翳り始めることで、日の入りを知る。河口の日暮の光の複雑な移ろいに注目したところ、詠ませる
。
● 御忌詣枝垂桜を潜りつつ 黒岩徳将
華やかな挨拶句。法然院に谷崎潤一郎が愛したという枝垂桜がある。そこをくぐるという気持ちの内で、異界(浄土)に達す。「御忌」を愛で、季節感豊か。哲学の道は、桜トンネルのような華麗さ、幾度も訪れてみたい。
● 傾いて豆雛凭れ合つてをり 黒岩徳将
これは好きな句。どの程度を豆雛というのだろうか。私が生まれた初雛は、遠くにいる祖父母から送られたのがあり、小さな小さなお雛様だった。とにかく小さいのでバランスを崩し直ぐ転ぶ。それが「凭れ合つてをり」と表現される。豆雛を飾ろうと取り出したら、内裏様とお姫様が睦まじく・・。可憐なその様子が「生き生き」と命あるかのように出されている。
● どの子にも光遍く御忌詣 蒼草
法然にはじまる浄土思想は、念仏を唱えればそれだけで極楽へ行ける、という他力本願である。無心な子ども達どの子にも、平等に光が注がれている、この日にふさわしい光景だ。
● 幾世かの黄塵駆くる兵馬俑 蒼草
兵馬俑とは、死者を守るための副葬品、兵士や馬の形をした土でかたどられている埴輪のようなものである。最も有名なのが、始皇帝の墓の「兵馬俑」。俳句の風景には、こういう時間が込められている。この句の風格は黄砂と兵馬俑がつかさどる大陸の「歴史時間」に与えられます。
● 銀閣寺 下りて黒谷 御忌阿弥陀 二宮
法然院へ行く道筋の地理を知っていなくても、だんだん信仰心が湧いてくるから不思議だ。
● 真如堂 降り真如荘 喫茶カンナ 二宮
こちらも、道筋を辿らされるのだが、「喫茶カンナ」で一休み、ということかな。こんな遊びも楽しい。「喫茶カンナ」に行ってみたい。
● 声明の和す声太し法然忌 遥香
法然忌とくれば声明。何度聞いてもありがたい。俳句になると、それだけではやや平凡。しかし、「太い声が」和しているという気づきが決め手ですね。一人の声が太くて、それが響くので、ここでタダゴトを抜け出している。
● ほどけゆく光のかけら薄氷 遥香
遥香さんの観察の視線が、いつもながら繊細だなあ、と思いました。「ものの見えたる光消えぬうちに書きとどむるべし。松尾芭蕉」ですね。この字であっているかしら。
● 御忌小袖まとひて京の遊山かな 幸男
法然院詣は、当時の女性は着飾って、御弁当などもって出かたようだ。信仰にことよせた観光行事になっていたらしい。その時の衣装を「御忌小袖」という、関連して「弁当初め」という季語もある。「御忌詣」に、そういうや楽しみが隠されていることは初めて知った。幸男さん、ありがとうございました。「御忌忌」が堅苦しくなくなった。
● 冬至る柚子とコロナのせめぎあい 幸男
あ、これに似た句を私も作ったことがあります。柚子の実はとにかくたくさん実り、その金色を見ていると、元気が出るのです。この冬にはなべ物に柚子ポン酢で、コロナを追い払おうとしました。
自句コメント
● 念仏の御忌や細胞入れ替わる 吟
あの世で救われなくてもいいからこの世で救ってほしい。念仏を唱えていると体がリフレッシュするだろう、という 不信心者のはかなき期待の句です。「細胞」と「念仏」では、ちょっとつきすぎかなとも反省するが。
● 凍星を摘みしか兵士白文地 吟
註・井上白文地。京大俳句事件に連座のち満州に出征。当地で行方不明。脱走か射殺されたか、諸説あり。
平畑静塔とともに京大俳句を創刊。非常に誠実な面倒みの良い人物だということで、慕われている。「天香」という新興俳句の総合誌を三鬼たち東京の新興俳人がつくったときにも、「京大俳句」の居場所とその誇りを守った。不幸なことに出征地の奥満州で消息が途絶え、その最後は生死不明。「凍て星を摘みしか」という表現には、私の思い入れがあり、高校時代の恩師が満州出征のご自分の戦争体験を、「満州では星が葡萄のように大きいて、手でもげそうじゃった」と教えて下さったことがとても印象深かった。様々な憂き目にあった白文地が末期に、近々とその凍った冷たい星を摘んだであろうか。と想像した。