
東山霊巌寺 Photo by Rakuhoo
<第179回 京大俳句会作品>
一句兼題 :「寒椿」及び傍題
受付順に並べています。互選はありません。
1)冬椿落ちたる寺の石畳 游々子
2)護摩の火や僧百人の息白し 游々子
3)清盛の愛憎凜と寒椿 嵐麿
4)人去りて嵯峨の竹林名残雪 嵐麿
5)冬椿だから家族になりましょう 赤野四羽
6)一月の空へ手紙を書く窓辺 赤野四羽
7)卓上の役者となりぬ実千両 つよし
8)おひさまと終日遊び寒雀 つよし
9)幾世ほど墓に彩添ふ寒椿 蒼草
10) 年惜しむ声の揃ふや謡納め 蒼草
11) 尼寺に紅一つ寒椿 遥香
12) 赴任地へ遥かなる空寒昴 遥香
13) 実存の一輪なりし寒椿 吟
14) 応召の眉やや寄りて根深汁 吟
15) 寒椿すっくと咲いて君子かな 幸男
16)祭壇に微笑み残し義母(はは)逝きぬ 幸男
17) 薄明り息をひそめる寒椿 明美
18) 舞う粉雪たわむれあうは陽の光 明美
19) なまくらの七十郎や寒椿 楽蜂
20) 東山雪一寸の薄化粧 楽蜂
21) 来ぬ春を恋に焦がれて小商人 武史
22) 葬儀の曲未完の花咲く丘にしてくれ 武史
23) 足摺の 遍路の見上ぐ 寒椿 二宮
24) 進化論 学び忘れん 身の寒さ 二宮
会誌自由船(最終号)へのメールでの寄稿は清水楽蜂(apisceran@gmail.com)にお願いします。










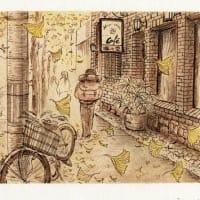















今回は、ありがたいことに赤野四羽さんにも投句いただきました。四羽さんは京大卒で、2016年現代俳句新人賞を受賞された俳人である。日本語俳句をイタリア語に訳した句集 『CHIODI BATTUTI (打たれた釘)』(2022)を出しておられる。「月を知る鳥は夜には従わぬ」「永遠に死なぬ顔して秋の猫」などの作品が収録されている。
自句自解
なまくらの七十郎や寒椿
カラーになる前の黒澤明の映画は、どれもすごく面白かった。とくに「用心棒」「椿三十郎」は何回も観た。いずれも活劇映画ではあるが、画面構成が隅々まで細かく計算されており、良質な俳句に似ている。ただ、「椿三十郎」で武家屋敷の庭に椿の木がたくさん植えられているのは腑に落ちなかった。椿の花は、そのままポトリと落ち縁起が悪いということで、武士の家には植えないのが習わしであった。
この時期、古寺を訪れこのありさまを見るたびに、新鮮な感動をもちます。椿には不思議な風格があり、どこにおいても、辺りにとけこみ、辺りを払います。
2)護摩の火や僧百人の息白し 游々子
白息の百人、「百本」の太い息が吐き出される様、視覚的に生々しい迫力。
3)清盛の愛憎凜と寒椿 嵐麿
「清盛の愛憎」で切るのだろう。実際の意味は「清盛への愛憎」なのだろう。場所は祇王寺の椿。清盛の傲慢な欲望に翻弄された、祇王や仏御前のことか。そう取るのが一番わかりやすい。
4)人去りて嵯峨の竹林名残雪 嵐麿
「人去りて」と「名残雪」は似合う、とも、しかし、技法的にはやや付きすぎだと思える。そこまで重ねるかどうかは、各人の好みによりますが。嵯峨には、かくも閑静な竹林が残雪の中に立っているのでしょう。俳句にあらわれる句景としては、様々な愛憎を包みこんだ込んだこの竹林だけが心に残る。
5)冬椿だから家族になりましょう 赤野四羽
「冬椿」なのだから、と書き出して、そのあと意外にも「家族になりましょう」。この挨拶句は、唐突になんとやさしく相手を引き込むことでしょう。「冬椿」で切るか、「冬椿だから」と句跨りで読むか、この選択も読み手に任せられていますが、どちらの方で意味をうけとるにしても、ここに出て来る「家族」なる共同性について、昔風にではなく今式の認識の方に転換をもとめられる。「友達になりましょう」「恋人になりましょう」「同志になりましょう。」それよりもっとよりもっと広い、いや、あるいはもっと閉じられた狭い親密さ。「家族」はいまや一種の虚構のコミュニティ。優しい口調の中に、現代的な「家族」の考えかたが取り込まれているので、私のように、情緒過多で頭でっかちのものは、そこで、やはりはっと立ちどまらさせる。一句に繰り出されている語彙には、変化があり、不思議な味わいが残ります。
赤野四羽さん。最後にしての初めての乗船。ようこそ。そしてさようなら。一期一会のとても気落ちのいい幻想の「家族」になれそうです。 「冬椿」そのものが一個の別世界の風景を作り出しています。こういうときに効果的ですね。
6)一月の空へ手紙を書く窓辺 赤野四羽
年も明けたが、しかしまだ一月の新しさのある寒空へ、「空」というを宛名で手紙を書く。この「窓辺」という場所も意味ありげである。家屋の内と外の境界である。この場所で、空に宛てて手紙を書く行為は、ロマンチックだ。この句はまさに全体が空想的な楽しい一句であ誰がこの一通の手紙を受け取るのだろう。われわれの「関係」のありあかたについて、韜晦というべき感覚の迷路につれていってくれる。
7)卓上の役者となりぬ実千両 つよし
ひとつの読み方。「卓上の役者」は実千両の真っ赤な実のこと。それが活けられて鮮やかに整っているいるので、その卓が特別の舞台になり、実千両が役者のように見事に映えている。もう一つの読み方。自分は、この卓上ででいろいろ空想を連ねて役者のように別人格になって、俳句や文章を書く。「千両の実」の鮮やかな紅色が卓上にあるから、ここが私の非日常の舞台である。机上の舞台のゆたかさ。「実千両」が象徴しています。
8)おひさまと終日遊び寒雀 つよし
つよしさんが、「おひさま」などというやわらかな言い方で、寒中の日差しに戯れてれている小さな生き物の動きを活写している。言い回し(表現)が与える不思議さ、ほほえましさ。いいい句ですね。
9)幾世ほど墓に彩添ふ寒椿 蒼草
いつ来てもこのお墓の傍には、椿が色あざやかに咲いている。何世紀も雄だったのだろう。過去と現在の融合の景。蒼草さん。叙景の句に徹しておられ、いつもみごとな句づくりですね。
10) 年惜しむ声の揃ふや謡納め 蒼草
母親が謡をしていて、こういう「謡納め」の会があった。台本一巻を謡い、最後は声をそろえて謡納められる。この抑揚最後はゆったり引き伸ばされて、「~消えにけり~~。」と声がそろってピタッと終わる。別の部屋で聞いていると、この呼吸はなかなか面白かった。
11) 尼寺に紅一つ寒椿 遥香
尼寺の寒椿。沢山咲いているはずなのに、一つしかみつからぬところがいいです。
12) 赴任地へ遥かなる空寒昴 遥香
誰かが遠い場所へ赴任したのでしょう。寒さの底で天を見上げると、真上に瞬きをくりかえす牡牛座のスバル、ここからはるかな空のかなた、その地でも、この星たちを見上げているでしょう。という意味の句。遥香さんは、風景の底から、心情を救い上げるそこがとても繊細な人です。読ませていただくのが楽しみでした。この句もそうです。この言い方のうちに、原作者のやわらかな思いが広がっているのですね。この「赴任地へ」の「へ」が取り留めなくて、私としては、最初気になりましたが、心が夜の大空がはるか向こうに広がってゆく、そこに茫漠とした空閒が重なります。間近な頭上の「寒昴」の画然としたきらめきに戻ります。夜の大空を行き来する交歓・・。スケールあります。
15) 寒椿すっくと咲いて君子かな 幸男
椿がすっくとどうどうと咲く、ということだと思うが、「君子」と置いたところで、今一つ立ち止まる。椿に他を圧する鮮やかさであるので、そういう意味にとってみれば、納得できる。「君子」とは4っつの徳をそなえた大人物のこと、それになぞらえて、「蘭 竹 梅、菊」を「四君子」という。それに加えて「椿、松、花菖蒲」を「七君子」と言って、この七つの花を描き上げることで、墨絵の精神や技法を学ぶそうです。これを知らないと、どうしても唐突に響くので、感動がそがれてくる。惜しいなと思いました。大幅に省略したり抽象化して真意を伝えるのが俳句の詩形の特徴ですが、もうすこしほんのすこし、「寒椿」と「君子」のつながりを暗示する工夫があってもいいかな、と思いました。幸男さん、またメールで意見交換しましょうか?
16) 祭壇に微笑み残し義母(はは)逝きぬ 幸男
お悔やみ申し上げます。笑顔の美しいお義母様だったのですね。母を失った身近なひとが、早く微笑みを取り戻されますよう祈ります。
17) 薄明り息をひそめる寒椿 明美
ひそやかな風景。葉陰に隠れ悲しみを秘めている椿。上五と中七に言い難い思いが潜んでいます。寒椿の新しい魅力。
18) 舞う粉雪たわむれあうは陽の光 明美
雪に陽が射している珍しい風景。ダイヤモンドダストではなく、晴れた日の粉雪。素敵な光景です。
19) なまくらの七十郎や寒椿 楽蜂
樂蜂俳句はたいていは意味が通りやすくで、句の構造もそう難しくない。しかも内容はそうとう個性的だ。そして、これは意味自体がわかりにくかったのです。「なまくら」はヤキが入っていない刀、「なまくら刀」」という日本最古のアニメ映画もあるらしい。が、どうもこのアニメとは関係ないようだ。問題は「七十郎」。お酒に「七重郎」というのがある。しかし、これもどうもそぐわない。とあれこれ考えていて、椿三十郎のファンだ、と、コメントの欄の「自句自解」にあったので、其れから察する。七十歳の坂を越えてなお椿三十郎にあこがれる「カリカチュア」。 この程度しか穿った見方が出来ないのだ。ともあれ、この「寒椿」で、「なまくら」に風格が備わった。諧謔をひそめた「大人の寒椿」です。
20) 東山雪一寸の薄化粧 楽蜂
雪の東山三十六峰・・必ずそこに在るものの日々の変化を、今日はかそけき華やぎの姿である。私も生駒山と西に広がる大阪の空の景を毎日毎日眺めるが、こちらはあまり雪が降らないのです。
21) 来ぬ春を恋に焦がれて小商人 武史
「小商人」がちょっとわかりにくいけれど・・。
22) 葬儀の曲未完の花咲く丘にしてくれ 武史
「みかんの花咲く丘」川田正子ちゃんのかわいい声に魅了された子供時代。「葬儀」の曲のご希望は承りましたが、武史さんは、少年期の初恋が未だまっとうされていなのでしょうね?恋の生命力は強いから、まだまだ安心。お元気でいてください。
23) 足摺の 遍路の見上ぐ 寒椿 二宮
旅情豊か。寒風の中、辺境に咲く椿の姿。いいですね。
24) 進化論 学び忘れん 身の寒さ 二宮
二宮さんの思考の機微というか、わからない。逆にそこが面白い。進化論を学び。忘れようと思ったんですね。急に身ぶるいが来て「おお、寒!」、とどうしてこうなるんだろうね。進化のエネルギー掻き立ててください。
25) 降る雪や野辺の彩り寒椿 のんき
大寒の雪中に咲く椿の色合いは格別の紅さ。白い野原ではさらに赤さが目立つ。
26) もくもくと灰色舞って山は雪 のんき
正確な写生ですが、「もくもく」というイメージ描写が効果的で、雪雲の動きが詩的な凄みを持ってくるのです。
自句コメント
13) 実存の一輪なりし寒椿 吟
椿の花は、その一輪というの存在感が素晴らしい。この場合、やたらに花の色は出しません。薔薇も牡丹も美しいけど、椿はつくづく一輪としてそれだけで、美しい奇麗な花だ、飽きず眺めています。
14) 応召の眉やや寄りて根深汁 吟
若者が徴兵された時代。貧しいが心のこもった暖かい大根汁を作って送りだす母の思い。緊張して眉根を寄せるその息子になりかわったつもりです。日本に徴兵制が敷かれたら、どうなるだろうかと、この頃はしばしば考えます。