 「聴衆が望むものだけを伝えるのが、ジャーナリズムの仕事ではない。彼らが見たくないと目をそむけるもの、彼らが気付いていない事実を伝えることも、ジャーナリストの義務だ」
「聴衆が望むものだけを伝えるのが、ジャーナリズムの仕事ではない。彼らが見たくないと目をそむけるもの、彼らが気付いていない事実を伝えることも、ジャーナリストの義務だ」
日独の航空戦を目の当たりにしたエド・マローの自戒。
1940年代初頭、アジア情勢は緊迫の一途を辿っていた。フランス極東艦隊の奇襲によって日本は戦艦4隻を失った。その一方で、アメリカとの関係は急激に悪化していた……。
タイトルには「大和撫子紫電改」とありますが、まだ紫電が投入されたばかりで主役は瑞山だし、「山本五十六・米本土侵攻」とあるけれど、アメリカと戦争せんといかんぞーという各国かけひきの段階です。とりあえず、この巻の話はユダヤ難民を輸送していた帝国の艦隊が、地中海でドイツ・イタリアの航空戦力とぶつかるところまで。ハンス・マルセイユは貧乏くじ、チャーチルはタヌキ親父で、山本五十六は……。
こまかなポイントで歴史はいろいろ変わっていますが、ポイントの1つは山本権兵衛内閣がシーメンス事件を乗り切り、欧州派兵したことで日本の国際的地位が向上し、それと連動するように経済力が強くなったこと。
もう1つは1920年代なかばに日本を襲った6つの大地震とインフルエンザの流行によって人口の3割と都市機能を失いつつも再生に成功したこと。
この2点が許せない人はダメかもしれませんが、架空戦記なんてシロモノは、(興ざめにならない範囲で)事実よりマシな歴史を求めるべきものなので、自分は素直に「経済力と国際的地位を手に入れた日本が、近衛内閣の舵取りで対米戦にはまり込んでいく」過程を楽しみたいと思いました。
人口の急激な減少から女性の社会進出が進み、数は多くないものの女性士官の姿も見られるようになり、トンキン湾空戦でエースパイロットとなった千葉貴子中尉が大活躍!……というのも見せ場ですが、読了後の感想は「山本権兵衛、偉いなー。近衛はいかんなー」に尽きるかと。
【大和撫子紫電改】【山本五十六・米本土侵攻】【志真元】【冨沢和雄】【中村亮】【空母<扶桑>】【エドワード・マロー】【ウォルター・クロンカイト】【人造石油】【レンドリース】
 「どうしてこうなった?」
「どうしてこうなった?」









 坂本龍馬が暗殺されなかった、もう1つの20世紀。
坂本龍馬が暗殺されなかった、もう1つの20世紀。 坂本龍馬が暗殺されなかった、もう1つの20世紀。
坂本龍馬が暗殺されなかった、もう1つの20世紀。 「大使、我が国の最高機密を教えよう。大英帝国最大の秘密兵器は……アドルフ・ヒトラーなのだよ」
「大使、我が国の最高機密を教えよう。大英帝国最大の秘密兵器は……アドルフ・ヒトラーなのだよ」 「人は常に十全でいることは難しい。どんなに気を付けても何かミスを犯す。だから部下と助け合い、互いの欠点を補い合う。しかし時として、全員がミスを犯すことがある。そういう時、責任を取るのは指揮官の務めだ」
「人は常に十全でいることは難しい。どんなに気を付けても何かミスを犯す。だから部下と助け合い、互いの欠点を補い合う。しかし時として、全員がミスを犯すことがある。そういう時、責任を取るのは指揮官の務めだ」 柳河邦彦大佐が新艦長として赴任した、戦艦大和の乗員の士気は落ち込んでいた。
柳河邦彦大佐が新艦長として赴任した、戦艦大和の乗員の士気は落ち込んでいた。 「真の豪傑はの、常によか女のケツば追いかけとうもんじゃ」
「真の豪傑はの、常によか女のケツば追いかけとうもんじゃ」 「聴衆が望むものだけを伝えるのが、ジャーナリズムの仕事ではない。彼らが見たくないと目をそむけるもの、彼らが気付いていない事実を伝えることも、ジャーナリストの義務だ」
「聴衆が望むものだけを伝えるのが、ジャーナリズムの仕事ではない。彼らが見たくないと目をそむけるもの、彼らが気付いていない事実を伝えることも、ジャーナリストの義務だ」 「戦車殺しを心底楽しめるやつは、未だに戦争へ参加しているやつのことだよ」
「戦車殺しを心底楽しめるやつは、未だに戦争へ参加しているやつのことだよ」 ライバル校からサバゲーで挑戦された聖ラファイエット女子高。ところが自由参加と言いつつ、聖ラフェ校の参加者8人に対し、対戦校は総勢600人が「志願」してきた上に、いつの間にか負けた学校の文化祭は戦勝校に吸収されるという条件が付いていて……。
ライバル校からサバゲーで挑戦された聖ラファイエット女子高。ところが自由参加と言いつつ、聖ラフェ校の参加者8人に対し、対戦校は総勢600人が「志願」してきた上に、いつの間にか負けた学校の文化祭は戦勝校に吸収されるという条件が付いていて……。 「我々が最高の偽善を為すために」
「我々が最高の偽善を為すために」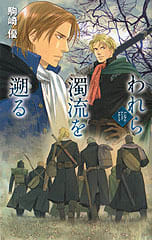 「人生なんてものはな、濁流を手探りで遡っているようなものなんだよ」
「人生なんてものはな、濁流を手探りで遡っているようなものなんだよ」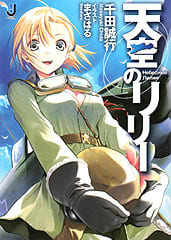 「時に信頼は、自信よりも強い武器になるんだ」
「時に信頼は、自信よりも強い武器になるんだ」 速水螺旋人によるコミック&イラストエッセイ集『速水螺旋人の馬車馬大作戦』収録の「パルスジェットのフラミンゴ」の後日談を小説化したもの。
速水螺旋人によるコミック&イラストエッセイ集『速水螺旋人の馬車馬大作戦』収録の「パルスジェットのフラミンゴ」の後日談を小説化したもの。 インフルエンザにやられてしまったらしく、しばらく死んでました。熱で体がだるくて本を読む気力もありません。ただただ寝続け、ヘンな寝方で筋肉痛になり、ただでさえ忙しい年末進行が大混乱です。
インフルエンザにやられてしまったらしく、しばらく死んでました。熱で体がだるくて本を読む気力もありません。ただただ寝続け、ヘンな寝方で筋肉痛になり、ただでさえ忙しい年末進行が大混乱です。



