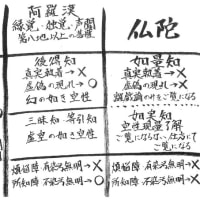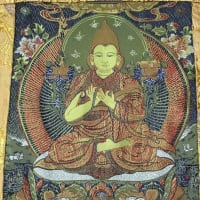親鸞聖人の一如宝海論の依拠する経典、論書を調べていたところ、これかもというのをやっと見つけることができました。
ヒントは釈摩訶衍論の不二摩訶衍について考究する中にありました。
釈論ではありませんが、やはり同じく龍樹に仮託された論書。
ちなみに十住毘婆沙論ではなく、龍樹に仮託された論書となれば、あともう一つとなる「大智度論」です。
親鸞聖人の還相回向論、従果還因論の根拠、二種法身論の根拠もおそらくそれになるのだろうと思われます。
親鸞聖人は、曇鸞の「論註」や道綽の「安楽集」から二種回向や二種法身の論を引いては来ているものの、その解釈は、曇鸞や道綽とは全く異なるものになっていることに、ずっと違和感がありました。
その謎がやっと解けた感じであります。
それは、まず、大智度論の仏身論が説かれてある有名な箇所になります。
大智度論巻第九
「復次,仏有二種身:一者、法性身,二者、父母生身。是法性身満十方虚空,無量無辺,色像端正,相好荘厳,無量光明,無量音声,聴法衆亦満虚空。此衆亦是法性身,非生死人所得見。常出種種身,種種名号,種種生処,種種方便度衆生;常度一切,無須臾息時。如是法性身仏,能度十方衆生。受諸罪報者,是生身仏;生身仏,次第説法如人法。以有二種仏故,受諸罪無咎。」
この中で重要なのは、「聴法衆亦満虚空。此衆亦是法性身」。
ここになります。
「法を聴く衆生もまた虚空に満ちてあり、この衆生もまた法性身である。」
様々な方便のはたらき(方便法身)により衆生を法性法身と化していくありようが説かれてあり、自らの方便法身と法性法身のありようと共に、教化した衆生もまた法性法身であるとして同一同体(同化)させていくと解釈することのできるここが要となります。
そして、大智度論で説かれる「法性説」が、そのまま「一如宝海論」へと繋がってくるところとなります。
それはまた別に考察することにしますが、その「法性説」の親鸞聖人の解釈は、やはり本覚思想的な枠内で留まってしまったために、最後は一気に自力修行無用論へと傾斜することになってしまいました。
そして、「八十華厳」の下記の「発心」を「信心」とすり替える論理により、一如宝海成仏論を展開していくことになったのだと思われるのであります。
「以是発心。即得仏故。応知此人即与三世諸仏同等。即与三世諸仏如来境界平等。即与三世諸仏如来功徳平等。得如来一身無量身究竟平等真実智慧。纔発心時。即為十方一切諸仏。所共称嘆。」
要は、阿弥陀如来の法性法身からの方便法身のはたらきとなる報身阿弥陀仏、応身釈迦仏の教え、名号をいただくことになる衆生も、法性身そのものになるということで、そのためには、一応は輪廻(生死)からは離れての一如宝海への往生の必要性が説かれることになり、その往生に「信心」を必要としたのであります。
その「信心」を「八十華厳」の「発心」と同じようなものと解釈した上で、それ以外は雑修、雑行、雑善としたのであります。
まあ、八十華厳よりも、大品般若経・往生品の方がその意図としてはより近いのかもしれません。
下記の初発意を信心として、ということです。
「有菩薩摩訶薩 初発意時 即得阿耨多羅三藐三菩提 転法輪 与無量阿僧祇衆生 作益厚 已入無余涅槃」
こちらの方が法性と方便の二種法身を同時に得られるものとして捉えやすいですし、還相回向の説明としてもすっきりとしやすくなります。
また、大智度論においては、色々な三昧についても説明がなされる中で、首楞厳三昧は、初発心の菩薩による方便法身三昧であるとして、その菩薩は、ナント、法身も既に備わってあるものと説明されているのであります。
初発心の菩薩にです。
この初発心を信心と置き換えれば、そのまま、「信心の獲得」=「方便法身と法性法身の二種法身の獲得」と言えることに。更に還相回向のあり方についても説明がつくことになるのであります。
ヒントは釈摩訶衍論の不二摩訶衍について考究する中にありました。
釈論ではありませんが、やはり同じく龍樹に仮託された論書。
ちなみに十住毘婆沙論ではなく、龍樹に仮託された論書となれば、あともう一つとなる「大智度論」です。
親鸞聖人の還相回向論、従果還因論の根拠、二種法身論の根拠もおそらくそれになるのだろうと思われます。
親鸞聖人は、曇鸞の「論註」や道綽の「安楽集」から二種回向や二種法身の論を引いては来ているものの、その解釈は、曇鸞や道綽とは全く異なるものになっていることに、ずっと違和感がありました。
その謎がやっと解けた感じであります。
それは、まず、大智度論の仏身論が説かれてある有名な箇所になります。
大智度論巻第九
「復次,仏有二種身:一者、法性身,二者、父母生身。是法性身満十方虚空,無量無辺,色像端正,相好荘厳,無量光明,無量音声,聴法衆亦満虚空。此衆亦是法性身,非生死人所得見。常出種種身,種種名号,種種生処,種種方便度衆生;常度一切,無須臾息時。如是法性身仏,能度十方衆生。受諸罪報者,是生身仏;生身仏,次第説法如人法。以有二種仏故,受諸罪無咎。」
この中で重要なのは、「聴法衆亦満虚空。此衆亦是法性身」。
ここになります。
「法を聴く衆生もまた虚空に満ちてあり、この衆生もまた法性身である。」
様々な方便のはたらき(方便法身)により衆生を法性法身と化していくありようが説かれてあり、自らの方便法身と法性法身のありようと共に、教化した衆生もまた法性法身であるとして同一同体(同化)させていくと解釈することのできるここが要となります。
そして、大智度論で説かれる「法性説」が、そのまま「一如宝海論」へと繋がってくるところとなります。
それはまた別に考察することにしますが、その「法性説」の親鸞聖人の解釈は、やはり本覚思想的な枠内で留まってしまったために、最後は一気に自力修行無用論へと傾斜することになってしまいました。
そして、「八十華厳」の下記の「発心」を「信心」とすり替える論理により、一如宝海成仏論を展開していくことになったのだと思われるのであります。
「以是発心。即得仏故。応知此人即与三世諸仏同等。即与三世諸仏如来境界平等。即与三世諸仏如来功徳平等。得如来一身無量身究竟平等真実智慧。纔発心時。即為十方一切諸仏。所共称嘆。」
要は、阿弥陀如来の法性法身からの方便法身のはたらきとなる報身阿弥陀仏、応身釈迦仏の教え、名号をいただくことになる衆生も、法性身そのものになるということで、そのためには、一応は輪廻(生死)からは離れての一如宝海への往生の必要性が説かれることになり、その往生に「信心」を必要としたのであります。
その「信心」を「八十華厳」の「発心」と同じようなものと解釈した上で、それ以外は雑修、雑行、雑善としたのであります。
まあ、八十華厳よりも、大品般若経・往生品の方がその意図としてはより近いのかもしれません。
下記の初発意を信心として、ということです。
「有菩薩摩訶薩 初発意時 即得阿耨多羅三藐三菩提 転法輪 与無量阿僧祇衆生 作益厚 已入無余涅槃」
こちらの方が法性と方便の二種法身を同時に得られるものとして捉えやすいですし、還相回向の説明としてもすっきりとしやすくなります。
また、大智度論においては、色々な三昧についても説明がなされる中で、首楞厳三昧は、初発心の菩薩による方便法身三昧であるとして、その菩薩は、ナント、法身も既に備わってあるものと説明されているのであります。
初発心の菩薩にです。
この初発心を信心と置き換えれば、そのまま、「信心の獲得」=「方便法身と法性法身の二種法身の獲得」と言えることに。更に還相回向のあり方についても説明がつくことになるのであります。