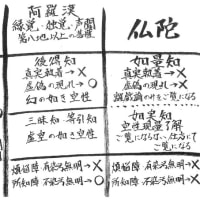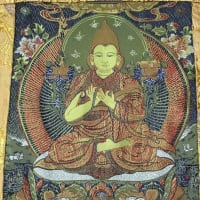後半の雑修、雑行、雑善の部分への言及となりましたね。
通仏教、聖道門自力行であれば、まあ、大丈夫かなと、普通になる表現が続く後段ですが、浄土真宗では、凡夫ではどうしようもないほどに致し方もない煩悩、執着、愚心を、何よりも深く深く自覚していくことが大切なことになります。
執着を離れることなど、とてもとてもできない凡夫へと向けてこその尊く有り難い弥陀本願であるわけです。
「みずから執着の心を離れることができるのであれば、如来の本願建立の理由すらも失われてしまう」
ということであります。
更に次弾も雑修、雑行、雑善の勧めを少なくとも未信者へ向けて述べたてることには全く意味がないと、厳しくご裁定なさられることでしょう。
「新しい領解文」(浄土真宗のみ教え)に対する声明(四)
このたびご消息として発布された「新しい領解文(浄土真宗のみ教え)」(以下、「新しい領解文」)の内容について、勧学・司教有志の会は第一段落・第二段落について、宗祖親鸞聖人のご法義に重大な誤解を生ずるおそれのあることを声明(一)(三)で指摘してきた。しかし「新しい領解文」について危惧される文言は第三段落にもあり、それはこれまでのご門主さまのご著書等には見られなかったものであることを指摘しておきたい。
み教えを依りどころに生きる者 となり
少しずつ 執われの心を 離れます
まず本段の冒頭には「み教えを依りどころに生きる者 となり」という文言があるが、これは「ご親教(浄土真宗のみ教え)」の時点(二〇二一年四月一五日)では、直前の「仏恩報謝の お念仏」の語を承けて述べられていた内容であった。しかし「新しい領解文」では、阿弥陀如来の本願をさしおいて、「宗祖親鸞聖人と 法灯を伝承された 歴代宗主の 尊いお導き」によって「み教えを依りどころに生きる者」になるように文脈が変化しており、唐突に感じられる。これは声明(三)に指摘したように、十分な検討もなされないまま〈師徳〉が挿入されたためと考えられるが、このような文脈で語られる内容も、ご法義に照らして違和感を覚えるところである。
そして、この一段で最大の問題となるのは、つづく「少しずつ 執われの心を 離れます」という表現である。我々は煩悩具足の凡夫である。執われの心を離れるというのは、果たして浄土真宗のみ教えなのだろうか。
ご門主さまは、伝灯報告法要(二〇一六年一〇月一日)に際して発表された「ご親教(念仏者の生き方)」において、私たちが「我執、我欲の世界に迷い込み、そこから抜け出せない私」であり「この命を終える瞬間まで、我欲に執われた煩悩具足の愚かな存在」であることを明確にお示しになっておられる。その前提の上で、
しかし、それでも仏法を依りどころとして生きていくことで、私たちは他者の喜びを自らの喜びとし、他者の苦しみを自らの苦しみとするなど、少しでも仏さまのお心にかなう生き方を目指し、精一杯努力させていただく人間になるのです。
と述べられている。この念仏者の生き方に関する内容は、ご門主さまが常々お示しくださっていることであるが、その際には必ず「煩悩を離れることはできない」ことを厳格に押さえた上でのご教示であった。
しかしながら、このたびの「新しい領解文」では、その前提もないどころか、「少しずつ 執われの心を 離れます」という文言のみが示されている。これは第一段落において、煩悩具足の凡夫という機実(私の真実のあり方)を押さえることなく、むしろ煩悩とさとりとを「本来一つ」と表現していることとも関連する重大な問題である。煩悩具足という機実を離れて、浄土真宗の本義はない。そして、みずから執着の心を離れることができるのであれば、如来の本願建立の理由すらも失われてしまうであろう。これまでご法義を大切にされてきた全国の僧侶・門信徒が、今回の「新しい領解文」によって困惑した大きな要因の一つが、ここにあると言えよう。これは浄土真宗のみ教えの根幹に関わる問題である。
たしかに、前掲の「ご親教」において引用されている親鸞聖人の『御消息』には、本願を聞く者はおのずとその生き方を変えられていくことが、次のように説かれている。
もとは無明の酒に酔ひて、貪欲・瞋恚・愚痴の三毒をのみ好みめしあうて候ひつるに、仏のちかひをききはじめしより、無明の酔ひもやうやうすこしづつさめ、三毒をもすこしづつ好まずして、阿弥陀仏の薬をつねに好みめす身となりておはしましあうて候ふぞかし。
ただし、この『御消息』の背景には、罪深き凡夫を救うという如来の本願を身勝手に理解し、「悪をおそれずに造ることこそ本願にかなっている」と主張していた異解者の存在がある。親鸞聖人はそのような理解をする者に対して、如来の本願に出遇(あ)った者は、三毒の煩悩にまみれたわが身を悲しみ、つつしむ心こそあれ、煩悩のままに悪をなすことを正当化する生き方などあり得ないことを示されているのである。このお示しは、少しずつ煩悩を離れることができるなどと言われたものではない。親鸞聖人が『一念多念文意』の中に、
「凡夫」といふは、無明煩悩われらが身にみちみちて、欲もおほく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおほくひまなくして、臨終の一念にいたるまでとどまらず、きえず、たえずと、水火二河のたとへにあらはれたり。
と示されているように、私たち凡夫は命終えるその時まで、煩悩を抱えてしか生きることができないのである。ご門主さまは、念仏者の生き方を示された同じ「ご親教」において、
我執、我欲の世界に迷い込み、そこから抜け出せない私を、そのままの姿で救うとはたらき続けていてくださる阿弥陀如来のご本願ほど、有り難いお慈悲はありません。
とも述べられている。念仏者は煩悩を抱えて生き、自分では決して迷いの世界を出ることのできない自力無功のわが身を知らされ、悲しみ、慚愧する(恥じる)心をたまわるのであるが、それと共にそのような自分こそ如来大悲のまさしき目当てであったことを知らされ、如来におまかせをして安堵し、よろこぶのである。これが二種深信といわれる真実信心のすがたであり、この両面があってこそ、ご門主さまが常々お示しになられている念仏者の生き方が成立していくのであろう。それは「少しずつ 執われの心を 離れます」とのみ表現されるような生き方とは、異質のものである。
以上、第三段落に「少しずつ 執われの心を 離れます」とのみ示された文言は、浄土真宗の本義を逸脱するものであり、ご門主さまのご本意に沿うものとも思えない。したがって浄土真宗の領解を示す文言としてはふさわしくないと言わざるを得ない。本願寺派総局は、ご門主さまが示された伝灯報告法要の「ご親教」のこころに立ち戻り、そのお示しを真摯に受け止め、速やかに「新しい領解文」を取り下げて、本来の宗意安心に立ち戻るべきである。
最後に、この声明文は本願寺派の勧学・司教有志により発するものであるが、その「志」(こころざし)とは、ご法義を尊び、ご門主さまを大切に思う、愛山護法の志であることはいうまでもない。
合掌
二〇二三年 五月五日
浄土真宗本願寺派 勧学・司教有志の会
代表 深川 宣暢(勧学)
森田 眞円(勧学)
普賢 保之(勧学)
武田 宏道(勧学)
宇野 惠教(勧学)
内藤 昭文(司教)
安藤 光慈(司教)
楠 淳證(司教)
佐々木義英(司教)
東光 爾英(司教)
殿内 恒(司教)
武田 晋(司教)
藤丸 要(司教)
能仁 正顕(司教)
松尾 宣昭(司教)
福井 智行(司教)
井上 善幸(司教)
藤田 祥道(司教)
武田 一真(司教)
井上 見淳(司教)
他数名
通仏教、聖道門自力行であれば、まあ、大丈夫かなと、普通になる表現が続く後段ですが、浄土真宗では、凡夫ではどうしようもないほどに致し方もない煩悩、執着、愚心を、何よりも深く深く自覚していくことが大切なことになります。
執着を離れることなど、とてもとてもできない凡夫へと向けてこその尊く有り難い弥陀本願であるわけです。
「みずから執着の心を離れることができるのであれば、如来の本願建立の理由すらも失われてしまう」
ということであります。
更に次弾も雑修、雑行、雑善の勧めを少なくとも未信者へ向けて述べたてることには全く意味がないと、厳しくご裁定なさられることでしょう。
「新しい領解文」(浄土真宗のみ教え)に対する声明(四)
このたびご消息として発布された「新しい領解文(浄土真宗のみ教え)」(以下、「新しい領解文」)の内容について、勧学・司教有志の会は第一段落・第二段落について、宗祖親鸞聖人のご法義に重大な誤解を生ずるおそれのあることを声明(一)(三)で指摘してきた。しかし「新しい領解文」について危惧される文言は第三段落にもあり、それはこれまでのご門主さまのご著書等には見られなかったものであることを指摘しておきたい。
み教えを依りどころに生きる者 となり
少しずつ 執われの心を 離れます
まず本段の冒頭には「み教えを依りどころに生きる者 となり」という文言があるが、これは「ご親教(浄土真宗のみ教え)」の時点(二〇二一年四月一五日)では、直前の「仏恩報謝の お念仏」の語を承けて述べられていた内容であった。しかし「新しい領解文」では、阿弥陀如来の本願をさしおいて、「宗祖親鸞聖人と 法灯を伝承された 歴代宗主の 尊いお導き」によって「み教えを依りどころに生きる者」になるように文脈が変化しており、唐突に感じられる。これは声明(三)に指摘したように、十分な検討もなされないまま〈師徳〉が挿入されたためと考えられるが、このような文脈で語られる内容も、ご法義に照らして違和感を覚えるところである。
そして、この一段で最大の問題となるのは、つづく「少しずつ 執われの心を 離れます」という表現である。我々は煩悩具足の凡夫である。執われの心を離れるというのは、果たして浄土真宗のみ教えなのだろうか。
ご門主さまは、伝灯報告法要(二〇一六年一〇月一日)に際して発表された「ご親教(念仏者の生き方)」において、私たちが「我執、我欲の世界に迷い込み、そこから抜け出せない私」であり「この命を終える瞬間まで、我欲に執われた煩悩具足の愚かな存在」であることを明確にお示しになっておられる。その前提の上で、
しかし、それでも仏法を依りどころとして生きていくことで、私たちは他者の喜びを自らの喜びとし、他者の苦しみを自らの苦しみとするなど、少しでも仏さまのお心にかなう生き方を目指し、精一杯努力させていただく人間になるのです。
と述べられている。この念仏者の生き方に関する内容は、ご門主さまが常々お示しくださっていることであるが、その際には必ず「煩悩を離れることはできない」ことを厳格に押さえた上でのご教示であった。
しかしながら、このたびの「新しい領解文」では、その前提もないどころか、「少しずつ 執われの心を 離れます」という文言のみが示されている。これは第一段落において、煩悩具足の凡夫という機実(私の真実のあり方)を押さえることなく、むしろ煩悩とさとりとを「本来一つ」と表現していることとも関連する重大な問題である。煩悩具足という機実を離れて、浄土真宗の本義はない。そして、みずから執着の心を離れることができるのであれば、如来の本願建立の理由すらも失われてしまうであろう。これまでご法義を大切にされてきた全国の僧侶・門信徒が、今回の「新しい領解文」によって困惑した大きな要因の一つが、ここにあると言えよう。これは浄土真宗のみ教えの根幹に関わる問題である。
たしかに、前掲の「ご親教」において引用されている親鸞聖人の『御消息』には、本願を聞く者はおのずとその生き方を変えられていくことが、次のように説かれている。
もとは無明の酒に酔ひて、貪欲・瞋恚・愚痴の三毒をのみ好みめしあうて候ひつるに、仏のちかひをききはじめしより、無明の酔ひもやうやうすこしづつさめ、三毒をもすこしづつ好まずして、阿弥陀仏の薬をつねに好みめす身となりておはしましあうて候ふぞかし。
ただし、この『御消息』の背景には、罪深き凡夫を救うという如来の本願を身勝手に理解し、「悪をおそれずに造ることこそ本願にかなっている」と主張していた異解者の存在がある。親鸞聖人はそのような理解をする者に対して、如来の本願に出遇(あ)った者は、三毒の煩悩にまみれたわが身を悲しみ、つつしむ心こそあれ、煩悩のままに悪をなすことを正当化する生き方などあり得ないことを示されているのである。このお示しは、少しずつ煩悩を離れることができるなどと言われたものではない。親鸞聖人が『一念多念文意』の中に、
「凡夫」といふは、無明煩悩われらが身にみちみちて、欲もおほく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおほくひまなくして、臨終の一念にいたるまでとどまらず、きえず、たえずと、水火二河のたとへにあらはれたり。
と示されているように、私たち凡夫は命終えるその時まで、煩悩を抱えてしか生きることができないのである。ご門主さまは、念仏者の生き方を示された同じ「ご親教」において、
我執、我欲の世界に迷い込み、そこから抜け出せない私を、そのままの姿で救うとはたらき続けていてくださる阿弥陀如来のご本願ほど、有り難いお慈悲はありません。
とも述べられている。念仏者は煩悩を抱えて生き、自分では決して迷いの世界を出ることのできない自力無功のわが身を知らされ、悲しみ、慚愧する(恥じる)心をたまわるのであるが、それと共にそのような自分こそ如来大悲のまさしき目当てであったことを知らされ、如来におまかせをして安堵し、よろこぶのである。これが二種深信といわれる真実信心のすがたであり、この両面があってこそ、ご門主さまが常々お示しになられている念仏者の生き方が成立していくのであろう。それは「少しずつ 執われの心を 離れます」とのみ表現されるような生き方とは、異質のものである。
以上、第三段落に「少しずつ 執われの心を 離れます」とのみ示された文言は、浄土真宗の本義を逸脱するものであり、ご門主さまのご本意に沿うものとも思えない。したがって浄土真宗の領解を示す文言としてはふさわしくないと言わざるを得ない。本願寺派総局は、ご門主さまが示された伝灯報告法要の「ご親教」のこころに立ち戻り、そのお示しを真摯に受け止め、速やかに「新しい領解文」を取り下げて、本来の宗意安心に立ち戻るべきである。
最後に、この声明文は本願寺派の勧学・司教有志により発するものであるが、その「志」(こころざし)とは、ご法義を尊び、ご門主さまを大切に思う、愛山護法の志であることはいうまでもない。
合掌
二〇二三年 五月五日
浄土真宗本願寺派 勧学・司教有志の会
代表 深川 宣暢(勧学)
森田 眞円(勧学)
普賢 保之(勧学)
武田 宏道(勧学)
宇野 惠教(勧学)
内藤 昭文(司教)
安藤 光慈(司教)
楠 淳證(司教)
佐々木義英(司教)
東光 爾英(司教)
殿内 恒(司教)
武田 晋(司教)
藤丸 要(司教)
能仁 正顕(司教)
松尾 宣昭(司教)
福井 智行(司教)
井上 善幸(司教)
藤田 祥道(司教)
武田 一真(司教)
井上 見淳(司教)
他数名