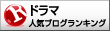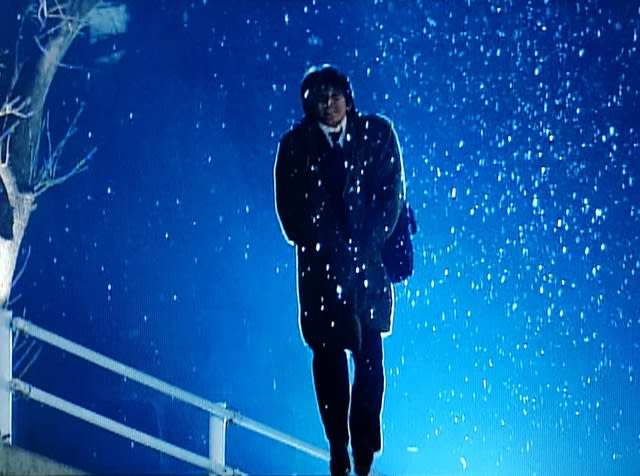




さて、管内で殺人事件が起こったというのに「所轄だから」という理由で現場検証にすら参加させてもらえず、和久さん(いかりや長介)と一緒にトボトボ湾岸署に戻った青島(織田裕二)は、ようやく強行犯係の同僚たちと初対面します。
出勤時に誰もいなかった理由は、魚住係長(佐戸井けん太)が弁当の買い出し、袴田課長(小野武彦)が署長の接待ゴルフ、真下刑事(ユースケ・サンタマリア)が昇進試験の受験勉強で、それぞれ忙しかったからw これもあくまで君塚良一さん流のジョークだと思いたいですね。
かように刑事たちが事件じゃなく日々の雑用に追われる感じは、後の『デカワンコ』を彷彿させます。魚住係長が部下たちにしつこく健康診断の受診を促す描写も『デカワンコ』でパロってましたw そうして遺伝子は受け継がれて行くんですよね。
結局、やることが無い青島は忙しい盗犯係を手伝うことになり、すみれ(深津絵里)の聞き込み捜査について行くんだけど、そこでもパトカーは使わずタクシー移動w 青島は脱サラして刑事になったというのに、これじゃ営業回りと何も変わりません。
「なんか、サラリーマンみたいだな……」
「刑事はヒーローじゃない、公務員よ。警察署はアパッチ砦じゃない、会社なの」
すみれが自虐的に言ったこの台詞に、『踊る大捜査線』が大ヒットする理由の1つが端的に表れてます。つまり、それまで憧れのヒーローだった刑事ドラマの主人公たちが、我々視聴者と同じ悩みを抱えた身近な存在に、つまり自己投影しやすい対象になったんですよね。
そして『踊る~』でもう1つ画期的だったのが、警察の細かい日常業務を丁寧に、そして面白おかしく描いたこと。和久さんが「これだけは所轄の仕事だ」と言って取り組んだのは、会議室に貼り出す捜査本部の戒名を書く仕事。単なるお習字ですw
で、その戒名を考えるのは神田署長(北村総一朗)や秋山副署長(斉藤 暁)たちの仕事。
「インパクトが無いねえ」「『凶悪』って文字入れようよ」「レインボーブリッジの名前使ってみたいね」等とけんけんがくがく議論した結果、貼り出されたのが『会社員殺人事件特別捜査本部』という平凡極まる戒名だったのには笑いましたw
そうして捜査会議が開かれ、捜査の割り振りも決まるワケだけど、青島に回って来たのは室井管理官(柳葉敏郎)の運転手という、やっぱりただの雑用仕事なのでした。
それでも本部のトップと捜査について語り合うチャンスとばかりに、青島は車内であれこれ質問攻めするんだけど、室井は眉間にシワを寄せてこう言います。
「捜査はこっちでやるから、キミは運転だけしてくれ」
捜査について語り合うことも出来ないという、この絶望的な格差。室井がまた極端に取っつきにくいキャラクターで、距離を縮めるすべは一切無さそうに見えます。
で、青島の運転で室井が向かった先は、遺体の第一発見者であり被害者の娘である柏木雪乃(水野美紀)が入院中の病院。精神的ショックで口が聞けない状態の雪乃を、室井は「犯人の可能性だってある」との理由で容赦なく質問攻めするのでした。
捜査の鬼で、弱者の味方にはとても見えない室井に、青島は失望します。この場面では本庁の刑事たちが室井の陰口を叩く様子も描かれ、彼が組織内で孤立してることが示唆されます。
地方(東北大)出身の室井は、同じキャリア組でも東大出身の連中から差別されてるんですね。だから偉くなって見返してやりたい、その為には鬼に徹して実績を上げなきゃいけない。所轄もツラいけど、実はキャリアもキャリアでツラいワケです。
そんな二重構造の設定が、このシリーズに深みを与えてますよね。室井が青島の味方について以降、つまり劇場版シリーズに登場するキャリアたちはステレオタイプな悪役ばかりで、青島や和久さんに名台詞を吐かせる為の狂言回しに過ぎず、『踊る~』から深みを無くしちゃいました。だから『踊る~』はTVシリーズだけで終わるべきだったんです。
劇場版のことに触れると愚痴が止まらないのでw、テレビ版に話を戻します。
室井の送迎を終えた青島が署に戻ると、バッグに合鍵の束を隠し持ってた田中という男(近藤芳正)が連行されて来て、多忙な盗犯係に替わって青島が取調べする羽目になります。
「ほかの係の手伝いばっかじゃねえか……」
ストレスが溜まる一方の青島は、田中の職業が保険会社の営業マンと聞いて、知らず知らず愚痴をこぼしちゃいます。同じく営業マンだった青島がなぜ刑事に転職したのか、その理由もここで明かされます。
「毎日毎日おんなじ人のとこ行って、ペコペコペコペコ頭下げて……僕には耐えらんなかった。キミもでしょ?」
「僕は、別に」
「うそうそ。生活マンネリで刺激なくて、毎日つまんないクセに」
「そんなことないです、楽しいですよ」
「……営業先のお得意さんに言われたよ。キミが来るとウチの社員の手が止まる、キミはウチの会社の寄生虫か?って」
「寄生虫ですか……」
「そう。その日に辞めた。人間でいたかったから」
そんな青島も、警官になって交番勤務に就いてからは、毎日いろんな刺激があり、頑張れば地域の人たちに感謝されもし、やり甲斐を感じるようになった。
「脱サラして良かったですね」
「……でも、念願の刑事になったら、ここは前と変わんないよ」
「そうなんですか?」
「殺人事件があったのに捜査させてくんないんだよ、所轄の刑事はさ」
「どうしてですか?」
「大きな事件っていうのはね、本店が仕切る」
「本店?」
「警視庁。うちは支店」
「ええ? 警察でもそう言うんですか」
「サラリーマンやってた時と変わんないもんなあ」
「大変なんですね、色々と」
同世代で同じ職種を経験した者どうし、なんとなく心が通じ合う二人だけど、青島は再び室井管理官の送迎に駆り出され、取調べは盗犯係に引き継がれます。結局、合鍵の束を持ってるだけじゃ犯罪行為を立証できず、田中は釈放されるのでした。
よその係の手伝いや雑用に振り回され、モチベーションを失いかけてる青島を見て、すみれは自分自身の新米時代を思い出します。
「私も刑事になった頃は、張り切りすぎて空回りしてたなあ……」
そんなすみれに、和久さんがここぞとばかりに、味のある台詞を決めます。
「みんなそうさ。タンコブが出来るまではな」
「タンコブ?」
「事件をいくつもやってく内に、被害者と関わるとな、俺たち刑事も傷つくことがある。そのタンコブが、まだアイツには無いのさ」
そう言いながら和久さんは、わざとらしく過去の未解決事件の資料に目を通すのでした。
「また昔の事件の資料読んでるんですか?」
「ん……これは、俺のタンコブだ。この事件解決するまで、俺の傷は治らねえ!……なんてな (笑) 」
その事件の内容は後のエピソードで明かされますが、この、いかにも名演してますっていう和久さん=いかりや長介さんの芝居が、私はどうにも好きになれません。わざとらしいし、口先でモゴモゴ言っててすこぶる聞き取りづらい。
同じ「いぶし銀」でも『太陽にほえろ!』の山さん=露口 茂さんは「あざとさ」を感じさせなかったし、どんなに小声でも台詞は一言一句明瞭に聞き取れました。そこはやっぱ、格が違うんだよと言わざるを得ません。
一方、再び雪乃の病室を訪れた室井は、ある策略を立ててました。
「病室にわざと写真を忘れて来た、取って来てくれ。そして何か思い出したかと聞くんだ」
室井にそう言われて青島が病室へ行くと、雪乃が泣きながら写真を見つめてる。それは殺害現場の検証写真、つまり雪乃の父親の遺体を撮った写真だった!
『太陽にほえろ!』のマカロニやジーパンだったら怒り心頭、後先考えず室井に抗議するか、下手すりゃパンチを浴びせかねないけど、『踊る~』の世界では許されません。ぐっと堪えて本音を呑み込む青島に、室井は言います。
「警察の捜査に協力するのは市民の義務だ。キミは刑事になりたてか?」
「はい……先週まで交番勤務でした」
「交番勤務の時は市民のために働いてたんだろうが、これからはそんな考えは捨てた方がいい。犯人逮捕が第一。市民の気持ちなどには構ってられない」
『太陽~』のスコッチ刑事(の初期)に負けないくらい冷徹で、ガチガチに閉ざされた室井の心。それを青島が、元営業マンならではのコミュニケーション術で開かせていく過程は、このTVシリーズ最大の見所と言っても過言じゃないぐらい感動的で、私は最終回を観て号泣した記憶があります。
映画版が残念だった最大の理由も、多分そこにあります。二人がすでに友情を結んだ状態で映画は始まりますから、そこにドラマが生まれない。TVシリーズで肝になってた部分がすっぽり抜け落ちてるワケです。
また映画版の愚痴になっちゃいましたm(__)m でもホントに、それだけTVシリーズと映画版とじゃ伝わって来るものが全然違う。要するに青島俊作の物語はテレビの最終回で完結してるんですよね。全11話で語るべきことは語り尽くしたんです。つくづく、そこで終わっとけば良かった。
閑話休題。捜査本部が立ち上がってから僅か3日目にして、事件は唐突に終焉を迎えます。雪乃の父親を殺した犯人が、自ら交番に出頭して来たのでした。
「本店」の刑事たちにより連行されて来た、その男の顔を見て青島は愕然となります。犯人は、つい昨日、自分が取調べた……と言うより愚痴を聞いてもらった、あの保険マンの田中だった!
思わず駆け寄った青島に、田中はむしろ晴れやかな顔をして言います。
「あんたに、言いたい事あって自首したんだ……殺すつもり無かった。忍び込むのが楽しかったのに、見つかっちゃって……」
「…………」
「あんたの言った通りだ。本当は、僕も毎日刺激なかったんだ」
「……キミも刑事になれば良かったのに」
「……でも、そっちも刺激ないんでしょ?」
「……あるよ。毎日ドキドキしてる」
「……そう……いいな」
昨日たまたま交番巡査の職務質問に引っ掛かり、窃盗の疑いで連行されて来た男が、実は殺人事件の真犯人だったという、万に一つあるか無いかの偶然。これも『踊る~』がよく使う手で、今回は1発目ゆえ効果バツグンだったけど、あまりに何度も繰り返し過ぎて、映画版では「んなワケあるかい!」って、ただただシラケるだけでした。だいたい、映画版がなってないのは……やめときましょうw
そんなことより注目すべきは、このあと青島がすみれに漏らした、この言葉です。
「俺がアイツになってたかも知れない……」
あれ? 刑事の心情が犯人のそれとリンクする『太陽にほえろ!』式の作劇って、禁じ手にしたんじゃなかったの?って一瞬思うんだけど、これもたぶん逆説的な意味なんですよね。
『太陽~』では刑事が自身の影を感じた犯人を逮捕する、あるいは射殺しちゃう悲劇が描かれたけど、このエピソードの場合は犯人の側が刑事に共感し、自首をするというハッピーエンドになってる。やっぱり真逆なんですよね。
冷静に考えればえらく強引な話で、刑事に共感したからって、それだけで殺人犯が自首するか?とは思うんだけどw、初めて観た時は意表を突かれて「やられた!」「こりゃ面白い!」ってなっちゃう。つまりエンターテイメントとして成立してる。
そう、『踊る大捜査線』で最も衝撃的だったのがコレです。主人公が捜査せず、逮捕もしてない。当然ながらアクションシーンも説得シーンも無い。なのに、なぜかこれが面白い!
それはやっぱり、画期的に新しかったと思います。たとえ映画版の大ヒットが無くても、この瞬間『踊る大捜査線』は刑事ドラマの歴史に刻まれる作品になりました。むしろ映画版さえ無ければ『踊る~』はもっと伝説化し、リスペクトされてた筈。そもそも映画版のダメなところは……(省略)
「僕、刑事になったばかりなんです。まだ右も左も分かんないし、なにも、分からない事だらけなんですけど……」
青島が語りかけてる相手は、雪乃。もう事件は終わったから、被害者には関わるなと室井に釘を刺されたのに、青島は一人で病室を訪ねたのでした。
「ただ、犯人がいくら捕まったからと言って、被害に遭った人のことをすぐに忘れろって言うのは……そういう刑事には、なりたくないんです」
「…………」
「また来ます」
もちろん、雪乃の閉ざされた心も、ゆくゆくは青島が開かせることになります。当初は青島&雪乃、そして室井&すみれの恋愛、あるいは青島・すみれ・雪乃の三角関係、つまりラブストーリー展開が予定されてたのに、同じフジテレビで放映中だった恋愛物とのブッキングを避けるため中止になった、てな裏事情はファンの間じゃ有名な話。そうならなくて良かったです。
そんなワケで、本当に『踊る大捜査線』のTVシリーズは革命的な作品だった、っていうお話でした。
だけど、再三書いて来たように、その面白さはテレビ番組だからこそ成立した。テレビ番組だからこそ革命的であり得たんです。
そもそも日本映画で描かれる警察は、昔からリアルでした。さんざん荒唐無稽なことをして来たテレビの刑事ドラマだからこそ、『踊る~』のリアルさが新鮮に感じられたワケです。
また、全国規模で公開するメジャー映画となると大がかりな見せ場を作らざるを得なくなり、すると結局スタンダードな刑事物に戻って行っちゃうんですよね。
あらゆる意味で、テレビ番組だからこそ活きた『踊る大捜査線』の良さが、映画化することでどんどん消去され、どう贔屓目に観てもつまんないものになり果てた。
にも関わらず大ヒットしたのは、TVシリーズを観た人たちが「これは凄い」とインターネットで騒いだからであり、映画そのものの力じゃなかったんだと私は思います。
「平成」に代わる新元号が「令和」に決まった時、駅で配られる新聞の号外に大衆が群がり、やむなく配布を中止する駅もあったとか、その号外がネットオークションで1万円で売れてるとかいう報道を見た時、私は本当に心底驚きました。みんな一体、なんでそんな物が欲しいの? なんでそんな物にそんな値段がつくの?って。
その理由を考えると、答えは「みんなが欲しがるから」の1つしか無いんですよね。
まず、ああいうのを記念に保管したがるコレクター気質の人らが飛びつき、それを見た通りすがりの人らが「え、何があったの?」と寄って来て、それが大人数になればなるほど「これはゲットすべき物なんだ!」って、皆が催眠術にかかっちゃった。冷静に考えればあんな紙切れにそんな価値があるワケ無いのに、みんな陶酔状態で感覚が麻痺しちゃってる。集団心理の恐ろしさです。
劇場版『踊る大捜査線』シリーズの異常な大ヒットも、それと似たようなもんだろうと思います。本当はTVシリーズほど斬新でも面白くもないのに、みんなが絶賛するもんだから錯覚に陥っちゃった。『君の名は。』も『カメラを止めるな!』も同じで、極端にヒットした作品には多かれ少なかれそういう側面がある。
劇場版の1作目はまだ、TVシリーズの総集編リメイクみたいなもんだから、それなりの面白さはありました。だけど2作目以降はもう、ヒット狙い丸出しの典型的アトラクション映画に成り下がり、ひたすら「あざとさ」しか感じられない代物になっちゃった。
でもそれは当たり前のことなんですね。1作目がヒットすれば次はそれを超えることが目標になり、予算が増えれば増えるほど失敗が許されなくなる。そうなると「おんな・こども」が喜ぶ要素をてんこ盛りにせざるを得ず、「新しさ」なんか入り込む余地が無くなっちゃう。
『踊る~』に限らず、日本のメジャー映画はどれもこれも似たような作りになってしまい、新しさを求めるコアなファンはお呼びじゃない世界になっちゃった。破滅です。
そんな傾向は確実に日本のメジャーシーンの首を締めてます。『踊る大捜査線』のお陰で大出世した亀山千広プロデューサーが、ついに社長にまで上り詰めた途端フジテレビが失速し、けっきょく退任に追い込まれた事実が全てを物語ってます。
せっかく歴史的な傑作になった刑事ドラマ『踊る大捜査線』を、生みの親が自ら商売と名声のために利用し、食い尽くした、典型的な成れの果てです。
だから私は、『踊る大捜査線』が大好きであると同時に、虫酸が走るほど大嫌いなんです。