メタエンジニアの眼シリーズ(153)
TITLE: ビジョナリー・カンパニー KMB4139
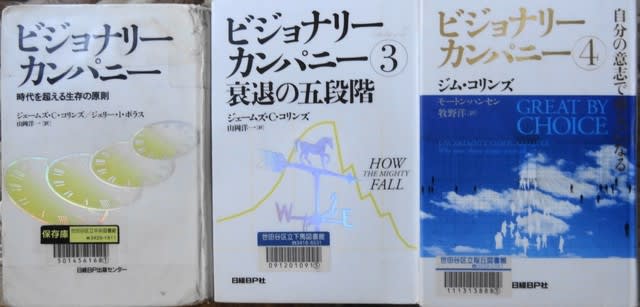
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。
『』内は,著書からの引用部分です。
書籍名;『ビジョナリー・カンパニー』 [1995]
著者;ジェームズ・コリンズ、ジェリー・ポラス
発行所;日経BP出版センター 発行日;1995.9.29
初回作成日;R2.1.8 最終改定日;
副題は「時代を超える生存の原則」で、このシリーズの1冊目になる。原本の発行は1994年。シリーズの第4巻「自分の意志で偉大になる」は8年後の2002年の発行。その間は、第2巻「飛躍の法則」、第3巻「衰退の第5段階」となっている。この時点では、コリンズとポラスはともにスタンフォード大学教授だった。
冒頭の「はじめに」で目的と方法、結論が纏められている。
『この世のすべての経営者、経営幹部、起業家は、本書を読むべきである。取締役も、コンサルタントも、投資家も、ジャーナリストも、ビジネス・スクールの学生も、この世でとくに長く統き、とくに成功している企業の特徴に関心があるすべての人は、本書を読むべきである。わたしたちが大胆にもこう主張するのは、手前味暫ではない。ここで紹介した企業には、学べることが多いからだ。
この調査プロジェクトも、本書も、わたしたちが知るかぎり、はじめての試みである。設立年が平均で一八九七年という、時の試練を乗り越えてきた真に卓越した企業を選び出し、設立から現在に至るまでの発展の軌跡をあますところなく調査した。さらに、同じような機会がありながら、同じようには成長できなかった別の優良企業と比較分析した。創業時の様子を調べた。中堅企業だったころを調べた。大企業に発展してからを調べた。戦争、不況、技術革新、文化の変化など、周囲の世界の劇的な変化をどのように乗り切ったかを調べた。このプロジェクトの全体を通じて、こう問い続けた。 「真に卓越した企業と、それ以外の企業との違いはどこにあるのか。』(pp.なし)
この文章は、自信過剰にも思えるのだが、彼らが行った調査の方法と念入りに行った過程を知れば、当然のように思う。特にポラスはその道の専門家だった。
調査の過程で分かったことは、
『「革新的な」経営手法も、決して新しくはないことが明らかになった。従業員持ち株制度、権限の委譲、不断の改善、総合的品質管理、経営理念の発表、価値観の共有といった今日の経営手法の多くは、場合によっては一八〇〇年代にはじまった慣行に、新しい衣装をまとわせたものにすぎない。』(pp.なし)
つまり、その時代に盛んに発行された、新たな経営手法を絶賛する著書を暗に批判している。そして、意外なことも分かった。
『広く信じられている神話が十二も覆された。従来の枠組みは疑問符がつけられ、崩れていった。このプロジェクトの途中で、わたしたちは方向を見失った。わたしたちの先人観や「常識」に反するデータが、次々に集まってきたからだ。先入観や知識を捨てなければ、新しい概念を生み出すことはできない。古い枠組みを捨て去り、新しい枠組みを、ときには最初から組み立てなければならなかった。この作業には、六年かかった。しかし、そうするだけの価値はあった。』(pp.なし)
そして、最後に「教訓」として、このように結んでいる。
『何よりも、本書のなかにある教訓は、「自分には関係のないもの、とても活かせないもの」ではないと、 自信と意欲を持ってほしい。だれでも、教訓を学べる。だれでも、その教訓を活かせる。だれでも、ビジョナリー・カンバニーを築けるのであるる。』(pp.なし)
私は、現役時代に多くのアンケートを依頼したり、答えたりした。経験上は、日本人の回答は建前論が多く、信用度は高くないが、アメリカ人の回答は率直で本音を語っているように思えた。つまり、この結果には大いに興味が湧く。そこで、この部分に限って、詳細に検討する。
「12の崩れた神話」について、その理由が丁寧に語られている。
『教訓一 すばらしい会社をはじめるには、すばらしいアイデアが必要である。
「すばらしいアイデア」を持って会社をはじめるのは、悪いアイデアかもしれない。ビジナリー・カンパニーには、具体的なアイデアをまったく持たずに設立されたものもあり、スタートで完全につまずいたものも少なくない。さらに、会社設立の構想に関係なく、設立当初から成功を収めた企業の比率は、比較対象企業よりビジョナリー・カンパニーの方がかなり低かった。ウサギとカメの寓話のように、ビジョナリー・カンパニーはスタートでは後れをとるが、長距離レースには勝つことが多い。』(pp.11)
このことは、すばらしいアイデアが必要条件でも、十分条件でもないというだけで、そのことに拘るのは善くない、とのことだろう。スタート時に集まった人材が問題。
『神話二 ピジョナリー・カンパニーには、ピジョンを持った偉大なカリスマ的指導者が必要である。
ピジョナリー・カンパニーにとって、ピジョンを持った偉大なカリスマ的指導者はまったく必要ない。
こうした指導者はかえって、会社の長期の展望にマイナスになることもある。ビジョリー・カンパニーの歴代のCEO (最高経営責任者)のなかでもとくに重要な人物には、世間の注目を集めるカリスマ的指導者のモデルにあてはまらない人もおり、むしろ、そうしたモデルを意識して避けてきた人もいる。』(pp.11)
これも、神話一と同じ根っこのはなしに思える。
『神話三 とくに成功している企業は、利益の追求を最大の目的としている。
ビジネス・スクールの教えに反して、「株主の富を最大限に高めること」や「利益を最大限に増やすこと」は、ビジョナリー・カンパニーの大きな原動力でも、最大の目標でもない。』(pp.12)
このことは、21世紀には顕著になるのだが、当時下降気味だった米経済の中での発言は興味深い。
『神話四 ピジョナリー・カンパニーには共通した「正しい」基本的価値観がある。
ビジョナリー・カンパニーであるための基本的価値観に、「正解」と言えるものはない。二社をとってみると、対照的とも言えるほど理念が違っているケースもある。』(pp.12-13)
会社経営は、他社の真似では成功しないということ。
『神話五 変わらない点は、変わり続けることだけである。
ビジョナリー・カンパニーは、基本理念を信仰に近いほどの情熱を持って維持しており、基本理念は変えることがあるとしても、まれである。ビジョナリー・カンパニーの基本的価値観は揺るぎなく、時代の流れや流行に左右されることはない。』(pp.13)
ここからは「基本理念」という言葉が多発してくる。「基本理念」だけは、長期間維持すべきとのことらしい。それは、「基本的価値観」と同義語に扱われている。
『神話六 優良企業は、危険を冒さない。
ビジョナリー・カンバニーは、外部からみれば、堅苦しく、保守的だと思えるかもしれない。しかし、・・・。』(pp.13-14)
特に、「社運を賭けた大胆な目標」にチャレンジする姿勢を評価している。
『神話七 ビジョリー・カンパニーは、だれにとってもすばらしい職場である。
ビジョナリー・力ンパニーは、その基本理念と高い要求にぴったりと「合う」者にとってだけ、すばらしい職場である。』(pp.14)
後に出てくるのだが、社内基準は厳しいものがあるのが特徴で、それに合わなければならないということ。
『神話八 大きく成功している企業は、綿密で複雑な戦略を立てて、最善の動きをとる。
ビジョナリー・カンパニーがとる最善の動きのなかには、実験、試行錯誤、臨機応変によって、そして、文字どおりの偶然によって生まれたものがある。あとから見れば、じつに先見の明がある計画によるものに違いないと思えても、「大量のものを試し、うまくいったものを残す」方針の結果であることが多い。』(pp.14-15)
このやり方は、最近のコンビニが採用しているように思う。大会社になったのだから、できることとも云える。
『神話九 根本的な変化を促すには、社外からCEOを迎えるべきだ。
ビジョナリー ・カンパニーの延べ千七百年の歴史のなかで、社外からCEOを迎えた例はわずか四回、
それも二社だけだった。』(pp.15)
社外CEOは、一時は業績改善になるが、しょせん「基本理念」が異なるということなのだと思われる。
『神話十 最も成功している企業は、競争に勝つことを第一に考えている。
ビジョナリー・カンパニーは、自らに勝つことを第一に考えている。これらの企業が成功し、競争に勝っているのは、最終目標を達成しているからというより、「明日にはどうすれば、今日よりうまくやれるか」と厳しく問い続けた結果、自然に成功が生まれてくるからだ。』(pp.14-15)
どの世界でも、「自らに勝つことを第一に考えている」は、当てはまるのではないだろうか。
『神話十一 二つの相反することは、同時に獲得することはできない。
ビジョナリー・カンパニーは、「ORの抑圧」で自分の首をしめるようなことはしない。 「ORの抑圧」とは、手に入れられるのはAかBのどちらかで、両方を手に入れることはできないという、いってみれば理性的な考え方である。しかし、ビジョナリー・カンパニーは、安定か前進か、集団としての文化か個人の自主性か、生え抜きの経営陣か根本的な変化か、保守的なやり方か社運を賭けた大胆な目標か、利益の追求か価値観と目的の尊重か、といつた二者択一を拒否する。そして、「ANDの才能」を大切にする。これは逆説的な考え方で、 AとBの両方を同時に追求できるとする考え方である。』(pp.16)
つまり、多様性を捨てないということなのだろう。
『神話十ニ ビジョナリー・カンパニーになるのは主に、経営者が先見的な発言をしているからだ。
ビジョナリー・力ンバニーが成長を遂げたのは、経営者の発言が先見的だからではまったくない。(ただし、そのような発言は多い)。』(pp.16)
このことは、先に挙げられた神話六、八と十一などに通じている。
最後に、同じようテーマで発行された著書について、その内容との合否を述べている。
『おわりに
この本は、「エクセレント・カンパニー」などのほかの経営書とどういう関係にあるのか
トム・ピーターズとロバート・ウォータマンの『エクセレント・カンパニー』は過去二十年問に出版された経営書のなかで際立っており、それだけの価値がある本だ。必読書と言える。わたしたちは、本書と共通する点をいくつも見つけ出している。しかし、基本的な違いもいくつかある。違いのひとつは、調査の方法にある。わたしたちは、『エクセレンー・カンパニー』の場合とは違って、設立以米、現在に至るまで、企業の歴史の全体を対象にし、類似した企業と比較していった。もうひとつの基本的な違いは、わたしたちが調査結果をすべて、基本的な考え方の枠組みにまで煮詰めたことだろう。具体的にいえば、基本理念を維持し、進歩を促すという考え方が、調査結果のほぼすべての土台なっている。『エクセレント・カンパニー』の八つの基本的特質のうちいくつかは、わたしたちの調査でもその正しさが裏付けられている。とくに、「価値観に基づく実践の重視」、「自主性と企業家精神」、「行動の重視」、「厳しさと穏やかさの両面を同時に持つ」の四つがそうだ。』(pp.385)
たとえば、「基軸から離れない」については、「基本理念」をしっかりと持ち続ければ、基軸から離れることが成功をもたらす場合もあるとしている。
また、「顧客に密着する」については、密着することは善いことだが、それによって基本理念が侵されてはならない、としている。つまり、「基本理念」が最重要というわけのようだ。
そして、最後に21世紀には、このような考え方が、より重要視されることになるであろうとしている。その言葉は、当たっているように思える。
TITLE: ビジョナリー・カンパニー KMB4139
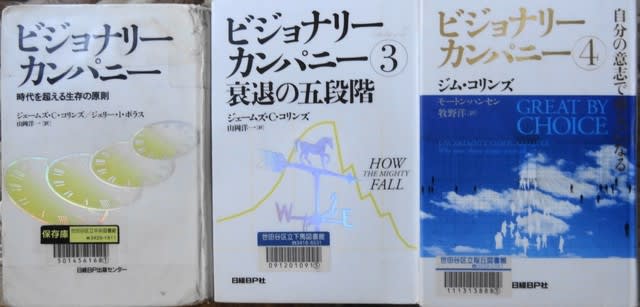
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。
『』内は,著書からの引用部分です。
書籍名;『ビジョナリー・カンパニー』 [1995]
著者;ジェームズ・コリンズ、ジェリー・ポラス
発行所;日経BP出版センター 発行日;1995.9.29
初回作成日;R2.1.8 最終改定日;
副題は「時代を超える生存の原則」で、このシリーズの1冊目になる。原本の発行は1994年。シリーズの第4巻「自分の意志で偉大になる」は8年後の2002年の発行。その間は、第2巻「飛躍の法則」、第3巻「衰退の第5段階」となっている。この時点では、コリンズとポラスはともにスタンフォード大学教授だった。
冒頭の「はじめに」で目的と方法、結論が纏められている。
『この世のすべての経営者、経営幹部、起業家は、本書を読むべきである。取締役も、コンサルタントも、投資家も、ジャーナリストも、ビジネス・スクールの学生も、この世でとくに長く統き、とくに成功している企業の特徴に関心があるすべての人は、本書を読むべきである。わたしたちが大胆にもこう主張するのは、手前味暫ではない。ここで紹介した企業には、学べることが多いからだ。
この調査プロジェクトも、本書も、わたしたちが知るかぎり、はじめての試みである。設立年が平均で一八九七年という、時の試練を乗り越えてきた真に卓越した企業を選び出し、設立から現在に至るまでの発展の軌跡をあますところなく調査した。さらに、同じような機会がありながら、同じようには成長できなかった別の優良企業と比較分析した。創業時の様子を調べた。中堅企業だったころを調べた。大企業に発展してからを調べた。戦争、不況、技術革新、文化の変化など、周囲の世界の劇的な変化をどのように乗り切ったかを調べた。このプロジェクトの全体を通じて、こう問い続けた。 「真に卓越した企業と、それ以外の企業との違いはどこにあるのか。』(pp.なし)
この文章は、自信過剰にも思えるのだが、彼らが行った調査の方法と念入りに行った過程を知れば、当然のように思う。特にポラスはその道の専門家だった。
調査の過程で分かったことは、
『「革新的な」経営手法も、決して新しくはないことが明らかになった。従業員持ち株制度、権限の委譲、不断の改善、総合的品質管理、経営理念の発表、価値観の共有といった今日の経営手法の多くは、場合によっては一八〇〇年代にはじまった慣行に、新しい衣装をまとわせたものにすぎない。』(pp.なし)
つまり、その時代に盛んに発行された、新たな経営手法を絶賛する著書を暗に批判している。そして、意外なことも分かった。
『広く信じられている神話が十二も覆された。従来の枠組みは疑問符がつけられ、崩れていった。このプロジェクトの途中で、わたしたちは方向を見失った。わたしたちの先人観や「常識」に反するデータが、次々に集まってきたからだ。先入観や知識を捨てなければ、新しい概念を生み出すことはできない。古い枠組みを捨て去り、新しい枠組みを、ときには最初から組み立てなければならなかった。この作業には、六年かかった。しかし、そうするだけの価値はあった。』(pp.なし)
そして、最後に「教訓」として、このように結んでいる。
『何よりも、本書のなかにある教訓は、「自分には関係のないもの、とても活かせないもの」ではないと、 自信と意欲を持ってほしい。だれでも、教訓を学べる。だれでも、その教訓を活かせる。だれでも、ビジョナリー・カンバニーを築けるのであるる。』(pp.なし)
私は、現役時代に多くのアンケートを依頼したり、答えたりした。経験上は、日本人の回答は建前論が多く、信用度は高くないが、アメリカ人の回答は率直で本音を語っているように思えた。つまり、この結果には大いに興味が湧く。そこで、この部分に限って、詳細に検討する。
「12の崩れた神話」について、その理由が丁寧に語られている。
『教訓一 すばらしい会社をはじめるには、すばらしいアイデアが必要である。
「すばらしいアイデア」を持って会社をはじめるのは、悪いアイデアかもしれない。ビジナリー・カンパニーには、具体的なアイデアをまったく持たずに設立されたものもあり、スタートで完全につまずいたものも少なくない。さらに、会社設立の構想に関係なく、設立当初から成功を収めた企業の比率は、比較対象企業よりビジョナリー・カンパニーの方がかなり低かった。ウサギとカメの寓話のように、ビジョナリー・カンパニーはスタートでは後れをとるが、長距離レースには勝つことが多い。』(pp.11)
このことは、すばらしいアイデアが必要条件でも、十分条件でもないというだけで、そのことに拘るのは善くない、とのことだろう。スタート時に集まった人材が問題。
『神話二 ピジョナリー・カンパニーには、ピジョンを持った偉大なカリスマ的指導者が必要である。
ピジョナリー・カンパニーにとって、ピジョンを持った偉大なカリスマ的指導者はまったく必要ない。
こうした指導者はかえって、会社の長期の展望にマイナスになることもある。ビジョリー・カンパニーの歴代のCEO (最高経営責任者)のなかでもとくに重要な人物には、世間の注目を集めるカリスマ的指導者のモデルにあてはまらない人もおり、むしろ、そうしたモデルを意識して避けてきた人もいる。』(pp.11)
これも、神話一と同じ根っこのはなしに思える。
『神話三 とくに成功している企業は、利益の追求を最大の目的としている。
ビジネス・スクールの教えに反して、「株主の富を最大限に高めること」や「利益を最大限に増やすこと」は、ビジョナリー・カンパニーの大きな原動力でも、最大の目標でもない。』(pp.12)
このことは、21世紀には顕著になるのだが、当時下降気味だった米経済の中での発言は興味深い。
『神話四 ピジョナリー・カンパニーには共通した「正しい」基本的価値観がある。
ビジョナリー・カンパニーであるための基本的価値観に、「正解」と言えるものはない。二社をとってみると、対照的とも言えるほど理念が違っているケースもある。』(pp.12-13)
会社経営は、他社の真似では成功しないということ。
『神話五 変わらない点は、変わり続けることだけである。
ビジョナリー・カンパニーは、基本理念を信仰に近いほどの情熱を持って維持しており、基本理念は変えることがあるとしても、まれである。ビジョナリー・カンパニーの基本的価値観は揺るぎなく、時代の流れや流行に左右されることはない。』(pp.13)
ここからは「基本理念」という言葉が多発してくる。「基本理念」だけは、長期間維持すべきとのことらしい。それは、「基本的価値観」と同義語に扱われている。
『神話六 優良企業は、危険を冒さない。
ビジョナリー・カンバニーは、外部からみれば、堅苦しく、保守的だと思えるかもしれない。しかし、・・・。』(pp.13-14)
特に、「社運を賭けた大胆な目標」にチャレンジする姿勢を評価している。
『神話七 ビジョリー・カンパニーは、だれにとってもすばらしい職場である。
ビジョナリー・力ンパニーは、その基本理念と高い要求にぴったりと「合う」者にとってだけ、すばらしい職場である。』(pp.14)
後に出てくるのだが、社内基準は厳しいものがあるのが特徴で、それに合わなければならないということ。
『神話八 大きく成功している企業は、綿密で複雑な戦略を立てて、最善の動きをとる。
ビジョナリー・カンパニーがとる最善の動きのなかには、実験、試行錯誤、臨機応変によって、そして、文字どおりの偶然によって生まれたものがある。あとから見れば、じつに先見の明がある計画によるものに違いないと思えても、「大量のものを試し、うまくいったものを残す」方針の結果であることが多い。』(pp.14-15)
このやり方は、最近のコンビニが採用しているように思う。大会社になったのだから、できることとも云える。
『神話九 根本的な変化を促すには、社外からCEOを迎えるべきだ。
ビジョナリー ・カンパニーの延べ千七百年の歴史のなかで、社外からCEOを迎えた例はわずか四回、
それも二社だけだった。』(pp.15)
社外CEOは、一時は業績改善になるが、しょせん「基本理念」が異なるということなのだと思われる。
『神話十 最も成功している企業は、競争に勝つことを第一に考えている。
ビジョナリー・カンパニーは、自らに勝つことを第一に考えている。これらの企業が成功し、競争に勝っているのは、最終目標を達成しているからというより、「明日にはどうすれば、今日よりうまくやれるか」と厳しく問い続けた結果、自然に成功が生まれてくるからだ。』(pp.14-15)
どの世界でも、「自らに勝つことを第一に考えている」は、当てはまるのではないだろうか。
『神話十一 二つの相反することは、同時に獲得することはできない。
ビジョナリー・カンパニーは、「ORの抑圧」で自分の首をしめるようなことはしない。 「ORの抑圧」とは、手に入れられるのはAかBのどちらかで、両方を手に入れることはできないという、いってみれば理性的な考え方である。しかし、ビジョナリー・カンパニーは、安定か前進か、集団としての文化か個人の自主性か、生え抜きの経営陣か根本的な変化か、保守的なやり方か社運を賭けた大胆な目標か、利益の追求か価値観と目的の尊重か、といつた二者択一を拒否する。そして、「ANDの才能」を大切にする。これは逆説的な考え方で、 AとBの両方を同時に追求できるとする考え方である。』(pp.16)
つまり、多様性を捨てないということなのだろう。
『神話十ニ ビジョナリー・カンパニーになるのは主に、経営者が先見的な発言をしているからだ。
ビジョナリー・力ンバニーが成長を遂げたのは、経営者の発言が先見的だからではまったくない。(ただし、そのような発言は多い)。』(pp.16)
このことは、先に挙げられた神話六、八と十一などに通じている。
最後に、同じようテーマで発行された著書について、その内容との合否を述べている。
『おわりに
この本は、「エクセレント・カンパニー」などのほかの経営書とどういう関係にあるのか
トム・ピーターズとロバート・ウォータマンの『エクセレント・カンパニー』は過去二十年問に出版された経営書のなかで際立っており、それだけの価値がある本だ。必読書と言える。わたしたちは、本書と共通する点をいくつも見つけ出している。しかし、基本的な違いもいくつかある。違いのひとつは、調査の方法にある。わたしたちは、『エクセレンー・カンパニー』の場合とは違って、設立以米、現在に至るまで、企業の歴史の全体を対象にし、類似した企業と比較していった。もうひとつの基本的な違いは、わたしたちが調査結果をすべて、基本的な考え方の枠組みにまで煮詰めたことだろう。具体的にいえば、基本理念を維持し、進歩を促すという考え方が、調査結果のほぼすべての土台なっている。『エクセレント・カンパニー』の八つの基本的特質のうちいくつかは、わたしたちの調査でもその正しさが裏付けられている。とくに、「価値観に基づく実践の重視」、「自主性と企業家精神」、「行動の重視」、「厳しさと穏やかさの両面を同時に持つ」の四つがそうだ。』(pp.385)
たとえば、「基軸から離れない」については、「基本理念」をしっかりと持ち続ければ、基軸から離れることが成功をもたらす場合もあるとしている。
また、「顧客に密着する」については、密着することは善いことだが、それによって基本理念が侵されてはならない、としている。つまり、「基本理念」が最重要というわけのようだ。
そして、最後に21世紀には、このような考え方が、より重要視されることになるであろうとしている。その言葉は、当たっているように思える。









