メタエンジニアの眼シリーズ(154)
TITLE: ビジョナリー・カンパニー
このシリーズは「企業の進化」考える際に参考にした著作の紹介です。
『』内は,著書からの引用部分です。
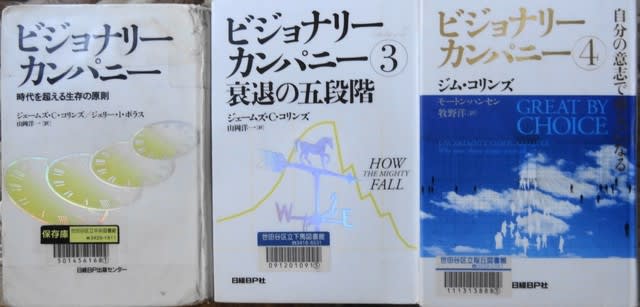
書籍名;『ビジョナリー・カンパニー3』 [2010]
著者;ジェームズ・コリンズ
発行所;日経BP社 発行日;2010.7.26
初回作成日;R2.1.10
副題は「衰退の5段階」で、このシリーズの3冊目になる。第1巻の発行は1994年。全4巻のうち、これだけがコリンズ単独の著書になっている。理由は、「前書き」に次のように記されている。
『わたしはスイカを二つ、同時に飲み込んだ蛇のような気分になっている。このプロジェクトは記事を書くことだけを目的にはじめたものだ。つぎの著書のテーマ、周囲の世界が制御できない混乱状態に陥ったときに耐え抜き、勝利を収めるには何が必要かの研究(同僚のモーテン・ハンセンとともに取り組んでいる六年間のプロジェクト) が最終段階に入ったなかで、気分を変えるために書いてみようと考えたのである。しかし、強大な組織がいかにして衰退するのかという問いは、長さに制約のある記事では扱いきれず、この短い本になった。当初は、波乱のなかで勝利する企業に関する本が完成するまで、原稿を寝かせておくつもりだったが、その後、まるで巨大なドミノ がつぎつぎ。倒れるように、強大な企業が倒れていく事態が起こった』(pp.7)
倒壊した企業名は、リーマン・ブラザースを始めとして、大型買収を含めて数社の名前が挙げられている。そこから、この著書の副題が生まれた。
「衰退の5段階」は、目次度見ただけで明らかになる。
『第一章 静かに忍び寄る危機; 危機の瀬戸際にあって気づかない
第二章 衰退の五段階; 調査の過程, 調査結果ー五段階の枠組み, 脱出への道はあるのか
第三章 第一段階 成功から生まれる倣慢; 倣慢な無視, 何となぜの混同
第四章 第二段階 規律なき拡大路線;自己満足ではなく、拡張しすぎ、成長への固執、パッカードの法則の無視、問題のある権力継承
第五章 第三段階 リスクと問題の否認;方針の誤りを示す事実が積み上がるなかで大きな賭けにでる、喫水線下のリスクをおかす、否認の文化
第六章 第四段階 一発逆転策の追求;特効薬を探す、パニックと必死の行動
第七章 第五段階 屈服と凡庸な企業への転落か消滅; 戦いをあきらめる、選択肢が尽きる、 否認なのか希望なのか』(pp.10-13)
そこで、ここでは「付録7」の「良好な企業から偉大な企業への飛躍の法則」の詳細を検討する。第1段階から第4段階まである。
第1段階は「規律ある人材」で、次のようにある。
『第五水準のリーダーシップ 第五水準の指導者は野心を何よりも組織と活動に向けており、自分自身には向けていない。そして、この野心を達成するために必要なことは何でも行うという強烈な意思をもっている。個人としての謙虚さと職業人としての意思の強さという矛盾した性格をあわせもつ。
最初に人を選び、その後に目標を選ぶ 偉大な組織を築いた指導者は適切な人をバスに乗せ、不適切な人をバスから降ろし、適切な人を主要な席につけ、その後に、バスの行き先を決めている。「だれを選ぶか」をまず決めて、その後に「何をすべきか」を決める。 』(pp.281)
第2段階は「規律ある考え」で、「厳しい現実を直視する」と「針鼠の概念」とある。針鼠の概念は、「世界一の可能性」と「情熱を傾ける」と「最高の経済的原動力」の3つの円の中心に存在するものを指す。
第3段階は「規律ある行動」で、次のようにある。
『規律の文化 規律ある考えができ、規律ある行動をとる規律ある人材が各人の責任の範囲内で自由に行動することが、偉大な組織を築く規律ある文化のカギである。規律ある文化では、人々は仕事を与えられるのではなく、責任を与えられる。
弾み車 偉大な組織を築くとき、決定的な行動や壮大な計画、画期的なイノベーション、たったひとつの大きな幸運、魔法の瞬間といったものがあるわけではない。偉大な組織への飛躍は、巨大で重い弾み車をひとつの方向に押しつづけ、回転数を増やして勢いをつけていき、やがて突破の段階に入ってもさらに押しつづけるようなものだ。』(pp.383)
第4段階は「偉大さが永続する組織をつくる」で、これが難問になる。
『時を告げるのではなく、時計をつくる ほんとうに偉大な組織は、何世代にもわたる指導者のもとで繁栄を続けていくのであり、ひとりの偉大な指導者、ひとつの偉大なアイデアやプログラムを中心に作られる組織とはまったく違っている。偉大な組織の指導者は進歩を促す仕組みを作っており、カリスマ的な個性に頼って物事を進めようとはしない。逆に、カリスマとは正反対の性格である場合が多い。
基本理念を維持し、進歩を促す 永続する偉大な組織は、基本的な部分で二面性をもっている。一方では、時代を超える基本的価値観と基本的な存在、創造性を発揮したいという強い欲求がときにBHAG(組織の命運を賭けた大胆な目標)の形であらわれてくる。偉大な組織は、基本的価値観(組織にとって不変の主義)と戦略や慣行(世界の変化に適応して絶えず変えてゆくもの)をはっきりと区別している。』(pp.284)」
他の3巻と同じで、「基本的理念」の維持と、そのもとでの「創造性の発揮」が重要視されている。
TITLE: ビジョナリー・カンパニー
このシリーズは「企業の進化」考える際に参考にした著作の紹介です。
『』内は,著書からの引用部分です。
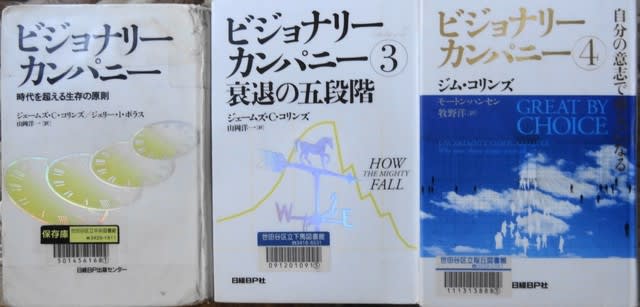
書籍名;『ビジョナリー・カンパニー3』 [2010]
著者;ジェームズ・コリンズ
発行所;日経BP社 発行日;2010.7.26
初回作成日;R2.1.10
副題は「衰退の5段階」で、このシリーズの3冊目になる。第1巻の発行は1994年。全4巻のうち、これだけがコリンズ単独の著書になっている。理由は、「前書き」に次のように記されている。
『わたしはスイカを二つ、同時に飲み込んだ蛇のような気分になっている。このプロジェクトは記事を書くことだけを目的にはじめたものだ。つぎの著書のテーマ、周囲の世界が制御できない混乱状態に陥ったときに耐え抜き、勝利を収めるには何が必要かの研究(同僚のモーテン・ハンセンとともに取り組んでいる六年間のプロジェクト) が最終段階に入ったなかで、気分を変えるために書いてみようと考えたのである。しかし、強大な組織がいかにして衰退するのかという問いは、長さに制約のある記事では扱いきれず、この短い本になった。当初は、波乱のなかで勝利する企業に関する本が完成するまで、原稿を寝かせておくつもりだったが、その後、まるで巨大なドミノ がつぎつぎ。倒れるように、強大な企業が倒れていく事態が起こった』(pp.7)
倒壊した企業名は、リーマン・ブラザースを始めとして、大型買収を含めて数社の名前が挙げられている。そこから、この著書の副題が生まれた。
「衰退の5段階」は、目次度見ただけで明らかになる。
『第一章 静かに忍び寄る危機; 危機の瀬戸際にあって気づかない
第二章 衰退の五段階; 調査の過程, 調査結果ー五段階の枠組み, 脱出への道はあるのか
第三章 第一段階 成功から生まれる倣慢; 倣慢な無視, 何となぜの混同
第四章 第二段階 規律なき拡大路線;自己満足ではなく、拡張しすぎ、成長への固執、パッカードの法則の無視、問題のある権力継承
第五章 第三段階 リスクと問題の否認;方針の誤りを示す事実が積み上がるなかで大きな賭けにでる、喫水線下のリスクをおかす、否認の文化
第六章 第四段階 一発逆転策の追求;特効薬を探す、パニックと必死の行動
第七章 第五段階 屈服と凡庸な企業への転落か消滅; 戦いをあきらめる、選択肢が尽きる、 否認なのか希望なのか』(pp.10-13)
そこで、ここでは「付録7」の「良好な企業から偉大な企業への飛躍の法則」の詳細を検討する。第1段階から第4段階まである。
第1段階は「規律ある人材」で、次のようにある。
『第五水準のリーダーシップ 第五水準の指導者は野心を何よりも組織と活動に向けており、自分自身には向けていない。そして、この野心を達成するために必要なことは何でも行うという強烈な意思をもっている。個人としての謙虚さと職業人としての意思の強さという矛盾した性格をあわせもつ。
最初に人を選び、その後に目標を選ぶ 偉大な組織を築いた指導者は適切な人をバスに乗せ、不適切な人をバスから降ろし、適切な人を主要な席につけ、その後に、バスの行き先を決めている。「だれを選ぶか」をまず決めて、その後に「何をすべきか」を決める。 』(pp.281)
第2段階は「規律ある考え」で、「厳しい現実を直視する」と「針鼠の概念」とある。針鼠の概念は、「世界一の可能性」と「情熱を傾ける」と「最高の経済的原動力」の3つの円の中心に存在するものを指す。
第3段階は「規律ある行動」で、次のようにある。
『規律の文化 規律ある考えができ、規律ある行動をとる規律ある人材が各人の責任の範囲内で自由に行動することが、偉大な組織を築く規律ある文化のカギである。規律ある文化では、人々は仕事を与えられるのではなく、責任を与えられる。
弾み車 偉大な組織を築くとき、決定的な行動や壮大な計画、画期的なイノベーション、たったひとつの大きな幸運、魔法の瞬間といったものがあるわけではない。偉大な組織への飛躍は、巨大で重い弾み車をひとつの方向に押しつづけ、回転数を増やして勢いをつけていき、やがて突破の段階に入ってもさらに押しつづけるようなものだ。』(pp.383)
第4段階は「偉大さが永続する組織をつくる」で、これが難問になる。
『時を告げるのではなく、時計をつくる ほんとうに偉大な組織は、何世代にもわたる指導者のもとで繁栄を続けていくのであり、ひとりの偉大な指導者、ひとつの偉大なアイデアやプログラムを中心に作られる組織とはまったく違っている。偉大な組織の指導者は進歩を促す仕組みを作っており、カリスマ的な個性に頼って物事を進めようとはしない。逆に、カリスマとは正反対の性格である場合が多い。
基本理念を維持し、進歩を促す 永続する偉大な組織は、基本的な部分で二面性をもっている。一方では、時代を超える基本的価値観と基本的な存在、創造性を発揮したいという強い欲求がときにBHAG(組織の命運を賭けた大胆な目標)の形であらわれてくる。偉大な組織は、基本的価値観(組織にとって不変の主義)と戦略や慣行(世界の変化に適応して絶えず変えてゆくもの)をはっきりと区別している。』(pp.284)」
他の3巻と同じで、「基本的理念」の維持と、そのもとでの「創造性の発揮」が重要視されている。









