昨日に引き続き、佐々木中さんの『切りとれ、
あの祈る手を』から、中心的テーマの
「中世解釈者革命」について。
そんな革命の存在すら知らなかったので、
面白い。6世紀に東ローマ帝国で編纂された
全50巻の『ローマ法大全』が長らく忘れられて
いたんだけど、11世紀末に発見されたことに
革命は端を発するそうだ。

『ローマ法大全』のうちの1巻
『ハンムラビ法典』、『ナポレオン法典』と並ぶ
世界三大法典ってなんとなく頭にあるけど、そこ
どまり。六本全書の原型みたいなもんだろうから
興味がわくハズもないw
それを読み、精密に書き換えることによって、12世紀に
教会法が成立したそうだ。その近代国家(および官僚制)の
原型がもたらされたと言う。
中世解釈者革命は教会法の書き変えであり、テキストの
革命であった。彼らは読み、彼らは書いた。そしてその
教会法は、洗礼、教育、救貧、婚姻、家族、異端や魔術の
禁止、性犯罪、孤児・寡婦・病人・老人の保護などを
統括する「生の掟」「再生産の法」であった。(P143)
中世というと、教皇や司教が法にかかわらず好き勝手
やったようなイメージはあるけど、確かにカトリックが
つくった掟には従っていたし(薔薇の名前なんかでも)、
「12世紀から、教皇や王であっても法を無視しにくく
なっていくのはこの革命あってのこと」(p145)なんだって。
とは言え劇的な事件があったというよりは、多くの
神学者や法学者が本をめくり、辞書を引き判例を調べて
法文を書き換えるという、地味な革命。
その結果、近代法、近代国家、近代主権のみならず、
会社、契約、組合などの近代資本主義や、近代議会や
選挙をはじめとする近代政治制度原型すらも発明した。
それって16世紀の30年戦争後とか、ルネッサンスで
整備されてきたようなイメージがあったけど、その前に
この革命が大きな役割を創り出したとは驚き。
あの祈る手を』から、中心的テーマの
「中世解釈者革命」について。
そんな革命の存在すら知らなかったので、
面白い。6世紀に東ローマ帝国で編纂された
全50巻の『ローマ法大全』が長らく忘れられて
いたんだけど、11世紀末に発見されたことに
革命は端を発するそうだ。

『ローマ法大全』のうちの1巻
『ハンムラビ法典』、『ナポレオン法典』と並ぶ
世界三大法典ってなんとなく頭にあるけど、そこ
どまり。六本全書の原型みたいなもんだろうから
興味がわくハズもないw
それを読み、精密に書き換えることによって、12世紀に
教会法が成立したそうだ。その近代国家(および官僚制)の
原型がもたらされたと言う。
中世解釈者革命は教会法の書き変えであり、テキストの
革命であった。彼らは読み、彼らは書いた。そしてその
教会法は、洗礼、教育、救貧、婚姻、家族、異端や魔術の
禁止、性犯罪、孤児・寡婦・病人・老人の保護などを
統括する「生の掟」「再生産の法」であった。(P143)
中世というと、教皇や司教が法にかかわらず好き勝手
やったようなイメージはあるけど、確かにカトリックが
つくった掟には従っていたし(薔薇の名前なんかでも)、
「12世紀から、教皇や王であっても法を無視しにくく
なっていくのはこの革命あってのこと」(p145)なんだって。
とは言え劇的な事件があったというよりは、多くの
神学者や法学者が本をめくり、辞書を引き判例を調べて
法文を書き換えるという、地味な革命。
その結果、近代法、近代国家、近代主権のみならず、
会社、契約、組合などの近代資本主義や、近代議会や
選挙をはじめとする近代政治制度原型すらも発明した。
それって16世紀の30年戦争後とか、ルネッサンスで
整備されてきたようなイメージがあったけど、その前に
この革命が大きな役割を創り出したとは驚き。













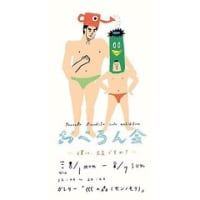






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます