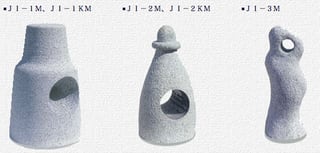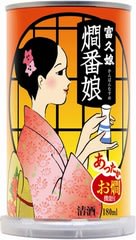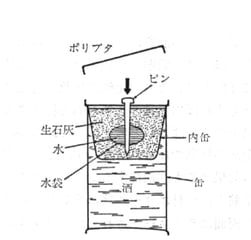高校の数学の宮原繁先生がこの3月15日に亡くなられる。
享年96歳。幾何学、数学を教わった日々の断片を思い出
すが、甘酸っぱい香りはせず、息苦しく寂しい。

卒業文集から引用
宮原先生に教わって、数学の才能がないっていうか理科
系ではないなって悟る。
授業で理解できんことが多々あったけど、それを同級生
がすらすら解いていくシーンを何度も目にすると、さっ
さと諦めた。
考え方が変わったのは卒業してから。周囲よりは数学と
いうか数学的な考え方ができることにだんだんと気づい
ていく。
宮原先生のおかげと心のなかで何度も呟いた。ありがと
うございました。
☆
能がご趣味で、独特の語り口でお話下さったことも、あ
まり理解できておらず、遠い話の様に聞くだけだった。
初めて知ったんだけど、JR芦屋駅のそばに山村サロンと
いう音楽ホールがあって、その一角に宮原文庫があるら
しい;

いまだに能がわかっていない。これもトライしなさいね、
と先生に言われている気がする。安らかなご冥福をお祈りします。
享年96歳。幾何学、数学を教わった日々の断片を思い出
すが、甘酸っぱい香りはせず、息苦しく寂しい。

卒業文集から引用
宮原先生に教わって、数学の才能がないっていうか理科
系ではないなって悟る。
授業で理解できんことが多々あったけど、それを同級生
がすらすら解いていくシーンを何度も目にすると、さっ
さと諦めた。
考え方が変わったのは卒業してから。周囲よりは数学と
いうか数学的な考え方ができることにだんだんと気づい
ていく。
宮原先生のおかげと心のなかで何度も呟いた。ありがと
うございました。
☆
能がご趣味で、独特の語り口でお話下さったことも、あ
まり理解できておらず、遠い話の様に聞くだけだった。
初めて知ったんだけど、JR芦屋駅のそばに山村サロンと
いう音楽ホールがあって、その一角に宮原文庫があるら
しい;

宮原繁氏の能・狂言に関する蔵書を集めた私設の
資料室です。各種雑誌と諸方からの寄贈図書など
約1,000冊が収められています。
資料室です。各種雑誌と諸方からの寄贈図書など
約1,000冊が収められています。
いまだに能がわかっていない。これもトライしなさいね、
と先生に言われている気がする。安らかなご冥福をお祈りします。