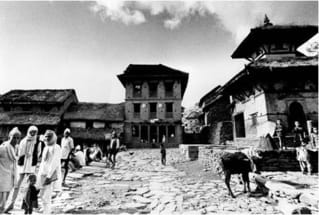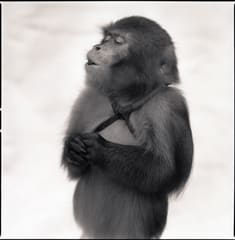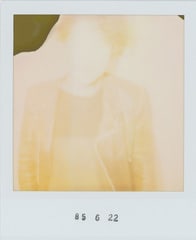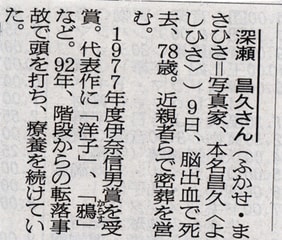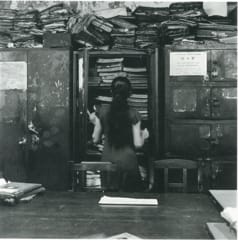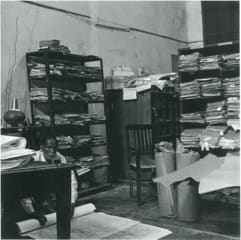京都国際写真祭(KYOTO GRAPHIE)の今回のテーマは
「Circle of Life いのちの環」なんだけど、それ以上
に特集されたのが写真家サラ・ムーン。
長年の親交がある何必館がかなりの協力体制をとられた
のがみてとれる。重森三玲旧宅、ギャラリー素形と3会
場で展開。彼女も何度も来日したそうだし。

重森三玲旧宅での展示
何必館の梶川夫妻の力の入れようは、集大成の様な5冊
組の全集を刊行したことにも表われている、凄い。それ
には手がでなかったけど普及版を買い求める。彼らはこ
れまでもサラ・ムーンの写真+動画集など数冊発行して
きたことを知る。
☆
同じフランス人のティエリー・ブエットによる「うまれ
て1時間のぼくたち」といって赤ん坊が並んでるのは面白
かった。

シワシワだとは思ってたけど、猿というより老成した感じ。
遠くを見つめるかの様な視線は何もかもわかっている、っ
て感じがした。仏像のモデルにしたのではと思ったほど。
マイクで歌ってるような子もいるし、だいたい男の子か
女の子かぜんぜんあたらんw
出産を迎える両親に撮影許可をとりつけるのは、ハッピー
な時だろうから容易だったかもしれないけど、こんな写真
みたことない。自分の赤ん坊ならともかく。
☆
クリス・ジョーダンはミッドウェー島の鳥達の死を撮る。
漂流してきたプラスチック類を飲み込んだのが死因。大陸
から2000マイル離れているミッドウェー島に漂着するとい
うことは、太平洋にどれだけ多くの廃棄物が浮遊しているか、
想像をこえる。

漂流するプラスチック類をランプに再生させたのが2年前
に亡くなったヨーガン・レール。クリス・ジョーダンのプ
ロジェクトに共感し、一緒に展示されることを望んでいた
そうだ。
☆
古賀絵里子の新作「Tryadhvan(トリャドヴァン)」を
見ることができたのも嬉しかった。旧呉服問屋の美しい
町屋で絵巻物のように展示されていた。
近年お坊さんと結婚し、出産されたそうで、そういった
身近な過程をはさみながら、彼女のテーマである「生と
死」にさまざまな時間軸が加わった感じ。写真撮影はN
Gだったので、中庭からの様子。(以上すべて敬称略)

「Circle of Life いのちの環」なんだけど、それ以上
に特集されたのが写真家サラ・ムーン。
長年の親交がある何必館がかなりの協力体制をとられた
のがみてとれる。重森三玲旧宅、ギャラリー素形と3会
場で展開。彼女も何度も来日したそうだし。

重森三玲旧宅での展示
何必館の梶川夫妻の力の入れようは、集大成の様な5冊
組の全集を刊行したことにも表われている、凄い。それ
には手がでなかったけど普及版を買い求める。彼らはこ
れまでもサラ・ムーンの写真+動画集など数冊発行して
きたことを知る。
☆
同じフランス人のティエリー・ブエットによる「うまれ
て1時間のぼくたち」といって赤ん坊が並んでるのは面白
かった。

シワシワだとは思ってたけど、猿というより老成した感じ。
遠くを見つめるかの様な視線は何もかもわかっている、っ
て感じがした。仏像のモデルにしたのではと思ったほど。
マイクで歌ってるような子もいるし、だいたい男の子か
女の子かぜんぜんあたらんw
出産を迎える両親に撮影許可をとりつけるのは、ハッピー
な時だろうから容易だったかもしれないけど、こんな写真
みたことない。自分の赤ん坊ならともかく。
☆
クリス・ジョーダンはミッドウェー島の鳥達の死を撮る。
漂流してきたプラスチック類を飲み込んだのが死因。大陸
から2000マイル離れているミッドウェー島に漂着するとい
うことは、太平洋にどれだけ多くの廃棄物が浮遊しているか、
想像をこえる。

漂流するプラスチック類をランプに再生させたのが2年前
に亡くなったヨーガン・レール。クリス・ジョーダンのプ
ロジェクトに共感し、一緒に展示されることを望んでいた
そうだ。
☆
古賀絵里子の新作「Tryadhvan(トリャドヴァン)」を
見ることができたのも嬉しかった。旧呉服問屋の美しい
町屋で絵巻物のように展示されていた。
近年お坊さんと結婚し、出産されたそうで、そういった
身近な過程をはさみながら、彼女のテーマである「生と
死」にさまざまな時間軸が加わった感じ。写真撮影はN
Gだったので、中庭からの様子。(以上すべて敬称略)