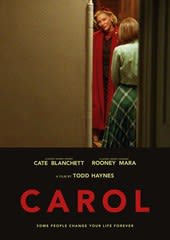
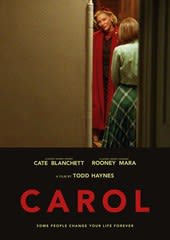
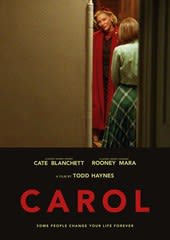
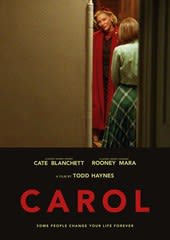
トッド・ヘインズの『キャロル』が評判のようだが、これは僕が去年に観たなかでも特に気に入った映画だった。
いまは遠い時代のラブストーリーであり、同時に一人の女性の成長物語である。女性とデパート、レコードとラジオ、カメラとフィルム、非米活動委員会と盗聴――保守と抑圧の50年代を柔らかに胸を締めつけるような緊張美で飾りつけて洗練を極め、たまらなく魅惑的だ。全編が名演技、名演出の連なりからなり、撮影、衣装、美術、音楽に至る入念な時代考証とその繊細な表現力が観る者に「現在」を忘れさせる。ヘインズは当時のフォト・ジャーナリズムを参考にし、同時にデヴィッド・リーンの『逢いびき』を引き合いに出していると語るが、これは、社会的、政治的な抑圧と困難に直面したアウトサイダーのソウルを描き続けるヘインズの新たな到達になった。心許なく華奢な身体で人の現実を凝視する才能を秘めるルーニー・マーラと孤独で誇り高くゴージャスなケイトブランシェットは映画ファンに記憶されるカップルになるだろう。
アカデミー賞の作品・監督賞から外されたが、ほかの賞ではノミネートされていることを考えると、ちょっと解せない。またケイト・ブランシェットが主演女優賞、ルーニー・マーラが助演女優賞という分け方にもピンとこない。同時に主演ノミネートか、ルーニー・マーラが主演賞でなければおかしいと思うのだが、こういうことはよくあることで、別に目くじらを立てるほどのことではないかもしれない(『ゴッドファーザー』では当時に知名度の違いからだろうか、ブランドが主演、パチーノが助演だった。内容からすればむしろ逆だと思うが)。
ところで、『キャロル』は女性カップルの恋愛を描いた作品である。映画の監督へインズ自身がゲイであり、そのことはよく知られているが、原作者のパトリシア・ハイスミスもレズビアンだった。このことは比較的最近知られるようになったことで、原作の発表時には「クレア・モーガン」名義で出版している。
ハイスミス作品の映画化といえば、ルネ・クレマン監督による『太陽がいっぱい』が有名である。クレマンもまたゲイだったと読んだことがあるが、主演のアラン・ドロンは、クレマンとやはりゲイの巨匠ルキノ・ヴィスコンティに愛された俳優であった。ハイスミス原作の映画化では他にヒッチコックの『見知らぬ乗客』があり、これも有名だが、主演のファーリー・グレンジャーはバイセクシャルだったと聞く。それを知ってかヒッチコックは、ゲイ・カップルによる殺人事件をモデルとする『ロープ』にも彼を起用。その事件は、リチャード・フライシャーの『脅迫/ローブ殺人事件』や、トッド・ヘインズと同じ頃に登場したトム・ケイリンの『恍惚』にも描かれていた。
『恍惚』はこれまでの映画化とは比較にならないほど率直にゲイと殺人を描いていた。ケイリンとヘインズは共に、90年代に台頭した「ニュー・クィア・シネマ」の旗手として注目されたが、ことにヘインズの才能はそうしたカテゴライズをはるかに超えるものだったと言える。ヘインズの興味と姿勢は、『ポイズン』『SAFE』『ベルベット・ゴールドマイン』『エデンより彼方に』『アイム・ノット・ゼア』『ミルドレット・ピアース』『キャロル』と続いてきた多彩なフィルモグラフィーを貫く個性で、そのことは彼が『ポイズン』を語る次の言葉に集約されていると思える。
「映画の中のリアリティを、ハリウッドの伝統的ジャンル、そのスタイルを検証しつつ、示してみようと思った。映画と観客の間の距離が、物語によって次第に奪い取られてゆく。映画のそんな仕組み、内面に働きかける力、ストーリー・テリング。ただ物語に別の角度を与えること、その角度のつけ方も同じ位、重要だと考えている。面白いのは、当時の恐怖映画が冷戦とか非行とか50年代にあった問題を使ってある種、危機感を煽るように作られている点だ。(中略)ハリウッドのホモ恐怖症のせいばかりではない。実験的な映画を撮ろうとしているから伝統的なハリウッドのフォーマットには収まらなかったんだ」(1991年『FLIX』より)
91年の言葉だが、いま読んでも、新作を語っているように読める。最後の部分について補足すれば、『キャロル』でのヘインズは、失われた(50年代の)ハリウッド・フォーマットにフィットさせた上で、その「角度」を微妙なかたちで異化して自らに引き寄せている。50年代のハリウッド映画は「安全・無害」に殺菌された映画の代名詞だが、それは検閲が厳しかったからであり、悪名高い「赤狩り」による思想弾圧も行われていた。それゆえ野心的な作者たちは自らの思想を、権力に「見えない角度」からこっそり忍び込ませていた。その大家が、たとえばヒッチコックでありビリー・ワイルダーだったわけだ。




冷戦と赤狩りが支配した50年代の同性愛を描いた『キャロル』は、「50年代を背景とする50年代スタイルの映画」である。ヘインズはここで、微細かつ微妙な表現と率直な表現を、交互に、抜け目なく施すことで「50年代を現在の眼から批評」しているが、その結果、「50年代には決してつくれない50年代についての映画」になっている。ここで少し長くなるが、ジェフ・アンドリューが1998年に発表した「ヘインズ論」を引用する。
「(トッド・)ヘインズは、社会の価値判断の指標として、そして自己規定の根源になりうる要素として捉えたうえで、病気や”異常”に関心を示している。この考え方は、今の時代を反映していながら、斬新でもある。またヘインズは、個人の生活が心理や性、経済、歴史、政治、文化的要因によってかたち作られていることを、知的な視点からはっきりと意識している。そして彼の現実と”イメージ”の間の隔たりへのこだわり(これはおそらくヘインズが記号学に興味を持っていることに起因している)や、私的な生活と表向きの顔が矛盾しながら共存することに対する興味を、成功、名声、ファッション、メディアに縛られた現代のなかで浮き彫りにしている。またヘインズが、特定の病気や欲望、人間のアイデンティティなどを我々が許容できない、またはしたがらない結果として生じるダメージが何なのかは結局分からない、と認めているところは、理性的で巧妙だといえる。映画的手法という観点から見ても、非常に大胆で、その才能には驚かされるばかりだ。ヘインズは、様式やストーリー運びの形式を自在に操り、新鮮なアプローチで題材に挑み、伝統的なジャンル映画を操作して切り崩しながら、ポップ・カルチャーが映し出す世界像を浮き彫りにし、問いを投げかけている。主題やスタイル、分析的な手法という点でいうと、彼の作品は、間違いなく現代的だ――記号学から得た知識に着目したアメリカ人の監督は、彼をおいてほかにいないだろう。批評家や観客が、ヘインズの作品を特徴づけている両義性を受け入れる心構えを持ち、理解しようと努力しさえすれば、映画作家としてのヘインズの未来は光り輝くに違いない」(『インディーズ監督10人の肖像』/キネマ旬報社より)
これもまた、すでに『キャロル』を知る2015年において、古びていないどころか、いまも的を射ており、彼の一連の作品への理解が深まる論考だったと思う(本では1998年時点における全作品について書かれている)。
ここでやっと話を元に戻すが、ハイスミス×クレマンの映画『太陽がいっぱい』を「ゲイの物語」だと最初期に見抜たのが、かの映画評論家・淀川長治だった。当時に限らずこの作品をそのように見立てた人は少ないと思われ、仮にそう見抜いていたとしても、そのように語る勇気を持てなかったに違いない。一般的には、貧乏な若者が金持ちの若者に近づき、殺して、彼のすべてを手に入れようと目論む「犯罪ドラマ」であり、もしくは『アメリカの悲劇』(モンゴメリー・クリフト主演の『陽のあたる場所』の原作)のような悲劇的な青春ドラマとして観たかもしれない。
僕も、淀川さんの説明を読み、ピンとこないながらも、そういう見方があること、それ自体に刺激を感じた。「おや?」と思ったのは、アンソニー・ミンゲラ監督(彼もゲイと聞いたことがあるが、どうなのだろう)が、同原作を再映画化した『リプリー』を観てからである。ここでマット・デイモン扮するリプリー(『太陽がいっぱい』でドロンが演じた役)は、よりはっきりゲイとして描かれていたからで――この時点でハイスミスがレズビアンとは知らなかったが――淀川さんの「見立て」の確かさに驚いたのだった。
その淀川さんと吉行淳之介の対談を引用する。
映画は開かれたテキストであり、人の想像力は画面に描かれている事柄をいくらでも自らの問題に置き換えたり、引き寄せたりして観ることができるものである。淀川さんの「見立て」を過分に意識する必要もないが、頭の片隅に置いておくことで、より深い理解につながるということもあるだろう。と、どこからともなくサービス精神が沸き起こってきたのである。以下、
淀川 それに、あの映画はホモセクシャル映画の第一号なんですよね。
吉行 (和田、同席の男性も)え、そんな馬鹿な。
淀川 あれ見たら完全にそうですよ。貧乏人の息子のアラン・ドロンが金持ちの家に、坊ちゃんを連れ戻しに行く。彼は金持ちの坊ちゃんのすべてが好きになっちゃうのね。ワイシャツから、ネクタイから、靴から、全部自分のものになったらいいなあと思う。坊ちゃんのほうはそんなもの飽きて困ってる。そして、そんなものほしがる子供みたいな男を喜ぶのね、モーリス・ロネは。手紙を書くのも、サイン教えて彼にやらせるようになる。そのうち、彼がおらな面白くなくなってくる。ラヴシーンだろうが、連れて行く。どっちも無いものねだり。片っ方はネクタイから靴から全部ほしい。片っ方はそんなこという感覚の人間がほしい。
吉行 違うと思うんだがなあ。
淀川 ちょっと待って(笑)。どっちも無いものねだりで、憎らしいけど離れられない。それがだんだんクライマックスになってくるとエキサイトしてくるのね。それは、俺が憎いんだろう、憎いんだろう、憎いんだろうで、とうとう殺すところまでゆく。そして殺しちゃった。なにもそこまでエイキサイトしなくてもいいのに、エキサイトして、片っ方は死んだ。そして、死体になっても、ふたりは離れられないのよ。
吉行 今、それをいおうと思った。スクリューにからみついた死体が離れない、それは淀川流解釈では、そういうとになるんでしょう、と。
淀川 もうちょっと待ちなさい(笑)。アラン・ドロンの方は、洋服からタイプライターから、全部自分のものになった。そこで、サインの練習するでしょう。
吉行 あれが面白かった。いつか深夜劇場で見たらカットされてましたけど。
淀川 あれ、大きなサインでしょう。プロジェクターで伸ばして練習するでしょう。まるでキスマークみたい。あんな大きくする必要ないのに、大きく大きくする。あれ、一生懸命、片っ方の唇をなすってるのね。
吉行 それはどうですか……。
淀川 なぜ、そんなことわかるかというと、映画の文法いうのがあるんです。一番最初、ふたりが遊びに行って、三日くらい遅れて帰ってくるでしょう、マリー・ラフォレの家へ。マリー・ラフォレのこと絵本でも買ってごまかそういって。ふたりが船から降りる時ね。あのふたりは、主従の関係になっている。映画の原則では、そういう時、銃のほう、つまりアラン・ドロンが先に降りてボートをロープで引っ張るのが常識なのね。ところが、ふたりがキチッと並んで降りてくる。こんなことあり得ないのよ。そうすると、そばで見ていたおじいちゃんが、あのふたり可愛いね、いうのね。そして、絵本渡したら、マリー・ラフォレ怒ってしまうでしょう。あの映画、マリー・ラフォレとモーリス・ロネ、マリー・ラフォレとアラン・ドロンのラヴシーンほとんどないのね。
吉行 うーん。映画の文法か。説得力が出てきたな。
淀川 そして、モーリス・ロネを殺してしまって、最後のシーンがくるでしょ。その時に、ヨットが一艘沖にいる。あれは幽霊なの。おまえもすぐ俺のところへ来るよ、という暗示なのね。
吉行 なるほど、あのヨットは何だろう、とおもっていた。
淀川 そこへあなたのいうシーン、太陽がいっぱいのシーンがくる。足をバンとあげて喜んじゃう。その前に、マリー・ラフォレと濡れ場があるはずなのね。ちょっとあるんだけど、それは見せない。で、電話がかかってきて、そうかといった時にワインのグラスを持った。彼の手が若くて美少年らしい。それと一緒にモーリス・ロネの死体の手が写るのね。ダブって。握手してるのね。そこへ、また呼ばれていっち……あれは後追い心中なのよ。
吉行 はあーっ(笑)。映画の文法として、ふたり一緒に降りるのはおかしいというところ、迫力がありましたね。
淀川 ふたつの殺しがあるのね。ひとつはモーリス・ロネの、もうひとつは憎ったらしい太っちょを殺すの。ちゃんと分けてる。太っちょのほうは銅像みたいのんでガーン、モーリス・ロネのほうはナイフで刺す。刃物で殺すのはラヴシーン、前のは単なる殺しですよ。片っぽうのは夢の殺しなの。殺せるか、殺せるか、殺してごらん、とうとう殺してくれたいうね。
吉行 ぼくは、貧乏人と金持ちというパターンであの映画見てましたけどね……。
淀川 また、監督がルネ・クレマンだから、いえるのね。
吉行 そうですか……。いや、勉強になりました。長いこと小説やってて、そこに気がつかないんじゃ駄目だな。
淀川 善良なのよ、あなたさんは。これはさっきの仇討ち(笑)。
吉行 いや、こわかったですねえ。勉強になりましたねえ(笑)。
淀川さんはここで、映画の「文法」から『太陽がいっぱい』に隠された「含み」を読み解いていくが、当時、奇抜とも思えたその「読み」は正しかったことが、いまはわかっている。多分、この時の吉行さんは半信半疑のままだったと思うし、読者の多くも困惑したに違いない。実に面白い対談だが、ほかにスピルバーグの『激突!』やウィリアム・ワイラーの『コレクター』なんかの話をしている。(1977年、新潮社刊の『恐怖対談』所収)。
トッド・ヘインズもまた「含み」の天才であり、彼が新作『キャロル』の繊細な映像に忍び込ませた「隠し絵」の数々を読み解いてみるのも映画鑑賞の醍醐味だと思う。淀川さんならどのように観ただろう。
(渡部幻)





















