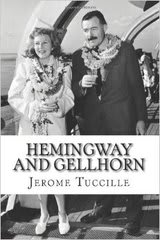イマジカBSが『愛の嵐』を流していた。リリアーナ・カヴァーニは、これがあればもういいというくらいに濃密で危険な男と女の官能の劇を撮り上げた。女優とシャーロット・ランプリング、男優はダーク・ボガード。そういえば、いま、この名優を普通に語るような映画ファンをすっかり見かけなくなった。あの柔らかな毒を含む色気にあてられないのは、皆、それだけ健康・健全になったということか。いや、別にそんなこともないだろう。多分、語りたくても求められないし、語っても反応がないから、止めてしまうのだ。そういう風潮ならたしかにある。
僕が子供の頃こういう大人の世界を垣間見せてくれる役者たちがいた。彼らの作品の広告もそのことを強調し、それをそのように伝えてくれる批評もあった。それらは人間の闇に微かな光を当てていた。なにしろダーク・ボガードである。ジョセフ・ロージーの『召使』『できごと』、ジョン・シュレシンジャーの『ダーリング』、ジョン・フランケンハイマーの『フィクサー』、ルキノ・ヴィスコンティの『地獄に堕ちた勇者ども』『ベニスに死す』、そしてカヴァーニの『愛の嵐』に出演したイギリス出身の国際的な名優なのである。


『愛の嵐』を観ていてその迫力におされるのは、ボガードとランプリングの身体から滲み立ち上がる精神のただならぬ妖気ゆえである。しかし翻って現在の映画やその鑑賞のされかたを思うと、役者の持つ身体性に対する反応が鈍くなってる、と感じられることがある。鍛えられた筋肉とかスタイル美だとかそんなものではなく、精神を包み込む皮膚の、肌合いに隠された秘密の、そんなもののことである。観る側もそうだが、役者自身、監督自身の側にもその感覚の劣化があると思えることがあるのだ。


映画を見慣れた人なら気づいているが、映像にも皮膚があり、その感触がある。映画の映像に直接触れることは出来ないが、それは目で触れた感触であり、そこにも人間の官能があるのだ。しかし、そうしたことに反応することは、もはやジョークかパロディの一種に成り下がっている。だがそれは人間の敗北だろう。70年代初頭のSF映画やマンガがしきりと描いたのは身体性を剥奪された無機質な未来像だった。そうした予感、恐怖心への反発や反動が、同時代を描いた映画のなかに描かれる人間の身体性を剥き出しにしていた。生身の痛みや喜び、快楽やその拒絶感までを描き出すことに腐心していた。『愛の嵐』や『ラストタンゴ・イン・パリ』(ベルナルド・ベルトルッチ)のセックス、『ベニスに死す』に描かれた若さと老醜の対比がそれだし、また異なるタイプの作品だが、『ジョニーは戦場へ行った』(ダルトン・トランボ)『こわれゆく女』(ジョン・カサヴェテス)『エクソシスト』(ウィリアム・フリードキン)『燃えよドラゴン』(ロバート・クローズ)『仁義なき戦い』(深作欣二)『タクシードライバー』(マーティン・スコセッシ)などが強烈に主張し、白日の下にさらしていたのも、人間の肉体と精神の関係、その脆さと強さだった。


84年の『ターミネーター』(ジェームズ・キャメロン)に登場する,人間と瓜二つのロボットに扮suruシュワルツェネッガーのボディビルで鍛えられた人工的な肉体と、人間のマイケル・ビーンの植えて痩せ身の引き締まった肉体を捉えるキャメロンの目には、明確な差別化と対立化が意識されていたと思うが、2015年の『ターミネーター新起動ジェニシス』のシュワルツェネッガーとジェイ・コートニーの肉体からはそれほど明確な違いが伝わってこないから不思議だ。いま、それら古いSF映画に描かれていたような状況が加速して区別のない世界が現出しているということを踏まえて、意識的か無意識的かは分からないが、映画の映像に反映されているということだろうか。その結果、映画の映像の「目で触れる感触」も変化し、俳優の持つ身体性への反応の仕方も、否応なく新しいものになっているのだろう。自分自身その流れに絡めとられており、そのことが残念だが、記憶の底にには、人の生きた身体が持つ感触や官能を捉えた映像への惹かれる想いが、かつてのまま消えずに残っているのだ。
(渡部幻)