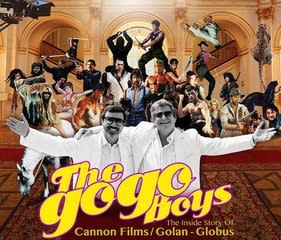デヴィッド・ロバート・ミッチェル『イット・フォローズ』はユニークなホラー映画である。個人的にはまるで怖くないのだが、それは筆者の感受性の問題である。ホラーにも色々あり、『エクソシスト』などは大好きだが、『リング』にはなにも感じないというところがある。ホラーは好きだが「怖い」から好きなわけではないし、多分その方面の感性すれっからしになってる。本作は「青春ホラー」だが、個人的にはこのジャンルに思い入れがないし、若者がいくら脅えていても(大げさに言えば)なんとも思わないようなところがあるのだ。ただ、非常にインスパイアリングな作品であり、奇妙に尾を引くところがある。その感触からホラー好きなら『ハロウィン』などの初期ジョン・カーペンター作品を連想するだろう。いっけん二番煎じみたいだが、それで終わらないひらめきを感じさせる。高評価もうなずける異色作なのだ。
映画は視覚・聴覚の感覚表現である。本作はひと目でその映像感覚に目をみはらされる。映画は総合表現なので一口に感覚と言っても、撮影、被写体、編集、それとも全部の総合を指しているのかわからない。どれを指しているのかで受け取り方も変わってくる。『イット・フォローズ』で僕が感心したのは撮影である。シネマスコープを活かした構図の陰影が深く、しかも「ほぼ動かない」。それゆえ観る者は動かないロングショットのワイドな構図のなかを観察し、目玉を動かす。ホラーだからその「目の動き」は脅えにもとずき、「恐怖の対象」を探しているのである。アングルの「固定」は、ここで劇場の椅子に固定された観客の視線と結びついている。冒頭で椅子に縛られた少女を見せるが、それはスクリーンの鏡に映った観客の似姿なのである。
映画の画面は「世の映し鏡」である。スクリーンは鏡であり、その反映としての世界を眺める行為が映画鑑賞なのである。映画の鏡の世界は多彩である。「写実的なもの」から「奇妙に歪んだもの」まで色々だが、観客はスクリーンを覗き込んで、そのなかに自らの似姿を見出す。観客はその似姿=登場人物に共感したり嫌悪したりするが、作者はその心理を利用してドラマを様々な方向へ転がしていく。娯楽映画の多くは、極力、大衆の要望に合わせ理想化された人物を描くことが多いが、しかしホラーの場合は、必ずしも理想的な人物像である必要はない。こと青春ホラーではむしろ欠陥を持つ普通の人物がひどい目に合わされることが多いかもしれない。


「鏡」を始終覗き込んでいるような人がいるが、あれはどうしてだろうか。自分の顔をそんなに眺めるとは、極端に神経質な人か、もしくはナルシスト、それともマゾヒストだろうか? 「ホラーの鏡」の場合どうだろう。映画は鏡だと書いたが、自らの似姿=分身たる登場人物を通じて恐怖に脅えてみたいなどとというのはどちらかといえばマゾヒスト的ではないか? ホラー映画ファンにかぎらず映画ファンなどという存在は多少なり歪なところを持っているものだと、自らを省みて思うのだが、しかしホラー映画に描かれる恐怖のつるべ打ちを観て喜んでいるとはどういう風の吹き回しからくるのだろうか。この世にはびこる者どもが痛めつけられるのをみて喜んでいるのか。それとも自らを鞭打っているのだろうか?? よくよく考えると奇妙に思えるものだが、ファンはそれを糧として生きているし、ホラー中毒者はあとを絶たない。
ホラーファンにもいくつかあり、被害者の立場に身を置くマゾヒスト型の人物と、加害者の立場に身を置くサディスト型の人物とがいる。言い換えれば被害者の立場に身を置くのは普通のファン。加害者側に身を置くのはマニアックなファンである。マニアックなファンは作者たる監督の側に身を置こうとする癖がある。つまり脅かす側に身を置くため、脅される一方となるお化け屋敷には腹を立てる傾向がある。しかし『イット・フォローズ』の場合、ほとんどサディスト型の立場に身を置くことはむずかしいのではないか。本作には具体的な加害者が存在しない。もっぱら被害者側の心理状況を追体験させられ、恐怖の正体と理由を、観る者に自ら「考えさせる」ようつくられている。僕が怖くなかったのはここが理由だった。おもしろいのだがホラーとしてみれば適者生存の本能を直撃する恐怖感を煽ってほしいのだが、本作のつくりは「知的」に過ぎるように思えたのである。




『イット・フォローズ』の主人公は青春盛りのティーンたちだが、彼らに襲いかかる「それ」は「レザーフェイス」や「ブギーマン」のように「具体的」かつ「特定的」な怪物ではない。たしかに「人の形」をしたゾンビのごとき存在が登場する。「それ」はただ歩きながら近づいてくる。単にそれだけなのだが、それらは「死」の象徴であり、その要因は「セックス」にあるのだ。ポイントは「死という観念」である。「死」を思わせるなにかが、ただ「こちらに近づいてくる」のが怖いという映画なのだが、言葉で説明するのは難しい。それは悪夢の感触に似て、目覚めたあと他人に話しても、まったく伝えられないのと似ている。相手の表情に「恐怖」が浮かんでいないのである。「ああなって、こうなって」というようなストーリーラインはここであまり関係はない。悪夢のなかの「あの雰囲気」。それが真に迫って「恐ろしかった」のだが。『イット・フォローズ』はあえて言えば「そういう」雰囲気を持つホラー映画なのである。「恐怖感」というより「不安感」といったほうニュアンスが近いかもしれないが、この映像は若者に特有の漠とした孤立感をよく捉えている。自らがいまだ不確かな存在でしかないことからくる孤立感。これに押しつぶされて人生を終えてしまうことも稀なことではない。




ジョン・アーヴィングに『ガープの世界』という小説がある。ホラーではないが「死」が蔓延する世界が描かれる。登場人物たちに襲い掛かる「死」は、質、量ともに『イット・フォローズ』をはるかに超え、子供だましに見せる。この本で人々を死に追いやる要因は「暴力」「事故」そして「病い」である。ホラーでなくむしろユーモラスなの小説だが、そのことがかえって強力なリアリティを生む。次々に不条理な死が描かれていき、死が山積みの状態になるが、この状況を生き延び、ついに心の平和を得たころには「老い」という名の病いに襲われ、あっけなく死んでしまう。アーヴィング的な人生観。主人公のひとりに型破りな看護婦が登場し、彼女が言うように、人間はみな漏れなく「死という病」を患っている。世に生まれ落ちた瞬間に作動を始めた時限爆弾を抱えながら右往左往し、そして死んでいく。かように「生きる」とはイコールで「死に向かう」ことと同義なのだ。
主人公ガープは、第二次大戦中に死にかけた兵士を犯して孕んだ看護婦が生んだ子供である。この本には死と同じくらい多様な性とセックスが描かれるのだが、性と死は分かちがたく結びついている。
人はその成長過程で擬似的な「死」をいくつか経験するが、そのひとつは「眠り」である。誰もが一度くらい「眠ったまま二度と起きなかったとしたら」と考えてみる。日々の眠りは死の予行演習であり、明日よりよく生きるべく「眠る=死ぬる」のである。次に「病い」がある。風邪で高熱を出して意識が遠のくと肉体から魂が遊離していくような感覚にとらわれることがある。病いもまた死の予行演習であり、病いが完治すると毒素が抜けて以前にも増してサッパリするのもそのためである(ときに失敗するとそのまま死ぬ)。さらに「セックス」がある。セックスの目的のひとつは生殖だが、そこにはセックスでしか得られない快楽が伴うため、それだけを目的として人はその行為を求める。性的快楽の絶頂が死を思わせる感覚を呼び起こすことは大人なら身を持って経験している。絶頂で死に近づき解き放たれる快感を知った者たちは、繰り返しそれを求めるようになるが、快楽重視のセックスに付きまとう不安と危険がある。妊娠し、もしも産むつもりがなければ堕胎しかない。それは命の死を意味するから避妊を考えるが、しかし避妊も突き詰めれば命の種の死を伴うものである。男性はマスターベーションで精子を殺すことに慣れているよるようなところがあるが、それもまた「死の予行演習」のひとつだろう。人の肉体は日々さまざまな生と死の繰り返しのなかにあり、子供のときの「肝試し」や「探検」、「いじめ」や「殴り合い」、「大怪我」それに「近親者の死」など、さまざまなかたちで「死の擬似的体験」もしくは「死に至るための通過儀礼」が、人生のそここには用意されているのだ。そして「恐怖小説」を読んだり「ホラー映画」を観ることもまたそんな「死のレッスン」のひとつなのである。言い換えてみれば「死に至る通過儀礼」なのである。




ホラー映画『イット・フォローズ』で若者たちのもとへ「死」を運んでくるのは「セックス」だ。思春期の若者が感じる孤独と不安がセックスを求め、そのまま「死」へと直結してしまう恐怖の底には罪の意識がある。いまだ大人の保護下にあり、監視されている彼らにとって、セックスは「大人からの解放」と結びついている。彼らはいまだ真の「恍惚」は知らないかもしれないが、そこに「死」の匂いを嗅ぎ取るからこそ、いわれのない罪の意識を感じる。ここから恐怖が生まれるのだが、気になるのは本作の背景にある宗教観である。しかしそこには踏み込まない。映画は宗教を超えているし、宗教もまた突き詰めれば普遍的な性格を帯びるものだからだ。
子供と大人を対立軸に置いたセックスはある種の背徳性を帯びる。セックスが大人の保護からの開放を錯覚させ、その開放感がセックスをより求めさせる。人間は、普段、他者の裸体に触れる機会を持たないものである。「触れない」ということは「触れられない」ということでもあり、それ自体が存在の孤立なのである。多くの人は、どこかの誰かに恋愛感情を抱き、それを伝え、了解を得ることで相手の裸体に触れる禁を破ることが許される。他者との肉体的な結びつきがひととき孤独を忘れさせるが、普段、誰にも触れることなく触れられることもない「皮膚」は敏感であり、触れ合うことで強い喜びを覚える。その喜びは「生きている」実感であり陶酔感につながるが、やがて快感が絶頂に至ると「死に近づくことの」の恍惚へと変わる。しかし、絶頂の瞬間はやはり孤独である。死ぬときは誰も一人ぼっちでなのだ。脳がしびれ、純粋に肉体的な存在になると、すべてが溶け出し、消えていくような感覚に陥る。「死の予行演習」である。


セックスの喜びを知ったばかりの若者は――通常どのくらいか知らないが――15から19年近く孤立してきた肉体を他者と結びつけ、生きる実感を得ることに夢中になる。『イット・フォローズ』は「セックス」がイコールで「死」と結びつく恐怖を描いている。セックスは「生死の分別」から解き放つ麻薬だが、ここでは無防備な若者の他者を求める心が「死」を撒き散らすことになるのだが、別に性病のメタファーというわけでもないだろう。『ハロウィン』などと異なるのは主人公が処女でない点である。主人公の少女は性的に開放されているが、ことさら潔癖でも奔放でもなく、セックスが先行し、恋や愛の感情があとから付いてくる状態であるかもしれない。彼女らが性的に潔癖でないぶん「それ」が「うつる」可能性が高くなるが、不潔さはなく、むしろ清潔なのは、その根に他者との触れあいを求める気持ちが感じられるからだ。セックスの描写に扇情性がなく、会話や食事もしくは睡眠の延長のようにスケッチされるのが新鮮だが、映画の仕掛けどころもここにある。カジュアルなセックスが「死」を「うつし合う」状況を誘発し、恐怖に怯え肩を寄せ合い助け合えば合うほどセックスの機会が増えてしまう。また、舞台となるデトロイトの町並みがシネマスコープの画面に印象的に描かれ、若者の心身を包囲して蝕んでいる。ここでは、町そのものが「死」の象徴なのであり、若者たちを孤立させる装置ともなっている。また大人の気配がなく、それが映画全体に「夢の性格」を付与している。若者らは無気力であり、熱情を伴わぬセックスの氾濫が、彼らをより弱い存在にしているともいえる。彼らはセックスによって生死の境をさまようことになるが、生か死のいずれかを選ぶことはできない。両側をまたぎ死とともに生きていくほかはないのだ。


劇中に何度か登場するプールは、彼らがいまだ羊水に浸かる子供であることを示唆するが、いずれ出なければならないが、彼らを取り囲む死に体のボストンから抜け出すこともできない。受け入れなければ死ぬ。浜辺で死んだ少女のように。もっとも『イット・フォローズ』はホラーだから『スターウォーズ』のごとく「愛と連帯」が「悪と弱気」に打ち勝つ可能性は低い。純粋が死に追われ、敗北の危機に瀕してこそホラーだ。これは「セックス」を通じて「死」と出会ってしまった現代アメリカの若者たちの通過儀礼でありサバイバルのドラマなのである。
『イット・フォローズ』は「死」を「克服されるべきもの」でも「克服できないもの」でもなく「受け入れるべきもの」として描いているように思える。それは正論であり、非常に教育的だと思うが、映画は正論や理知でおもしろくなるわけでもない。『イット・フォローズ』でユニークなのはホラーにしては身体性に欠けている点である。観念的かつ知的に構成されている本作はまるで肝心要の「本能」をどこかへ置き忘れているかのようだ。黒沢清の『回路』に描かれた「死の蔓延」と「愛と友情」を思わせなくもないが、あちらのほうがスケールが大きかったし、死の観念にもより膨らみがあったように思える。が、視覚的には『イット・フォローズ』のほうがはるかに好みなのである。