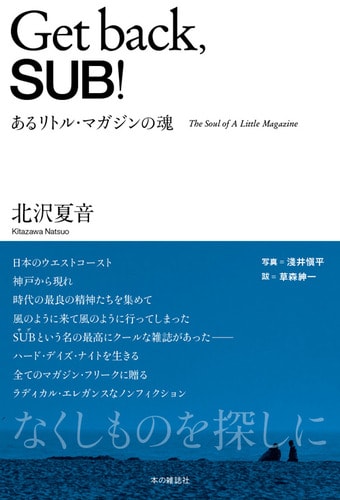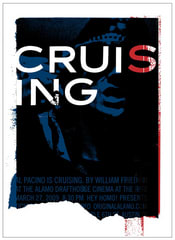草森紳一の「絶対の宣伝 ナチス・プロパガンダ」の第2巻目『宣伝的人間の研究 ヒットラー』が12月7日に発売されることが決まった。
版元はサブカルチャー本に強い文遊社。もうだいぶ前になるけど初めて企画を持ち込んだ日が懐かしい。
単純に「復刊」と言っても、その作業にはさまざまな困難がともなった。テクニカルな面だけでなく、昨今の時代状況も少なからず影響したからだ。しかし念願叶って、順調に刊行されている事実が嬉しい。
新たな装いで再登場した全四巻を早く揃いで本棚に並べて眺めてみたいものだ。
冒頭にある画像が今回の「絶対の宣伝 ナチス・プロパガンダ」(文遊社)の第一巻『宣伝的人間の研究 ゲッベルス」と第二巻『宣伝的人間の研究 ヒットラー』のカバーデザイン。全四巻が揃うとひとつながりのデザインになるはずなのだ。
ちなみに[目次]は次のような内容。
◎民衆の孤独を撃つ ◎ヒットラーの柔らかい髪
◎ヒットラーの妖眼 ◎ヒットラー青少年団
◎平和(ピンフ)の倦怠(アンニュイ) ◎アドルフおじさん
◎陳列効果と象徴 木村恒久・草森紳一
◎附録Ⅰ ヒットラーとレーニンの煽動術 ◎附録Ⅱ ムッソリーニのスキンシップ
◎跋章 知識と官能の無力
今回の復刊にあたり[解説]を書いてくださったのはなんと池内紀さん。
ちょうどいま、池内さん翻訳のホフマン『砂男』を読んでいたところで、これが最高に面白いのだ。



このブログは映画が中心なので、本書の[跋章]から「映画ネタ」の部分を抜粋する。
2015年の年末は『スターウォーズ』の新作が公開で、街のあちこちで宣伝が盛んだが、本書の初版はジョージ・ルーカスが監督した最初の『スターウォーズ』の日本公開と同じ1978年の刊行であり、当時は現代とでは比較にならないほどド派手な「絶対の宣伝」が繰り広げられているように見えた。そのことからはじめる視点が草森らしく、同時にそれは「70年代後半という時代」を思い起こさせるものでもあり、37年後の新作がまさにこれから公開されようとしている21世紀のいまと比較すると、ちょっと考えさせられるものがあって面白い。
以下、引用。
『スターウォーズ』という前宣伝の華々しかった映画を見た、超満員かと思って入ったが、案外、空席が目立った。現代人は、宣伝には、相当にすれっからしになっているな、と思った。理屈抜きに面白いという前評判がたっていた。この「理屈抜き」は、宣伝の決まり文句のようでいて、すこし綾がある。それは、ひところのあの騒がしかった理屈時代の反動の言葉で、他愛なく楽しがることを好む風潮に乗じていたからである。(略)
『未知との遭遇』には、戦慄があった。『スターウォーズ』は、他愛なく楽しむものでよいにしても、あまりにも玩具的であった。現代人は、他愛ない中に、もうすこし現実感がほしかったのではないか。
(略)
日常のファシズムが、資本主義社会に進行しているというのは、常識になっているが、これだけしたたかであれば十分、と安心することはできない。
『スターウォーズ』は、私に言わせれば、理屈をつけて見なければ、どうにもならぬ映画に思えたからである。
このスペースオペラの道具立ては、すべてパロディになっている。パロディは、前承知で動くシビアな世界だから、なんのパロディかがわからなければ、その楽しさは減じる。パロディは記号の美学だから、その発せられた信号を傍受できなかったら、なにがなにやらわからないということになる。『スターウォーズ』は、このパロディ記号の集積でできあがったモザイクであり、わかった分だけ喜びは増えるが、わからなくても、まあ楽しめるような作りになっている。他愛ないといっても、きわめてソフィスティケートな映画であったとも言えるのだ。ソフィスティケーションは、日本人のもっとも苦手とするところであり、満員になるはずもない。(略)
『スターウォーズ』の宣伝口車にのらなかった大衆を思う時、(もっとも興行収入は本年度第一位だそうだが)かえってその危険性を私は感じる。インテリたちの理屈と知識は、無力であり、理屈を語っているだけヒットラーの言う通り、どうしようもない滑稽な存在だが、「理屈抜き」の感性主義もまた泣きを見やすい精神状況である。しかし現代人の官能は、どうしようもなく渇いていることだけは、確実なのである。
( 草森紳一『絶対の宣伝 ナチス・プロパガンダ2 宣伝的人間の研究 ヒットラー』の「跋章」より抜粋)
渡部幻

〈僕もこの光景を記憶している。ここと渋谷東宝で観た。http://wearenocturnalnyc.tumblr.com/より〉