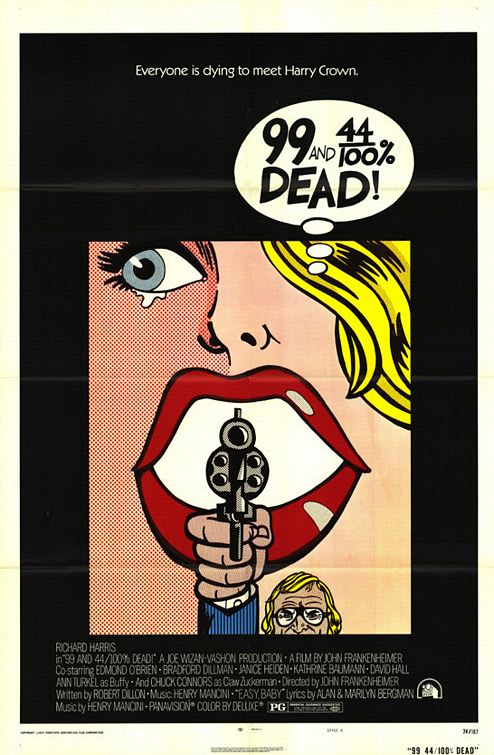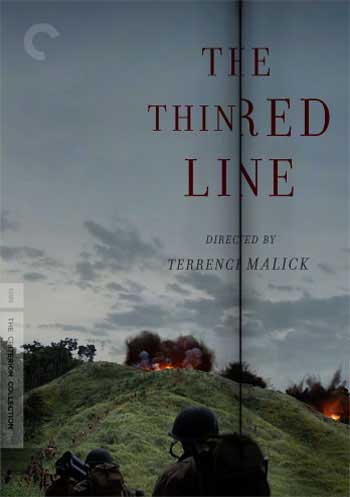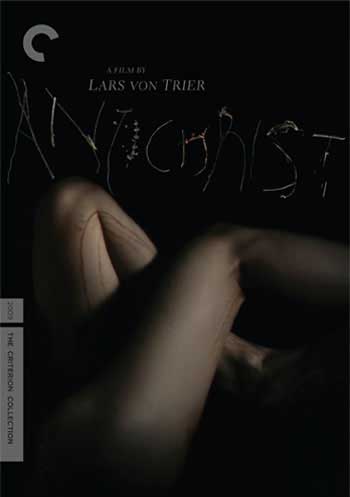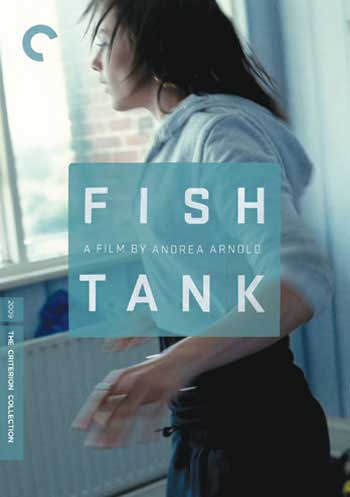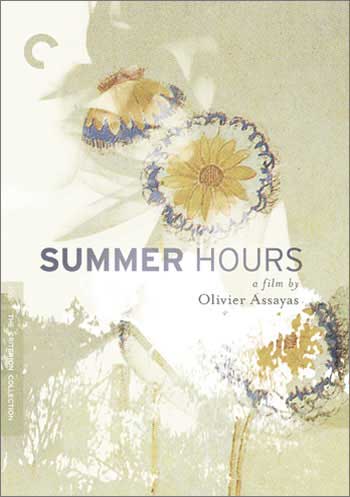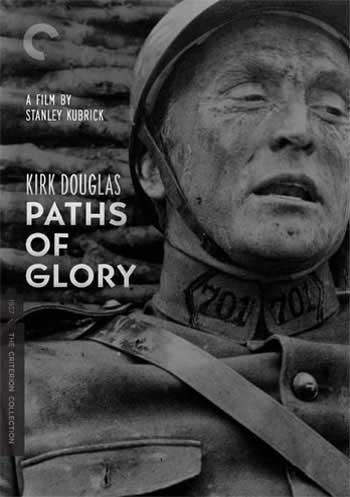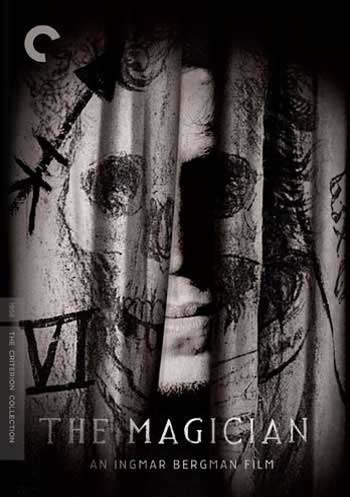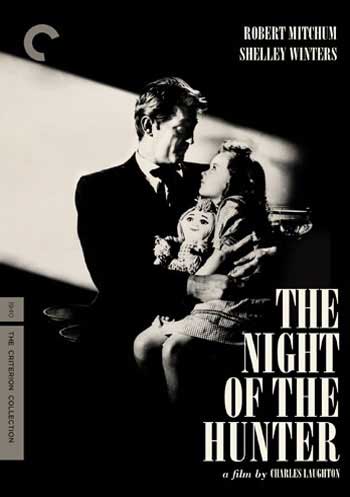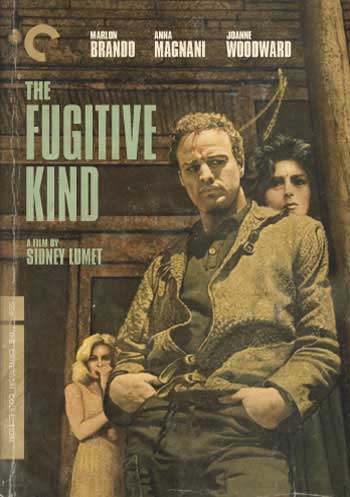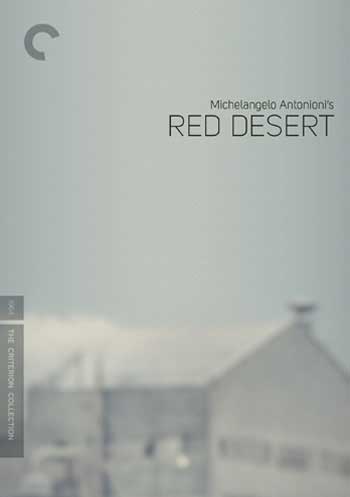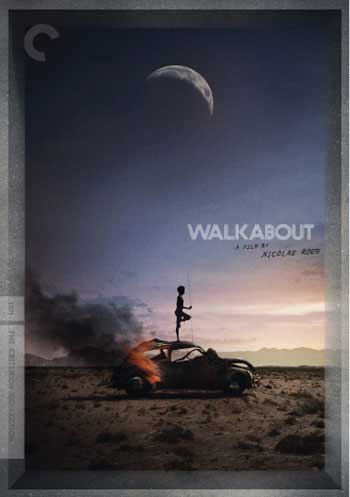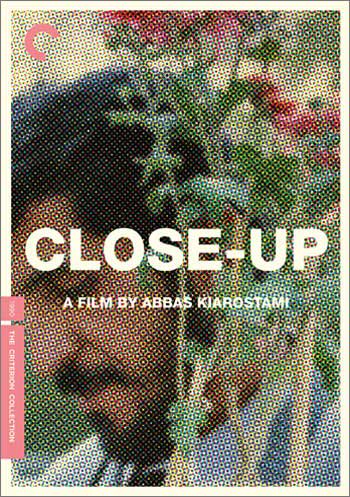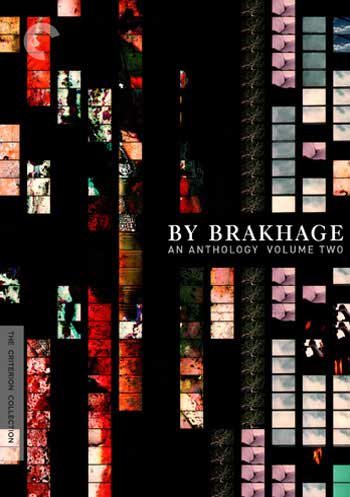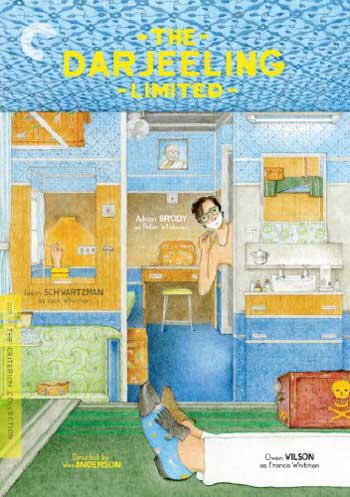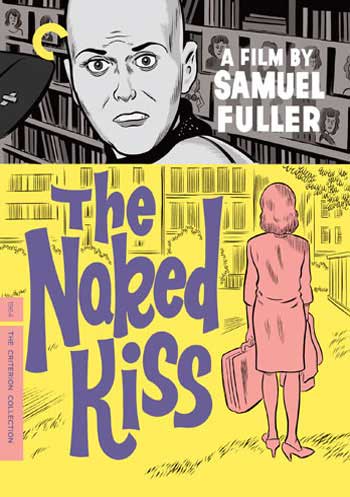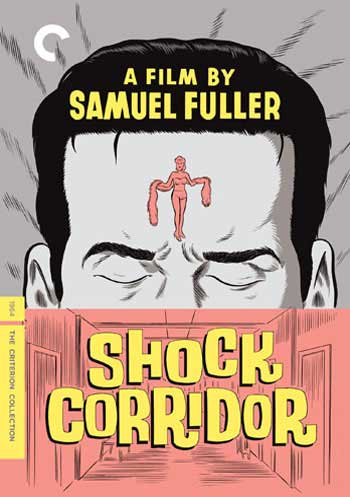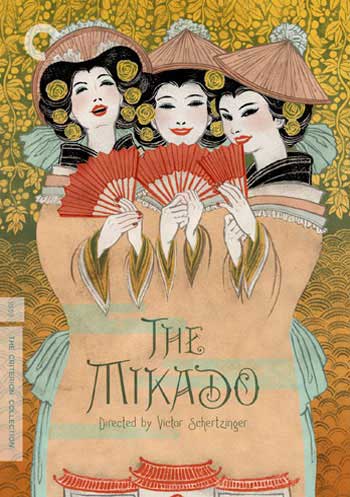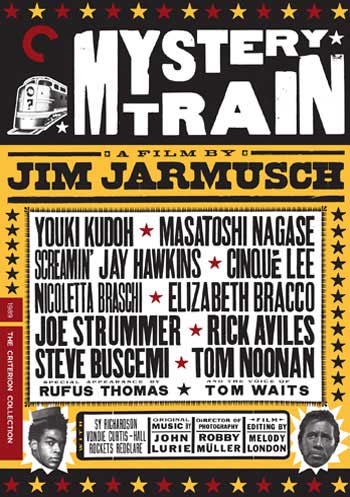ネッド・ベンソンの『ラブストーリーズ』2部作は拾いものの恋愛映画だ。現代のニューヨークを舞台に、若い夫婦の別れからはじまる物語を、夫と妻それぞれの視点からなる「2本の映画」に仕立てている。いわばイーストウッドの『硫黄島』2部作みたいな感じなのだ。
立場の異なる者の争いを視点を変えて描くというのは、公平さや平等への意識が高まる「いま」らしい着想であり、これから流行るかも知れない。しかし今後もそれが面白い展開を見せるかは微妙なところだが、とりあえず現状では新鮮である(表現から独断と偏見を奪うのは危険だ)。人と人のすれ違いや諍い、ことに男女のそれは「解決のないミステリー」のようなものだから、つねに闘争を描く映画という表現にはピッタリだ。
1部「コナーの涙」がジェームズ・マカヴォイ、2部「エリナーの愛情」がジェシカ・チャステインという構成で、個人的には2部目のほうがよいと思うが、当初は1部目のみだったところを監督の友人のチャステインが「女性編」をつくるよう進言したらしい。1部目だけなら大したことはないからチャステインの功績は大きい。


ちなみこの映画、どちらから観てもいいとは思わない。1部目で分からなかった妻の心理が、2部目で見えてくるという構成であり、逆にしてしまうとそういう構成にならず、効果は半減する。DVDの特典に「1本の映画」にまとめたものが入っており、これも観たが、やはり「2部作版」のほうがはるかにいいのだ。
ジェームズ・マカヴォイはいつもながらの好演だが、くせがなさすぎてサラサラしてしまっている。ジェシカ・チャステインの心理表現のほうに見応えがあり、近作の『アメリカン・ドリーマー』でもそうだったが、彼女は目元と口元、そしてアゴの動かし方ひとつで役の心理状況を伝えてしまう。若き日のメリル・ストリープやジェシカ・ラングを思わせる実力派女優として将来が期待されるひとりだろう。二人の両親役で出ているウィリアム・ハート、イザベラ・ユペール、キーラン・ハインズの芝居もしっとりと落ち着いていて悪くない。


『ラブストーリーズ』は『(500)日のサマー』みたいなコメディではないし、『ブルーバレンタイン』のように鈍痛に襲われるヘヴィな作品でもない。包み込む優しさが身上で、その意味で古典的とも言えるが、そこは「2部作」の利点を発揮して観る人の経験で解釈を変えるであろうおもしろさがある。もしこれをカップルで観て「意見が一致」したとすればそれは赤信号である。本作が描くようにそんなわけはないのだから。しかし「恋愛映画」とはそもそもがそういうものなのであり、だとすると、このつくり方は少々「お澄ましに過ぎる」かもしれない。
ニューヨークをとらえた撮影がなかなか綺麗そうだったが、劇場でなくDVD鑑賞だったので、ぼんやり画面を頭のなかで修正しつつ観なければならなかった。とはいえ、「★★★」という感じのこうした作品を、たまに観るのもいいものだと思った。
(渡部幻)