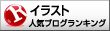『70年代アメリカ映画100』の「はじめに」(執筆・渡部幻)より。
60年代のアメリカ社会は「抗議」と「造反」と「革命」に燃えあがった。
ベトナム戦争、軍の隊列、機動隊、選挙、公民権運動、学園紛争……。1969年にウッドストックに集まる40万のヒッピー、70年5月のニューヨークにおけるブルーカラーと反戦学生たちの衝突――これらの記録映像に通低している視覚的なイメージは、祭りとも見紛わせる人の群れ、つまり「群集」のド迫力である。平和的、暴力的、もしくは中立的なそれであっても、群集は共通して社会への帰属意識に目覚め、ときに巨大な群れになることで、前例のない「祭り(政)の季節」を生きた。


俺たちは負けたんだ――デニス・ホッパー監督『イージー・ライダー』(69)より
1967年、アーサー・ペンが『俺たちに明日はない』で大恐慌期に実在したギャングカップルと彼らを蜂の巣にした体制による87発の銃弾を描いて「ニューシネマ時代」が到来。そして69年、デニス・ホッパーの『イージー・ライダー』で無害なバイカー2人が射殺された瞬間、その頂点を極めたとするなら――「ニューシネマ時代」を「ハリウッド帝国」を揺るがした映画版「祭りの季節」と呼ぶとして――続く70年代が幕を開けた時点で、その熱波は、すでに「終わっていた」、もしくは「終わりつつあった」ということになるだろうか。
確かに、同時期に現れた傑作群――マイク・ニコルズの『卒業』(67)、スチュアート・ローゼンバーグの『暴力脱獄』(67)、ジョン・ブアマンの『殺しの分け前/ポイントブランク』(67)、フランク・ペリーの『泳ぐひと』(68)、ジョン・シュレシンジャーの『真夜中のカーボーイ』(69)など――は、改革に燃える熱狂というよりも、むしろどこか醒めた自己批評精神にこそ、その優れた特性を示し得ていた。
『イージー・ライダー』と同年にハスケル・ウェクスラーは『アメリカを斬る』を発表。68年のシカゴ民主党大会で起こった群集のデモに対する体制側の弾圧を、テレビ報道メディアの問題と絡めて炙りだした。その予告編では女性のナレーションが次のように語りかけてくる。
「“純粋さ”とは感情。“自由”とは感覚。感情を失うってどんな感覚? 誰もが感情をなくしたら、国中が暴力で満ち溢れるはずよ。我々の良識を問う現代ドラマ。純粋な時代は過ぎ去り、認識の時代が到来――」


70年代初頭――祭りのあとの索漠とした雰囲気のなかで、人々は離散し、個々の世界へと舞い戻りはじめていた。そんな「70年代」の世相は「60年代」に比べるとあまり革新的な時代ではなかったかも知れない。
だが、アメリカ映画はここから「ルネッサンス期」を迎えるのだ。新しい映画作家たちが次々に産声をあげた。彼らは、人と時代と環境の関係を観察し、掘り下げ、洞察した。観る者の心をかき乱す猥雑な表現を生みだし、旧来の型を打ち破って、かつてないエネルギッシュな一時代を築き上げていった。
しかし、いつの時代の映画や監督にも、それが生まれてきた背景があり、決してそこから逃れることはできない。映画がイメージを扱う芸術表現である以上、それは必然であり、一種の宿命として作品に反映される。
では、ニューシネマを代表した反骨の監督たちの人格や個性の形成に影響を及ぼした「背景」には一体どんな「時代」があったのだろうか。
アーサー・ペン、ジョージ・ロイ・ヒルは1923年生まれ。ロバート・アルトマン、サム・ペキンパーは25年。ノーマン・ジュイシン、ロジャー・コーマンは26年。スタンリー・キューブリックは28年。ハル・アシュビーは29年。クリント・イーストウッド、ジョン・フランケンハイマーは30年。マイク・ニコルズが31年、シドニー・歩ラックが34年の生まれ……彼らは20年代から30年代の生まれだったと分かる。


1920年代は「ローリング・トゥエンティーズ(狂乱の20年代)」と呼ばれ、都市化と大衆消費が加速して繁栄に沸いた時代である。しかし一転、29年の株価大暴落によって30年代は未曾有の大恐慌に突入。40~50年代は、第二次世界大戦を通過(従軍経験を持つ監督は多い)して、戦後景気に沸き、パクス・アメリカーナの完成、米ソ冷戦、核戦争の恐怖、赤狩り、そして朝鮮戦争へと辿る過程にあった。文化的に見るならそこには、20年代のロスト・ジェネレーション、ギャングエイジ、ハーレムルネッサンス、フラッパー、ラジオ文化、そして黄金期ハリウッドの西部劇やギャング映画があり、さらにのちにはビートジェネレーションや続くロックジェネレーションの台頭があり、こうしたサブカルチャーが恐慌と戦争の時代を生きる者たちの鬱積や怒りを受け止めてきた。彼ら監督たちもまたこうした時代に青春を過ごし、その感慨と屈折が、「70年代アメリカ映画」の背景を彩る大きな要素となり、作品に反映して、次なる世代=ベビーブーマーの感性とも結びついていくのだ。


「人生は祭りだ」――フェデリコ・フェリーニ監督『81/2』(63)より
イタリアの巨匠フェリーニは映画と人生を結びつけて「祭りの場」へと昇華させたが、「アメリカのフェリーニ」と形成されたロバート・アルトマンは、75年の『ナッシュビル』で「アメリカ建築200年」の「祝祭」に宛てた革新的な「映画の祭典」を生みだした。
当時50歳の彼は、政治に汚されたカントリー&ウエスタン音楽祭における、とある女性歌手の暗殺をとらえ、その直後に、風に重く揺らぐスターズ・アンド・ストライプスの上に広がる曇り空を見上げていた。
共和党のリチャード・ニクソンの大統領再選に対する、アルトマンの憤怒から生まれたというこの異型の作品について、そのニクソンに敗れた民主党のジョージ・マクガバンがうまく要約している。
「意気があがったとは、とても言えないね。あの映画は悲劇と喜劇の両方だ。79年代のわれわれの生活の良いドラマと辛辣な状況をうまく描いているよ。この国の魂をえぐりだして、しかも何も答えもないままで終わっている」(「ローリング・ストーン」誌1976月5月号)


二年後の77年。やはり「空を見上げる者」として登場したのがベビーブーム世代の若き天才スティーヴン・スピルバーグである。
彼は『未知との遭遇』で、夜空を覆う雲のなかから現れてくる数機のUFOと巨大なマザーシップの降臨を見上げてみせた。ステンドグラスを思わせる色彩と光の洪水、それを見上げ、息を呑む群集の恍惚とした表情――。最初は「驚異」、次に「信心」、そして天上的な「至福」へと至るそれは、人智を超えた存在に対する、一種、宗教的とも言えるような「祭典」としての映画だった。
これは70ミリの巨大スクリーンで、しかも満員の劇場で他者と共有することによって、初めて体感することのできる映像体験であり、また、そのようにつくられてもいる。
満天の星空に『ピノキオ』(40)のテーマ曲「星に願いを」を聴かせる、この作品の持つ「オプティミズム」を理解するためには、例えば、あの『ナッシュビル』の「曇り空」に象徴されたいたような「ペシミズム」と、擦れっ枯らしになる以前の無防備な感受性を前提とし、理解することが、多少なりとも必要かもしれない。対照的な2本の映画は、ともに時代の落とし子であり、もはや当時と同様の驚嘆を、現在にもたらすことはありえないだろう。


「we are not alone 我々は一人ではない」――スティーヴン・スピルバーグ監督『未知との遭遇』の広告コピーより
映画と宗教は似て、それを売るものとっては宣伝であり商品の一つに過ぎないかもしれない。しかし、ビデオが普及するはるか以前の観衆にとっては、映画はいまだ手に取れる「物」としての商品ではありえなかった。あくまでも映画鑑賞は闇のなかで光を仰ぎ観る「祭り」であり、人はそこで得た感慨を、みずからの記憶に焼きつけて残すほかのすべを持たなかったのである。
その意味では、スピルバーグと同世代に当たる『タクシードライバー』(76)のマーティン・スコセッシが、「教会と映画館」を結びつけて語る言葉も、それほど突飛な物言いではない。つまり大げさに言えば、劇場で映画を観るということは、大衆が一つ屋根の下に集まり、もうひとつの人生と向かい合う「祭りの場」として、単に商品として消費されるだけに終わらない「何か」としての役割をも果たし得ていたのだ。
そんなスピルバーグ世代が志向し、かつ成功させていくのは映画ならではの祝祭性、つもり「エンターテインメント」の復権である。
ベトナム戦争が終結、ニクソンは失脚し、さして盛り上がらない建国200年祭も過ぎたあとで、人々は見上げることのできる「祭りの場」としての「エンターテインメント」を欲した。
先輩格にあたるフランシス・フォード・コッポラが『ゴッドファーザー』(72)で描いたイタリア系マフィアの結婚式や、『地獄の黙示録』(79)でジャングルを焼き払うナパームの華麗なスペクタクル(祝祭)には、「ポリティクス」と「エンターテインメント」の融合があったが、そのコッポラと同じイタリア系アメリカ人俳優から、『ロッキー』(76、ジョン・G・アヴィルドセン監督)のシルヴェスター・スタローンと『サタデー・ナイト・フィーバー』(77、ジョン・バダム監督)のジョン・トラヴォルタが登場。彼らをスターへと祭り上げた。ヘビー級タイトルマッチとディスコ・コンテストもまた、ささやかながら「祭りの場」としての映画興行を盛りあげていた。


もう一つ、70年代後半で思い出されるのは、喫茶店やゲームセンターの窓もない暗く狭い室内に整然と設置されたテーブルゲームと、レモン入りコカ・コーラのグラスとストローである。「スペースインベーダー」のモニター画面に展開する小さな宇宙と電子音の世界に、黙々と興じている風景は、なぜかそのまま80年代に隆盛した初期ビデオレンタル店の狭くて淫靡な雰囲気と重なっており、そこには、自分独りだけのための「侘しき祭り」の贅沢と官能があった。
80~90年代は、この「極私性」から以前とは別種の活況が生みだされていくこととなるが、さらに時を経た現在、より記号化が進み、細分化され、ときに格安商品として店頭に並べられた中古ビデオやDVDという名の「時の記憶」のなかから、新たな「祭りの熱狂」を引きだせるかどうかは、個々の官能力に関わってくるのかも知れない。



(渡部幻)