ジョン・ブアマンという面白い監督がいるのだが大抵は忘れているか、最初から知らない。
スタンリー・キューブリックの友人で、なんと坂東玉三郎が好きな監督としてあげる人物である。
しかし、日本ではあまり取り上げられない映画作家の一人なのだ。
ブアマン映画は基本的に奇抜である。
二度同じ事をやらない。ハードボイルド、戦争、冒険アクション、SF、ホラー、と娯楽映画に欠かせない王道的なジャンルばかりなのだが、共通して映像感覚が変わっていて、どれもが定型から逸脱した奇矯な作品ばかりなのだ。
リー・マービン主演の「殺しの分け前/ポイントブランク」マルチェロ・マストロヤンニ主演の「最後の栄光(LEO THE LAST)」、マービンと三船敏郎の二人しか出ない「太平洋の地獄」、ジョン・ボイトとバート・レイノルズ共演の「脱出」、ショーン・コネリーの「未来惑星ザルドス」、リチャード・バートンの「エクソシスト2」、アーサー王伝説を描く「エクスカリバー」、パワーズ・ブースの「エメラルド・フォレスト」、ブレンダン・グリーソンの「ジェネラル」、それに自伝映画「戦場の小さな天使たち」もあるが、かなり男っぽい配役をする監督ではある。
また、「LEO THE LAST」と「ジェネラル」でカンヌ映画祭の監督賞を受賞しているが、その2本ともが日本ではまともに公開されていない。ちょっと不遇の作家なのである。



1972年の「脱出」は日本でもよく知られた作品だろう。
僕はテレビで観て衝撃を受けたが、多分、多くの人もそうだろうと思う。
都会のサラリーマン4人組が恐ろしい目に会うという物語である。
彼らが南部の河にレジャーでやってくるところから始まる。急流でカヌーに挑戦しようというのだ。
冒頭でバート・レイノルズは言う。「いまこの世界では自然が破壊されている。この河もすぐにダムになってしまうんだ。許せるか? だから俺たちはここまで来たんだ」
彼は仲間を率いて二台の車でやってくる。レイノルズの他、ジョン・ヴォイド、ネッド・ビーティー、ロニー・コックスという顔ぶれであり、みなが各々の存在感を発揮している。ヴォイドとレイノルズの間にそこはかとないホモセクシュアルな雰囲気が漂っているが、70年代のアメリカ映画らしい描写だ。


彼らがたどり着く南部の村は貧しい。ネッド・ビーティーは差別意識丸出しの男で、彼らをホワイトラッシュだとバカにしている。ロニー・コックスはリベラルな男で、たぶん近親相姦によるものと想像させる少年とともに音楽を奏でたりする。彼がギターを弾くと、吊り椅子に腰掛けた少年がバンジョーを奏でる。伝説的なデュエリング・バンジョーの場面だが、ブアマンの演出はこの心温まる場面のなかに得も言われぬ不安感を染み込ませていく。このあと起こるだろう得体の知れぬ禍々しいものの蠢きを予感させるのである。

男たちはここに暮らす人に乗用車を預けて下流まで持っていくよう指示する。臨場感溢れるカヌーによる激流下りが見所になるが、ブアマンの主眼は、人の奥底に眠る原始的本能の目覚めを描くことにある。『脱出』はアクション映画としても秀逸だが、それ以上に、人間と自然の関係に迫る心理劇的な側面にこそ観る者の息を飲ませる凄みを有している。
文明人のアウトドア・レジャーは、次第に悪夢の様相を色濃くしていく。
「自然」は彼らが思うほど甘くも美しいものでもなかった。彼らの、思い込みとも思い上がりとも取れる見識と態度が、痛烈なしっぺ返しとなって返ってくるのである。南部の森の奥深くへの冒険旅行は、原始に遡る旅となる。やがて森から現地の薄汚れた男の二人組みが現れ、文明人のうちの二人ジョン・ヴォイトとネッド・ビーティーがホモ・レイプの犠牲者となる。
ブアマンは「自然によるレイプ」だと説明するが、それは自然をレイプしてダムをつくり続ける文明人への復讐を意味する。レイプシーンの凄まじさはただごとでなく、語り草となるのに相応しい鮮烈な演出と演技だ。
これをテレビで見たのはまだ小学生の時だったが全身が凍りついた。あの、現地男の俳優とは思えない芝居の「本物らしさ」、後背位からビーティーをレイプしながら「豚のようにわめけえ!ブキィー!ブキィー!」と言うときの絶叫が耳から離れなくなった。これに、もう歯の欠けたもう一人の現地男がヴォイトを見つめにやけて「こいつ……可愛い唇してやがるぜ」と言う場面を加えて、映画における恐怖表現の革命といって過言ではないと思う。(こういう「教育的」な映画をテレビでひんぱんに放送していたものである)


そこへタフガイ男のバート・レイノルズと最も大人しいロニー・コックスが到着し、レイノルズが得意の弓矢で現地男の一人を殺害。もう一人には逃げられてしまう。射抜かれた男はすぐに死なない。森に手をかざして口をアングリと空けたままでユックリと彷徨い、やがて息絶えるのである。レイノルズは男の身体から刺さった矢引き抜く。バカンス気分を木っ端微塵に打ち砕く、すごい演出だが、ブアマンは異様な細部の積み重ねによって、単純な「冒険物語」を異化しているのだ。
四人の前に現地男の死体が残されている。これをどうするか。しかも一人には逃げられてしまってる。
文明人四人は言い争いを始める。唯一「原始の野生」に対抗できそうなレイノルズは「現地の奴らと裁判で争っても勝ち目はない。よく考えろ。ここはダムになるんだ。水の底だ。ここに埋めりゃあいい。誰にも分からない」と言う。理性の声の代表者コックスは「これは殺人だ。我々は人を殺したんだ。警察に訳を話して任せるべきだ」と叫ぶ。彼らは民主主義に則り多数決で決める。理性の声は敗れる。死体を埋め、残るは逃げたもう一人の男を始末すること。そして映画はここから「ジョン・ブアマン節」の悪夢的なシュルレアリスム・タッチを全開にしていくのだ。
『脱出』を迫真の作品にした功績者としてヴィルモス・ジグモンドの撮影お挙げておく必要があるだろう。
かくも大胆な作品はアメリカでヒットを記録。アカデミー賞で「ゴッドファーザー」「キャバレー」と肩を並べる作品賞候補作となって、後世に残るカルト作となったのである。




『脱出』は後味が長く残る作品で、気がつけば僕はブアマン・ファンになっていた。
80年代初頭のことだが、調べるとすでに劇場で『エクソシスト2』を観ていた。
この映画も大好きだったが、ここではあとに回す。
僕が何よりも先に観たかったのは1967年の『殺しの分け前/ポイントブランク』だ。リー・マービン主演、リチャード・スターク原作のハードボイルドだが、テレビでの放送を見て驚いた。これもまたブアマンのシュルレアリスム・タッチを縦横無尽に展開させた実験的かつ超難解なノワール・フィルムだったのだ。
物語そのものはシンプルである。主人公リー・マーヴィンは無二の親友に懇願されてアルカトラズ刑務所での現金取引を襲う計画を引き受けるが、友人のみならず彼と密通していた自らの妻にまで裏切られてしまう。リーは撃たれ、その場においていかれるが、蘇えり、裏切り者に復讐すべくサンフランシスコへと舞い戻ってくるというもの。しかしブアマンは、原作にないフラッシュバックとフラッシュフォワードを多用、全篇をコラージュして「記憶の地獄めぐり」のごとき異色作に仕立て上げた。


「ポイントブランク」のスタイルは、リチャード・レスターの「華やかな情事」やニコラス・ローグの『パフォーマンス」「赤い影」と共鳴している。マイク・ニコルズの『キャッチ22』やジョージ・ロイ・ヒルの『スローターハウス5」も同様のスタイルが見られるが、より本家に近いのは、ずっと後にスティーヴン・ソダーバーグがつくった「蒼い記憶」と「イギリスからきた男」である。
「ポイントブランク」は映画が始まるとすぐに銃声を聞かせる。そして、タイトルとともに狭い部屋の隅に倒れるリーの姿。彼の視覚から見える天井、痙攣する指、そして「ムショだ……刑務所だ……なんでここにいる・・・…」とうめく、リーの声。始まってものの何十秒かの間のことである。映像は過去に戻り、ここに到る顛末を走馬灯のように描き出す。そして再び冒頭と同じ銃声と倒れるリーの姿と「ムショだ……」のうめき声。だが、絶命したと思えたリーがムクリと起き上がり、映像はストップモーションに。ここからクレジットが始まるが、実はよく見ると「静止画」でないことがわかる。つまり、演じるリー・マーヴィン自身が実際に身体を止まってみせているのだ。金網をよじ登るリーの静止したすがたの背景に広がる空には鳥が悠々と飛び回っている。ブアマンはここで、この主人公が一種のゴーストであり、以後のドラマが「記憶の反復」からなることを示唆しているのだ。




リー・マーヴィンは60年代にジョン・フォードの『リバティ・バランスを撃った男』の悪役で主役のジョン・ウェインやジェームズ・スチュアートを食ってしまった。完全無欠の英雄よりもすねに傷を持つ悪に共鳴を覚える反体制的な気分の時代が始まったが、リーはここで同時代の出演作「殺人者たち」「特攻大作戦」「太平洋の地獄」と並ぶ名演を披露して、実に格好いい。ブアマンが撮ったリーが妻の自宅を襲撃する場面や、長い廊下を歩き続ける姿は最高である。こんな歩行は軍人だった彼にしか出来ないだろう。ここではリー自身の記憶が反復しているのだ。「ポイントブランク」は、アラン・レネとゴダールとヒューストンが一緒に作ったかのような作品であり、ブアマンによる一つの「発明」だと言える。
僕の最初のブアマン体験は「エクソシスト2」だと書いた。勿論、これはかのフリードキン監督の伝説的オカルト映画の続編企画で、フリードキンと原作者のウイリアム・ピーター・ブラッディが揃って認めないと怒りを露わにした問題作だ。重厚な感動で前作に遠く及ばないが、実はこれはこれでかなりの傑作というか異色作なのだ。主演は前作に引き続きリンダ・ブレアーとマックス・フォン・シドー。新たにルイーズ・フレッチャーとリチャード・バートン、ジェームズ・アール・ジョーンズなど演技派が顔を揃える。
映画史に残るの悪魔憑き少女リーガンももう思春期である。前作が74年公開、『2』は77年公開だから3年ほどの時間の間に驚くような成長をみせる(演技ではなく肉体的にだ)。「エクソシスト」の凄まじい怪奇現象は、実は少女リーガンノの抱えている成長期特有の不安定さにある。彼女を取り巻く大人たちの振る舞いが、少女の心を揺るがせ「悪魔」が隙き入る余地を与えていた。その意味で罪人たるは大人たちだが、彼らもまた苦しみに耐えている。彼らが悪魔に翻弄されながらいかに対処していくのかが主眼になっているのである。


ブアマンの「2」は現代社会における信仰の問題にリーガンの青春物語を絡み合わせた作品だ。
フリードキンがドキュメンタリー的な客観描写を重視したのに対し、ブアマンの選んだのは主観的かつ超心理的な映像スタイルで、これによって観る者を「内なる世界への旅」に招待しようというのだ。
例えば、イナゴの主観(同時に神父の視点)になったカメラが世界中を飛び回り、その途中、コクモというアフリカ人の口のなかから虎が飛びだしてくるなど、奇怪かつ夢幻的な映像が続出してくる。
ケン・ラッセルの「アルタード・ステーツ」に通じるような、これはそういう難解な作品なのである。
忘れがたいエンニオ・モリコーネのテーマ曲。ロック的なビートを大々的にフィーチャーしたプロモ・ビデオのような予告編があるが、これがまた奇抜であり、実にカッコイイ。公開当時「渋谷の本のデパート」と呼ばれた太盛堂の地下のレコード売り場でシングル・レコードを購入。これを毎朝学校に行く前に聴いていたことがあった。



「太平洋の地獄」も好きな作品だ。第二次大戦末期に無人島へ流れ着いた日米の軍人二人をリー・マーヴィンと三船敏郎が演じる。最高の組み合わせであり、しかも文字通り二人のみの主演。子供じみてしかし切実な喧嘩を繰り広げる異色大作だが、最後まで互いの言葉が通じ合わず、ゆえに醸し出してくるユーモアの妙がリアルかつ秀逸。だが、ラストシーンは衝撃的で、思わず言葉を失なう。
「未来惑星ザルドス」こそブアマンの最高作に挙げる人もいるかもしれない。彼の思想哲学が炸裂する難解なSF大作で、ルネ・マグリットのシュルレアリスム絵画からのインスパイアも見られる。主演にショーン・コネリーとシャーロット・ランプリングという豪華だがなんとも妙な配役がまた効いてる。
いつだかの未来の話である。コネリー扮する知性を持った「獣人」の妙な衣装や空中に浮かぶ偽の神「ザルドス」の巨大な石顔。科学的に不老不死の命を得た人々の暮らす桃源郷ヴォルテックスには、カラフルな色彩が乱舞し、何もかもが奇抜である。フェリーニとキューブリックとケン・ラッセルが作ったSFがあるとすればこんな感じであろうか。ここでもラストが印象的で、ベートーヴェンが流れるなか、子を作り、老い、そして死んでゆく男と女のモンタージュが美しい。


「エクスカリバー」はブアマンが少年時代からこだわる「アーサー王伝説」の念願の映画化。黒澤明の「影武者」を彷彿とさせるファーストシーンから魅力あふれるダークファンタジーの世界を披露する。個人的には役者たちが一つ魅力に欠けていたが、海外ではアーサー王伝説の教材に使用されるほどの評価を確立しているという。


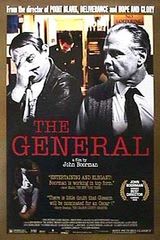
「エメラルドフォレスト」は「脱出」と「エクソシスト2」をかけ合わせたような作品だ。
文明と自然の齟齬と対立を幻想的なアクション描写で調理しているが、エコロジー問題は、ブアマンのライフワークなテーマなのだ。南米のジャングルを切り開きダムをつくる工事が進んでいる。これに携わる主人公の息子が、その森に暮らす部族にさらわれてしまう。数年後も彼を探し続けていた父親はついに再会を果たすが、しかしかつての少年はいまや部族の戦士となっていた……。宮崎駿の「もののけ姫」に大分先駆けた映画である。というよりは宮崎駿も好きな映画かもしれない。主演はパワーズ・ブース。そしてブアマンの息子チャーリーである。
「戦場の小さな天使たち」は普段とはかなり毛色の違う見事な自伝映画である。
ブアマンの少年時代は第二次大戦さなかのイギリス。ときに空爆のあるなか、夢見がちな少年だった彼は、川や水、アーサー王を偏愛している。日本タイトルがひどいが戦時下のイギリス家族のスケッチは美しく、追想が温かなユーモアに包まれた名品だった。
「ジェネラル」もユニークな作品だ。アイルランドのフォーク・ヒーローとなった伝説的な泥棒と彼の人気に嫉妬した警官の対立を描いた物語で、日本未公開の「LEO THE LAST」以来久しぶりにカンヌの監督賞を獲得した。かつての「ブアマン節」を期待すると正攻法の仕上がりに戸惑うかも知れないが、ブアマンはアイルランド映画に貢献してきたのであり、しかも自宅をこの泥棒に狙われている。加えて、同じ題材を描いた「私の愛したギャングスター」というケビン・スペイシー主演の凡作と比較すれば、さすがブアマン演出は素晴らしい。モノクロ・シネマスコープの撮影、反体制と体制のせめぎ合いが、ブレンダン・グリーソンとジョン・ヴォイトの演技によって浮き上がり、格段に優れているのである。
ブアマンも近年はすっかり「渋く」なったが、70年代に放った知的かつ実験的な作品群は今もその刺激を失っておらず、その多くは予見的なテーマを扱っている。ことに「ポイントブランク」と「脱出」は、映画ファンなら観ておくべきだろうが、個人的には「太平洋の地獄」も観て欲しい。
そして作家ジョン・ブアマンを発見して欲しい。大著『キューブリック』で有名なミシェル・シマンの『ブアマン』を是非、翻訳して欲しいものだ。同時にリー・マーヴィンという類稀なる男優の魅力も発見されるといいのだが。
2008年発表の日本未公開作「tigers tail」を観てみたいのだけど無理だろうか?

スタンリー・キューブリックの友人で、なんと坂東玉三郎が好きな監督としてあげる人物である。
しかし、日本ではあまり取り上げられない映画作家の一人なのだ。
ブアマン映画は基本的に奇抜である。
二度同じ事をやらない。ハードボイルド、戦争、冒険アクション、SF、ホラー、と娯楽映画に欠かせない王道的なジャンルばかりなのだが、共通して映像感覚が変わっていて、どれもが定型から逸脱した奇矯な作品ばかりなのだ。
リー・マービン主演の「殺しの分け前/ポイントブランク」マルチェロ・マストロヤンニ主演の「最後の栄光(LEO THE LAST)」、マービンと三船敏郎の二人しか出ない「太平洋の地獄」、ジョン・ボイトとバート・レイノルズ共演の「脱出」、ショーン・コネリーの「未来惑星ザルドス」、リチャード・バートンの「エクソシスト2」、アーサー王伝説を描く「エクスカリバー」、パワーズ・ブースの「エメラルド・フォレスト」、ブレンダン・グリーソンの「ジェネラル」、それに自伝映画「戦場の小さな天使たち」もあるが、かなり男っぽい配役をする監督ではある。
また、「LEO THE LAST」と「ジェネラル」でカンヌ映画祭の監督賞を受賞しているが、その2本ともが日本ではまともに公開されていない。ちょっと不遇の作家なのである。



1972年の「脱出」は日本でもよく知られた作品だろう。
僕はテレビで観て衝撃を受けたが、多分、多くの人もそうだろうと思う。
都会のサラリーマン4人組が恐ろしい目に会うという物語である。
彼らが南部の河にレジャーでやってくるところから始まる。急流でカヌーに挑戦しようというのだ。
冒頭でバート・レイノルズは言う。「いまこの世界では自然が破壊されている。この河もすぐにダムになってしまうんだ。許せるか? だから俺たちはここまで来たんだ」
彼は仲間を率いて二台の車でやってくる。レイノルズの他、ジョン・ヴォイド、ネッド・ビーティー、ロニー・コックスという顔ぶれであり、みなが各々の存在感を発揮している。ヴォイドとレイノルズの間にそこはかとないホモセクシュアルな雰囲気が漂っているが、70年代のアメリカ映画らしい描写だ。


彼らがたどり着く南部の村は貧しい。ネッド・ビーティーは差別意識丸出しの男で、彼らをホワイトラッシュだとバカにしている。ロニー・コックスはリベラルな男で、たぶん近親相姦によるものと想像させる少年とともに音楽を奏でたりする。彼がギターを弾くと、吊り椅子に腰掛けた少年がバンジョーを奏でる。伝説的なデュエリング・バンジョーの場面だが、ブアマンの演出はこの心温まる場面のなかに得も言われぬ不安感を染み込ませていく。このあと起こるだろう得体の知れぬ禍々しいものの蠢きを予感させるのである。

男たちはここに暮らす人に乗用車を預けて下流まで持っていくよう指示する。臨場感溢れるカヌーによる激流下りが見所になるが、ブアマンの主眼は、人の奥底に眠る原始的本能の目覚めを描くことにある。『脱出』はアクション映画としても秀逸だが、それ以上に、人間と自然の関係に迫る心理劇的な側面にこそ観る者の息を飲ませる凄みを有している。
文明人のアウトドア・レジャーは、次第に悪夢の様相を色濃くしていく。
「自然」は彼らが思うほど甘くも美しいものでもなかった。彼らの、思い込みとも思い上がりとも取れる見識と態度が、痛烈なしっぺ返しとなって返ってくるのである。南部の森の奥深くへの冒険旅行は、原始に遡る旅となる。やがて森から現地の薄汚れた男の二人組みが現れ、文明人のうちの二人ジョン・ヴォイトとネッド・ビーティーがホモ・レイプの犠牲者となる。
ブアマンは「自然によるレイプ」だと説明するが、それは自然をレイプしてダムをつくり続ける文明人への復讐を意味する。レイプシーンの凄まじさはただごとでなく、語り草となるのに相応しい鮮烈な演出と演技だ。
これをテレビで見たのはまだ小学生の時だったが全身が凍りついた。あの、現地男の俳優とは思えない芝居の「本物らしさ」、後背位からビーティーをレイプしながら「豚のようにわめけえ!ブキィー!ブキィー!」と言うときの絶叫が耳から離れなくなった。これに、もう歯の欠けたもう一人の現地男がヴォイトを見つめにやけて「こいつ……可愛い唇してやがるぜ」と言う場面を加えて、映画における恐怖表現の革命といって過言ではないと思う。(こういう「教育的」な映画をテレビでひんぱんに放送していたものである)


そこへタフガイ男のバート・レイノルズと最も大人しいロニー・コックスが到着し、レイノルズが得意の弓矢で現地男の一人を殺害。もう一人には逃げられてしまう。射抜かれた男はすぐに死なない。森に手をかざして口をアングリと空けたままでユックリと彷徨い、やがて息絶えるのである。レイノルズは男の身体から刺さった矢引き抜く。バカンス気分を木っ端微塵に打ち砕く、すごい演出だが、ブアマンは異様な細部の積み重ねによって、単純な「冒険物語」を異化しているのだ。
四人の前に現地男の死体が残されている。これをどうするか。しかも一人には逃げられてしまってる。
文明人四人は言い争いを始める。唯一「原始の野生」に対抗できそうなレイノルズは「現地の奴らと裁判で争っても勝ち目はない。よく考えろ。ここはダムになるんだ。水の底だ。ここに埋めりゃあいい。誰にも分からない」と言う。理性の声の代表者コックスは「これは殺人だ。我々は人を殺したんだ。警察に訳を話して任せるべきだ」と叫ぶ。彼らは民主主義に則り多数決で決める。理性の声は敗れる。死体を埋め、残るは逃げたもう一人の男を始末すること。そして映画はここから「ジョン・ブアマン節」の悪夢的なシュルレアリスム・タッチを全開にしていくのだ。
『脱出』を迫真の作品にした功績者としてヴィルモス・ジグモンドの撮影お挙げておく必要があるだろう。
かくも大胆な作品はアメリカでヒットを記録。アカデミー賞で「ゴッドファーザー」「キャバレー」と肩を並べる作品賞候補作となって、後世に残るカルト作となったのである。




『脱出』は後味が長く残る作品で、気がつけば僕はブアマン・ファンになっていた。
80年代初頭のことだが、調べるとすでに劇場で『エクソシスト2』を観ていた。
この映画も大好きだったが、ここではあとに回す。
僕が何よりも先に観たかったのは1967年の『殺しの分け前/ポイントブランク』だ。リー・マービン主演、リチャード・スターク原作のハードボイルドだが、テレビでの放送を見て驚いた。これもまたブアマンのシュルレアリスム・タッチを縦横無尽に展開させた実験的かつ超難解なノワール・フィルムだったのだ。
物語そのものはシンプルである。主人公リー・マーヴィンは無二の親友に懇願されてアルカトラズ刑務所での現金取引を襲う計画を引き受けるが、友人のみならず彼と密通していた自らの妻にまで裏切られてしまう。リーは撃たれ、その場においていかれるが、蘇えり、裏切り者に復讐すべくサンフランシスコへと舞い戻ってくるというもの。しかしブアマンは、原作にないフラッシュバックとフラッシュフォワードを多用、全篇をコラージュして「記憶の地獄めぐり」のごとき異色作に仕立て上げた。


「ポイントブランク」のスタイルは、リチャード・レスターの「華やかな情事」やニコラス・ローグの『パフォーマンス」「赤い影」と共鳴している。マイク・ニコルズの『キャッチ22』やジョージ・ロイ・ヒルの『スローターハウス5」も同様のスタイルが見られるが、より本家に近いのは、ずっと後にスティーヴン・ソダーバーグがつくった「蒼い記憶」と「イギリスからきた男」である。
「ポイントブランク」は映画が始まるとすぐに銃声を聞かせる。そして、タイトルとともに狭い部屋の隅に倒れるリーの姿。彼の視覚から見える天井、痙攣する指、そして「ムショだ……刑務所だ……なんでここにいる・・・…」とうめく、リーの声。始まってものの何十秒かの間のことである。映像は過去に戻り、ここに到る顛末を走馬灯のように描き出す。そして再び冒頭と同じ銃声と倒れるリーの姿と「ムショだ……」のうめき声。だが、絶命したと思えたリーがムクリと起き上がり、映像はストップモーションに。ここからクレジットが始まるが、実はよく見ると「静止画」でないことがわかる。つまり、演じるリー・マーヴィン自身が実際に身体を止まってみせているのだ。金網をよじ登るリーの静止したすがたの背景に広がる空には鳥が悠々と飛び回っている。ブアマンはここで、この主人公が一種のゴーストであり、以後のドラマが「記憶の反復」からなることを示唆しているのだ。




リー・マーヴィンは60年代にジョン・フォードの『リバティ・バランスを撃った男』の悪役で主役のジョン・ウェインやジェームズ・スチュアートを食ってしまった。完全無欠の英雄よりもすねに傷を持つ悪に共鳴を覚える反体制的な気分の時代が始まったが、リーはここで同時代の出演作「殺人者たち」「特攻大作戦」「太平洋の地獄」と並ぶ名演を披露して、実に格好いい。ブアマンが撮ったリーが妻の自宅を襲撃する場面や、長い廊下を歩き続ける姿は最高である。こんな歩行は軍人だった彼にしか出来ないだろう。ここではリー自身の記憶が反復しているのだ。「ポイントブランク」は、アラン・レネとゴダールとヒューストンが一緒に作ったかのような作品であり、ブアマンによる一つの「発明」だと言える。
僕の最初のブアマン体験は「エクソシスト2」だと書いた。勿論、これはかのフリードキン監督の伝説的オカルト映画の続編企画で、フリードキンと原作者のウイリアム・ピーター・ブラッディが揃って認めないと怒りを露わにした問題作だ。重厚な感動で前作に遠く及ばないが、実はこれはこれでかなりの傑作というか異色作なのだ。主演は前作に引き続きリンダ・ブレアーとマックス・フォン・シドー。新たにルイーズ・フレッチャーとリチャード・バートン、ジェームズ・アール・ジョーンズなど演技派が顔を揃える。
映画史に残るの悪魔憑き少女リーガンももう思春期である。前作が74年公開、『2』は77年公開だから3年ほどの時間の間に驚くような成長をみせる(演技ではなく肉体的にだ)。「エクソシスト」の凄まじい怪奇現象は、実は少女リーガンノの抱えている成長期特有の不安定さにある。彼女を取り巻く大人たちの振る舞いが、少女の心を揺るがせ「悪魔」が隙き入る余地を与えていた。その意味で罪人たるは大人たちだが、彼らもまた苦しみに耐えている。彼らが悪魔に翻弄されながらいかに対処していくのかが主眼になっているのである。


ブアマンの「2」は現代社会における信仰の問題にリーガンの青春物語を絡み合わせた作品だ。
フリードキンがドキュメンタリー的な客観描写を重視したのに対し、ブアマンの選んだのは主観的かつ超心理的な映像スタイルで、これによって観る者を「内なる世界への旅」に招待しようというのだ。
例えば、イナゴの主観(同時に神父の視点)になったカメラが世界中を飛び回り、その途中、コクモというアフリカ人の口のなかから虎が飛びだしてくるなど、奇怪かつ夢幻的な映像が続出してくる。
ケン・ラッセルの「アルタード・ステーツ」に通じるような、これはそういう難解な作品なのである。
忘れがたいエンニオ・モリコーネのテーマ曲。ロック的なビートを大々的にフィーチャーしたプロモ・ビデオのような予告編があるが、これがまた奇抜であり、実にカッコイイ。公開当時「渋谷の本のデパート」と呼ばれた太盛堂の地下のレコード売り場でシングル・レコードを購入。これを毎朝学校に行く前に聴いていたことがあった。



「太平洋の地獄」も好きな作品だ。第二次大戦末期に無人島へ流れ着いた日米の軍人二人をリー・マーヴィンと三船敏郎が演じる。最高の組み合わせであり、しかも文字通り二人のみの主演。子供じみてしかし切実な喧嘩を繰り広げる異色大作だが、最後まで互いの言葉が通じ合わず、ゆえに醸し出してくるユーモアの妙がリアルかつ秀逸。だが、ラストシーンは衝撃的で、思わず言葉を失なう。
「未来惑星ザルドス」こそブアマンの最高作に挙げる人もいるかもしれない。彼の思想哲学が炸裂する難解なSF大作で、ルネ・マグリットのシュルレアリスム絵画からのインスパイアも見られる。主演にショーン・コネリーとシャーロット・ランプリングという豪華だがなんとも妙な配役がまた効いてる。
いつだかの未来の話である。コネリー扮する知性を持った「獣人」の妙な衣装や空中に浮かぶ偽の神「ザルドス」の巨大な石顔。科学的に不老不死の命を得た人々の暮らす桃源郷ヴォルテックスには、カラフルな色彩が乱舞し、何もかもが奇抜である。フェリーニとキューブリックとケン・ラッセルが作ったSFがあるとすればこんな感じであろうか。ここでもラストが印象的で、ベートーヴェンが流れるなか、子を作り、老い、そして死んでゆく男と女のモンタージュが美しい。


「エクスカリバー」はブアマンが少年時代からこだわる「アーサー王伝説」の念願の映画化。黒澤明の「影武者」を彷彿とさせるファーストシーンから魅力あふれるダークファンタジーの世界を披露する。個人的には役者たちが一つ魅力に欠けていたが、海外ではアーサー王伝説の教材に使用されるほどの評価を確立しているという。


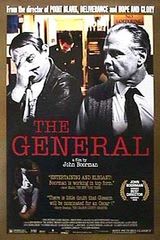
「エメラルドフォレスト」は「脱出」と「エクソシスト2」をかけ合わせたような作品だ。
文明と自然の齟齬と対立を幻想的なアクション描写で調理しているが、エコロジー問題は、ブアマンのライフワークなテーマなのだ。南米のジャングルを切り開きダムをつくる工事が進んでいる。これに携わる主人公の息子が、その森に暮らす部族にさらわれてしまう。数年後も彼を探し続けていた父親はついに再会を果たすが、しかしかつての少年はいまや部族の戦士となっていた……。宮崎駿の「もののけ姫」に大分先駆けた映画である。というよりは宮崎駿も好きな映画かもしれない。主演はパワーズ・ブース。そしてブアマンの息子チャーリーである。
「戦場の小さな天使たち」は普段とはかなり毛色の違う見事な自伝映画である。
ブアマンの少年時代は第二次大戦さなかのイギリス。ときに空爆のあるなか、夢見がちな少年だった彼は、川や水、アーサー王を偏愛している。日本タイトルがひどいが戦時下のイギリス家族のスケッチは美しく、追想が温かなユーモアに包まれた名品だった。
「ジェネラル」もユニークな作品だ。アイルランドのフォーク・ヒーローとなった伝説的な泥棒と彼の人気に嫉妬した警官の対立を描いた物語で、日本未公開の「LEO THE LAST」以来久しぶりにカンヌの監督賞を獲得した。かつての「ブアマン節」を期待すると正攻法の仕上がりに戸惑うかも知れないが、ブアマンはアイルランド映画に貢献してきたのであり、しかも自宅をこの泥棒に狙われている。加えて、同じ題材を描いた「私の愛したギャングスター」というケビン・スペイシー主演の凡作と比較すれば、さすがブアマン演出は素晴らしい。モノクロ・シネマスコープの撮影、反体制と体制のせめぎ合いが、ブレンダン・グリーソンとジョン・ヴォイトの演技によって浮き上がり、格段に優れているのである。
ブアマンも近年はすっかり「渋く」なったが、70年代に放った知的かつ実験的な作品群は今もその刺激を失っておらず、その多くは予見的なテーマを扱っている。ことに「ポイントブランク」と「脱出」は、映画ファンなら観ておくべきだろうが、個人的には「太平洋の地獄」も観て欲しい。
そして作家ジョン・ブアマンを発見して欲しい。大著『キューブリック』で有名なミシェル・シマンの『ブアマン』を是非、翻訳して欲しいものだ。同時にリー・マーヴィンという類稀なる男優の魅力も発見されるといいのだが。
2008年発表の日本未公開作「tigers tail」を観てみたいのだけど無理だろうか?




















