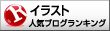ロバート・アルトマンの『バード★シット』とハル・アシュビーの『ハロルドとモード/少年は虹を渡る』が新宿武蔵野館でリバイバル上映される。こんな日がいつかやって来ると信じてどれほど待ち望んだだろうか。
1
『バード★シット』は異色作揃いの70年代アメリカ映画のなかでもひときわ異色なロバート・アルトマンの代表作である。知る人ぞ知るカルト・ムービーなのだ。主演はバット・コートとシェリー・デヴァル、アメリカを脱出して空を自由に飛び回ろうとする少年のブラック・コメディである。
映画は冒頭から珍妙。変な鳥類学者(ルネ・オーベルジョノア)が登場し、生徒(観客)に向かって講義を始める。
「鳥は空を飛び、人も空を飛ぶ。人は鳥に近く、鳥は人に近い。これがテーマだ。これから約一時間論じるつもりだが結論は出すまい。さもなくば興味は色あせ、残り少ない夢が、また一つ消えることになる。ドイツの詩人ゲーテの言葉を引こう。彼は空への憧れをこう表現した。“無限の空間に身を投げ出し奈落の上を漂いたい”。人間は最も進化した生き物だが、重力にとらわれて鳥のようには飛べない。空を飛びたいという欲求は昔から人間の中にあった。だが夢の実現は遠い。人間は本当に夢を理解しているのか。まず夢の正体をはっきりさせよう。空を飛ぶことが夢なのか。空を飛ぶことで自由を獲得することが夢なのか?」
ここでアルトマン映画の重要テーマたる「夢」について言及される。アルトマンの作品にはよく「夢」や「幻想」などが描かれる。それは大抵、人物が自らの中で飼いならしている妄執に過ぎないが、それを育ませる国家、政治もしくは文化の正体を見定め、笑殺しながら、他ならぬ彼自身の「夢や幻想」をも突き放して「異化」してしまう。『バード★シット』はオープニングでこれは「そういう」映画なのだと宣言しているわけだ。
教授は講義を次のように締めくくる。
「人間は深刻な環境破壊で鳥たちの生命を脅かし、鳥は糞尿によって人間を悩ませる。いずれ広大な保護施設を建設する必要があるだろう。人間と鳥の両方を守るためだ。それでも状況次第で、人間が鳥を受け入れるか排除するかは変わるだろう」
アルトマンはテキサス州ヒューストンにあるアストロドームの外観を映し出し、続いて、高台にのった星条旗色のドレスに身を包んだ中年女性が、黒人たちのバックバンドを前に「音程のずれた」国家を歌っている。ヒューストンは宇宙開発のメッカ、つまり人類の飛翔の夢の行き着いた場所である。主人公のブリュースター・マクロードはここのアストロドームの一室に隠れて「巨大な翼」をつくっているのだ。


2
僕が本作の存在を知ったのは小学5年生のころ。母に友人夫婦宅に連れられて旦那さんから教えられたのであった。映画と音楽が好きなデザイナーの旦那さんは遊びに行くといつも様々な映画のレーザーディスク(LD)やビデオ(ベータ)を見せてくれたが、この日はパンフレットのコレクションも見せてくれた。その中からひとつ取りだし指し示したのが『バード★シット』だったのだ。タイトルは古い映画雑誌で知っていたが詳しくは知らない。だが、一目見てそのビジュアルに惹かれた。パンフの表紙には丸めがねにラガーシャツの少年が羽をつけて飛んでいて、背景に女性の豊満なバストがあしらわれていた。僕の食い入るような様子に旦那さんは微笑み、こう話し出した。「“バード・シット”は“鳥の糞”という意味。鳥のように飛びたい少年が出てくる。それを邪魔する人が出てくるたびに全員殺されてしまう。するとその死体の上に鳥の糞が落っこちてくる。これがとにかく可笑しくてしょうがない」。ニコニコしながら台所にいる奥さんに向かって「なあ、そうだよな?」と声をかける。奥さんは「でも、アルトマンってちょっと怖いじゃない。頭がヘンみたい」。旦那さんは無視して僕に聞いた「これ欲しいかい?」。うなずくともったいをつけた表情で「う~ん、でもなあ、これは大切にしてるからなあ。そうだ、代わりにこれをあげるよ」と言って、なぜか、ロバート・アルドリッチの『ハッスル』をくれたのだった。


3
それからずっと『バード★シット』が気になって仕方なかった。これを見ないと「映画ファンといえないのじゃないか?」――そう思いつめていたが、名画座にかからず、ビデオ発売もなかった。そして数年経ったある日、当時付き合っていた彼女から「あのパンフレット」をプレゼントされたのである。「作品解説」には次のように説明する。
「これは、『マッシュ』のロバート・アルトマン監督が、もちまえの奇才ぶりを思う存分に発揮し、「最も独創的で、型破りで、しかも不思議な魅力を持ち、何よりも大いに楽しめる」と評されている作品である。ストーリーはむしろ簡単である。鳥のように自分の力で飛翔したい一心から、ヒューストンの屋内野球場の地下の一室に巣食って、翼を作り、腕の筋肉を鍛錬する一方、その目的の邪魔になる人物を次々に消してゆく話である。だが、この話の軸が回転するにつれ、人間や人間社会への諷刺、ユーモア、パロディ、皮肉、幻想的な狂気、無法、笑い、セックス、アクションなどが、まるで期間銃弾のようにバラバラバラバラはじき出される。ほんとに普通のコメディ1ダース分たっぷりの材料だ! 初めは、あまり考えすぎないように、しばらくの間は、映画に慣れるだけ、それからは自分の好きなように見るとよい。ある批評家がこう言っているが、今までに見たこともないような新しい、楽しい映画である。」




同様にプレゼントされた公開時のチラシには「海外での批評」が並ぶ。
最高に創意に富み、破壊的で無法、不思議な魅力を持つ、スリリングなコメディ。――ニューズデイ
想像力の勝利。1930年代の素晴らしい型破りのコメディ以来、最も自由で、荒々しく、こっけいな、現代社会の批判だ。――ニューズウィーク
見たい。しかしどうすることもできない。『ザ・プレイヤー』で復活する以前のことで「アルトマン」は忘れられたも同然の存在だった。彼は80年の『ポパイ』でハリウッドから干されていて以降フランスのパリに渡り、細々と映画を作り続けていた。日本でも数本の作品が公開されているが、話題にならなかった。そもそも日本ではむかしからマイナーな監督だったからビデオ化のニーズがなかったのである(「実は」好きだったと「通たち」が騒ぎ出すのはあとのことだ)。
4
1972年公開時の「映画批評」誌に評論家の由良君美氏が『バード★シット』論を寄稿している。
ここで由良は一風変わった形式――「仮想対談形式」を採用して、本作の原題『Brewster McCloud』の意味について「仮想の生徒」に説明する。
A 原題はBrewster McCloudというのね、主人公の男の子の名前。邦題がBird★sht。
B そうだった。BrewsterというのはBrew-starの謎語だろうから、<星を醸成する者>ということかな。McCloudの<マック>というのは諷刺の常套でね……。
A あ、それでドライデンの「マック・フレクノー」なんかのことを、ひきあいにだしたのね?
B ハハ、見抜かれたか。そうなんだ。<マック>はね、<子供><息子><二世><二番煎じ><一代目に及ばざる者>の接頭語なんだ。人名によくあるが、諷刺のときにはこの意味で使って、棚おろしをやるわけさ。だから、<マック・クラウド>は<雲に及ばざる者>ということになる。とうとう鳥になれなかった男の子だから。


5
僕が「ついに」見たのは90年代の中頃。アメリカでノートリミング版のLDが発売されたのだ。かつて渋谷に「ディスク&ギャラリー」という輸入レーザーディスク専門店があったのだが、そこで「発見」したときの興奮たるや忘れがたいものがある。
家に帰ると着替える間も惜しんでデッキに挿入。それは噂に違わぬ超異色の映画だった。この作品と同じ1971年には寺山修司監督の『書を捨てよ町へ出よう』がある。これにも「人力飛行機で飛ぼうとする男」が登場し、『バード★シット』との共通に思いを馳せたが、しかし、寺山演出が「前衛演劇的」なのに比べ、アルトマンのそれは「B級映画的」でカラフルなおもちゃ箱をひっくり返したかのようなポップアートだった。LDの「画質」には不満が残ったが、欲を出してはいけない。見れただけで大した進歩なのである(「MGM/UA」のソフトはいつも画質が荒かったのだ)。
ただ、これは劇場の大きなスクリーンで見たくなるような作品である。アメリカ国旗を想起させる原色の洪水、ロングショットを活かした構図と「外し」の美学、アルトマンのクレイジーな想像力が横溢する世界観を十分に堪能にすためには、家のテレビモニターではいかにも小さく、発色もいまひとつだったのである。
6
2007年。ロバート・アルトマンが逝った。この年「ぴあフィルムフェスティヴァル」がアルトマンの「レトロスペクティブ」を開催。このとき、僕は遂に「本物」と出会ったのである。開催地は渋谷の東邦生命ビル内にある渋谷東急。ここの大きなスクリーンに展開するシネマスコープ、映像空間を乱れ飛ぶ原色、ぶつ切りのサウンドトラックとブラックユーモアが「アメリカの夢」を異化していくさまのエネルギーは圧巻である。アルトマンは「現代アメリカ」における「自由の失墜」を笑いのめし、そして嘆いていた。僕は我を忘れて食い入るように見ていたが、やがて伝説的なクライマックス――サーカス・エンディング――を迎えていく。すべてを失い孤独のなかで少年は翼を背負うとついに飛びたつ。だが、そこは屋根つきのアメリカ、あの「アストロドーム」の中でしかないのだ。
冒頭の教授のあらぶる声が重なる。
「人間のどん欲な心は欠陥のある体に追い立てられて洗練された機械を生み出すだろう。だが決して自由に飛ぶことはできまい。鳥は何百年もの長い年月をかけて空を飛ぶために自らの体を進化させてきたのだ!クワァー!」
やがて落下していくときの「叫び声」が耳を離れない。これはいわゆる同時代のニューシネマが描いた自由に対する明らかな当てこすりだったが、その「冷たさ」が「心地いい」のだ。アルトマン演出は冷酷かつ滑稽だが、同時に、ひどく切なくて心優しいのである。


7
ブルースターに彼を「守護する者であるルイーズは問いかける。
ルイーズ 「考えたことない?」
ブルースター 「何を?」
ルイーズ 「女の子とかセックスよ」
ブルースター「ホープと話したの? 彼女にも同じことを聞かれた」
ルイーズ(サリー・ケラーマン)は彼を子供のように風呂に入れてやる。彼女は鳥の化身であり、ブルースターの純粋を汚す「メス」としてのホープ(シェリー・デュヴァル)を警戒している。
ブルーター「なぜホープの話を?」
ルイーズ 「あなたを巻き込んでる」
ブルースター 「何に」
ルイーズ 「セックス」
ブルースター 「ホープが言ったの?」
ルイーズ 「あの子は命令に従う。自由を知らない。可能性も考えない……セックスが一番近いの」
ブルースター 「飛ぶことに」
ルイーズ 「そう飛ぶことにね」
ブルースター 「飛べばいい」
ルイーズ 「最初は飛びたがるわ。でも変わるのよ。どんどん地上に近づき、セックスで満足する。そして仲間を増やすのよ。誘惑されないで。あなたは仕事に集中するの」
ブルースター 「君の助けが必要だ」
ルイーズ 「私はつねにそばにいる。あなたが飛び立つまでね」
彼女は微笑み、そして子守唄を歌いはじめる。
お眠り 赤ちゃん 木のてっぺんで
風が吹けばゆりかごが揺れる
枝が折れれば ゆりかごが落ちる
赤ちゃんは地面にまっさかさま
ゆりかごもろとも
……落ちる
(渡部幻)