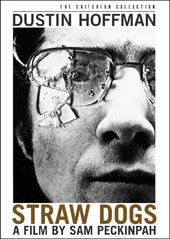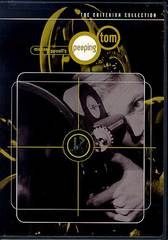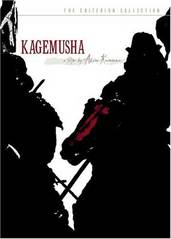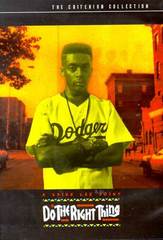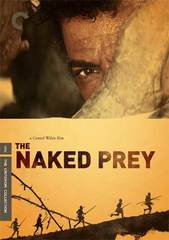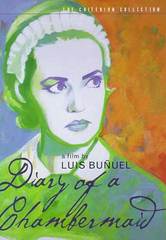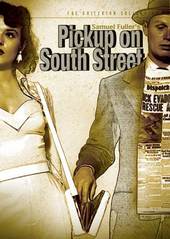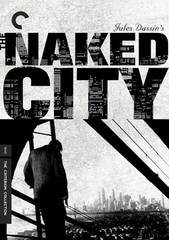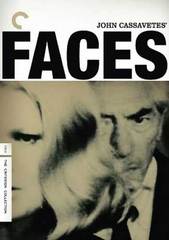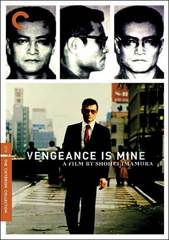北沢夏音さんに誘われて、60年代に金坂健二が撮ったアングラ・フィルムを特別に見せてもらった。内容に触れることはできないが、久々フィルムの色香を味わうことができた。なんというか「フィルムの流れ」を観ているだけで飽きることがないのである。
しかし「金坂健二」と言ってみたところで分からない人が多いに違いないのは、彼が忘れられた人物だからである。60年代に映画評論家・映画作家として前衛活動を展開。アメリカでカウンターカルチャーを至近距離で目撃し、それを迫力ある写真に収めつつ「キネマ旬報」などで現地からの実況報告を書き続け、70年代にはジャーナリスティックで尖がった映画評論家として人気を博した。





僕が金坂健二を知ったのは小学校の5年生頃だった。80年代初頭に恵比寿の駅前に「シネプラザ」という店があって通っていた。店内に「スペース50」という自主映画上映スペースを併設していて、大学の映研だろうか、よく賑わっていたが、僕の眼目は映画の前売り券や様々なグッズにあり、ここで始めて購入した映画雑誌が「キネマ旬報」と「スターログ」だったのである。
当時の「キネ旬」には「シナリオ採録」が掲載されていて、ビデオのない時代に映画のシーンやセリフを確認するのに重宝していた。主な映画のバックナンバーを揃えたくなり、同じ恵比寿の「パテ書房」というサブカルチャーに強い古本屋にも通いだして小遣いのほとんどはそれとゲームセンターにつぎ込んだ。
雑誌というものは熟読するうちに何となく気になる執筆者が現れてくるものである。81年ごろの話だから古本で買ったバックナンバーのほとんどは70年代のものだ。当時の「キネ旬」は実に豪華で、ざっと挙げると――
和田誠、山田宏一、佐藤重臣、小野耕世、筈見有弘、品田雄吉、石上三登志、今野雄二、田山力哉、荻昌弘、河野基比古、白井佳夫、淀川長治、双葉十三郎、佐藤忠男、南部圭之助、飯島正、川本三郎、渡辺祥子、宇田川幸洋、河原晶子、日野康一、赤瀬川源平、南俊子、小林信彦、永六輔、水野晴夫、斉藤正治、渡辺武信、紀田順一郎、小林信彦、片岡義男、永六輔、矢崎泰久らが、常連もしくは連載を持っていた。
いまからすればそうそうたる布陣で、ひとつに矢崎泰久と和田誠の『話の特集』的なサブカルチャーの横断性が参考にされていると思われるが、当時は当たり前のこととしてあった。
映画専門家の見識と、必ずしも映画専門でない書き手の見識が、映画の見方を豊かにしていたが、このなかでひと際硬派かつ長文で、読みづらいが、興味深々の文章で目を引いたのが「金坂健二」だったのである。これも「いまからすれば」不思議だが、僕のような遅れた子供の目にも刺激的で目立つ存在だった。映画とアメリカの歴史を独断と偏見で紐解き、アートフィルムやアンダーグラウンドのみならず、メジャー映画への造詣も深かいところが好きだった(多くはいずれかに偏るものだ)。
金坂が書いていたのは、「映画の表面」の「裏側」にある禍々しく得体のしれない世界の蠢きである。それはアングラの教祖的なケネス・アンガーの『ハリウッド・バビロン』などにも影響されたかも知れないが、彼自身は60~70年代の「燃えるアメリカ」を「異邦人の眼」から眺め、その中へ身を投じながら、同時に「日本人」としてのわが身を引き裂きもがいているようなところがあるのだ。
当時「アングラ映画」など見たこともなかったが、金坂のつんのめるような文章を通じて、映画という騙し絵の奥に隠れた「もう一つの世界」を垣間見る思いがした。子供心にその「危ない世界」にスリルを感じていたのだと思う。金坂はインタビューも得意で、ヤコペッティ、ミロス・フォアマン、ジャック・ニコルソン、ウイリアム・ピーター・ブラッディ、リー・ストラスバーグ、マーティン・スコセッシ、ロバート・デ・ニーロ、ローレンス・カスダン、ジョン・ウォーターズなどに取材していた。「プレイボーイ」誌でのフランシス・フォード・コッポラ・インタビューが読み応えで一番だが、『コンボイ』当時サム・ペキンパーの恋人で秘書だったケイティ・ペイパーなど多種多様だったが、アメリカ現地ではニューヨークを中心とするアンダーグラウンド・シーンに出入りしていたようだから、貴重な「言葉」を多く聞いていたのに違いない。
だが、金坂健二という人は60~70年代の申し子のようなところがあって、80年代に時代の空気が変わるとあまり目にしなくなった。たまに目にしても生気がなくなっていた。金坂が気に入り筆が走るような映画が少なくなっただけでなく、時代そのものが変質していくなかで、独特の難解な批評も読まれなくなっていったのである。




70年代に映画はただの娯楽をこえるものになろうとしていた。観客を挑発する表現となり、作者たちと批評家は創造的な火花を散らした。こうした現象は50年代には基本見られなかったことで、映画表現は芸術であり発言の場としての可能性を斬り開いていったのである。「新しい観客」もまた「新しい映画」の挑発と勢いに乗り、だからこそ、ヌーヴェル・ヴァーグやアメリカン・ニューシネマの先鋭的で難解な映像を受け入れ、「イージー・ライダー」「真夜中のカーボーイ」「M★A★S★H」「チャイナタウン」「タクシードライバー」「ディアハンター」「地獄の黙示録」などの一筋縄ではいかぬ異色作群がヒットして「時代の顔」に成り得たのだ。




70年代のそれは、これに先駆ける50~60年代の実験映画、アンダーグラウンド映画、インディペンデント映画、もしくはB級C級のジャンル映画の持つ荒々しさや禍々しさをメジャー展開させたもので、初めは良かったが、やがて「大商業化」する運命から逃れなかった。しかし彼ら当時の新しい作者たちが切り拓き、評論家たちが紹介した、意識の在り方や世界観を新たにさせる映像は、当時の子供たちの目にも触れて大いに触発したのだった。ポルノ映画やそのポスター、暴力と精液にまみれたエロ劇画誌などもそうだが、80年代くらいまではそのへんにいくらでも転がっているものであった。映画なら大きなスクリーンで展開するそうした暴力的でエロティックな世界は、やがて大人になるだろう子供たちの無意識を覚醒させる劇薬の役割を果たした。難解で実験的かつ政治的な映画が雪崩をうって子供のもとにまで押し寄せてくるさまは、いま思い出すと圧巻の光景だろう。
金坂健二もまた映画評論家としてアメリカ体験の実感とともにそうした世界を世に広めようとしていたのである。
アメリカ映画におけるこうした動きを止めるきっかけとなったのは、80年にマイケル・チミノが発表した超大作「天国の門」の公開である。「作家の映画」は無惨にも興行的失敗を喫して、監督主体の映画の老舗ユナイテッド・アーティスツ社を倒産に追い込むこととなった。この「怪物」は作者たるチミノのみならず、ロバート・アルトマンなど多くの「ハリウッドの映画作家」たちを業界から弾き飛ばしてしまった。そしてはじまる80年代のハリウッドは保守化の波にさらされていくが、新しい才能たち――80年デビューのジム・ジャームッシュなど――は初めから「ハリウッド・メジャー」をしりぞけ「インディペンデント」の立場から自らを発信する「映画作家」としての頭角を現すこととなる。




(『天国の門』が公開された80年(日本では81年)あたりにはまだ「作家の映画」が存在していたが、彼らのつくるいわゆる「野心作」や「問題作」に観客たちの多くはついていけなくなっていた。ウィリアム・フリードキンの「クルージング」、アルトマンの「ポパイ」、スピルバーグの「1941」、コッポラの「ワン・フロム・ザ・ハート」などの興行的な失敗はそのことを実感させたが、個人的には非常に面白く、特に81年は当時思われていたより重要な作品が多いのだ)
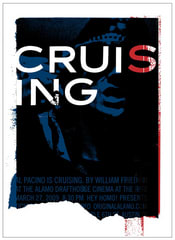
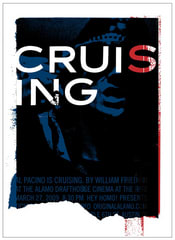
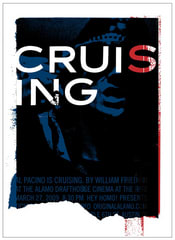
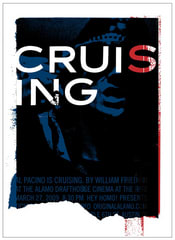
80年代の保守的なハリウッドでは、一度は手にしたクリエイティブの実権が「映画作家」から「製作者」に引き戻される。つまり、実権を監督たちが握るためには製作者としても名を連る必要があった(この先駆けがユナイテッド・アーティスツのビリー・ワイルダーやノーマン・ジュイソン作品に見られる)。しかし製作者でもあれば余計に興行的な責任が生じ、作品をヒットさせる必要性がより重くなるのは必然である。クリエイティヴとプロデュースの両立は簡単なことではない。時代の流行を先取りし、もしくは仕掛ける才能を持っていたのはスティーヴン・スピルバーグだった。彼の一連の大ヒット作のなかで「E.T.」は時代全体の方向性をかえるだけの力を発揮していた。彼は以後ファンタジー映画の大御所として「グレムリン」「グーニーズ」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」などを「プロデュース」したが、実は同時期に自身でつくったファンタジー映画はほとんどない。スピルバーグには「映画作家」としての野心があり、その野心と情熱をむしろ「カラーパープル」や「太陽の帝国」などの歴史映画に向けていたが、それらを実現させるために「流行作をプロデュ-ス」して、それで儲けることをいとわなかったし、実際にそういう映画も嫌いではなかったのだ。彼のこうした資質は、実際問題、誰もが持てるものではないから、フリードキンやボブ・ラフェルソンのように半端な「転向」を余儀なくされるか、アルトマンやペキンパー、ハル・アシュビーら反逆児たちは干される運命にあったのである。




金坂健二という評論家が歩んだのは、もちろん後者の道であった。アメリカのアンダーグラウンドやカウンターカルチャーの精神を日本にも広めようとしたこの無頼漢もまた、居場所を見失って苦悩したに違いない。人には筋というものがあり、仮に、転向や転進の必要性を感じているからといって、そう器用に変わり身を遂げられるわけでもない。金坂はそれがうまくできなかったが、先に書いたインディペンデントの動向は多少なりとも接点を見つけられるものであった。ただ新世代作家たちの「個性」を掴むにはすでに「旧世代」に属していた。「新世代」は革命になど見向きもしない「革新児」たちだったのである。
ただ80年代の日本にはビデオレンタルとミニシアター時代が到来していて、インディペンデント映画や、60~70年代の日本では未公開に終わったカルト映画群が相次いで公開されるようになった。アレハンドロ・ホドロフスキーの「エル・トポ」やジョン・ウォーターズの「ピンク・フラミンゴ」、ロバート・アルトマンの「三人の女」、テレンス・マリックの「天国の日々」、ホッパーの「ラストムービー」などは、本国公開時にまっさきに金坂が「キネ旬」誌上で紹介していたものだったから、そうした作品の原稿を頼まれたときには「力量」を発揮していた。
しかし70年代の当時、その「過激さ」によって注目を集めたゲリラ的なカルト・ムービー群も、日本の大企業の手にかかればファッション化してしまう。金坂健二の居場所はいよいよなくなっていったのである。


しかしこうした歴史自体がもはや遠いもので、いまあらためて「金坂健二」を読むとやはりたいそう刺激的で滅法おもしろいのだった。僕の個人的な少年時代の映画風景には、一方に淀川長治的なるものと金坂健二的なるものの両極があったと思える(もっとも中間に、上に列挙した評論家たちがいたわけだが)。
金坂健二の興味は当時のアメリカ社会とその文化的坩堝を捉える表現としての映画に向かっており、翻って日本人と日本の映画表現はどうだろうと、しつこいくらい問いかけ、ときに挑発しようとしているところがあった。単行本で読むとかなり難解だが、「キネ旬」では難解になるぎりぎりで抑えながら読み物としておもしろく読ませるものが多い。
個人的には「アングラ」が漂わせるムードが苦手だが、不思議なことに金坂健二は嫌いではない。文章が意外に「ポップ」だからである。アンディ・ウォーホルは当然、アメリカン・ニューシネマ、僕の好きなロバート・アルトマンにしてもポップなのである。「ポップ」のイメージは移り気で軽薄だが、過去を抱え、すねに傷を隠している。映画はそもそもの性質が「過去を内に抱え込む」ことで成り立つ表現であり、ゆえに「ポップ」なのだ。金坂健二はそういう映画の熱気のなかに死臭を嗅ぎ取り、それを反転させてエネルギーに変えようとする力みがあった。「映画評論家」のみならず「写真家」であり「実験映画作家」としての顔も持っていたことを後で知ったが、「クリエイター」としてどれほど評価されていたのかは分からない。ただひとつ言えるのは、写真も映画も文章と同様、受け手を巻き込まんとする「つんのめった迫力」があるということだ。時代に殉じたゆえの美点と欠点があるからこそ後続世代にとっての発見も多いと思うが、どうだろう。もう少し注目されてもいい書き手だと思うし、彼の撮ったアメリカ写真はかなり荒っぽいが、だからこそ、時代精神を写し取っていまに伝える臨場感がある。ある種の「捨て身の姿勢」には「退屈な00年代」を照射する魅力があると思うし、あれほど活躍していた人が、ここまで記憶の彼方に葬りさられてきた事実がちょっと不思議なくらいだ。






近ごろの日本映画は退屈な流行が目立つが、すっかり客が入らなくなったアメリカ映画は娯楽的・芸術的な洗練を極めつつあるものが出てきている。アン・リーの「ブロークバック・マウンテン」、コーエン兄弟の「ノーカントリー」、リドリー・スコットの「アメリカン・ギャングスター」、クリント・イーストウッドの「チェンジリング」、トッド・ヘインズの「アイム・ノット・ゼア」、ポール・トーマス・アンダーソンの「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」、ガス・ヴァン・サントの「ミルク」、ブライアン・デ・パルマの「リダクテッド」、クリストファー・ノーランの「ダークナイト」、サム・メンデスの「レボリューショナリー・ロード」、ザック・スナイダーの「ウォッチメン」、スティーヴン・ソダーバーグの「チェ二部作」、ロン・ハワードの「フロスト×ニクソン」など、ざっと挙げてみても力作揃いだと思える。極めてアメリカ映画的な正当性――性と暴力の氾濫、社会と政治への批評性、娯楽と芸術の折衷――が「現代的」な状況や人間の諸相を掴みとることに成功しているのである。
いま「町山智浩」が大ブレイク中だが、淀川長治の人懐っこさと金坂健二の過激さをミックスしてかき混ぜたようなジャーナリスティックな視点を持つ「映画の語り部」として実におもしろい。その異様な熱気が特有のユーモアを伴い加速していく様は圧巻で、アメリカ在住の強みを活かした現地リポートなどインターネットにも精通していて、非常に現代的でかついま最も求められている「映画解説」の有り様を体現している人なのだ。

ところで「金坂健二写真展」なる企画が開催されると聞いて驚いている。雑誌「スペクテーター」でも特集が組まれると言うし、ビックリである。「スペクテーター」は個人的な金坂健二の印象から意外なようでいて実は合っているのかもしれない。かつて「鶴本正三」特集も組んでいたし、何より金坂は60年代のヒッピー・カルチャーやカウンターカルチャーを目撃してきた人物なのだから。






しかし「金坂健二」と言ってみたところで分からない人が多いに違いないのは、彼が忘れられた人物だからである。60年代に映画評論家・映画作家として前衛活動を展開。アメリカでカウンターカルチャーを至近距離で目撃し、それを迫力ある写真に収めつつ「キネマ旬報」などで現地からの実況報告を書き続け、70年代にはジャーナリスティックで尖がった映画評論家として人気を博した。





僕が金坂健二を知ったのは小学校の5年生頃だった。80年代初頭に恵比寿の駅前に「シネプラザ」という店があって通っていた。店内に「スペース50」という自主映画上映スペースを併設していて、大学の映研だろうか、よく賑わっていたが、僕の眼目は映画の前売り券や様々なグッズにあり、ここで始めて購入した映画雑誌が「キネマ旬報」と「スターログ」だったのである。
当時の「キネ旬」には「シナリオ採録」が掲載されていて、ビデオのない時代に映画のシーンやセリフを確認するのに重宝していた。主な映画のバックナンバーを揃えたくなり、同じ恵比寿の「パテ書房」というサブカルチャーに強い古本屋にも通いだして小遣いのほとんどはそれとゲームセンターにつぎ込んだ。
雑誌というものは熟読するうちに何となく気になる執筆者が現れてくるものである。81年ごろの話だから古本で買ったバックナンバーのほとんどは70年代のものだ。当時の「キネ旬」は実に豪華で、ざっと挙げると――
和田誠、山田宏一、佐藤重臣、小野耕世、筈見有弘、品田雄吉、石上三登志、今野雄二、田山力哉、荻昌弘、河野基比古、白井佳夫、淀川長治、双葉十三郎、佐藤忠男、南部圭之助、飯島正、川本三郎、渡辺祥子、宇田川幸洋、河原晶子、日野康一、赤瀬川源平、南俊子、小林信彦、永六輔、水野晴夫、斉藤正治、渡辺武信、紀田順一郎、小林信彦、片岡義男、永六輔、矢崎泰久らが、常連もしくは連載を持っていた。
いまからすればそうそうたる布陣で、ひとつに矢崎泰久と和田誠の『話の特集』的なサブカルチャーの横断性が参考にされていると思われるが、当時は当たり前のこととしてあった。
映画専門家の見識と、必ずしも映画専門でない書き手の見識が、映画の見方を豊かにしていたが、このなかでひと際硬派かつ長文で、読みづらいが、興味深々の文章で目を引いたのが「金坂健二」だったのである。これも「いまからすれば」不思議だが、僕のような遅れた子供の目にも刺激的で目立つ存在だった。映画とアメリカの歴史を独断と偏見で紐解き、アートフィルムやアンダーグラウンドのみならず、メジャー映画への造詣も深かいところが好きだった(多くはいずれかに偏るものだ)。
金坂が書いていたのは、「映画の表面」の「裏側」にある禍々しく得体のしれない世界の蠢きである。それはアングラの教祖的なケネス・アンガーの『ハリウッド・バビロン』などにも影響されたかも知れないが、彼自身は60~70年代の「燃えるアメリカ」を「異邦人の眼」から眺め、その中へ身を投じながら、同時に「日本人」としてのわが身を引き裂きもがいているようなところがあるのだ。
当時「アングラ映画」など見たこともなかったが、金坂のつんのめるような文章を通じて、映画という騙し絵の奥に隠れた「もう一つの世界」を垣間見る思いがした。子供心にその「危ない世界」にスリルを感じていたのだと思う。金坂はインタビューも得意で、ヤコペッティ、ミロス・フォアマン、ジャック・ニコルソン、ウイリアム・ピーター・ブラッディ、リー・ストラスバーグ、マーティン・スコセッシ、ロバート・デ・ニーロ、ローレンス・カスダン、ジョン・ウォーターズなどに取材していた。「プレイボーイ」誌でのフランシス・フォード・コッポラ・インタビューが読み応えで一番だが、『コンボイ』当時サム・ペキンパーの恋人で秘書だったケイティ・ペイパーなど多種多様だったが、アメリカ現地ではニューヨークを中心とするアンダーグラウンド・シーンに出入りしていたようだから、貴重な「言葉」を多く聞いていたのに違いない。
だが、金坂健二という人は60~70年代の申し子のようなところがあって、80年代に時代の空気が変わるとあまり目にしなくなった。たまに目にしても生気がなくなっていた。金坂が気に入り筆が走るような映画が少なくなっただけでなく、時代そのものが変質していくなかで、独特の難解な批評も読まれなくなっていったのである。




70年代に映画はただの娯楽をこえるものになろうとしていた。観客を挑発する表現となり、作者たちと批評家は創造的な火花を散らした。こうした現象は50年代には基本見られなかったことで、映画表現は芸術であり発言の場としての可能性を斬り開いていったのである。「新しい観客」もまた「新しい映画」の挑発と勢いに乗り、だからこそ、ヌーヴェル・ヴァーグやアメリカン・ニューシネマの先鋭的で難解な映像を受け入れ、「イージー・ライダー」「真夜中のカーボーイ」「M★A★S★H」「チャイナタウン」「タクシードライバー」「ディアハンター」「地獄の黙示録」などの一筋縄ではいかぬ異色作群がヒットして「時代の顔」に成り得たのだ。




70年代のそれは、これに先駆ける50~60年代の実験映画、アンダーグラウンド映画、インディペンデント映画、もしくはB級C級のジャンル映画の持つ荒々しさや禍々しさをメジャー展開させたもので、初めは良かったが、やがて「大商業化」する運命から逃れなかった。しかし彼ら当時の新しい作者たちが切り拓き、評論家たちが紹介した、意識の在り方や世界観を新たにさせる映像は、当時の子供たちの目にも触れて大いに触発したのだった。ポルノ映画やそのポスター、暴力と精液にまみれたエロ劇画誌などもそうだが、80年代くらいまではそのへんにいくらでも転がっているものであった。映画なら大きなスクリーンで展開するそうした暴力的でエロティックな世界は、やがて大人になるだろう子供たちの無意識を覚醒させる劇薬の役割を果たした。難解で実験的かつ政治的な映画が雪崩をうって子供のもとにまで押し寄せてくるさまは、いま思い出すと圧巻の光景だろう。
金坂健二もまた映画評論家としてアメリカ体験の実感とともにそうした世界を世に広めようとしていたのである。
アメリカ映画におけるこうした動きを止めるきっかけとなったのは、80年にマイケル・チミノが発表した超大作「天国の門」の公開である。「作家の映画」は無惨にも興行的失敗を喫して、監督主体の映画の老舗ユナイテッド・アーティスツ社を倒産に追い込むこととなった。この「怪物」は作者たるチミノのみならず、ロバート・アルトマンなど多くの「ハリウッドの映画作家」たちを業界から弾き飛ばしてしまった。そしてはじまる80年代のハリウッドは保守化の波にさらされていくが、新しい才能たち――80年デビューのジム・ジャームッシュなど――は初めから「ハリウッド・メジャー」をしりぞけ「インディペンデント」の立場から自らを発信する「映画作家」としての頭角を現すこととなる。




(『天国の門』が公開された80年(日本では81年)あたりにはまだ「作家の映画」が存在していたが、彼らのつくるいわゆる「野心作」や「問題作」に観客たちの多くはついていけなくなっていた。ウィリアム・フリードキンの「クルージング」、アルトマンの「ポパイ」、スピルバーグの「1941」、コッポラの「ワン・フロム・ザ・ハート」などの興行的な失敗はそのことを実感させたが、個人的には非常に面白く、特に81年は当時思われていたより重要な作品が多いのだ)
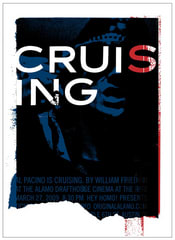
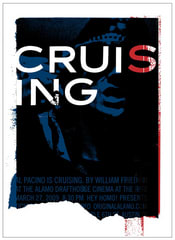
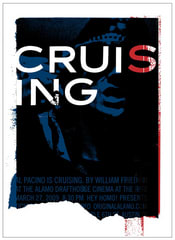
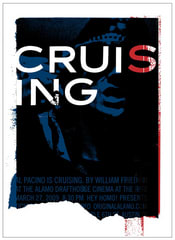
80年代の保守的なハリウッドでは、一度は手にしたクリエイティブの実権が「映画作家」から「製作者」に引き戻される。つまり、実権を監督たちが握るためには製作者としても名を連る必要があった(この先駆けがユナイテッド・アーティスツのビリー・ワイルダーやノーマン・ジュイソン作品に見られる)。しかし製作者でもあれば余計に興行的な責任が生じ、作品をヒットさせる必要性がより重くなるのは必然である。クリエイティヴとプロデュースの両立は簡単なことではない。時代の流行を先取りし、もしくは仕掛ける才能を持っていたのはスティーヴン・スピルバーグだった。彼の一連の大ヒット作のなかで「E.T.」は時代全体の方向性をかえるだけの力を発揮していた。彼は以後ファンタジー映画の大御所として「グレムリン」「グーニーズ」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」などを「プロデュース」したが、実は同時期に自身でつくったファンタジー映画はほとんどない。スピルバーグには「映画作家」としての野心があり、その野心と情熱をむしろ「カラーパープル」や「太陽の帝国」などの歴史映画に向けていたが、それらを実現させるために「流行作をプロデュ-ス」して、それで儲けることをいとわなかったし、実際にそういう映画も嫌いではなかったのだ。彼のこうした資質は、実際問題、誰もが持てるものではないから、フリードキンやボブ・ラフェルソンのように半端な「転向」を余儀なくされるか、アルトマンやペキンパー、ハル・アシュビーら反逆児たちは干される運命にあったのである。




金坂健二という評論家が歩んだのは、もちろん後者の道であった。アメリカのアンダーグラウンドやカウンターカルチャーの精神を日本にも広めようとしたこの無頼漢もまた、居場所を見失って苦悩したに違いない。人には筋というものがあり、仮に、転向や転進の必要性を感じているからといって、そう器用に変わり身を遂げられるわけでもない。金坂はそれがうまくできなかったが、先に書いたインディペンデントの動向は多少なりとも接点を見つけられるものであった。ただ新世代作家たちの「個性」を掴むにはすでに「旧世代」に属していた。「新世代」は革命になど見向きもしない「革新児」たちだったのである。
ただ80年代の日本にはビデオレンタルとミニシアター時代が到来していて、インディペンデント映画や、60~70年代の日本では未公開に終わったカルト映画群が相次いで公開されるようになった。アレハンドロ・ホドロフスキーの「エル・トポ」やジョン・ウォーターズの「ピンク・フラミンゴ」、ロバート・アルトマンの「三人の女」、テレンス・マリックの「天国の日々」、ホッパーの「ラストムービー」などは、本国公開時にまっさきに金坂が「キネ旬」誌上で紹介していたものだったから、そうした作品の原稿を頼まれたときには「力量」を発揮していた。
しかし70年代の当時、その「過激さ」によって注目を集めたゲリラ的なカルト・ムービー群も、日本の大企業の手にかかればファッション化してしまう。金坂健二の居場所はいよいよなくなっていったのである。


しかしこうした歴史自体がもはや遠いもので、いまあらためて「金坂健二」を読むとやはりたいそう刺激的で滅法おもしろいのだった。僕の個人的な少年時代の映画風景には、一方に淀川長治的なるものと金坂健二的なるものの両極があったと思える(もっとも中間に、上に列挙した評論家たちがいたわけだが)。
金坂健二の興味は当時のアメリカ社会とその文化的坩堝を捉える表現としての映画に向かっており、翻って日本人と日本の映画表現はどうだろうと、しつこいくらい問いかけ、ときに挑発しようとしているところがあった。単行本で読むとかなり難解だが、「キネ旬」では難解になるぎりぎりで抑えながら読み物としておもしろく読ませるものが多い。
個人的には「アングラ」が漂わせるムードが苦手だが、不思議なことに金坂健二は嫌いではない。文章が意外に「ポップ」だからである。アンディ・ウォーホルは当然、アメリカン・ニューシネマ、僕の好きなロバート・アルトマンにしてもポップなのである。「ポップ」のイメージは移り気で軽薄だが、過去を抱え、すねに傷を隠している。映画はそもそもの性質が「過去を内に抱え込む」ことで成り立つ表現であり、ゆえに「ポップ」なのだ。金坂健二はそういう映画の熱気のなかに死臭を嗅ぎ取り、それを反転させてエネルギーに変えようとする力みがあった。「映画評論家」のみならず「写真家」であり「実験映画作家」としての顔も持っていたことを後で知ったが、「クリエイター」としてどれほど評価されていたのかは分からない。ただひとつ言えるのは、写真も映画も文章と同様、受け手を巻き込まんとする「つんのめった迫力」があるということだ。時代に殉じたゆえの美点と欠点があるからこそ後続世代にとっての発見も多いと思うが、どうだろう。もう少し注目されてもいい書き手だと思うし、彼の撮ったアメリカ写真はかなり荒っぽいが、だからこそ、時代精神を写し取っていまに伝える臨場感がある。ある種の「捨て身の姿勢」には「退屈な00年代」を照射する魅力があると思うし、あれほど活躍していた人が、ここまで記憶の彼方に葬りさられてきた事実がちょっと不思議なくらいだ。






近ごろの日本映画は退屈な流行が目立つが、すっかり客が入らなくなったアメリカ映画は娯楽的・芸術的な洗練を極めつつあるものが出てきている。アン・リーの「ブロークバック・マウンテン」、コーエン兄弟の「ノーカントリー」、リドリー・スコットの「アメリカン・ギャングスター」、クリント・イーストウッドの「チェンジリング」、トッド・ヘインズの「アイム・ノット・ゼア」、ポール・トーマス・アンダーソンの「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」、ガス・ヴァン・サントの「ミルク」、ブライアン・デ・パルマの「リダクテッド」、クリストファー・ノーランの「ダークナイト」、サム・メンデスの「レボリューショナリー・ロード」、ザック・スナイダーの「ウォッチメン」、スティーヴン・ソダーバーグの「チェ二部作」、ロン・ハワードの「フロスト×ニクソン」など、ざっと挙げてみても力作揃いだと思える。極めてアメリカ映画的な正当性――性と暴力の氾濫、社会と政治への批評性、娯楽と芸術の折衷――が「現代的」な状況や人間の諸相を掴みとることに成功しているのである。
いま「町山智浩」が大ブレイク中だが、淀川長治の人懐っこさと金坂健二の過激さをミックスしてかき混ぜたようなジャーナリスティックな視点を持つ「映画の語り部」として実におもしろい。その異様な熱気が特有のユーモアを伴い加速していく様は圧巻で、アメリカ在住の強みを活かした現地リポートなどインターネットにも精通していて、非常に現代的でかついま最も求められている「映画解説」の有り様を体現している人なのだ。

ところで「金坂健二写真展」なる企画が開催されると聞いて驚いている。雑誌「スペクテーター」でも特集が組まれると言うし、ビックリである。「スペクテーター」は個人的な金坂健二の印象から意外なようでいて実は合っているのかもしれない。かつて「鶴本正三」特集も組んでいたし、何より金坂は60年代のヒッピー・カルチャーやカウンターカルチャーを目撃してきた人物なのだから。