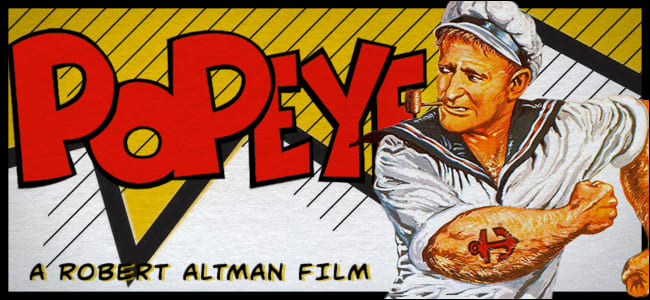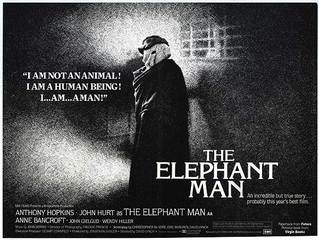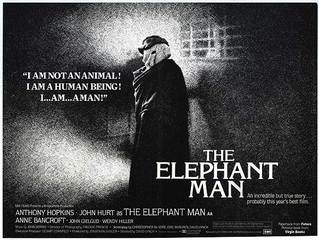『80年代アメリカ映画100』(芸術新聞社)の「はじめに」より。
『80年代アメリカ映画100』は、タイトルのとおり「80年代のアメリカ映画には、どんな映画があったろう」という本である。
この前の時代、つまり「70年代」のアメリカ映画は革新の季節として記憶されている。前半を象徴したアメリカン・ニューシネマは、勝利よりも敗北、夢よりも悪夢、体制よりも大衆に、積極的な肩入れをすることによって、いわゆる「ハリウッド」を迎え撃ち、カウンターカルチャーとしての「映画」を燃え上がらせたが、それは自らをも焼き尽くすほどの業火だった。
一九七九年、当時を代表する若き映画作家フランシス・フォード・コッポラが総決算的な超大作『地獄の黙示録』を発表。この作品に登場するキルゴア大佐は、ベトナムのジャングルにナパーム弾を撃ち込み、敵の殲滅に成功すると、次のような言葉を吐く。
「ナパームのガソリンの焼ける匂いは、勝利を実感させる」
この言葉には恍惚があった。それは、本作の制作にすべてを投げ打つコッポラの恍惚であり、狂気でもあったろう。
やがてカウンターカルチャーは、その濃艶のなかに昇天して、終焉を告げる。
では、80年代はどうだったろう。フラワー・ムーブメントはもちろん、パンク・ムーブメントすらもすでに終わって、残されたのは、ささやかな「レベル(反抗)カルチャー」だけ、とも囁かれた。


人は「80年代のアメリカ映画」と言われたときに、どんな作品を思いだすだろうか。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『E.T.』『トップガン』『ターミネーター』『ビバリーヒルズ・コップ』あたりだろうか? これらは80年代の大ヒット作。テレビでも繰り返し放送された。
しかしそれだけではない。
メインカルチャーとサブカルチャーが分裂と融合を繰り返しながら多彩なシーンをつくりだしていたのが80年代である。いまあらためて振り返ると、小粒ながら個性的な作品が、数多くあったことに気づく。ひとつひとつは小さく、短命であったが、結果、バラエティに富んだシーンを形成していた。
そのため、何をいつどこで、何歳のときに観たかのかによって、80年代の印象はガラリと変わる。万華鏡のごとくカラフルで、赤や青はより原色に近く、白はより白く、黒はより黒かった。
ロナルド・レーガン大統領とレーガノミクスの時代。
その背景としての冷戦。そして核戦争、さらにエイズの恐怖。もしくは、パーソナル型パソコンの登場、CD、ビデオデッキとビデオレンタルの普及によるライフスタイルの変化。人の意識は、社会的であるより、より個人的に、より快楽的な方向に傾いてったかもしれない。
“Good bye 70s...Hello 80s”
70年代から80年代初頭にかけてのポルノ映画産業を題材とする93年のアメリカ映画『ブギーナイツ』(ポール・トーマス・アンダーソン監督)に登場する言葉。
この作品では70年代の終わりに仲間うちの一人が自殺。80年代が不穏さとともに始まる。隆盛を誇った産業はビデオカメラの登場によって内部から崩壊。志が失われ、そのことに傷つきながら、軽薄に染まってゆく。


80年代初頭、映画界は曲がり角にあった。
アルフレッド・ヒッチコック、スティーヴ・マックィーン、ウィリアム・ホールデン、イングリット・バーグマン、ヘンリー・フォンダ、グレース・ケリーら往年の大スターが次々にこの世を去り、テレビは追悼番組であふれた。スターとは手の届かぬもの、同じ地平に生きていると思えぬ、遥か遠い彼方の存在を差していう。彼らこそ真のスターであり、フィルムだけが捉えることのできる影だった。
光り輝く「黄金のハリウッド」が、いままさに去ろうとしていたのである。
ほぼ同じ頃かつてなら想像もできなかった世界観を持つ映画作家たちが現れてくる。
リドリー・スコット、ジェームズ・キャメロン、デヴィッド・リンチ、デヴィッド・クローネンバーグ――彼らのヴィジョンが「80年代アメリカ映画」の最も革新的な側面を担い、ジム・ジャームッシュ、スパイク・リー、ジョン・セイルズらニューヨーク・インディーズが、ハリウッドとは一線を画する極私的な主題と映像を武器に登場して注目を集めていく。
70年代までに隆盛を極めたロックの世界も曲がり角に立ち、音楽がただ音楽であれば良った時代が、終焉の時を向かえようとしていた。社会の不良分子であり、ゆえにカウンターカルチャーの先頭に立ち、若者の意識を先導したミュージシャンたちも、産業化し、肥大化した業界のなかで溺れていく。
80年、元ザ・ビートルズのジョン・レノンがニューヨークの街角でマーク・チャップマンに殺されたまさに同じ年にMTVが開局、「映像付きの音楽」がお茶の間に流れ込む。
「映像に音楽が付いている」のではなく「音楽に映像が付いている」。この転倒のなかから新たな感受性と価値観をもつ新世代の映像アーティストたちが現れてくる。彼らを起用することでマイケル・ジャクソンやマドンナが一時代を築き、テレビとロックの融合は「バンド・エイド」として結実。ロンドンのウェンブリー・スタジアムとフィラデルフィアのJFKスタジアムで開催された「アフリカ難民救済」の一大チャリティ・コンサートは、計12時間に及び、世界84カ国で同時衛星中継された。


しかし、80年代で最も画期的だったのは、ビデオデッキとソフトレンタルの急速な普及かもしれない。ビデオは、一家に一台、一人に一台の友となって、人と機械の境界を溶かし、より身近にしたのだ。
昔々、映画は劇場で観るほかに選択肢を持たなかった。たったいま、闇の銀幕を飾る映画も、来週になれば、また違う作品に入れ替わり、終幕の明かりが点れば消えてしまう。
映画は、打ち上げ花火であり、つねに滅びゆく運命にあると思えた。基本そういう認識があるからこそ、人々は劇場に出かけた。
映画は、後戻りすることのできない一回性の体験だった。変化し続ける川の流れ、車窓から眺める風景のようなもの。その儚さが切実だった。ドラマティックであり、ロマンティックで、ときにエロティックですらあった。
ビデオの出現はそれを変える。
二度と再会できないと信じてきた、あの作品をもう一度観ることができる。自宅で、しかも自ら選んで、早送りや巻き戻しまでも可能だ。
夢のマシン――大袈裟に言えばビデオは歴史や時間、記憶に対する人の意識をも変えたのだ。
レンタルビデオ店の宇宙空間にはあらゆる時代が並存している。
ビデオテープはさながら手の平サイズのタイムマシーンになり、80年代から50年代へ遡り、次は20年代に飛ぶことも可能だ。時の流れなど無視して、興味の趣くがままにランダムに飛んでゆけばいい。たったいま感動した作品が「あなたの最新作=現在」になるのだ。
それはビデオによる意識変革だった。人々の意識に潜む官能を刺激し、拡大しながら、同時に、人をより個人的な存在に変えた。
やがて「映画」はかつての栄光を失っていく。ましてカウンターカルチャーでなく、せめてサブカルチャーですらなくなってゆく。
フィルムは反映する。映画は、人の世の似姿なのだ。


人と同じように映画にも色気が、官能が必要なはずだろう。華やかな官能、疲労感の官能、淫靡な官能……映画鑑賞はひとつの色事だ。色事には生があり死がある。肉感的かつ触覚的で生々しく、人を幻に惑わせる官能の火照りに、その身上がある。
あの80年代にもそれはあったか? そして現在にもまだあるだろうか?
PB あなたにとって80年代の夢は何ですか?
ジョン・レノン 「自分の夢は自分でつくるのさ。ビートルズがそれだし、ヨーコもそれだよ。ぼくがいま言っていることがそれさ。自分自身の夢を作り出せ、さ。ペルーを救いたければ、ペルーを救うのさ。何をやるのも可能さ。でも、リーダーたち――つまりパーキング・メーターにやらせようとしても不可能だよ。ジミー・カーターやロナルド・レーガンやジョン・レノンやオノ・ヨーコやボブ・ディランがやって来て、君の代わりにやってくれるとは思わないことさ。自分でやらなきゃ駄目なんだ。遠い遠い昔から、偉大な男女が言ってきたことだよ。いま神聖なものと呼ばれ、内容ではなく、その表紙があがめたてまつられているいろいろな本の中で、偉人たちは道を指し示したり、道標やちょっとした指示を残したりできる。でも、そうした指示は誰もが見るようにそこにあるんだし、過去にも常にそこにあったし、未来でもそこにあるはずだよ。太陽の下では、新しいものなんか何もないんだよ。すべての道はローマに通ずさ。でも、君には他人にその道を提供することはできないんだ。ぼくには君の目を醒ますことはできない。君になら、君の目を醒ますことができるんだ。ぼくには君の傷を治せない。君になら君の傷を治せるんだ。」(『ジョン・レノン/PLAYBOYインタビュー』(集英社))
※原文を加筆修正。(渡部幻)