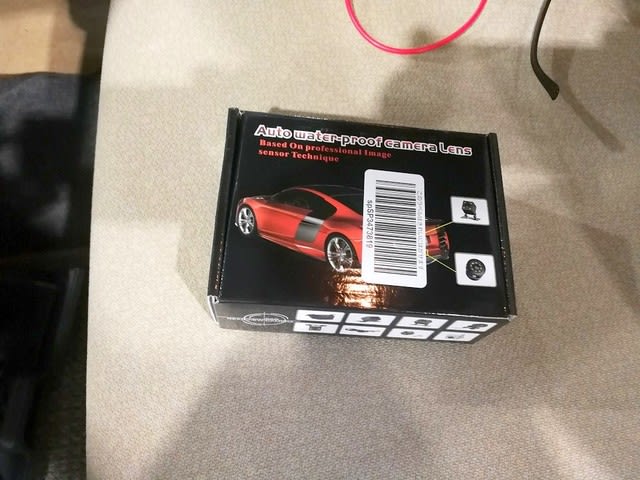家内が通勤している車ですが、エアコントラブルが発生。
去年まではなかったのが、今年になって突然起きたわけですが、 家内が「全然車が冷えない!」と騒いではいたのですが、この夏は気温35度とか連発していたので、
冷気は出ているけど、単純に車の内部加熱で冷え切らんのだろ・・・ なんて思ったいたのですが、オイル交換で職場に来た時にその減少に遭遇?
なんて思ったいたのですが、オイル交換で職場に来た時にその減少に遭遇? 「あらららら!」
「あらららら!」
昼に、銀行に用があって車に乗ったら、まったくエアコンが効かず、吹き出し口からは生ぬるい風しか出て来ない。
”おかし~な~”、と思ったのですが、 上に書いた様に真昼の暑さのせいか?とか自分でも思ってしまい、ただ、
可能性が有るとすれば4年ほどバッテリーを交換していないので、それが原因か???と。

ただ、このエアコンが効かない現象も、朝の通勤時は問題無かったし、帰りの途中から突然エアコンが効くようになって、”これって、単にバッテリーの熱だれかいな???”
そんなわけで、とりあえずその時はそのまま帰宅。
そして、すぐにバッテリーの新品を注文。

数日後、新品のバッテリーが来たので早速交換をしますが、やはり職場に来る時は全く問題無くエアコンは稼働していて、という事はやはりバッテリーの問題だけとはいえないよな~と。
着くとすぐにバッテリーを交換し、アイドリングでエアコンを作動させると普通に冷気が出てきて、
多分真昼の炎天下じゃ無いと判らないなと・・・

で、この日も昼に外へ出る用があったので、車で乗り出すと、案の定、途中でエアコンが効かなくなった。
その為、原因はバッテリーでは無いことが判明。 朝に交換したので。
となると・・・・・なんだべな?

交換時走行距離 155353km8月26日


と言うわけで、早速トラブルシューティングのための情報収集を開始。
エアコン不調の具体的症状の出方ですが、走行時にエアコンのスイッチをオン、サーモスイッチが入り、そこでコンプレッサーのクラッチが普通にONします。
冷気が出始めると、ところが、ややもして勝手にクラッチが解放されて、コンプレッサーが廻らなくなり=冷気が出なくなり、生暖かい風が場合により温風が出る。
信号などで停止しているアイドリング時、そして走行している時にもそれが起きる訳だけど、真昼の最高気温時だけ症状がでるわけでして、朝や夕方の涼しくなってきたときにはこの症状はなくて、普通にエアコンは動いている。
走行時にエアコンのサーモスイッチ???が入って、きちんとコンプレッサーのクラッチも接続されているらしい時は、冷気が出るので、コンプレッサーそのものが正常に動いているのは判るが、 ならばと送風を最大の4にしていると、冷えなくなることが多い、
そこで3にすると、冷気の出ている時間が長くなるが、やはり途中から冷えなくなる。
2にすると、送風は不十分となるが、冷気の出ている時間は最大よりはるかに長く、3より長くでている。
ただし、アイドリング時とかに突然生暖かい風が出てきて、冷えなくなる症状は変らず。
こんな感じで、まずは”オルターネーターの発電能力が落ちるのと連動”しているのでは無いか?と
バッテリーを交換してみたわけですが・・・・  結果駄目。
結果駄目。
交換によって、多少の改善が見られた物の、症状的には余り変りません。
少し良くなったのは、送風ファンの能力を2にしていると、割と長く冷気が出ていることで、ただ、それもガンガンに冷えている感じでは無い。
そこで、問題点を見つけるために、気がついたことを以下に整理してみた。
まずは電圧。
ナビの接続情報から電圧(オルターネーター)を見て走行していると、電圧は13.5~14.2V位の間を
行き来していて、信号で車が停止すると12.8V位まで低下する。
電圧が12.8V位まで落ちたときにクラッチが外れて、冷気が出なくなりやすいのは間違いなく。
ただ、必ずしもそうという訳ではなくて、12.8Vでもコンプレッサーが働いて冷気を出している時がある。
例えるとエンジン始動して暫くの間。
エアコンが冷えなくなる可能性の一つに、電動ファンがあるが、ボンネットを開け、エンジンの冷却水と連動して
冷却ファンがきちんと廻るかをみていると、水温が上昇すると普通に廻り始め、滑りやその逆の固着などが無いか?を調べたけど特に問題は無し。
コンプレッサーを動かすクラッチがきちんと働いているか?だけど、これは動作音がきちんとするし、
実際にコンプレッサーが動いて、送風口から冷気が出てくる。
エアコンが効かなくなる原因として、空調を司るダンパーモーターが不調になることが上げられるが、
各部のダンパー系統の動きをみていると問題は無い。
というわけで、上に書いた様に、基本的に疑う事が出来る、電圧、冷却、コンプレッサー、空調ダンパー
のいずれにも問題は無い、電圧はバッテリー交換済みで、発電電圧はナビの上方から問題無い事を確認済み。
はて・・・・・・となると、なんだべな?
やっかいなのは?朝と夕方の比較的気温が低いときは全く問題無くエアコンは動いていることで、
冷えの方も全然問題は無し、なので、コンプレッサー内部の破損や圧抜け、コンデンサーやエバポレーターにトラブルが有るとは思えない。
もしこれに問題があった場合は、ずっと冷えないわけでして、冷える時と、そうで無い時、というムラがそもそも起こりえない。
帰り間際に、 しばらくエンジンを掛けてエアコンを作動させて様子を見ていたのだけど、その時の送風は最大の4
でエンジンが完全に温まる状態まで放置。
当然というか、最初は効いていたエアコンが途中からやはり効かなくなった、まあ、上記の症状が出ているわけだが、当然と言えば当然。
そこでだ、ボンネットを開けてクラッチの入りとか見ていたら、カチン!という音と供にコンプレッサーが動き始め、
それに連動してラジェーターの冷却ファンが回転、車内の送風は最大の4、そしてこの時の電圧は12.8V
ラジェーターのファンと車内の空調ファンがフル回転なので、消費電力が大きく、電圧はそれにより12.8vくらいまで低下するのはおかしな事では無く、オルターネーターの発電限界を超えている訳ではないので、その電圧以下には下がりません。
様子を見ていると、5~10秒程するとクラッチが切れてしまい、コンプレッサーが停止。
とたんに冷気は出なくなり、温風になる。
ダッシュメーターのインディケーターは何にも点灯していないので、エンジン系統にはトラブルはおそらく無い。
ここで、ある事を開始。
何をしたのか?というなら、 ラジエーターの前から散水ガンのシャワーモードで水を吹き付けるんです。
すると、カチンと言う音と供にコンプレッサーが動き始め、冷却ファンも回転。
しばらくそのまま様子を見ていたら、すぐに切れるコンプレッサーがずっと接続したままとなり、
冷却ファンも動きっぱなし。
一度ここで放水をやめ、ドアを開けて吹き出し口からでている冷気に手をかざすとバカ冷え。

そのまましばらく様子をみていると、問題無くエアコンは作動して冷えている。
エアコンが動いているときと、そうで無い時の外部条件になんら差は無く、単にラジェーターの前から
水をかけただけのことだ。
そこで思いついたのは、もしかしてサーモスタット????? 

この車にはエブリィみたいに水温計が無く、もし異常が起きても警告灯で知らせるだけというどうせ見ても判らんから無くしてしまえ!というおバカ向け仕様車。
なので、冷却系統の温度の状態は普通に乗っている限りは皆目見当が付かないんです。
*エブリィなら水温計がきちんと付いているので、エアコンが効かないときの水温の状態とかもきちんとチェック出来る。
サーモスタットに何らかの不具合が生じたばあい、 大抵はサーモスタットが動かなくなる事が多いのですが、
内部のワックスが劣化して圧が抜けると、十分に開かないことがある。
その場合、冷却水の温度がとうぜん上昇していき、それが限界というところまで達すると
警告灯を点灯させるわけだが、これは”それ以上の温度になると良くないですよ!”というわけでして、
サーモスタットの仕様にもよりますが、それが通常85度で開いて、冷却水の温度を85度で保つ物であっても、サーモスタットが駄目になると、当然に温度はそれ以上になる。
ラジエーターのキャップによる多少の加圧があるので、100度くらいまでは沸騰しないので、警告灯が点灯する少し下の温度のまである事はあり得る。
となると・・・・・・・もしかして、 この車は冷却水の温度がある程度を越えた場合、オーバーヒート防止の為に
この車は冷却水の温度がある程度を越えた場合、オーバーヒート防止の為に
その原因として一番負荷の掛るエアコンシステムを自動停止させ、熱の発生を抑えることでエンジンを守っているののではないか?と推測が出来た。
とはいえど、サーモスタットが手元にあるはずもないので、今日はそのまま帰宅して、自分が思い当たった
エアコンが停止する原因をネットで探ってみると、 有りました!
このL350Sというタイプのタントは、 冷却水の温度が上がるとエアコンを自動停止させてしまうという事が
記載されている日記?記事?に出会った。
道理で、気温の低い朝とか、涼しくなった夕方にエアコンが効くわけです。
サーモの開きが不十分だと、冷却水がきちんとラジエーターに流れては行かず、冷えない状態で冷却水は
エンジンをグルグル廻る、温度が当然上昇するが、それが警告灯を点灯させるまでに温度が上がらなければ
そのまま車は走れてしまう。 上にも書きましたけど。
外気温が35度とかにまで上がり、その不十分な冷却の状態だと冷却が不十分となり、加熱するので、
システム的にオーバーヒートを防止する為に、エアコンを自動的に落としてしまう。
というわけです。
なので、気温が低い時には普通にエアコンが動くし、強制的に前から水をラジエーターに吹き付けると、気化熱によって冷却水の温度は下がって行きますから、まあ、朝と夕方と同じになるわけで、 そうなるとエアコンは問題無く動き続ける。
なんで”炎天下の下だけエアコンが効かなくなるのか???”という原因のほぼ99%はこれで判りました。
で、次は如何するか?というなら、当然に新しいサーモスタットを注文。そして交換します。
これで直ってくれれば良いのですけど












 とのこと。
とのこと。 という事です。
という事です。  ダハハハ!
ダハハハ!















 (笑)
(笑) 






























 とさ
とさ