エアコンや 炊飯器、電子レンジなどを駆動するのに使っているEU9i。
安いところもついでに紹介 ↓
★楽天の 安く買えるドットコム というところで、 カテゴリーのその他に 発電機があります、 そのほか日用品とか安いです★
性能的にとても優れていて、軽くて静かだしと、いいことずくめでお気に入りなのですが、一つだけ問題がある。
そう、周波数の切り替えが簡単にできない。
これを一番使うのがハイエースキャンピングカーですが、炊飯器もエアコンも 60Hzで動かしますが、 電子レンジだけは50Hzでないと、うまくない。
なぜなら、今使っているシャープの500w電子レンジが、 50Hzで950W 60Hzだと 1200~1300Wくらいの消費電力。
60Hzのセットのままで使うと、EU9iでは過負荷となって落ちてしまうんです。
そこで、周波数の切り替えスイッチをつけたくていたのですが、今ついているスイッチはこんなところに有り、尚且つ ラジオペンチみたいな物を使わないと切り替え出来ない。

第一、そんなものを逐一持ち歩くのは面倒この上ない。
なので、もっと使いやすいようにトグルスイッチを使った切り替えをつけてみました。
結果さえ分ってしまえば、簡単にできる改造なのですが、 スイッチそのものがどんな物?なのかを調べる必要があって、それが単なる 導通、抵抗無限大のON OFFスイッチならいいのですが、 見た感じトリマ抵抗みたいな抵抗値可変のようにも感じられてしまうし(普通はそんな設計しませんけど)・・・・・ 
万が一抵抗値可変で周波数制御なんかをしていたら、その適正抵抗値を入れてあげないときちんとした周波数が出ない可能性もある。 
そういったわけで、興味があるのと分解して中を見たい方もおられると思いますので、例のごとく人柱となって分解してみました。
やってみた感想ですが、 バラシは簡単ですが、組み立てに癖が有り、へたするときれいにくみ上げられない人が多いのでは無いか~?と思うのでスイッチの取り付けはともかくとして、実際に同じ事をするのはお勧めしません。
代わりに僕がやってみますので、中を見たい人はぜひじっくりと写真をみてくださいね。 
まず、サイドのメンテナンスカバーを取り外します。 次にコントロールパネルフェイス、最後にマフラーカバー



マフラーカバーを外すと、あっさりとマフラーが出てきますが、うまく出来ていて、フロント側にあるファンから取り入れられたエアがエンジンを冷却しつつ、最後に隙間(水色矢印)を通ってマフラーを冷やしながら後方へ排気されていくように出来ています。
マフラーの真下にあるステイの両サイドにはエンジンの振動を押さえる防振ゴムがあり、
こうした防振機構がエンジン周りに3カ所あって、 赤い色のケースによってエンジン全体をゴムで浮かせることで振動防止と騒音の軽減をしています。

パネルが外れたら、 次に エンジンの始動スイッチノブとと 始動用プルワイヤーを取り付けているプレートを外します。


この始動ノブですが、下の写真のように、 機械式で動くリンクで、制御系の電気回路を遮断する(黄色矢印)のと、 ノブのすぐ裏(赤矢印)に燃料のオンオフバルブが連動することで、燃料遮断と電気回路を同時にオフにする構造になっています。 

本体サイドのねじをはずしたら、殻割り~! ただし、この段階ではこのくらいでやめておきます。
ただし、この段階ではこのくらいでやめておきます。

というのは、こんなところにクリップがついていて、 簡単にばらけないようにしてあります。 実にうざったい・・・・・
簡単にばらけないようにしてあります。 実にうざったい・・・・・
こんな物いらないんだけど・・・・・ 

これはドライバーか、Cクリップライヤーで外せます。

クリップがはずれれば、カバーはいとも簡単に外せますが、 取り去るのは右側だけでして、右側は燃料ポンプ等の補助部品が、まだついてます。
ちなみに赤矢印はさっきも説明しました、 エンジンをカバーで浮き上がらせるための防振装置でゴムやらピンパイプやら。
ケースを戻すときはボディを左側に傾けて、すべてのパーツが適正な位置に入るように戻してから右側のカバーをつけます。
実はこれがうまくいかないんですね、  特に車整備や機器の分解になれている人はさしも苦労しませんが、そうで無い人はこれでまず失敗します。
特に車整備や機器の分解になれている人はさしも苦労しませんが、そうで無い人はこれでまず失敗します。
ですのでやらない方が賢明です。  やるなら燃料タンクの中身を空にして、オイルも抜き、左側に完全ごろりと横にして組み付ければ何とかなりますが・・・
やるなら燃料タンクの中身を空にして、オイルも抜き、左側に完全ごろりと横にして組み付ければ何とかなりますが・・・

さて、周波数切り替えスイッチを取り外しますが、その前に邪魔な部分をなんとかしなければならない。
まず緩めておいた 始動プルワイヤーを少しだけ引いて、出来た隙間からプレートを中に押し込み、ノブも押し込みます。

するとカバーがルーズになり、 負圧式燃料ポンプ(水色矢印)が見えてきます。
ちなみにこの黄色部分のゴムが落ちてしまいやすいので注意。

カバーをはずした時はたぶんインバータユニット側についてきますが、組み立てるときは緑色矢印のところに入るので覚えておいてください。
黄色矢印のゴムは防振と燃料タンク保持のためのもので、これは簡単に落ちてしまうので位置と方向を覚えておいてください。

燃料ポンプの留めネジを緩めると ポンプが浮きます。

周波数切り替えスイッチはこの裏にあります。 黄色丸で囲んだところがそれ。
爆チャチ! 

これの配線ですが、なぜが先ほどの防振ゴムの裏をとおっていて、たぶん電線が振動で揺れるのを防止していると思われます。
真ん中に輝いているのがインバータユニットですよ~! 

さて、ネジを緩めてコネクタを外してスイッチを調べます。
60Hz、50Hz側に切り替えて、抵抗を調べると、 やはり単純に導通と抵抗無限大の単純な物でした、 ただし信じられないほどチャチでして、 こんなスイッチじゃすぐに壊れる。
一度設定したら、ずっとそれで使うようにしか考えられていないんでしょうねきっと。 
ちなみに導通(0オーム)の時が、60Hzだったと思います。

さて、単純にスイッチでOKなのが分れば、切り替えスイッチをつけるだけですが、
ちょうど手持ちで中古のスイッチがあったのでそれを使います。
 配線をぶった切り、
配線をぶった切り、  半田すると完成。
半田すると完成。

問題は取り付け位置。
初めははもとの場所を使おうかと思いましたが、途中で変更して、コントロールパネルの アース線を接続するネジ部分を利用することにしました。
まずカバーを開けてと・・・・・ 黒いカバーの爪がプレートの穴に入っていますので指で押せば外れますが、薄くて割れやすいので注意。 

これで全部が見えます。
アース線を接続するなんていう琴はまず一生無いと思いますので、この無駄な?ネジを取り去り、再度穴を開け直して取り付けることにしました。

ドリルで ガ~~~~!と穴開け。 ばはははは! どうだ! 

スイッチの回り止め様穴もそのすぐ横に開けます。

で先ほどのスイッチを取り付けると。 グッド!

邪魔にならない。

そしたら先ほどの黒カバーを戻し、スイッチのコネクタを元通り差し込めば取り付けは終わりとなります。 簡単!
黄色矢印が周波数切り替えスイッチへいくコネクタ。

後は分解と逆の手順で組み立てれば終わりですが、気をつけなくてはならないのが燃料タンクの適正な位置確認、 本体を左側に出来るだけ傾け、 エンジンを適正な位置に動かして防振装置がきちんと収まっているかが重要。
特にゴムの真ん中を通っているピンチューブをきちんと入れます。
そしてインバータ固定のゴムが、先ほどの緑矢印の穴に入っているかを確認するのと、燃料タンクの配管類や電線を変なところに挟まらないように注意する。
右のカバーを取り付ける前に さっき紹介した防振ゴムをとりはずし、 その溝部分にインバータと燃料タンクがきちんと入るようにすればほぼ自動的に位置が決まりますから、その上からカバーをかぶせる。

燃料タンク上部のゴム受け部と、カバーの一番下の噛み合い、 防振ゴムとそのチューブピンがきちんと入っているかを最後に確認すれば、後は締めて終わりです。
ピンクのが周波数切り替えスイッチ。 黄色丸は元々ついていたスイッチです。

分解そのものはお勧めしませんが、 もしスイッチを取り付けるだけなら、こんな全分解をせずとも、コントロールパネルのフェイスカバーを取り外して、サイドのネジ(黄色矢印)2本取り外せばプレート全体がフリーになります。
プレート上部が引っかけてあるので、赤矢印のように少し下にすこし押し下げれば、プレートが簡単に引き出せますので作業そのものは楽にできます。
周波数切り替えのコネクタもプレートの真後ろにちょうど来ているので、適当なところで切断して同じようにスイッチをつけてあげればOKです。
もしやるならこの方が簡単だし安全です。
ちなみに 500Wパワー位の電子レンジは50Hzで消費電力が900~1000Wくらいなので、Eu9iでぎりぎり動作します。

一番最後に、 もし自分でやってみようか?という方がおられましたら、あくまでも自己責任でおねがいします。 お粗末様でした。(笑)
お粗末様でした。(笑)


 てなことになる。
てなことになる。

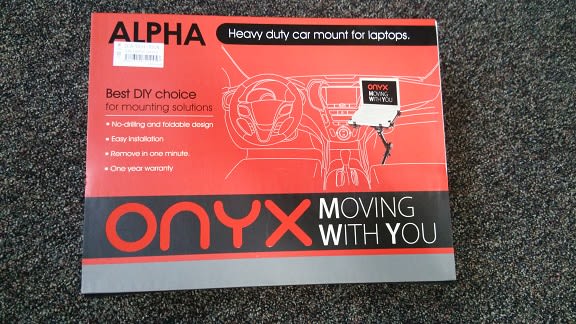







 カットしようか??
カットしようか?? 















 いやいや今日は 他の処を経由です。
いやいや今日は 他の処を経由です。 案の定日陰の為に激寒だったけど・・・
案の定日陰の為に激寒だったけど・・・ と思っていたら、ドライブレコーダのシガーライター用電源プラグが、お得意の中華品質故の接触不良で加熱して溶けていた。
と思っていたら、ドライブレコーダのシガーライター用電源プラグが、お得意の中華品質故の接触不良で加熱して溶けていた。 だめだこりゃ!
だめだこりゃ!

























 と思いつつも、 同時にこの天気ならニス塗りにはベスト。
と思いつつも、 同時にこの天気ならニス塗りにはベスト。 
























 うふふふ ← 気持ち悪い。
うふふふ ← 気持ち悪い。









 正直普段からスポーツをやっている人で無い限りは、 最低二人がかりでやる事をお勧めします。
正直普段からスポーツをやっている人で無い限りは、 最低二人がかりでやる事をお勧めします。
































 お粗末様でした。(笑)
お粗末様でした。(笑)













