
ライナー・マリア・リルケ(Rainer Maria Rilke、1875年12月4日 - 1926年12月29日)は、20世紀を代表するオーストリアの詩人、作家、評論家。独特の言語表現による詩は、ドイツ詩に新たな一面を切り開いた。20世紀のドイツ文学の代表者の一人であり、ドイツ文学史を通して見ても最高峰の詩人の一人に数えられる。また独自の宗教観や時代に対する不安や苦しみといった概念は、20世紀を象徴するようにも捉えられている。27歳の時からパリでの生活を始める。このパリ時代に経験した不安と孤独、憂愁の体験は『マルテの手記』を執筆するうえでの大きな源泉となる。この頃に彫刻家オーギュスト・ロダンと知り合ってその芸術観から多くを学び、ロダンの評論も書き上げている(のちロダンと不和を生じたが、リルケ自身のロダンの評価は変わることがなかった)。またシャルル・ボードレールやポール・セザンヌなど様々な芸術家に対する関心を深めつつ、自らの芸術についての考えや立場を転換していった。それまでの優美さや感受性の流露は影を潜め、パリで体験した現実と孤独、そして誠実な観察と職人的な仕事によって支えられたロダンの造形への意志の影響の下に、『新詩集』ではいわゆる「事物詩」をはじめとした、語られているものを言葉によって内側から形作ろうとする作風に達している。この転換を端的に表すものとして、「どんなに恐ろしい現実であっても、僕はその現実のためにどんな夢をも捨てて悔いないだろう」という言葉が残っている。1910年に『マルテの手記』が完成。その年から翌年にかけて北アフリカ・エジプトに旅行し、リルケの目は地中海地域全体にまで広がった
ライナー・マリア・リルケ
ブロークと同時代の世界的な意識の高揚がこの時期の芸術運動に象徴されている。リルケが描こうとしているのは、20世紀の終わりには多くの現代人の体験する孤独と不安であるのだが、まだ同時代人でそれを理解した人々は限られていた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「いつ一ひとりの人間が」
いつひとりの人間が 今朝ほど
目覚めたことがあったろう
花ばかりか 小川ばかりか
屋根までもが歓喜している
その古びてゆく縁でさえ
空の光に明らんで
感覚を持ち 風土であり
答えであり 世界である
一切が呼吸(いき)づいて 感謝している
おお 夜のもろもろの憂苦よ
お前たちがなんと痕跡(あとかた)もなく消え去ったことか
むらがる光の群で
夜の闇はできていた
純粋な自己矛盾であるあの闇が
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
夜と朝の対比という形で自分の心境の転換を語っている。パリですごした青年時代の悩みと不安をくぐりぬけて自分がするべきことを明確に確信できた喜びを語っているのではないかと思う。自分の芸術を創造するプロセスでアーティストは必ず生みの苦しみを味わう。それまでに誰も語らなかった真実を自分の言葉とスタイルで表現することが詩人の仕事だ。この詩はおそらく試作段階を経て自分の世界を確立した中盤の時期に発表した作品ではないだろうか。「むらがる光の群で夜の闇はできていた」この部分にリルケのすぐれた洞察を感じると共に翻訳者の観賞力の深さが現われている。光と闇が実は対立するものではなく同一の実在の異なる表現であったという認識は、現在われわれの目撃している終末の時代のテーマでもある。
ライナー・マリア・リルケ
ブロークと同時代の世界的な意識の高揚がこの時期の芸術運動に象徴されている。リルケが描こうとしているのは、20世紀の終わりには多くの現代人の体験する孤独と不安であるのだが、まだ同時代人でそれを理解した人々は限られていた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「いつ一ひとりの人間が」
いつひとりの人間が 今朝ほど
目覚めたことがあったろう
花ばかりか 小川ばかりか
屋根までもが歓喜している
その古びてゆく縁でさえ
空の光に明らんで
感覚を持ち 風土であり
答えであり 世界である
一切が呼吸(いき)づいて 感謝している
おお 夜のもろもろの憂苦よ
お前たちがなんと痕跡(あとかた)もなく消え去ったことか
むらがる光の群で
夜の闇はできていた
純粋な自己矛盾であるあの闇が
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
夜と朝の対比という形で自分の心境の転換を語っている。パリですごした青年時代の悩みと不安をくぐりぬけて自分がするべきことを明確に確信できた喜びを語っているのではないかと思う。自分の芸術を創造するプロセスでアーティストは必ず生みの苦しみを味わう。それまでに誰も語らなかった真実を自分の言葉とスタイルで表現することが詩人の仕事だ。この詩はおそらく試作段階を経て自分の世界を確立した中盤の時期に発表した作品ではないだろうか。「むらがる光の群で夜の闇はできていた」この部分にリルケのすぐれた洞察を感じると共に翻訳者の観賞力の深さが現われている。光と闇が実は対立するものではなく同一の実在の異なる表現であったという認識は、現在われわれの目撃している終末の時代のテーマでもある。










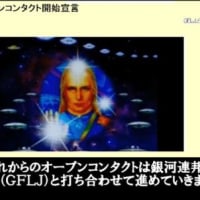



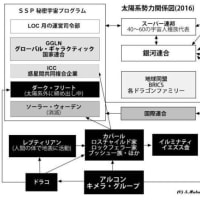
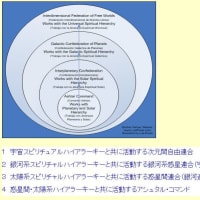




白血病に倒れる前の詩ですね。
小川のあらゆるささやきを
岩窟(いわや)のあらゆる水滴(したたり)を
ふるえながら かよわい腕で
私は神へ返すのだ
そして私たちは讃える 輪舞をば
風が向きを変える毎度に
それは招きであった 驚きだった
すべての深い発見が
再び私を幼な児にした-------
そして私は感じたのだ 私は知っていると
おお 私は知っている 私は理解している
もろもろの名の本質と変化とを
成熟の内部には休らっているのだ
原初の種子が
ただ限りなく倍加して
神なるものを捉えようと
呪文の言葉がたちあがる
そして言葉は消えやらず
聞きとどけられたその喜びに燃えている
歌いながら すこやかに
(ニーケとはナンニー・ヴンダリー=フォルカルトという人のようです。)
「時祷集ー1905年」はリルケがその独自の風格を表しはじめた最初の詩集。その主題においても、スタイルにおいても、相互に綿密な繋がりを持っていて、全体に有機的な統一のある連作詩の集まりである。それを一貫して流れているのは、ある原始的・汎神論的自然感情であってそこで呼びかけられている「神」も「純粋生命」とでもいうべき概念に近いものだと言うことができよう。その背景には、ニーチェ以来、当時のヨーロッパの精神界にみなぎっていた「生への意志」の風潮があることが明らかに感じられると言ってもいいのである。
「形象集」は1902年にその初版が出たが、1906年にその後に作られた多くの詩を補充した再販が出された。これらの詩にも、一種の汎神論的自然感情の表現が認められるが、それは個々の主題に集中して、しばしば美しい象徴的な風景詩や自然感情となっているのである。
1902年8月末からリルケはパリに移り住む。ロダンから受けた強い影響と、ボードレールをはじめとするフランス詩を耽読したことによって、この時期の彼の詩には一つの重大な転換が現われた。「新詩集1907ー1908」はこの時期の彼を代表する詩集である。彼はそこで広い事物の意味を、それ自身独立した一つの完全な存在として、時空をはなれたある絶対的な空間の中に置いて歌っている。批評家は彼のこのような詩を、「事物詩」と呼んでいるが、それは言葉によって作られる詩を、手で触れることの出来る「物」のように作り出そうという試みなのだったといえよう。そしてリルケはこの詩集によってその純正詩人としての近代詩史上の位置を確立したといってもいいのである。
「新詩集」出版以後、「ドゥイノの悲歌」の完成に至るまでの10年間に、リルケは詩集としては僅かに二冊の薄い詩集を出したに過ぎなかった。しかし、彼はこの期間にもそのほかにかなり多くの詩を作っていたのであって、それらの詩は第二次大戦後に、リルケの死後30年にして、はじめてその全貌が明らかになったのである。
「1913ー1920の詩」は、その書かれた時期からいっても内容から見ても「ドゥイノの悲歌」の序曲、もしくは前奏曲とでも言うべきものであって、それは「新詩集」を出版したのちのリルケがその詩境を踏まえながら、さらに新しい出発をしたことを語っている。この時期のリルケは人間や地上の事物の無常を痛感しながら、人間存在の意味を問う方向へ向かっているが、その究極が「ドゥイノの悲歌1923年」に結晶していることは、周知のところだろう。
「ドゥイノの悲歌」は一方で確かな足場を持たない人間実存の不安を歌うと共に、地上の事物を「目に見えないもの」に変形し、内面化することを人間の使命として説いているが、このような使命の自覚の上に立って、存在の世界を歌い讃えているのが次の詩集「オルフォイスへのソネット」である。この詩集ではいわば地上の事物を歌いながら、実存の危機と深淵を踏み越えて、変身してゆく人間の理想像として捉えられているということができよう。その明るく、軽快な歌いぶりは、リルケが既に「ドゥイノの悲歌」の詩境を脱しつつあったことを語るものである。
1922ー1926の詩は、リルケの最後の4年間に生まれた詩。「オルフォイス」に始まった明るく、軽快な歌いぶりは、これらの詩篇において、しっとりとした落ち着きを示し、清澄な調べを奏でている。同じ時期におびただしく生まれたフランス語の詩とともに、これらの詩は決して「ドゥイノの悲歌」の単なる余韻ではないのである。
彼はフランスに行った影響で優美さなどを得た半面、人生の無常感を、虚しさを味わってしまったのかなって思います。フランスはドイツに比べて刹那的な雰囲気がある気がするので。でも彼はやはりドイツの人なのですね。最終的には終末論的な、希望に向かう考え方が感じられますね。
岩窟(いわや)のあらゆる水滴(したたり)を
ふるえながら かよわい腕で
私は神へ返すのだ
そして私たちは讃える 輪舞をば
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
素直に神(自然)への讃美から導入される。「輪舞」で恋心を表している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
風が向きを変える毎度に
それは招きであった 驚きだった
すべての深い発見が
再び私を幼な児にした-------
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「風が向きを変える」でリルケは自分の人生の変化を言おうとしている。人生の変化の中に神の意思を感じようとしている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そして私は感じたのだ 私は知っていると
おお 私は知っている 私は理解している
もろもろの名の本質と変化とを
成熟の内部には休らっているのだ
原初の種子が
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この部分に詩の中心がある。人生の最初から、そして生まれる前から神の意思のままに人生は計画されていたことに気づく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ただ限りなく倍加して
神なるものを捉えようと
呪文の言葉がたちあがる
そして言葉は消えやらず
聞きとどけられたその喜びに燃えている
歌いながら すこやかに
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
神の実在を確信したリルケは祈りの中で自分の心が神に通じたと実感した。再び冒頭の生の喜びへ戻る。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドイツ人は思索・哲学をフランス人は美・芸術を愛好する。リルケは自分の思想を詩というスタイルで表現した。その思想は信仰と言いかえても良いだろう。
彼の詩は、彼自身の神への信仰と、ドイツの深い思索と、フランスの流れるような芸術センスの合体なのでしょうね。