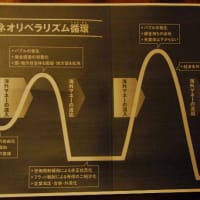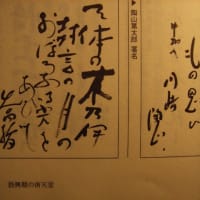第四章 冷戦はどうやって終ったのか
この章は大変面白い。例によって齧り書
資本主義は70年代に勝っていた。
「・・・社会主義経済の行き詰まりっていのはもう70年代の初めにはっきりしているわけです。・・・いわば決着はついちゃってたわけです」
ー資本主義対共産主義の決着はもう70年代についていた・・・。
「・・・市場経済を全面的に押さえ込んじゃった経済、私的所有を否定した経済、これがいわゆる社会主義国の経済ですね。これのやり方は、工業化のために大規模に資源を動員するにはかなり機能的で、最初は経済成長率が高いんですよ」
ーソ連も最初はすごいバラ色だったっていうやつですよね。
「そうそう。ただ犠牲も大きい。農業が犠牲になる。前にも触れましたが、ソ連では農業の集団化と飢饉が起こって、それで無理矢理工業を起していくことになった。中国でも大躍進政策で大変な犠牲を払って、工業化の方向に移行する。当初はよくても、非常に狭いマーケットに向けてモノを作っていくので、効率が悪いんですよね。高コストの経済なので次第に行き詰っていくわけです」
長くなるが、引用を続けると・・・。
「冷戦が経済体制の競争だけだったら決着はわかりやすいでしょう。行き詰まった経済体制を変えればいいんですから。中国はもう80年代から経済体制が大きく変わった。今や、あそこがどういう意味で社会主義国かよくわからないですよね。だけどアジアでヨーロッパと同じ意味で冷戦が終ったというふうに言われていないのは、やっぱり冷戦が経済体制の問題だけじゃなくて、政府の仕組みのことだってことを示している。やっぱり最後は共産党の支配が倒れないと冷戦は終わらないのか、っていうふうになりそうですよね」
この最後のくだりは意味深長である、と思う。こう言う風な考え方は私は知らなかった。ヨーロッパの平和とアジアの平和は違うようだ。
この章は大変面白い。例によって齧り書
資本主義は70年代に勝っていた。
「・・・社会主義経済の行き詰まりっていのはもう70年代の初めにはっきりしているわけです。・・・いわば決着はついちゃってたわけです」
ー資本主義対共産主義の決着はもう70年代についていた・・・。
「・・・市場経済を全面的に押さえ込んじゃった経済、私的所有を否定した経済、これがいわゆる社会主義国の経済ですね。これのやり方は、工業化のために大規模に資源を動員するにはかなり機能的で、最初は経済成長率が高いんですよ」
ーソ連も最初はすごいバラ色だったっていうやつですよね。
「そうそう。ただ犠牲も大きい。農業が犠牲になる。前にも触れましたが、ソ連では農業の集団化と飢饉が起こって、それで無理矢理工業を起していくことになった。中国でも大躍進政策で大変な犠牲を払って、工業化の方向に移行する。当初はよくても、非常に狭いマーケットに向けてモノを作っていくので、効率が悪いんですよね。高コストの経済なので次第に行き詰っていくわけです」
長くなるが、引用を続けると・・・。
「冷戦が経済体制の競争だけだったら決着はわかりやすいでしょう。行き詰まった経済体制を変えればいいんですから。中国はもう80年代から経済体制が大きく変わった。今や、あそこがどういう意味で社会主義国かよくわからないですよね。だけどアジアでヨーロッパと同じ意味で冷戦が終ったというふうに言われていないのは、やっぱり冷戦が経済体制の問題だけじゃなくて、政府の仕組みのことだってことを示している。やっぱり最後は共産党の支配が倒れないと冷戦は終わらないのか、っていうふうになりそうですよね」
この最後のくだりは意味深長である、と思う。こう言う風な考え方は私は知らなかった。ヨーロッパの平和とアジアの平和は違うようだ。