アンコン後、あまり開いていなかったチェロを取り出し
やっぱレッスンしてもらわないと・・と師匠のもとに向かった
第一声は予想通り
「かなり詰まってますね」
無理な演奏、してきたから、筋肉もクタクタだよね・・・ではなく
押し付けまくったボーイングですっかり萎縮してしまっているのはチェロ本体のこと。
それを師匠は一瞬にして見破ってしまうのだ。
しばらく師匠が全弓でボーイングをしていると”チェロ子”は
見違えるほど豊かに歌いだしてくれた。
こうしてチェロが鳴るようになってからレッスンは始まる。
それにしても、演奏会のたび、レッスンに合間が出来るたびに
同じような押しつけ型ボーイングに戻ってしまい、
チェロ子にも師匠にも申し訳ないという気持ちだ。
レッスンに通いだしてから丸5年になろうとしているのに、
基本ボーイングが遅々として進まない。
一歩前進二歩後退を繰り返している。
(無論経験年数の分少しは前進はあるんだけどね。)
相変わらず芯まで深く入りにくい、噛みにくい僕の状態を見かねてか
師匠は「面白いことをしましょう」と弓を弦の上空から落っことして
弾き始めるやり方を実演し、練習が始まった。
「壊れませんから、大丈夫です」
といわれながらも、腕の力を抜いてぶつけてはみるものの
「ゴツン!」「ガッツー」てな感じで、師匠のように
「ジャーン!」という風な音にはなかなか鳴らすことが出来なかった。
しばらくそんな練習をしたあと、手首と腕の力を抜いた状態から
次第に落とす起点を駒に近づけてゆき、
最後は「滑走路に横から着陸するように」
「毛の角、毛の一本から」スムーズに弾き始める練習に変っていった。
要するに、僕のボーイングは、すでに5年の間に癖が凝り固まってしまい
肩、腕、手首、指・・・・これらの硬直を一度解除しないと、前に進まないと
師匠は判断されたに違いなく、そのための落下練習だった。
そんな感じで基本の基本から始まったレッスンで、自分の沢山の「癖」に気付いた。
1)弓の持ち方、弓への指のアクセス角が浅すぎ(右から持っている)
2)弓の毛を弦にあてがう角度が、直角に近く、繊細な開始ができない
3)引き始めが「滑走路着陸型」ではなく、「ジャンプ落下型」に近い
4)「滑走路着陸型」を真似しても「上手いパイロット」ではなく「下手糞なパイロット」
5)ダウンボーイングの後半、半弓から残りは滑った音に変化してしまう
(これは本当のダウンボーイングのカタチになってないから)
6)ダウンからアップ、アップからダウンの切り替えで、音が一瞬途切れる
(これは、無意識に弓を持ち替える「癖」から抜け出ていないから)
7)左手の弦の押さえ方が「叩き型」ではなく、まだまだ「握りしめ型」に近くなっている
とまあ、開放弦のアップダウンと、ほんの1ポジションでの左指押さえ方のレッスンで
これだけの「癖」を自覚せざるをえなかった。
師匠からいちいち事細かに指摘されたわけではないけど、はっきり分かったのだった。
これらの癖を直すことを、年末年始の課題に加えよう。
これらの「癖」の克服をしなければ「明日はない!」のだと思う。
これまで5年かけて培ってきた「癖」だけに、脱出は容易ではないけど
これだけ言葉に出来るくらいに「自覚」できたことは「癖取り」の糸口になるはず。
「癖」と真正面に向き合うべく、年内もう一回のレッスンをお願いしてきた。
ぜひとも1.5歩前進したいと思う。











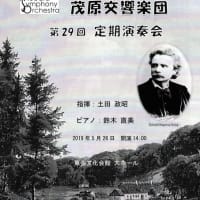








いまはレッスンで言われたことを思い出しながら、ボーイングを常に(オケの練習時も)心がけていますが、一番気にしているのは、その結果としてのチェロの反応(音の響き)ですね。
力が抜けていない、押し付け過ぎの場合は音色はやっぱり縮こまってます。また、弦の振幅なども視覚的に確認するようにしていますね。
まあ、私のアプローチの仕方ですが、参考になれば!
きづきの深さが深まっていると感じています。10cmの気づきで1mm進む感じですが(^_^)