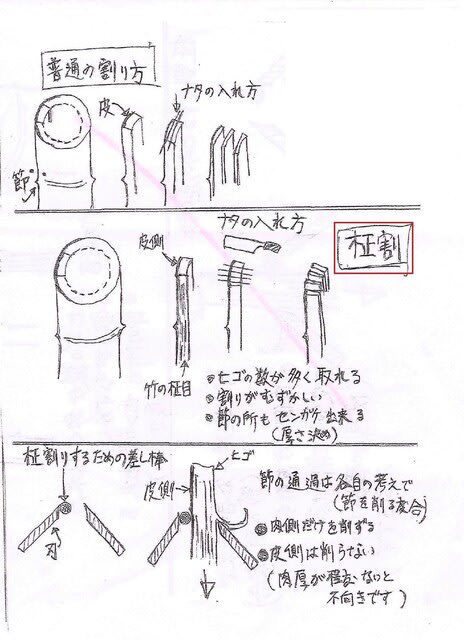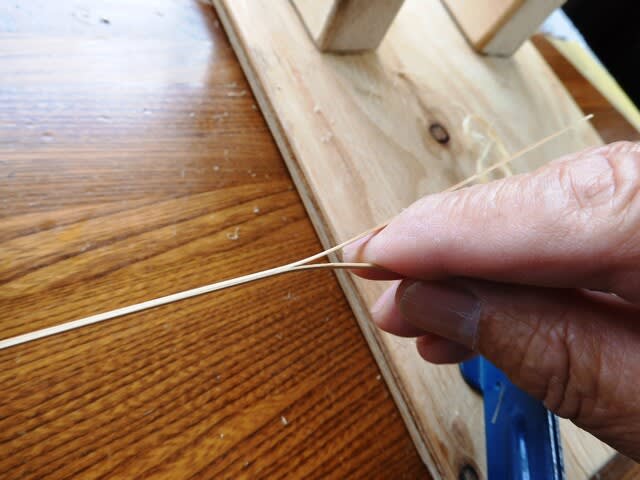友人から紹介され、竹細工教室に通い始めて一年!!
昨年の今頃、最初の行事が竹を伐り出す事だった。
ヒゴの材料になる竹を伐り出す事から教わった。
1年経った今日は二度目の竹伐りだった。
自宅から40km程離れた竹林まで出掛けた。
集まったのは他の教室のメンバーも合流して25人。
3年目の竹を選んで切り倒す。
竹を伐る人、所定の長さに刻む人、それを運ぶ人、皆で分担して作業を行う。

竹は根元に近い所は節の間隔が短く、上に行くほど節の間隔は長い。
下の方の間隔が短い所は切り落とし使わない。
目安は二節で60cmで、それ以上の所から上を使う。
笹が茂る先端の方も使わないので切りおとす。
今日の作業で6節毎の青竹を140本ほど作った。
節は鉄棒を通し穴を開け、来年の2月まで納屋に立て掛け乾燥させる。
そして、立ち枯れた竹や込み合っている余分な竹の伐採等、竹林の整備も併せて行った。
取り敢えず今回の作業はここまで!!
お昼の弁当を皆で戴き解散。