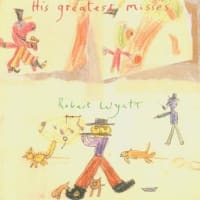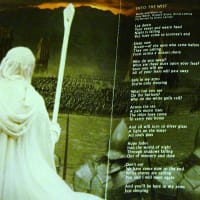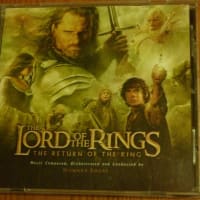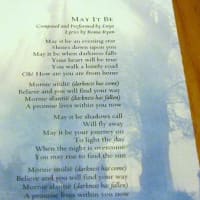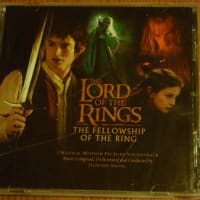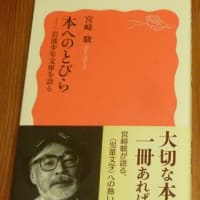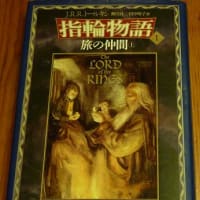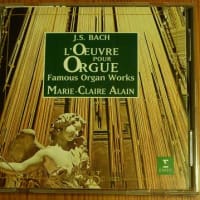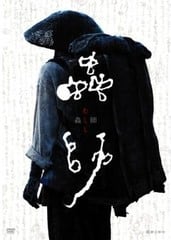
 ご訪問してくださり、ありがとうございます
ご訪問してくださり、ありがとうございます 
 エコと地球の環境について
エコと地球の環境について 
屋上庭園や草に覆われた土屋根、ツタの絡まる壁をもつ建築物は、各国で、古くから存在し、
人々は先人の知恵として、その恩恵を受けてきました。
日本でも古来、夏にはヒョウタンやヘチマの緑陰で家屋に涼を呼ぶ習慣があり、
極寒の国では屋根に生やした草が断熱材となり、寒さを防いでいました。
その根源は、自然と人間の共生に、根ざすものです

話は、変わりまして …

大友克洋監督作品の'07年の実写映画 『 蟲師 』 の、大友克洋完全監修 「蟲箱」です
 !!
!!貴重な、封入特典や映像特典が、付いています


漫画家・漆原友紀さんの原作 『 蟲師 』 (むしし)を読んだ、大友克洋監督は、いたく感動し
「是非、この作品を実写で映画化したい」と、原作者の漆原友紀さんへ、自ら願い出たそうです。
それを、漆原友紀さんが、快諾されて、この実写映画が、作られることになりました。
漆原友紀さんの希望として、ギンコ役には、オダギリジョーさんを推薦されていたそうです。
そして、オダギリジョーさんのほうも、「大友監督の作品なら」と、ギンコ役を快諾されたそうです。
【※ ここから先は、原作や映画のネタばれ・映画の場面や写真、
メイキングシーンなどが、含まれています ※】
蟲師 実写映画版 予告編
Mushi-shi part 10
Mushi-shi part 11
( 動画が、消えていたら、ごめんなさい

 )
)↑ いちばん上の画像は、実写映画 『 蟲師 』 の通常版 DVD
のジャケットです
 !
!
女蟲師のぬい。蟲を呼び寄せる体質で、白髪に緑眼である。蟲を寄せつけないために、蟲の嫌う成分の含まれた、蟲煙草をくわえている。

「奇妙な虹」に憑かれた父親を持つ虹郎(こうろう)は、父のため虹を採る旅に出るが、旅の途中でギンコに出会う。

全ての生命に死をもたらす強力な「禁種の蟲」を、蟲を屠った話を書物に書き記すことで体内に封じている、狩房家の4代目の筆記者、淡幽。

淡幽の書き記した「光脈筋」の場所を記した地図を手に、その場所を探すギンコと虹郎。

蟲師のギンコは、蟲を呼び寄せる体質の為、1ヵ所に留まることは出来ず、蟲の研究をしながら常に旅をしている。蟲が人や動植物と共存したいという考えを持つ。
『 指輪物語 』 を書いた、J.R.R.トールキンは、「イギリスの神話を、作りたかった」と、語っていたそうですが、
この 『 蟲師 』 という物語は、私は、「日本の伝説」ではないかと、思っています。
実際に、昔の日本で、ギンコのように、薬箱を背負って、深い山奥の村などに、わけ入って、
薬草を煎じたものなどを、売っていた人々が、いたそうです。
昔から、使われていた言葉に、「虫の知らせ」というのが、ありますが、
もしかしたら、昔の日本の人たちは、「蟲」と呼ばれていたのかは、わかりませんが、
目には見えない生きものを、とても近しい存在として、それらと、密接に関わっていて、
共存していたのでは、ないでしょうか…。
この 『 蟲師 』 という作品は、不思議な物語であると、同時に、太古の日本のロマンを、
かきたてられます …





 読んでくださり、ありがとうです
読んでくださり、ありがとうです 
それでは、また。。。