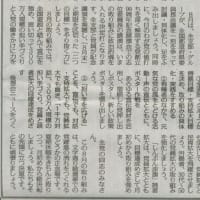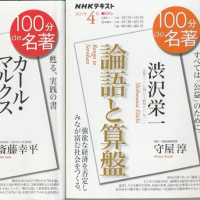将来への不安に応えているか!
社会保障を抑制しろ!
北朝鮮や中国の軍備増強に対し、日本も相応の防衛力を整備し、抑止力を高める必要がある!
北朝鮮と中国に言わせれば、日米核兵器軍事同盟を抑止するために!と言っているぞ!
核兵器軍事同盟安全神話論の暴論の典型!
来年度アベノミクス積極的平和主義予算で国民の命・安全安心・財産・幸福追求権は切れ目なく奪われる!社会保障・生活保護を悪者に、北朝鮮を口実に軍事費は青天井に! (2017-12-23 | アベノミクス)
巡航ミサイルを抑止力として位置づけ敵基地攻撃論を展開する読売社説・産経主張をよくよく読むと北朝鮮の核ミサイル大陸間弾道弾を容認!読売と産経は北朝鮮の労働新聞と同じ新聞だな! 2017-12-13 | 北朝鮮)
読売新聞 防衛予算増額/「陸上イージス」配備を着実に 2017/12/25
北朝鮮や中国の軍備増強に対し、日本も相応の防衛力を整備し、抑止力を高める必要がある。
政府の2018年度予算案で、防衛費は前年度当初比1・3%増の5兆1911億円と、過去最高を更新した。日本の安全を守り抜くため、6年連続の増額は適切である。
目玉は、北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射を踏まえた陸上型イージスシステムの導入だ。17年度補正予算案との合計で35億円を計上し、23年度運用開始を目指す。
2基で日本全土をカバーする。秋田、山口両県の陸上自衛隊演習場に高度1000キロ超の迎撃ミサイルを配備することで、ミサイル防衛能力は大きく向上しよう。
北朝鮮ミサイルに対する破壊措置命令の常時発令で、迎撃ミサイル搭載型のイージス艦は日本海での警戒監視活動に追われ、他の任務遂行に支障を来している。陸上型の導入は、イージス艦の負担軽減と有効活用に資するはずだ。
巡航ミサイルを迎撃できる新型ミサイルも配備する見通しだ。中国の戦略爆撃機H6が今月中旬に対馬海峡を通過するなど、日本付近で活動を活発化させている。こうした動きへの牽制(けんせい)となろう。
ステルス機能を持つF35A戦闘機の調達が進み、航空自衛隊三沢基地に飛行隊を新編する。護衛艦の54隻体制や潜水艦の22隻体制への移行、輸送機オスプレイの導入などにもメドが付く。
18年末には、新たな防衛大綱と中期防衛力整備計画を策定する。新たな脅威に的確に対処するため離島やサイバー空間の防御、テロ対策を含め、防衛態勢を多角的に強化することが欠かせない。
近年、「対外有償軍事援助(FMS)」に基づく米国からの防衛装備の購入が急増している。18年度は4000億円を超す。
F35Aや無人偵察機グローバルホークなど、米国の最新装備は高額だが、性能に優れ、代替できないものが多い。予算額の増大にはやむを得ない面があろう。
ただ、米国が価格や納期の設定に主導権を持つ制度のため、その言い値で購入を迫られがちだ。
他の装備の調達・維持費、自衛隊の訓練経費などへのしわ寄せが深刻化している。
陸上型イージスシステム1基の価格は1000億円弱で、今後も高騰する可能性が指摘される。
小野寺防衛相が「精査し、コスト縮減に努力する」と語ったのは当然だ。法外な価格上昇を招かないよう、米政府と粘り強く交渉することを忘れてはならない。(引用ここまで)
読売新聞 18年度予算案/将来への不安に応えているか 2017/12/23
◆財政健全化果たす意思に乏しい◆
国の財政難や社会保障を巡る国民の将来不安に応える予算になったか。政府の強い意思が表れているとは言い難い。2018年度の政府予算案が決まった。一般会計の総額は97・7兆円となり、6年連続で過去最大を更新した。景気回復を背景に、税収は17年度より1・4兆円多い59・1兆円と、バブル期の1991年度以来の高水準を見込んだ。歳入不足を補う新規国債発行は8年連続で減り、33・7兆円とした。
◆税収予測の前提が甘い
税収増は明るい要素だが、その見積もりの前提となる経済見通しには甘さが目立つ。政府は、来年度の経済成長率を名目2・5%と予想した。大方の民間予想が1%台後半にとどまるのとは対照的だ。実際の成長率が見込みを下回れば税収が想定に達せず、歳入に穴が開く。実際、2016年度は税収が見込みから2兆円規模で下振れした結果、補正予算で赤字国債の発行を余儀なくされた。政府経済見通しは、賃上げ促進といったアベノミクスの効果に期待した目標値の意味合いがある。税収を堅実に見積もるためには、より慎重な前提を置く必要があると言えよう。
歳出面で最大の課題は、全体の3分の1を占める社会保障費を、どう抑制していくかにある。
18年度は33兆円となり、6年連続で過去最大となった。
政府は16~18年度に、社会保障費の伸びを毎年5000億円に抑える方針を掲げた。18年度は高齢化に伴う自然増を6300億円と見積もり、1300億円圧縮して目標の範囲内に収めた。
◆社会保障は切り込めず
ただ、その大半は、薬の公定価格を市場実勢に合わせる薬価改定の効果による。早々に支出抑制の目標達成が視野に入ったことで、本格的な制度改革に踏み込む機運が失われた感がある。
25年には団塊の世代が全て75歳以上になり、医療・介護費の急増が予想される。改革を先送りする時間的余裕はない。
景気拡大が長期化する今が、持続可能な社会保障制度に転換する大きなチャンスだ。
高齢者でも経済力のゆとりの度合いに応じて負担を求める。要介護度の軽い人への在宅サービスを絞り込み、自立支援や重度化防止の取り組みを進めていく。
こうした施策を始めとして、サービスの質向上と費用抑制の両立に知恵を絞りたい。
予算案で、政府が歳出の目玉としたのは「人づくり革命」と「生産性革命」の関連施策だ。
人づくり関連としては、11万人分の保育所運営費や、保育士の賃金引き上げを盛り込んだ。
生産性の向上に向けては、政府が認定する高度な設備投資を行う企業への補助金を積み増す。
限られた財源を重点配分する以上、どれだけの成果を上げたか、事後の検証が欠かせまい。
農道や用水路を整備する土地改良事業は、民主党政権の時代に削減されたが、今回は09年度の政権交代前の水準に並んだ。
与党内で規模回復を求める声が強かった。厳しい財政事情を踏まえた慎重さが求められる。
政府は総額2兆7073億円の17年度補正予算案も併せて決定した。欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)発効に備えた農業対策費などを計上した。
◆抜け道となる補正予算
財源は、16年度決算の剰余金に加え、新たな借金である建設国債を1兆円余り発行した。
当初予算で財政規律を重視してみせても、補正予算でタガが外れれば元も子もない。
補正予算は、緊急時の災害対応などが本来の役割である。当初予算の編成時から補正予算を前提とするような財政運営は、再検討すべきではないか。
18年度末の長期債務残高は1100兆円を超える。先進国で最悪の財政状況を改善するには、長期的な改革が不可欠だ。
政府は、消費税率10%への引き上げを19年10月に先送りしたのに伴い、基礎的財政収支を20年度に黒字化する目標を放棄した。
もともと達成は難しいとみられていた。18年6月には新たな財政健全化の計画を策定する。今度こそ実現可能性が問われる。
消費税率を10%に引き上げた後も、さらなる引き上げを視野に入れねばならない。
社会保障制度と、それを支える税の将来像を一体として考え、そのための具体的な工程表を示すことが重要な課題となる。(引用ここまで)